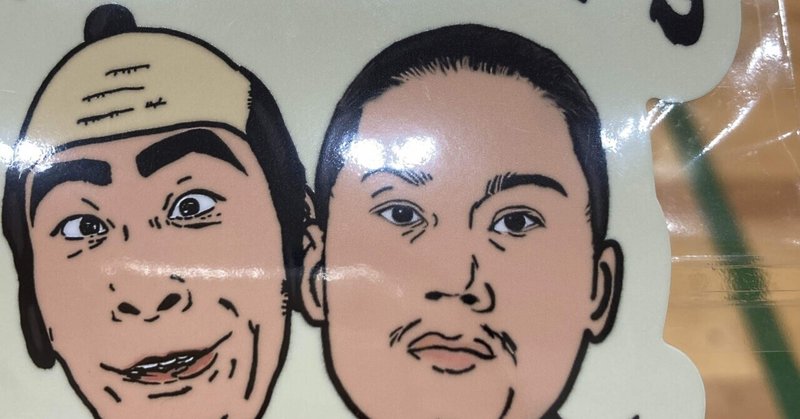
2023年の目標と世界観と香川ファイブアローズ
B2第12節 勝敗:8-15順位:西地区6位 全体12位
これを書いている2022年12月22日現在のBリーグ/ディヴィジョン2における香川ファイブアローズの順位は西地区の6位である。60試合あるレギュラーシーズンの約1/4を過ぎたところ。バスケットボールにおけるシーズンの序盤レースを終えた。

そしてこれから年末を迎えようとしている。
この一年をどう過ごしただろうか?そして来年はどう過ごして行くであろうか?
本屋に行けば2023年のカレンダーや新しい手帳を眺める時期になった。そういうことも考える時期である。
今年を振り返る。
2022年でスポーツに関する記事や著書を読んでいて面白いと思ったのが河内一馬さんの「競争闘争理論 サッカーは「競う」べきか「闘う」べきか?」だった。
元々彼を知ったのが、Twitterタイムラインで回ってきたnoteの記事「"ダサい"組織が死ぬ理由——。なぜサッカークラブは"クール"でなければならないのか」がバズっていて面白いらしいという話だった。
2019年の当時彼はアルゼンチンへ渡り現地のサッカー生活に浸りながらアグレッシブな記事をnoteに投稿していて、特に記事のキービジュアルやスライドが凝っており、南米アルゼンチンからヨーロッパそして日本を相対化しながら論じるなどしていた。
2022年現在は日本に帰国しており鎌倉インターナショナル F.CというクラブでHCをしていてなんと今シーズンは見事昇格まで果たしている。多彩な人である。
先日Noteでその河内一馬さんの記事を読んでいてとてもよかったのでここにリンクを貼っておく。年末に相応しいエントリーでもある。
「世界観とチューニング」ちょっと批評的でも哲学的でもある様なタイトルだ。
言葉の意味や定義は以下の様なものだ。
その言葉を思い浮かべた時に、それがある世界、あるいはそれを取り囲む空間の雰囲気、いろんなものが想像できる、そんな「世界観」(のようなもの)を持てれば、あとは歩みながらチューニング(調律・調整・同調)をしていくことでその世界に近づいていくことができます。具体計画を立てるよりも、寄り道ができたりして、楽しいです。
ここでいう世界観というのは、例えば1年での具体的計画をTOEIC600点クリアするなど資格取得をどの様に目指すのか?いつまでに何をしていくのか?だとすると「世界観とチューニング」は英語学習の習慣を日常に落とし込む事だと思った。
以下「世界観」と具体的計画の差について考えたことを書いてみる。
午前5時に携帯のアラームが鳴って真っ暗な中目を擦りながら身体を起こし、部屋の窓を開ける。目覚ましのブラックコーヒーを入れて、ラジオ英会話にチャンネルを合わせる。ノートを開いて覚えることをメモをする。時事問題に詳しくなるためにBBCの英文ニュースやニューヨークタイムズを購読する。コーヒーの香りが鼻につく。朝の冷たい空気が外から入ってくる。だんだん目が覚めてくる。朝の日差しが眩しい。
具体的計画はTOEICの試験で点数を取るために毎朝決まった時間に勉強する。〇月△日迄に教科書の勉強を仕上げる。だとすると「世界観」は、朝の雰囲気であるとか、コーヒーを入れたり、窓を開けて空気を取り入れたりだとか、それを取り巻く日常の空気まで含まれてくる。それは新しい生活パターンとも言えるし新しい世界でもある。コーヒーや窓を開けるけることは、具体的な目標ではないけれど、「世界観」にとってはとても重要なパーツだ。「世界観」とはそういう将来の目標の周辺の要素も含まれる。
私が例えたものよりも河内さん本人にとってはそのイメージする「世界観」がきっと詳細なことだとは思う。更に言うなら、自分の作る「世界観」に言葉を与えることで目標を形作ること。と言っても良いかもしれない。これはとても興味深いことだ。
この河内さんの記事を読んでいたときに、若林恵さんの著書「さよなら未来」も最近読んでいての以下のこの言葉がよぎった。
未来を考えるということは「いまとちがう時間」ではなく「いまとちがう場所」を探すことなのかもしれない。>若林恵『さよなら未来』115頁
— 若林恵『さよなら未来』発売中 (@KSayonaramirai) October 24, 2022
これは「さよなら未来」に収録されているエッセイのひとつ「テレビ電話とローマ字入力」の冒頭の言葉だ。若林さんのこのエッセイで指摘されている部分でおもしろいのは今となってはテレビと電話は全くの別物で実際はWeb会議や映像コミュニケーションサービスというべきものだし、ローマ字にしてもローマ字入力という観点からみれば、カタカナ、ひらがな、漢字に続くもはやもうひとつの日本語ともいえるものである、と指摘されていることだ。テレビ電話とローマ字の今ではZoomのようなサービスが標準化し、こうやってスマートフォンやPCで文字入力する際、ローマ字という言葉の形態は現代のもう一つの日本語に実質なってしまっているのだ。テレビと電話はそもそも異なるものだしやローマ字の導入にしたって日本語と英語の間を翻訳する過程に導入されたにすぎないようなものだ。当初作った計画ではなく、おぼろげながらにつくった「いまと違う場所」が今に繋がる未来を形作っている。
このエッセイのテーマはウィリアム・ギブスンというSF作家の「未来はすでにここにある」という箴言から端を発している。「ここ」という場所を設定することが、時間軸ではなく空間軸によって定義づけられていることがこの話の味噌である。
これは「世界観」=「空間軸」に非常に近いものの様な気がしたのだ。
未来を考える、というとき、将来に到達したいであろう目標に対して逆算する形でいつまでになにを行う、達成すると計画を立てていくのに対して、むしろ、そうではなく、「いまとちがう場所」を探していく。そうすることが将来のカタチにおぼろげながら近づいていくことになる。
「世界観」=未来というこれから先の時間のことではない「いまとちがう場所」を探すことなのかもしれないとも思った次第。
2023年の手帳も買ったし新年はTOEICの勉強かな。



参考文献など
・香川ファイブアローズグッズ
リニューアルされててgoodです。ヘッダー画像のTHE SAMURAI'Sシールは数量限定で会場で条件反射で購入しましたが後悔などしていま千円。ちなみにTHE SAMURAI'Sシールは¥500でした。
・競争闘争理論 サッカーは「競う」べきか「闘う」べきか?/河内一馬 著/ソル・メディア
前書きにもある様に「精神論」をめぐるジレンマを端に発する形で考え、書かれています。日本のスポーツでは「勝利至上主義」の弊害やそれに派生するハラスメントの様なものも俎上に上がったりするので、今一度当然考えないといけないテーマとして2022年のスポーツ・ベスト・テキストとして推しておきたいと思います。
・さよなら未来――エディターズ・クロニクル 2010-2017/若林恵 著/岩波書店
・B2順位表
・The Japan Times ST Plus はじめる! わたしの英語生活/ジャパンタイムズ
・ほぼ日手帳
香川ファイブアローズ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
