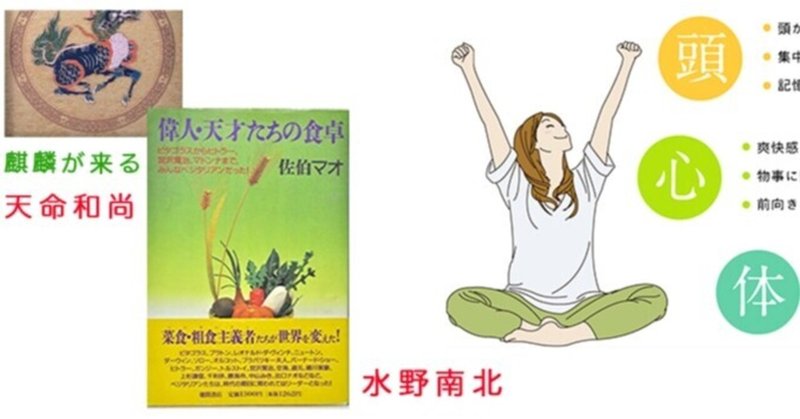
明智光秀は、ファースティングをしていた
皆さん、大河ドラマ「麒麟が来る」をご覧になりましたか?
本能寺の変で織田信長を打ち破った明智光秀は、その後、秀吉に敗れ、百姓の竹槍に倒れたというのが定説です。
ところが、歴史家の間では、納豆汁で108歳まで大往生を遂げた歴史上の人物でもっとも長生きした江戸初期の天海和尚こそが、明智光秀であるとささやかれております。
実は、百姓の竹槍で討たれたのは身代わりで、光秀は、密かに生き延びて、僧侶の身になって、天命和尚として家康に仕えたのではないか。そして江戸幕府の礎を支えていったというのです。理由としては、警視庁で筆跡鑑定をしていた人が、古文書の筆跡を調べて光秀の筆跡と天命和尚の筆跡は同一人物であるとしているのです。
天命和尚は、少食こそ長生きの秘訣であると明かしていました。家康から長生きの秘訣を尋ねられた時に、次の和歌を歌ったというのです。
『長寿は、粗食、正直、日湯、だらり、時おり、下風、あそばされかし』
ここで、粗食とは納豆汁のことです。天海は納豆汁が大好きで毎日のように食べていたとのことです。そして正直に生き、日湯、すなわち毎日風呂に入ること、だらりとは、無理しないで、ゆっくりとすること、下風とはオナラのこと、腸を大切にして毒を出すこと、という意味と捉えられます。
天海和尚は、108歳になっても、記憶力がしっかりしていて、坐禅をしたまま息をひきとったといわれています。私たちが病院で亡くなるのではなく、自然に亡くなる、まさにその見本でしょう。
江戸時代には、水野南北という思想家がいました。彼は、
『人の運は食にあり』
と食の大切さを伝えています。「幸運を招来する法」という本を書き記しています。この本は、「偉人・天才たちの食卓」(左伯マオ著、徳間書房)という形で出版されていましたが、現在は古本として探さないと手に入らない貴重な本です。食が健康や運勢にまでさらに精神の向上に大きく関わっていることを過去の偉人の食生活を紹介して詳細に書かれています。
・人格は、飲食の慎みによって決まる
・食を楽しむというような根性では、成功は望めない。
・酒肉を多く食べて、太っている者は生涯、出世栄達なし。
・少食の者は、死病の苦しみや長患いがない。
と水野南北は述べています。とても耳が痛い人も多いのではないでしょうか。
幸運を願う人、痩せたいという願望が強い人、ファースティングや少食は、なんともっと別の良いことがあるのです。南北は、「毎日の食を厳重に節制する」ことを勧めています。「望みを成し遂げるまでは、美食を慎み、仕事をなんとなくするのではなく楽しみに変えなさい」と勧めているのです。そうすれば、「自然に成功しますよ」と!!
さらに、彼は、「吉」「凶」は食できまるとまで言い切っています。
持って生まれた人相だけが、運勢を決めるのではない。それよりももっと大切なものは、「食生活」であると強調しています。
・食事の量が少ない者は、人相が不吉であっても、運勢は「吉」。恵まれた人生を送り早死しない。特に晩年は「吉」。
・常に大食・暴食のもの、たとえ人相が良くても、運勢は一定しない。もしその人が貧乏であれば、ますます困窮し、財産家であっても、家を傾ける。
・貧乏人で美食する者は、働いても働いても楽にならず、一生苦労する。
・いつも自分の生活水準よりも低い程度の粗食をしている者は、人相が貧相であっても、いずれは財産を形成して長寿を得る。晩年楽になる。
この教えは、「食」を節すればするほど、人生は富み、「食」をおごればおごるほど、人生は貧する。
「心の貧しい者は幸い・・悲しむ者は幸い・・・柔和な者は幸い・・・あわれみ深い者は幸い・・・」
と説いたキリストの教えに通じるものがあるようです。
このように、天命和尚や南北の教えは、具体的で、かつ分かりやすいです。大いに参考にして生きていきたいものです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
