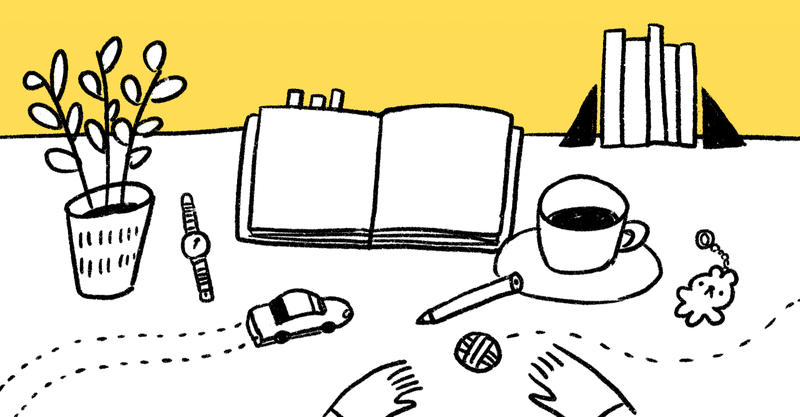
文章の「癖」について
いろいろな顔の人がいるように、文体にもいろいろある。文章の構築の仕方とか、よく使う言い回しとか、人それぞれ結構特徴が出るものです。
編集の仕事に就いて初めて記事を担当させてもらったときのこと。すごい気合を入れて、何度も見直して、よっしゃ名作じゃんワハハ天才かもしれん、などと思いながら提出したら、チェックしてくれた社長に言われました。
「小説書いてんじゃないんだからこれはないわ」
ちび〇子ちゃんとかで見る「ガーーン」が後ろに見えてたと思うあのとき。がんばったのに……としょんぼりする私に社長はいろいろ教えてくれました。
媒体には媒体ごとの、適した文章というものがあること。
例えば新聞は、情緒や感情を排した文章でなくてはなりません。反対に、情緒や感情を盛り込まないと小説にはならない。自己啓発は語り掛けたほうが効果的だし、ビジネス書や経済書の文章はなるべく完結に簡素に内容を伝え、対談やインタビューの記事なら口語体が混ざったほうが親近感もわくし読みやすい。
編集するときも、著者らしさを残したまま、想定読者層に向けて文章を整えなくてはいけません。たとえば、20代向けの生き方を説く本で「さはさりながら」とか出てきても戸惑うだろうし、逆にお堅い文章の先生の本で「ぶっちゃけ」とか入れてはいけない。ちょっとメリハリついておもしろいかもしれんけど。
そしてアドバイスを受け、なるほど!と思って反省して書き直し、今度こそ!と提出した私は、
「これじゃ論文だよ……両極端かよ……」
と呆れられたのでした。
それからしばらく時が経って、書籍の編集をしていたときのこと。少しわかりづらいなと思った部分をいくつか書き換えて著者の先生にチェックをお願いしていました。
赤入れた原稿渡すついでにご飯食べにおいでよ、と先生に誘っていただき、いそいそとお宅へお邪魔し、厚かましくもおいしい手料理をご馳走になっていると、先生が原稿を出してきました。なぜか半笑いで。
「Aさん、本当に私の娘くらいの年?サバ読んでるでしょ」
2つ3つサバ読むことはありますけど先生には嘘ついてませんよ!なんでですか!と慌てて尋ねる私。
「だって直してくれた言い回しが昭和すぎるwwwこの人私より年上なんじゃない?って思っちゃったwww」
そんなことある???
ぜんぜん自覚がなかったのでびっくりしすぎてごはんも1杯しかおかわりできませんでした(したんかい)。いやきれいな文章で私は好き、と最終的には褒めてくださったんですけど……。そのあと反省してまたちょっと直しましたけど……。
まあ文章なんて最終的に好みなので、よほど文法的におかしいとか意味が間違っているとかでない限りなんでもいいっちゃいいんですよね。
編集としてはあんまり言葉にこだわりを持ちすぎるのもよろしくないのかもしれないなあと思わされた出来事でした。
精進します。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
