
#0 これまでの活動
編境文学読書会は、東京のはずれ足立区の北千住にて、文学を読み合う読書会です。その場所にふさわしく、どこか辺境的で一人ではあまり手に取ることのない名作を課題図書に選んでいます。一作品を読んだら、その作品からインスピレーションをうけ次の作品を決めていくというスタイルで選書してきました。これでまで六回分の選書について紹介していきます。

一冊目は西村賢太の『苦役列車』。記念すべき最初の一冊は、足立区北千住の場末感感じさせる作品がふさわしいと考えました。日々の生活の生々しさを映し出した本作に議論も多様に飛び交い、読書会の始まりを告げるに足る内容となりました。その後の懇親会では、北千住の飲み屋街にくりだし、飲食街の喧騒の中で作品世界について改めて語り合いました。

二冊目はジョルジュ・バタイユの『眼球譚』です。『苦役列車』にあったエロス、暴力、酩酊、自由といった要素を極限まで振り切った作品を読まなくては、これ以降の読書会が退屈なものになっていくと考え、あえて本書を選書しました。結果的には、人間苦と歓喜の根源に向き合った崇高なる傑作との出会い、またそこから湧き起こる議論が、読書会に一つの基盤を与えてくれました。
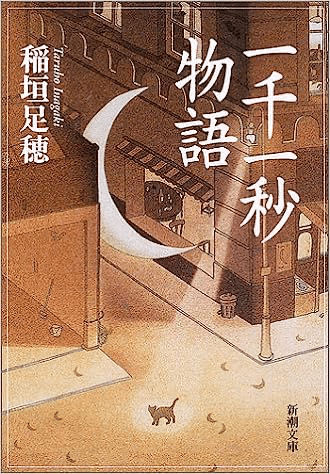
バタイユのエロスを宇宙的感覚に昇華させるというアイディアから、三冊目は稲垣足穂の『一千一秒物語』に決まりました。「お月様をポケットに入れて」現実世界の裏側を歩いていくような足穂の文体から、読書会のコンセプトに浮遊感という新たな要素が加わりました。この一冊によって、その後の三冊の選書の方向性が決まったように思います。

四冊目は、詩を読みたいとの参加者の声から、西脇順三郎の『ambarvalia /旅人かへらず』を読みました。足穂と同時代人である西脇は、明治、大正、昭和の三つの時代をまたぎ、第二次世界大戦を生きた人です。昭和初期の詩壇に宝石のように輝く『ambarvalia』、寂びた情景に敗戦の悲しみが映る『旅人かへらず』。二つの作品について語り合うことは、近代日本文学の路地裏を覗くかのようでした。

西脇の豊穣な詩的言語とギリシア・ローマ的神々の世界をうけ、より神話的な方向に舵を切ったのが五冊目のロード・ダンセイニ『ペガーナの神々』です。アイルランドの貴族ダンセイニの描いた本作は、ギリシア・ローマ以前の異教徒(ペガーナ)の神々の世界の創世神話です。ファンタジー文学にも大きな影響を与えた著者の神話的想像力は、壮大な広がりをもって読者を太古の世界へといざないます。ここでも稲垣足穂が、ダンセイニの日本への紹介者として登場しました。

六冊目はアーシュラ・K・ル=グウィンの『ゲド戦記』です。現代におけるファンタジー文学のあり方を問う会となりました。今の日本ではファンタジーはアニメの映像表現として見ることが多いですが、あえて児童文学として読み合うことで、幼少期の文学体験や映像体験に遡る議論となりました。

七作目は、リチャード・ブローディガン『西瓜糖の日々』(河出文庫)を読みます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
