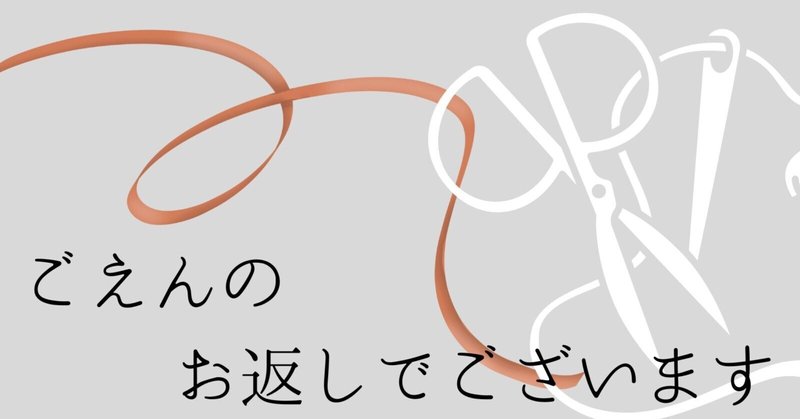
「ごえんのお返しでございます」2話 紅薔薇、白百合①
曇天の梅雨空は、低く感じる。頭のすぐ上に、分厚い雲が重くのしかかってきて、あまり好きではなかった。
今にも雨が降りそうな窓の外を、ぼんやりと眺めながら、先日の古典の授業のことを思い出していた。
古語の「眺む」は今と違って、「物思いにふける」という意味だ。そして「長雨」との掛詞にも使われる。
ぽつり、と最初の雨の一粒が窓を叩き、僕を現実に引き戻した。
デスクの前に座る白衣の男性――冴木(さえき)医師は、「雨が降ってきたね」と、微笑んだ。
彼の前に出ると、僕はなぜだか緊張してしまう。ふさふさとひげを蓄えた顔は、父親の神経質な頬のラインとは、まるで異なっている。柔和な微笑は患者をリラックスさせる効果があるはずで、実際、彼は名医であるらしい。
けれど、僕はいつも彼に対しては、必要以上に言葉を選んでしまう。常に緊張を強いられている。
「紡くん。最近、変わりはありませんか?」
警戒心はとけない。僕の声には、自然と険が宿る。
「それは、姉さんですか、僕ですか?」
冴木は、精神科の医者だ。本当は姉の主治医なのだが、姉は部屋から一切出てくることがないため、代わりに僕が通い、姉の様子を報告し、必要に応じて薬を処方してもらっている。
本当なら、親が来るべきだと思う。けれど、スマホの通話のみとはいえ、唯一つながっているのは、僕だ。
姉がいつか、自分から外に出たいと思う日まで、見守るのが僕の役目だ。
市内で一番大きい総合病院は、バスに乗らなければならないし、予約時間になっても待たされることも多いが、使命感から、月に二度の通院をこなしていた。
冴木の診察室は、ぱっと見は病院だということを忘れさせるつくりになっている。
白い壁、床の素材は他の場所と変わらないのだが、淡い色で描かれた花畑の絵が飾ってあったり、季節に応じた飾り物がしてあったりする。
梅雨真っ最中の現在は、窓枠にてるてる坊主がつるされているし、折り紙のあじさいが、先生越しに見える。
テディベアのような風貌にふさわしい、太さのある指は、とても器用には思えないのだが、あじさいは皺ひとつなく、丁寧に折られている。
看護師が作ったとばかり思っていたが、以前、何かの折にふと、「今回は苦労した」と語っていたから、彼のお手製だ。
医者になる前に、ひととおりの科で研修を受けるらしいので、意外と外科にも適性があったりするのかもしれない。
冴木は僕の目を見て、「どちらも」と言った。姉の主治医ならば、姉のことだけを気にしていればいいのに、彼は僕自身の話も積極的に聞こうとする。
『君は気づいていないかもしれないけれどね、お姉さんのこと、すべてを君が背負っている状況だろう? 知らず知らず、心に疲れが溜まっていても、おかしくはないんだよ』
医者は、特に精神科医は、口が上手い。説得力がある。
確かに、姉のこれからの人生すべてが、僕のこのか弱い肩にのしかかっていると思うと、急に重く感じた。
親は老いるし、今のこの時点で、姉に対して何もしてくれない。将来的に変わってくれるという、希望的観測を抱くことはできない。
「別に、姉さんはいつもと変わりありません」
気まぐれに電話がかかってくるのは、多いときでも週に一度かそのくらい。平気で一ヶ月、連絡が来ないこともある。こちらから電話をかけても、繋がらないことも多い。
通話中の電子音が聞こえるから、僕以外にも、連絡する先があるのだということにホッとしている。
姉の交友関係は、いまいちわからない。引きこもり以前でも、友人を家に連れてきたことはほとんどない。引きこもり後は、ネットを駆使して、知り合いを爆増させているかもしれない。
「この間かかってきたのは、ええと……事件のちょっと前ですね」
声が自然と小さくなってしまった。
篤久もまた、この病院に入院している。身体の傷は癒えたけれど、心の回復には時間がかかるらしい。病室へ行っても、刺激を与えることになるからと、面会謝絶が続いている。
家族ですら、長時間は病室にいられない。糸をよこせ、赤い糸だと暴れ始めるそうだ。
この後、一応病室には寄るつもりだった。会えないことは百も承知だが、それでも僕は、他の連中と同じ薄情者にはなりたくなかった。
決して優しいのではない。
赤い糸に縛られていたとはいえ、一時的にでも付き合っていた人間のことを、美希は最初から、いなかった者として扱っている。
彼女の隣の席は、「俺、目が悪いんでぇ」というあからさまな嘘の理由によって、渡瀬が埋めてしまった。すでに篤久の戻る席は、あの教室にはない。担任も、もはや篤久のことを生徒と思っていないだろう。
せめて僕くらいは、彼のことを待っていてやりたいのだ。愛想を尽かしてしまうほど、馬鹿なことをしでかしたけれど、彼が悪いのではない。
悪いのは、きっと。
「そうか。篤久くんの……ちなみに、結さんとは何を話したのかな?」
冴木は篤久の主治医でもある。この総合病院の精神科には、医師が四人いる。冴木は僕のよしみで、難しい状態の篤久のことも担当してくれることになった。ありがたいことだけれど、病気でもない僕のことまで、あれこれと聞いてくるのは、ちょっと嫌だった。
「別に。篤久のやつが調子乗っててちょっとむかつくって、愚痴を聞いてくれていただけです」
ハーレム云々の話は、伏せておいた。やや過激ともいえる姉の思考を、大人相手におおっぴらに話す気にはなれなかった。そのくらいの分別はある。
冴木は、ひげを弄る。僕はそんな彼を見ながら、そろそろ帰りたいなあ、と、ぼんやり窓の外を眺めた。
緑が濃く、水滴を弾く。ここは二階だから見えないが、下にはあじさいが、折り紙の平面的な色とは違う、複雑な色彩で咲いている。
「それじゃあ、君自身に何か変わったことがあった……かな?」
精神科医は、顔色を読むのが仕事だった。問いかけの途中から変わった僕の表情をもとに、確信を深めて尋ねてくるのが、気に入らない。
口を噤むのも手だったが、それも彼の思惑通りで、癪な気がする。むっとしながら、「バイト、始めました」と早口で言う。
「うん?」
絶対に聞こえているはずなのに、冴木はとぼけた様子で聞き返してきた。
「バイト! 始めました!」
声を張った僕に、冴木は満足そうだった。電子カルテに何事かを記入しながら、朴訥な田舎の農夫を思わせる声で、優しく語りかけてくる。
「そうだね。いいことだよ。お姉さん思いなのは君の長所だが、他にも交流を深めていくことで、見えてくる真実もあるんだから」
?
何を言っているのか、よくわからなかった。それに、交流する相手が「アレ」では、この医師も逆に心配になるのではないか。
まあ別に、僕は患者でもなんでもないのだから、詳しく答える義務はない。
それ以上話すことはなく、冴木は「いつもの薬を出しておくよ。君の分のビタミン剤も」と言った。
「別に、僕のはいらないです」
と言えば、冴木は少し困った顔をして、「そんな血色の悪い顔をして、何を言うんだい」と言った。鏡がないため、冴木の表情から自分の体調を読むしかないわけだが、僕にはそんな芸当はできない。
僕は医者に、特に精神科医には、向いていないらしい。
なりたいと思ったこともないけれど。
診察室を出て、支払いを済ませる。それからまっすぐに篤久の病室を目指そうとしたところで、ふと、見舞いの品のひとつも持ってきていないことに気がついた。
いかにも自分の(姉の)診察の「ついで」感が出てしまって、あまりよくない。
顔を合わせることはないとはいえ、手土産の有無によって、印象は大きく変わる。誰の、といえばナースステーションに詰めている看護師の、である。
僕は売店に行くことにした。この辺りでは、一番大きな総合病院である。見舞い客が時間を潰すことのできる食堂やカフェもあれば、売店も入っている。
大手コンビニの店舗が入っているが、街中の店とはちがい、規模も小さければ、店員は制服を着ていない。その一角だけ、病院の中とも外とも異なる空間が、できあがっている。
棚の前にやってきた僕のことを、店員は一瞥しただけで、「いらっしゃいませ」の一言もなかった。場所柄、大声を出せないのはわかるが、やっぱり独特だった。
このコンビニが入っている西棟は、精神科以外には、整形外科や皮膚科などの診療科が入っているため、食品の数もそこそこある。
これが東棟だと、食事に制限がある内科・外科の患者が、勝手に買い食いしないように、という配慮で、ほとんど入っていなかったりする。
僕は、篤久が毎週買っていたジャンプを買う。いつか正気に戻ったときに、「ワンピースが終わっている!?」なんてことにならないように。ハンターハンターは大丈夫だろうけど。
会計を済ませて、病室へ。入院患者がいるのは、三階から上だ。部屋の番号だけは、篤久の母に聞いてある。四階の、四〇一号室。
精神科の病室が並ぶ廊下は、寒々しく感じた。
なぜだろう、と考えてわかった。
精神科は立って歩いている人が少ない。看護師や医者くらいのものだった。
内科の病室なんて、元気な入院患者という矛盾めいた存在が、雑談をしたり、歩き回ったりしているというのに。
四○一号室の前で、僕は立ち尽くす。面会謝絶、と無機質に印刷された用紙をじっと見つめ、それから扉に耳をくっつけてみた。
うめき声は聞こえなかった。
僕はすぐに諦めて、ナースステーションにジャンプを預けた。名前を聞かれたので、「ツムグ、と言ってくれたらあいつはわかります」とだけ言付けて、僕は一礼して、エレベーターへと向かった。
一階にたどり着いたとき、僕はふと、喉の渇きを覚えた。さっき一緒に買えばよかったな、と売店へ向かう。自動販売機でもいいのだが、紙パックばかりで、この場で飲んでから帰らなければならない。
冷蔵の棚の中に、びっしりと詰められているのは麦茶だった。なるほど、ノンカフェインで、患者の多くが口にできる。回転もいいのだろう。実際、僕が手を伸ばす前に、パジャマ姿の女性が、扉を開けた。
「あれ?」
病院といえば老人。しかし、麦茶を買おうとしている彼女の髪の毛はふさふさ、艶のある黒だった。若い女性、僕と同年代だろう。彼女の「お願いします」という声に、僕は聞き覚えがあった。
「……濱屋さん?」
学校では髪の毛を結んだり巻いたりしているから、ぴょこりと頭の上で跳ねる寝癖? がついた髪型には違和感があるが、その下にくっついている顔は、愛らしく整っていて、どう見ても美希だった。
声をかけた僕に、彼女は普通の顔をして、振り向いた。
同じクラス、だけじゃない。僕は篤久の親友で、彼女は篤久の元カノ。決してポジティブなものではないが、顔と名前が一致する、というレベルの関係ではない。
なのに、美希は不思議そうな顔をして、首を傾げた。会釈に見えなくもないが、ただ単純に、困惑しているだけの顔。
そのまま彼女は、僕と言葉を交わすことをせず、無言で売店を、パタパタとスリッパの音を立てて去って行った。
残された僕は、ただ呆然。
少々やっかいな事情、わだかまりをお互いに抱えているとはいえ、無視をされるのは、気分がよくない。声をかけて損した。
僕は彼女のパジャマの後ろ姿を見送ることしかできなかった。
……パジャマ?
彼女は入院しているのか? 学校では、特に普通だったように思うのだが……。
美希が病院にいた事情に混乱していた僕は、買おうと思っていた麦茶を忘れ、帰路についた。バスに乗ってから、再び喉の渇きを思い出したけれど、もはや家の最寄りに着くまでは、どうしようもない。
いただいたサポートで自分の知識や感性を磨くべく、他の方のnoteを購入したり、本を読んだりいろんな体験をしたいです。食べ物には使わないことをここに宣言します。

