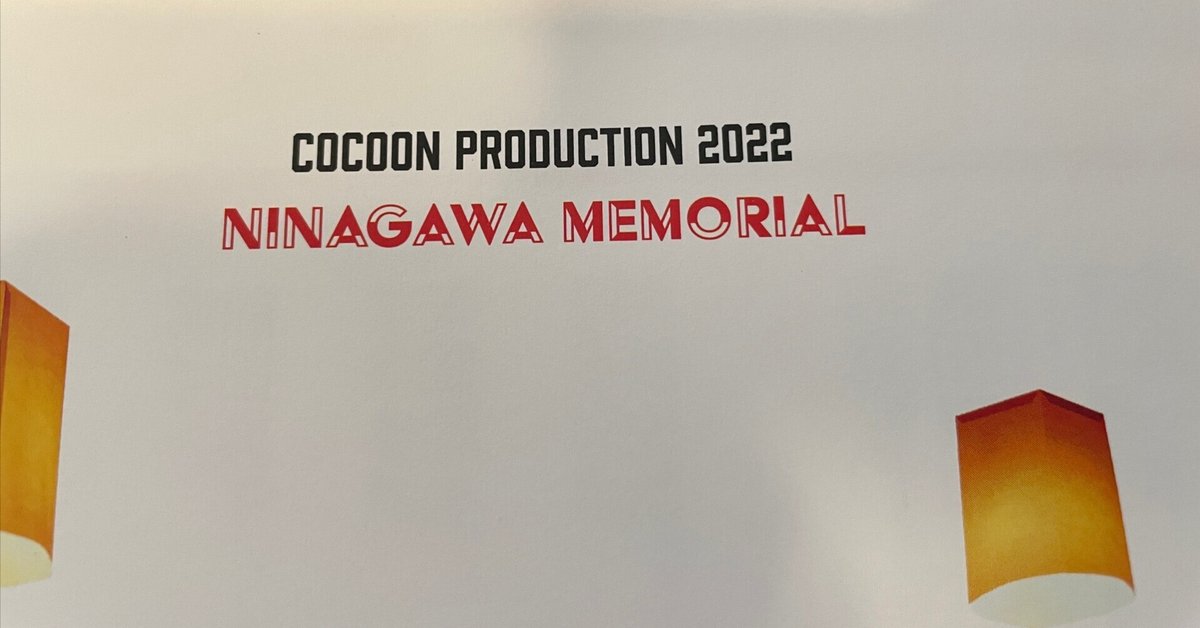
あの蜷川幸雄でさえ、野田秀樹戯曲に手こずり、のたうち回った『パンドラの鐘』をめぐって。七枚。
野田秀樹の戯曲を他の演出家が上演したとき成功例がほとんどないのはなぜか。
長年、疑問に思ってきたけれども、明解に言葉にできずに時間ばかりが過ぎていった。
シアターコクーンで上演されている『パンドラの鐘』(杉原邦生演出)を観て、いくつか考えることがあったので、書き留めておく。はじめに断っておきたいのは、この原稿は、杉原演出についての劇評ではない。また、その演出を貶めるために書くのではない。
今回の上演は、演出家蜷川幸雄の七回忌を祈念したNINAGAWA MEMORIALとされているので、初演当時のことを思い出している。
私は長年、野田秀樹の作品を見続けてきた。初期から現在まで、ほぼすべての作品について劇評を書いてきた。
そのなかでも、『パンドラの鐘』は、抜きんでた傑作であり、野田戯曲の特徴が明解に現れている。この構造については、『白い雲』(『野田秀樹の演劇』二○一四年 河出書房新社所収)に書いたので、読んでいただくとうれしい。
『パンドラの鐘』の初演は、一九九九年。蜷川幸雄演出と野田本人が演出した舞台が、ほぼ同時期に舞台に乗った。先に述べた『白い雲』は、雑誌「文學界」が初出だけれど、私の原稿は、ほぼすべて野田演出の解読に終始している。唯一、原稿の終わりに、こう書いている。
「当然のことながら、蜷川演出は、野田演出とは、演技スタイルにおいても、全く方向を異にしているが、女性性に希望を託す劇作の核心は、大竹の力量によって明確に伝わってきた。また、野田作品がリアリズムの演出手法によって、近代劇としても上演できると証明してみせたことで大きな意味を持った」
今、こうして書き写していても、歯切れのよくない評言だと思う。
もっとも重要なミズヲとヒメ女の配役を思い返してみると、野田版では、堤真一と天海祐希、蜷川版では、大竹しのぶと勝村政信である。いずれも劣らぬ当代の俳優だけれども、決定的に異なるのは、身分の違いが明確に示せるかどうかであった。ミズヲは血の滲むような幼児体験を持った葬儀をなりわいとする男性である。一方、ヒメ女は、皇室に生まれて人を疑うことなく、他者に君臨することを宿命づけられた女性である。この生まれと育ちの決定的な違いが、配役によって語られなければならなかった。
年々、演劇を観るのが楽しくなってきました。20代から30代のときの感触が戻ってきたようが気がします。これからは、小劇場からミュージカル、歌舞伎まで、ジャンルにこだわらず、よい舞台を紹介していきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。

