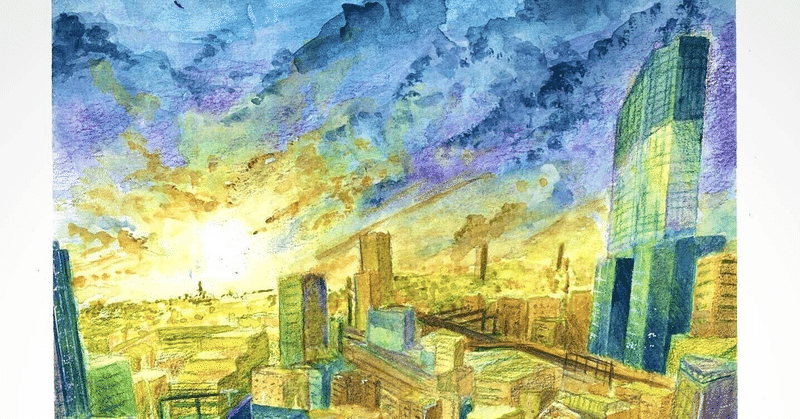
「リアル」と「リアリティ」〜それは現実か、それとも幻想か〜
ある炎上…絵じゃん
立て続けに二つのイラストが炎上した。ひとつは、八時ななころ(@nanakoro81)氏が「だんだんオタクに染まっていくギャル」と題した作品(図1)であり、二つ目が『生徒会にも穴がある!』公式(@seitokainoana)氏のイラスト「賞味期限が切れてない食材を探して深夜冷蔵庫を漁るアラサー女性教師の図」(図2)だ。


正確には炎上と言うべきでは無いだろう。少なくとも個人的に両者のイラストは素敵なものだと思うし、なんら批判に値する点はない。またTwitterの反応を見る限りでも、好意的なコメントの方が多い。では、何故このイラストが炎上に近い状況にあるのか。それは、「オタクに優しいギャルなどいない」、「これはギャルではない」、「洗濯バサミを髪留めにする女などいない」、「ブラホックを外したままの女はいない」など、これらイラストに描かれているような女性が、現実にはいないという点を指摘する批判がにわかに発生したからだ。
とりあえず言いたい。「絵じゃん」
存在しないもの(そもそも存在自体否定しきれないもの)をイラストにすることは、なんら批評にたる理由とはなり得ない。だって絵じゃん。「これこそがギャルです!」「アラサー女性教師の真の姿です!」と、作者らが主張したと言うならばともかく。
しかし、一部の者たちにとってはそうでは無いらしい。仮にイラストのようなシチュエーションは存在しなかったとして、それのどこか許せないのか不思議でならない程の攻撃的批判が今なお噴出している。作者を謎の童貞認定までする有様だ。ここまで来るともう、それは批評ではなくただの悪口雑言である。そこからわかるのは、彼ら彼女らは、作品単体が許せないのは勿論だが、それ以上にそれを生産・消費する、広く言えば「オタク」への嫌悪を発露したくてしようがないということであろう。作品への批判が高まって、気がつけば作者や、それを擁護するオタク批判に向いているという延焼。このような事態は最早珍しくない。少なくとも僕のこの記事を読んで頂いた人たちが思い浮かべる作品はひとつや二つじゃ済まないだろう。
しかし、今回の主題はそこにない。それは、題の通り「リアル」と「リアリティ」の違いにある。
ある批判…リアルとリアリティ
図2のイラストが炎上し、様々な批判や異議申し立てがなされる中で、あるツイートが僕の目を引いた。とはいえ、それはありきたりな内容である。

これは、図2のようなシチュエーションは現実にないとする批判者の指摘に対しての「表現の自由戦士」による「それ(イラスト)は絵(フィクション)である(よって現実にあるかは批判に値しない)」との反論に、また反論して岸辺露伴の言葉を引用したツイートである。
ここで彼が言いたいのは、「擁護者はイラストを「絵じゃん(リアルの話じゃない)」と擁護するが、岸辺露伴(荒木飛呂彦)が言うように良い作品にはリアリティが必要である。逆にリアリティに欠くそのイラストはダメな作品であって、よってイラスト擁護者はダメな作品を肯定することになるがいいのかい?」ということであろう。彼は、擁護=いい作品と認めることと、リアルでない=ダメな作品を擁護することを両立させる、「表現の自由戦士」のダブルスタンダードを皮肉っているのだ。
なるほど、いい皮肉のように思える。特に『ジョジョ』はオタクにとって教典のひとつに相応しい作品であり、中でも岸辺露伴の人気は高い。共によい作品であるイラストと『ジョジョ』。いずれかを否定することは、正にオタクにとってのトロッコ問題に他ならない。
ただし、

何故(この皮肉が)不可能なのか。それは、高度の柔軟性(以下略)氏が、おそらく「リアル」と「リアリティ」を混同して用いているからに他ならない。
「リアリティ」
我々が得てして何となく使うこの言葉は、実は曖昧なものである。
まずは僕を含めた大学生御用達Wikipediaで調べてみる。が、「リアリティ」ではヒットすることがない。それは「現実(Realty)」としてのみ現れるのだ。少し見ていくうちに、ようやく我々が思う所の意味をgoo辞書で発見した。曰く、
リアリティー【reality】 の解説
現実感。真実性。迫真性。レアリテ。「描写に―がない」
現実感、真実性、迫真性…やはり、曖昧である。
だがここで、ひとつ明らかになった。「リアル」とは言うまでもなく現実であり現実にのみある絶対的なものである一方、「リアリティ」は感や性の言葉に表れるように、それは誰かしらの感性によって読み取られる実体無きものだ。
振り返れば我々は、どのような時に「リアリティ」の言葉を使うだろうか。例えば、ホラー映画を観た時に「リアルだ」とはあまり言わないだろう。(仮に使われるにせよ、それは、例えば「バイオハザード」などのホラーを再現したUSJのゾンビのなりきりや展示など現物に対してである。あるいは、その時の「リアルで」は「リアルのようだ(リアルに迫る)」等、本来的「リアル」とは少し違う意味で用いられる。)なぜなら、ホラーな状況というのは現実にない(そう信じたい)からだ。だから、「リアリティに溢れる映像だ」と言う。「(ないけれど、)ありそうだ」と。絶対的にあるもの──例えばある風景を前にして「リアリティあるね」とは言わない。その言葉が使われる時、「リアリティ」に対する「リアル」は目前になく、「リアル」を効率的に想起させる、言わばリアリティ発生装置たる表象があるだけだ。
「表現」とリアリティ
「リアル」と「リアリティ」についての議論はかなり活発になされている。これは哲学の分野にあたるのだろうか。あるいは、文化人類学的なものにあたるのか。てんで素人の僕には測り兼ねる。思うままに書いてきたが、厳密にそれを語るにはあまりに知識が足らなすぎるし、その時間もない。ただ、僕の専門(とはいっても、学部レベルだが)は表現文化だ。表現に関わる以上、「リアル」と「リアリティ」の問題は避けて通れない。そこで、「表現」の立場からこの問題について僕なりの考察をしていきたい。
少し前の話になるが、卒業論文に向けての手慣らしとして、ミニ卒論なる論文を書かされた。テーマは自由で、字数は8000字以上の、学部生にとっては重重案件のレポートだ。執筆に取り掛かる前には自分の論文のアブストラクトを発表しなければならない。そこで、ある学生の発表に、僕が隠れて敬愛するM教授が指摘した。テーマは忘れてしまったが、彼の発表に「リアリティ」の言葉が用いれられたのだが、そこに対する学生にとっては肝が冷えるような指摘だ。
「そのリアリティって、どういう意味?」
問われた学生は、戸惑いながらも「現実っぽい」とかそんなことを応えた。
だがそれで教授は満足しない。いくつかの質問を重ねた後、言う。「リアリティ」はじめ曖昧な言葉を使う時、その意味を定義しなければならないと。
当然これは論文執筆の際に気を付けるべき話であって、普段「リアリティ」の定義を厳密に考えつつ使用しなければならないということを意味しない。だが、議論においてその曖昧さが理解の相違を生む可能性は大いにある。そのいい例が今回の炎上とそれに伴う議論だ。
では、表現における「リアリティ」とはいったい何か。
それについて学問的に論じるならば、数冊の書籍と幾らかの論文、あとは数万字の紙幅が要るだろう。当然そのような時間はなく、またやる気も、無論能力もない。だが先述のように僕はこの2年表現について学んできた。「リアリティ」について考える中で直接得た考えや、作品に触れて浮かんだ実感もある。それらをここに記すことで自分の中にありつつ捉えどころのなかった思考をひとつの形にしたいと思う。また、これを元にイラスト炎上問題を考えることを通じ、かの炎上がいかに無駄なものであるかを今一度可視化したい。
「リアル」と「リアリティ」、その言葉が使われる時、それぞれの対象は違う。これは先に述べた。前者は現実にあるものそのものに、後者は現実にない、或いは現実に存在しても現前にはない表象に向けられる言葉だ。そして前者は絶対的に存在するもので、後者はあくまでそれを感じ取る主体がいる相対的なものである。ある者にとってはそれはリアリティのないもので、またある者にとってはリアリティに溢れたものというのは存在する。つまり後者に関しては、「リアリティ」の根源たる「リアル」が必ずしも必要ない。我々は全く存在しないものに対して言いきれぬ「現実らしさ」を抱くことが出来る。
それは何故か、考えるに、それは人間には想像力があるからという他ない。宇宙人は(おそらく)いない。しかし、『メン・イン・ブラック』の奇妙な宇宙人は、それは虚構の存在ではあるのだが、リアリティを感じさせる。ここで宇宙人は、一般的に「ありそうな」宇宙人要素の組み立てにより現実感をもって生まれている。人のような知性らしきものを宿しながら、人とは違う。頭が大きかったり、触覚が生えていたり…そういった宇宙人らしさが、個人の想定する「宇宙人感」と照らし合わされて(スクリーンに)現前する奇妙な生物に(架空の)宇宙人としてのリアリティを感じるのだ。「MIB」の2作目には、見た目がパグ犬の宇宙人フランクが登場する。しかしそれは全く宇宙人らしくない。そこで、フランクは宇宙人らしき要素、ここでは言葉を話すことが加えられることによって宇宙人としての説得力・リアリティが持たせられる。奇妙な風貌、異様な力、など、無いものに対してリアリティをもたらすのは「らしさ」の要素だ。それが個人のイメージを刺激し、個人にリアリティを生む。先にホラー映画を例として「リアリティ発生装置」といった。作品に散りばめられた「らしさ」要素こそが「リアリティ発生装置」であり、それを感受する「リアリティレセプター」こそがリアリティを生成しているのだ。「レセプター」の正体は何となくわかると思う。それは、個人の趣味や知識、体験…言い換えれば知見。それが豊かであればある程、リアリティの幅も大きくなろう。

さて、図2は、「賞味期限が切れてない食材を探して深夜冷蔵庫を漁るアラサー女性教師」をイラストで表現したものだ。
ここでまた考えたい。表現とは何だろう。再びWeblioをひいてみる。
[名](スル)心理的、感情的、精神的などの内面的なものを、外面的、感性的形象として客観化すること。また、その客観的形象としての、表情・身振り・言語・記号・造形物など。「情感を—する」「全身で—する」
[補説] representationおよびexpressionの訳語。
内面的なものを他者にも捉えられるようにすること。それが表現である。とすると図2は、「(賞味期限の…)女性教師」像という作者の内面にあるイメージを、イラストで可視化した表現物ということになる。
図2に関して、「このような女性は(リアルに)いない」という批判ががなされていることは既に述べた。なるほど、女性の実態を知らない僕にその真偽はわからない。ある女性にとっても、彼女が全ての「女性」を知るわけがないのだから、その批判は見当違いも甚だしいと言わざるを得ないが、それは置いておく。だが、個人の水準で見れば、このような格好をする女性がいないとは言い切れない。批判へのカウンターとしてあのシチュエーションを再現した写真をTwitterに上げる者がいる程だ。
しかし、このような女性が「いる」「いない」の議論は全くもって無意味である。何度でも言うように、「そのような女性」はあくまでイメージの具現であり、仮に作者が「これがリアルな女性です」とでも宣言しない限り、そのイラストの女性は2次元の存在である。当然女性一般を代表しない。
ではそのようなイメージをイラストとして表現するに際して、作者はどうするか。僕はイラストレーターではないが、細々と小説を書く。その経験からすれば、イメージを表現するためにどのような要素が必要かを考えるだろう。どうすれば個人的なイメージをわかりやすく伝えられるか。例えばブタを描くこうとする時、我々は丸い鼻、捻れた尻尾などを思い浮かべるだろう。それらから描いたブタの絵は、衆人がこれはブタであると理解されつつも、しかし決してリアルなブタではない。
そこで自分の感受性のみを参考にしていれば、他者である作品の鑑賞者にはわかりにくいことがある。それはレベルの低いコスプレのようなものだ。大雑把すぎて、或いは細かすぎて何なのかわからないという問題だ。それは作者の独りよがりな作品となる。
そこで、作者はイメージを効果的に表わす要素をもって表現する。現実に本当にある/ないに関わらず、少なくとも「ありそうな」要素を組み込み事によって鑑賞者のレセプターを刺激し、リアリティを感じさせるのである。図2で言うならば、「洗濯バサミの髪留め」や「ホックの外れたブラ」などがそれに当たる。それらはリアルにないかもしれない。しかし、「女性教師」のズボラな女性というシチュエーションとの親和性は高そうだ。加えて、やや誇張された表現であることがポイントとなっている。ここで2つの誇張された要素は「女性教師」のズボラさをわかりやすく提示すると共に、エロティシズムという新たな魅力を加えることに成功している。
これはマンガやアニメなどでいう「デフォルメ」に近しい。必ずしも「リアル」に表すことは表現として優れていることを担保しない。むしろ、デフォルメされているからこその魅力があることは共有されている感覚だと思う。
そして、ここにこそ僕の思う「リアル」ではない「リアリティ」の魅力が詰まっていると思うのだ。つまり、「リアル」には出せない「現実らしさ」、そして「リアル」以上の魅力、それらを包含するのが「リアリティ」だ。
僕なりに定義したい。「リアリティ」とは、「リアルとは異なるが、それ以上に現実感と魅力を与えるもの」だと。
手塚治虫のデフォルメされた絵を思い出して欲しい。あの、現代マンガのような写実的絵とはかけ離れた簡略的な絵は、しかしそれらが人間らしさを描いた物語、構図などと組み合わさることで、リアリティを伴って普遍的なメッセージ性を持つ。
アニメーションを考える。モデルが白人だろうが日本人だろうがどうでもいいが、あの現実からすると美麗なキャラクターは、ストーリーを経てさらなるリアリティを獲得してゆく。
写真に至ってすら同様だ。いつだが見た写真──衰弱した少女が死肉となるのを待つ猛禽類の様子を捉えた1枚。敢えて選び取られたその景色、これはその景色以上の意味を、「貧しさ」のメッセージをより克明に、リアリティをもって訴えかける。
表現というものは恣意的だ。それはただそこにある「リアル」とは異なる。そして、恣意的だからこそ演出された魅力が加わってくるのである。パウル・クレーという画家がかつて言ったという。
「芸術は、見えるものを再現するのではない。芸術は、見えるようにするのだ」
これはなにも見えない「イメージ」を視覚化するものが芸術と言っただけではないだろう。芸術は作者の思考や経験、そして超現実とでもいうべきリアリティを視覚化するものだ。
さらに加えると、映画、小説、マンガ…表現において、鑑賞者の想像力が介入する余地は、その媒体により異なる。
特に映画とマンガはよく比較される。あるマンガを見て、「まるで映画のようだ」とする感想を聞いたことがあるだろう。マンガ論において「映画とマンガ」のテーマはかなり重要な地位を占めている。映画の撮影法をマンガのコマに活かした「映画的手法」なる言葉がある程だ。そしてこのような映画的手法を日本マンガに導入した人こそが手塚治虫であり、そのことが「マンガの神様」と彼が呼ばれる所以のひとつである。(なおこの「手塚神話」には否定的な言説も多い)
その言説空間の中では当然、映画とマンガというメディアの違いが語られる。端的に言うと、両者の違いは鑑賞者の態度にある。即ち、映画は消極的、マンガは積極的鑑賞が求められる、或いは強いられるといってもいい。
映画は、基本的に一方通行である。今こそ一時停止や巻き戻し、倍速視聴も可能だが、映画館で見る映画体験において、その時間に鑑賞者の及ぶ余地はない。ただ流れる時間と共に物語が提示され、その速度で鑑賞者は映画を楽しむ。そのようなメディアの求める態度が消極的と表現される。
一方で、マンガにおいては積極的鑑賞が可能となる。なぜなら、マンガにおける時間は読者に委ねられるからだ。マンガの一コマに、読者は好きなだけ時間をかけることが出来る。このことは「愛の時間」と呼ばれるのだが、これによってマンガはより個人的な時間を持つこととなる。言い換えれば、読者の積極的な読みがマンガを策定するのだ。
消極的鑑賞と積極的鑑賞。どちらがより想像的であるかは言うまでもないだろう。考えて見てほしい。1ページせいぜい10数コマが1冊200ページそこらのマンガと、1秒で24コマの映画、どちらが想像の介入する余地があるか。しかし、間違えて欲しくないのは、よってマンガはより優れているだとか、映画はより高尚であるとかいう話ではないということだ。要は、それぞれのメディアには表現のキャパシティがあるのであり、それを踏まえた上で想像的を活用つつ表現しなければいい表現とはならないのである。
このことを踏まえイラストについて考えると、「絵画(イラスト)」はより想像的なメディアだとわかる。特に図1、2などのイラストは大きくはない。マンガや、映画などに比して「イメージ(或いは物語といってもいいだろう)」にかけられる余地は圧倒的に少ない。そこで作者が用いたのが「洗濯バサミの髪留め」や「ホックの外れたブラ」というやや誇張が激しくもわかりやすい要素(記号)である。それらが想像力を刺激し、効率的に「女性教師」としてのリアリティを生成する。
とにかく、繰り返し述べるように、「リアル」と「リアリティ」は似て非なるものだ。それは、あくまで現実のイメージが幻想を生むように、現実との繋がりを持ちつつ現実から浮き上がる。そしてそれは、表現のキャパシティに左右される。小説に絵、マンガ・アニメに映画、そして写真に至るまで、表現においてこの問題は断ち切れぬものだ。
図2に関わる議論の末、あるイラストが掲載された。

「夜中に冷蔵庫を漁るよーなズボラなアラサーの現実はこうだよ…」
図2のイラストに対して「ズボラなアラサーの現実はこうだ」と言ってしまった以上、このイラストには「リアル」が求められる。僕はうら若い青年であるので、このイラストが示すシチュエーションが現実にあるのかどうかについては語れない。しかし、リアリティある表現だと思う。
僕以外に関しても、いくらか批判はあるものの、概ね受け入れられているようには思う。しかし、これが図2のイラストよりも優れてズボラな女性を描けているかというと、これもまたわからない。そもそも同じシチュエーションでも、人により想像するレベルは異なるのだから。ただ、個人的な感覚としては図3の面白さはあるものの図2の魅力には勝らない。何故なら、図3のイラストは「リアル」による事を主眼とした表現であるために、フィクションであるからこその魅力に欠けると思うのだ。
ただ、図2にまつわる議論において、もっとも建設的な指摘(反論の反論?)が図3だと僕は感じた。
この炎上における主な議論は「女性教師」のシチュエーション、特に「洗濯バサミの髪留め」や「ホックの外れたブラ」を現実の女性がするか/しないかの次元に留まってばかりいる。しかし、分かりきったことだが、このようなシチュエーションのある/なしはイラストとしての出来はおろか、その道徳的存在の善し悪しを決定しない。ぶっちゃけあってもなくてもいい。前半に立ち戻ると、
絵じゃん。
あるシチュエーションをイラストにするのに、それが現実になくてはならない/ないからそれはダメな絵だという主張は馬鹿らしいものだ。
それをわかってなお批判者の批判者(ここでいう擁護者)は反論する。「(かのシチュエーションは現実に)ある!」と。無論、それは悪いことでは無い。だが、リアルにあるかないかは枝葉末節の問題だ。なのに何故か彼らの反論は多くの場合「リアル」の水準にある。言ってやればいい。フィクション(イラスト)に対して「リアル」を持ち出す批判者へ、「それは論点のズレた話では無いか」と。何も批判者が準備した虚構の土俵に立つ必要はない。
その点で図3のイラストは、同じシチュエーションを違った解釈で描いたイラストを持って批判している。悲しいことにそれは「これが〜だよ」と言ってしまっているために寧ろ、非リアル的なリアリティに即した図2の魅力を再確認させることになっているが、「リアリティ」という同じ土俵に立っている時点で図3は比較して誠実な批判であるとの印象を受けたのだ。また視覚的に見て面白いというのも個人的には好きだ。
まとめ
ほんの数千字で終わらせるはずが、かなり長くなってしまった。とっちらかった文章で申し訳ない。かのイラスト群の炎上に際して、僕が主張したいのは以下の2点だ。
そのシチュエーションが現実にあるかないかの問題は取るに足らないものである
もしかすると、特定のシチュエーションにこだわりや、アイデンティティを持つ人がいるかもしれない。そもそも、普段している行為(図2でいう「洗濯バサミの髪留め」など)を否定されて嫌な気持ちになる人の存在は大いに考えうる(というより、その不快感が擁護者を駆り立てるのだろう)。そのような方々には申し訳のない物言いとなる。しかし、厳密にある現実のシチュエーションを描いたわけでもない、あくまでそのイメージを視覚化したフィクションにおいてその対立は意味を持たない。実際、炎上を引き起こしたのは批判者である。その点からすれば擁護者による反論は最もなことで、彼らを批判するのはやや腰がひける。だが、この議論は見ていて馬鹿らしいと言わざるを得ないというのが僕の感想だ。
そして、
2.「リアル」と「リアリティ」には同等に語れぬ違いがある
リアルは現実そのものである。一方でリアリティは現実に無いものに宿る(正確には読み込む)。そして、だからこそリアリティには現実以上の意味を込めることが可能となる。つまり、それは必ずしも現実を忠実に表さずとも、記号(或いは要素)と鑑賞者の想像力という助けを得ることにより、現実感を与えつつそれに加わる魅力があるものだと僕は考える。そして、自己のキャパシティを踏まえた表現こそが真にリアリティを持った表現となるのだ。
この記事を書いている間に、この話題も冷めてしまったようだ。ただ、未だに火は燻っているようでしつこい。批判者と擁護者、双方をある程度批判してきたつもりだが、僕はどちらかと言うと擁護側だ。自信を持って言える。あのイラストたちは何ら批判されるものでは無い(無論、その自由はあって然るべきだ)。現実にないからダメなら、何も表現など出来まい。そんな貧しい表現に豊かな未来はないだろう。表現文化に携わり、また学ぶ身としてこの問題は大変興味深いものだった。これまでに起こった数しれぬイラスト、キャラクター、マンガ、等々を考えてみれば、必ずこの先同様の炎上が起こることだろう。その時我々は、何度も叫ばねばならない。
絵じゃん
と。当然思考なき発言は馬鹿の一つ覚えに過ぎないが……本文中何度か「馬鹿らしい」と述べた。その気持ちは心の底からのものである。しかし、何が馬鹿らしいのか、何故馬鹿らしいのか、そうやって思考をこらしていくと、その中にも気づきがあるはずだ。個人的には青識亜論さんなど、よくこんな馬鹿らしい意見と向き合っているなぁなどと(或いは彼自身一見馬鹿らしい発言をして、その度に思い知らされるのだが)思っているが、そこに伴う思考こそが有意義な意味をもたらすのかもしれない。また何かが炎上した時──例えそれが馬鹿らしい主張に思えても──その本質、背景となる思考、考えるに値する余地は幾らでもある筈だ。そして、その先で議論することこそ表現を守ることに、或いは新しい発見や同意に繋がるのだと思いたい。本文がその一端になれば幸いだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
