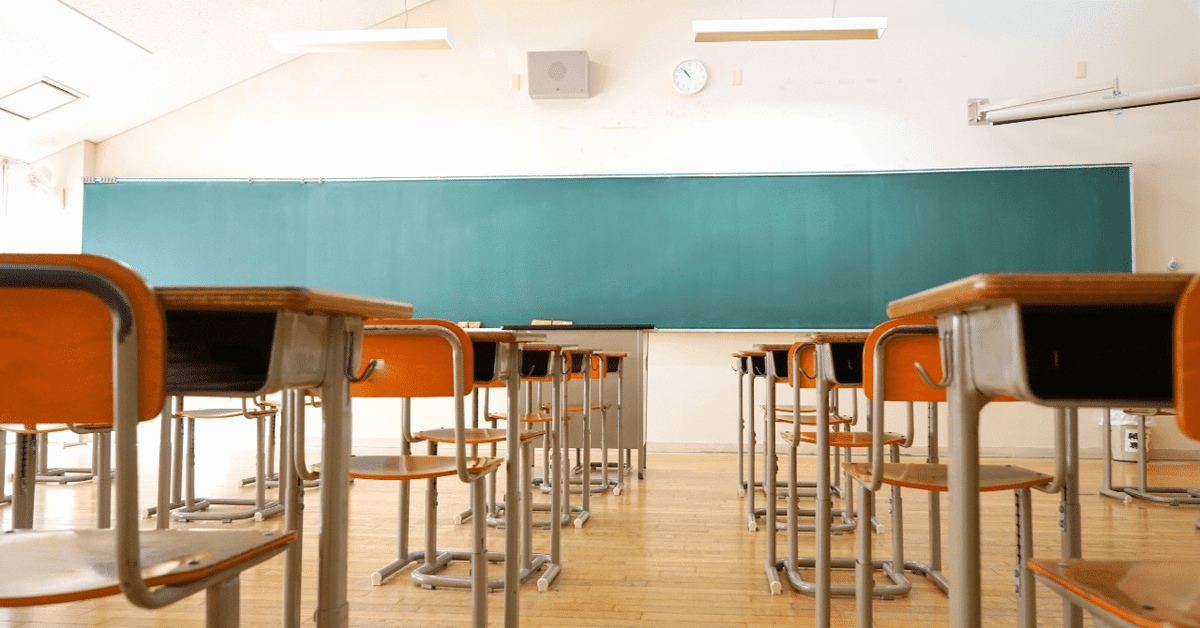
自分と子どもたちと学校教育を明日から変えたいと願う先生へ #センセイを捨ててみる。
読解力
日本 11位
デンマーク 13位
数学的リテラシー
日本 1位
デンマーク 8位
科学的リテラシー
日本 2位
デンマーク 20位
総合評価
日本 20位
デンマーク 1位
精神的幸福度
日本 37位
デンマーク 1位
日本 41位
デンマーク 5位
上記の数字は、ことあるごとに散見されるデータですが、目にするたびに「日本の学校教育のどこがうまくいっていないんだろう・・・?」と感じてしまいます。
一人の教師として、ずっとその答えを探してきましたが、この本を読んでリアリティのある答えにやっと巡り会うことができました。
能澤英樹さんの
『先生2.0 日本型「新』学校教育をつくる』
感想をひと言で表現すれば、
「現場で頑張っている教員に、自らが置かれている状況を早く知らせたい」ということ。
自分が誰のために、何をやっているのかをすべての教員や学校関係者に気づいてもらいたい。そんな思いで本書は書かれています。
本書では、「なぜ教師がこれほどまでに疲弊し、かつ子どもたちが幸せそうに見えないのか」という疑問に対する解答が、ほぼ説明されています。
その目的は明快で、「教員の業務量を減らしながら、子どもの幸せをどうやって保障していくか」というゴールに向かって、圧倒的な筆致で書き進められていきます。
私は普段、本に線を引くことはしないんですが、この本だけは別でした。全256ページを読み終わるまで、何か所に線を引いて、余白にメモを取ったかわかりません。私が今まで気づかなかったことや言語化できなかったことを教えてくれたからです。
たとえば、
・善意に満ちた圧力をお互いに仕向ける独特な文化(相互圧力構造)
・「おいしい肉を大量に」食べさせようとする二律背反のおかしさ
・学校運営では、スタートラインに着くまでの基礎代謝が非常に大きい点
・実は教員自身も何をしているのかよく分かっていない
・子どもというきわめて不完全な対象を扱う学校に入り込む完璧主義
・パートナー→傍観者→受益者へと変貌する保護者
・教員の労務管理から目をそらし続けてきた教育委員会
・健康で学力が高くても、自殺率が高く、生活に満足しておらず、友達もすぐにはできない日本の子ども
・学級崩壊の最大の被害者は担任
・「学校は思い出を作る場所」という期待が恐ろしいまでに肥大化している
・多くの教員は「理想の教育」を目指した結果、どれだけ時間がかかってもそれをこなすという単一の働き方しか知らない(ベター主義)
・教員の言うことさえ聞いていれば常に「安全圏内」にいられるという錯覚を与えられた子ども
・学校は「髪の毛を縛るゴムの色」のような、ささいなことでいじめが起こる場所
・そもそも受験勉強は家庭学習の守備範囲
・誰もが幸せになれる社会を目指すなら、「精神は平等、経済は自由」といった現状から「精神は自由、経済は平等」へのシフトが必要
・大人の都合のいいようにソフトランディングさせるのではなく、子どもたちに手綱を渡す
・スーパー教員ではない「普通の先生」が活躍できてこそ持続可能な学校教育が実現する(得意をもった平凡教員の推奨)
・学校に書けているのは「準備の時間を確保して業務を行う」という意識と、「成果物を共有する」という意識
・先生が得意を全面に出せる環境の方が、子どもたちにとって幸せ
・クラス担任廃止が「自分のクラスをきちんとしなければならない」という重圧の解消に繋がる
・これまでの職員室は、それぞれが自分の理想像を持ち、それに向かう自分を「よし」とし、そうでない他の教員を「だめ」と密かに思う(そして時として言葉や態度に出す)文化がなかっただろうか
・「幸せそうに働く教員」の姿を子どもたちに見せる
・「先生1.9」は「教育の求道者」を目指してきた。だから、勤務時間内にはとうてい終わらない業務を自らに課した。これが失敗であったことは明らかで、今、学校は崖っぷちである。
これでも一部です。「当たり!」と思う点が非常に多く、きりがありません。もしあなたが学校関係者なら、腑に落ちる点が多すぎて、鉛筆を手放せなくなるはずです。
ユニークなのは、「撤退戦」を勧めていること。
新しいことを始めれば、今までやってきた何かを止めるのが当たり前ですが、学校はそれができません。
本書では「戦略的な業務削減」を「撤退戦」と名づけ、「職員室内の意識改革と働き方改革」、「学校外部の保護者や地域への対応」に二分しています。
撤退戦のアプローチが4点示されていますが、学校関係者に最も考えてほしいことは「重点策を打ち出す」ことです。仕事に優先順位をつけ、優先度の低いものは削減していくといった、ごくごく当たり前の考え方です。
ただ、残念ながら日本の学校教育はこれができません。理由は多くの方々がご存じの通りですが、これが実現しなければ、教師が疲弊するだけでなく、教師と時間を共にして価値観を内面化する子どもたちも幸せにはなれないと感じます。
人は、良くも悪くも「ノスタルジーに生きる存在」です。教師も例外ではありません。自分が受けてきた教育を無意識的に反復しようとします。かなり自覚的な人でもノスタルジーから完全に逃れることはできません。
それでもなお、教師は過去の栄光や捨てきれなかった不合理な信念から脱却し、仕事を辞するまでアンラーンとリスキリングを続けていくしかありません。それが教師自身と次世代を担う子どもたちの幸せに繋がると思うからです。
本書は、学校関係者の心を激しく揺さぶるはずです。
理解されている喜びを与えてくれるだけではありません。
同時に、読者に対して変化を求めています。
学校教育に関する緻密な資料収集に基づく歴史的変遷が示され、問題が提起され、未来への指針が長年の現場経験に基づいた圧倒的なリアリティで語られる。
私は最初の30ページで引き込まれました。
あなたなら、きっと一気に読み終えてしまうと思います。
現役高校教師
オン&オフラインセミナー講師
ポッドキャスト(Spotify)
https://open.spotify.com/show/2pCy8yUiGRk3jKoVJo72VF
FBコミュニティ
https://www.facebook.com/groups/unlearnteachers
udemy
https://www.udemy.com/course/kqfpehod/
心理学修士(学校心理学)
NPO法人日本交渉協会認定「交渉アナリスト」1級
https://nego.jp/interview/karasawa/
一般社団法人7つの習慣アカデミー協会主催
「7つの習慣®実践会ファシリテーター養成講座」修了
思いつきと勢いだけで書いている私ですが、 あなたが読んでくれて、とっても嬉しいです!
