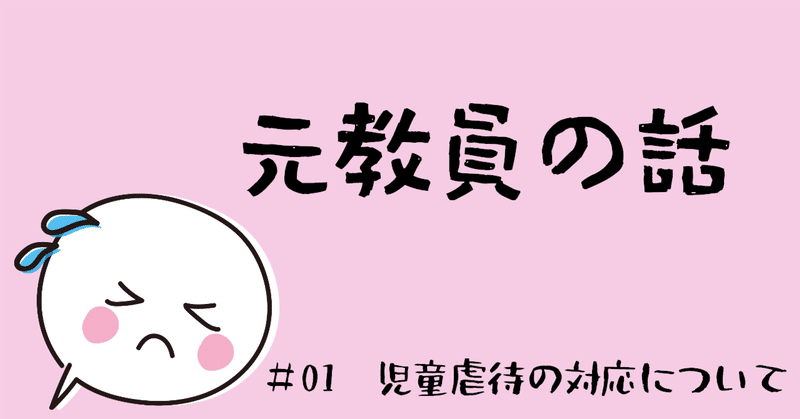
【元教員の話】♯01 児童虐待の対応について
こんにちは、ハルジマです。
元不登校・元小学校教員という肩書を活かして、皆さんに情報をお伝えしています。
よろしければ、紙とペンもしくはメモ帳を用意して、一緒に考えていきませんか。
今回から、【元教員】のほうの肩書を押し出して話をする場も作りたいと思います。
【不登校で困ったこと】で話をした、学校現場で蔓延るパワハラについて話そうと思ったんですが、その前に……。
あまりに痛ましい事件がここ最近、続いて起きているので、【児童虐待】について焦点を当ててお話しようと思います。
児童虐待は、悲しいことに、年々増え続けています。
つい先日も、4歳の女の子が命を落としましたね。
児童相談所の対応が話題になっています。
文部科学省が掲げる「児童虐待防止対策」の中で、
なお、児童虐待への対応に当たっては、
・学校等においては、児童虐待の早期発見・早期対応に努め、市町村や児童相談所等への通告や情報提供を速やかに行うこと
・児童相談所においては、児童虐待通告や学校等の関係機関からの情報提供を受け、子どもと家 族の状況の把握、対応方針の検討を行った上で、一時保護の実施や来所によるカウンセリング、家庭訪問による相談助言、保護者への指導、里親委託、児童福祉施設への入所措置など必要な支援・援助を行うこと
という文言があります。
学校は、児童虐待の早期発見・早期対応に努めなければならない。
では、その早期発見・早期対応はどうやって行うか?
まずは、目視。
子どもの身体に原因不明のあざや怪我がないか、子どもの様子がいつもと違っていないか。
次に、聞き取り。
子どもと個別に、あざや様子について、何があったかを確認する。
※子どもは基本的に、家の人を悪く言いません。
家の人に何かやられたとしても、隠そうとする場合が多いです。
そして、記録・報告。
もしそのあざや怪我が大きいものだった場合、本人の了承を得て写真を撮ります。
管理職や養護教諭に報告・相談し、必要だったら本人も連れて話をします。
家庭にも連絡を入れますが、ここで気を付けないといけないのが、
【虐待を疑っている雰囲気を醸し出さない】こと!!!!!
「ここにあざがあって、本人もよくわからないみたいなんですが、おうちで心当たりはありますか?」
この程度のふんわりとした雰囲気で聞くと良いと思います。
決して、「本人から申し出があった」とか、「本人がお家の人にやられたと言っている」とか、そんなことは言ってはいけません!!!
家に帰ったあと、「なんで先生に言ったんだ!」と、暴力を受ける可能性がゼロではないからです。
また、初手で学校に不信感を持たれてしまうと、次回以降の話し合いもうまくいかなくなる可能性が高いです。
担任としては、【子どもを守る!】この一点を心がけておくと、ぶれないと思います。
いざおうちの人に聞いてみたら、「昨日公園で転んじゃって~」とか、明るく理由を話してくれるかもしれません。
それでほっと一息……、してはいけません。
注意深く、その子を観察して、また、あざが増えていないか、表情は暗くないか、異変に気付けるようにします。
学校から連絡があった数日は、控えるかもしれませんが、一週間後、一か月後……
二回目、三回目、と、あざが増えていたら、要注意です。
管理職と相談し、この辺りで、児童相談所に通告を入れる頃合いです。
児童相談所は、野田市の事件以降、迅速に対応してくださるようになったと思います。
担当の方が来校し、本人と話をし、必要だと感じたら家庭訪問をして、必要な対応を決める。
家庭の対応はなるべく児童相談所に任せ、学校は家庭と信頼関係を築いたままにするのがベストだと思います。
わたしが実際に虐待家庭と接して感じたことは、
【おうちの人も困っている】
ということ。
どうして、自分がこうなってしまうのかわからない。
本当は子どもを愛してあげたいのに、愛し方がわからない。
思うようにいかなくなって、手が出てしまう。
虐待は、決して、許されることではないのです。
ですが、子どもに手を挙げてしまうような精神状態になっている方を、どうにか、別の支援・福祉にもつなげてあげられたらいいな、と思います。
なので、おうちの人を責めるのではなく、「一緒に考えていきましょう」というスタンスで話をすると、心を開いてくれやすくなるかなと。
また、幼少期に虐待を受けた子どもは、発達障害と似た脳の構造になってしまう、という研究結果があります。
結果として、発達障害の症例(ADHD、ASD)と似た言動をしてしまう。
そうなると、育てにくさがあり、余計に……という、悪循環が生まれてしまいますね。
学校としてできることは、個別の対応を充実したり、療育につなげたり、視野を広げてあげることかな、と思います。
虐待を受けた子どもは、やはり、「構って!」が強くなりがちだと思います。
でもこれって、当たり前ですよね。
誰かに気付いてもらえないと、命の危機に瀕しているのだから。
友達関係の中でワガママになったり、「先生先生!」って先生にまとわりついたり、
それって、その子の、SOSだと思います。
虐待が疑われる児童に対応していたら、「でも、子どもってウソつくよ」と、先輩の先生に言われたことがあります。
ウソつくからなんなんですか?
ウソの奥にある、その子の、「助けて!」という叫びを、担任じゃなくて誰が受け止めるんですか?
結果的に、ただの「構って!」であり、「助けて!」がなければ、それでオッケーじゃないですか。
(ちなみに、わたしは基本的に【自信がない】ので、そのとき、先輩に、言い返せませんでした……くやしい)
わたしは、丁寧に対応しすぎて、管理職に苦い顔をされることもありました。
「ハルジマさんは、あの子にどうなってほしいの?」と聞かれたこともありました。
そんなの決まってますよね。
「虐待に怯えることのない、健全な日常生活を送ってほしい」。
ただ――
親と子どもを離すことが、正解なのか。
単純に、施設に入れてしまうことが、最善の道なのか。
つらい思いをしながらでも、親子で一緒にいた方が良いのか。
この問いには、未だに答えが見つかりません。
(ただ、今回の事件のような、【明らかに重度の虐待】が目立つケースは、一刻も早く物理的に距離を置いた方が良いとは思っています)
日に日に増えている悲しい事件ですが、報道されている事件の影で、「学校が介入したことで」最悪の事態が防げたケースも、たくさんたくさん、あると思います。
これを読んでくださっている教育関係の皆様方、どうかどうか、ひとりひとりの子に、目を向けてあげてください。
「構ってちゃんだから……」で済ませないで、その奥にある胸のうちまで、見つけてあげてください。
管理職に鬱陶しがられても、もし、異変に気付いたら、すぐに報告してください。
自分ひとりの胸の中にしまっておいて、もしものことがあったら大変です!
責任は分散しておきましょう。
担任している子どものうち、時期をずらして二人が一時保護をされ、児童相談所で二人が再会したというレアケースを経験した元教員より。
一時保護として、一人の子を児童相談所の職員の方と一緒に車で施設まで送りましたが、送り終えた後、涙が出ました。やはり、とても悲しくて苦しいことで、本来なら、こんなことはあってはいけないことだと思います。
児童虐待家庭が、この世からなくなることを祈っています。
子どもは、宝!!!!!!!!!
熱く語ってしまった。
ハルジマでした。
ここまで読んでくださって、ありがとうございます!
質問や感想、相談などがあれば、お気軽にお問い合わせください。
Twitter、Noteのフォロー、サポート、よろしくお願いいたします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
