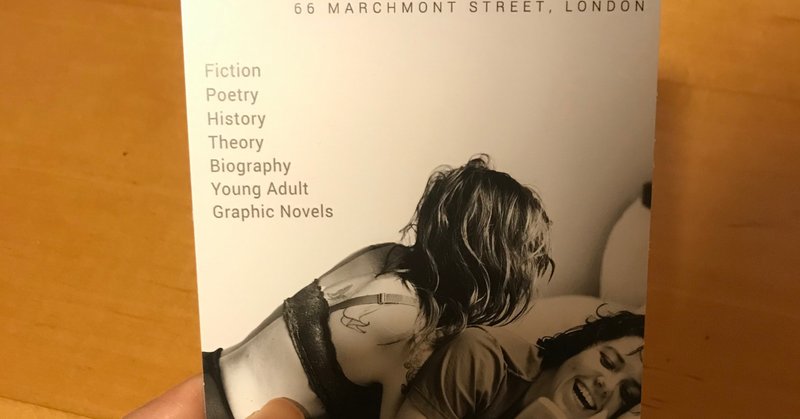
フェミニズム本すごろく(2020/8/19更新)
ジェンダー、セクシュアリティ、フェミニズムに関する本を「すごろく」の形式で紹介します。オンラインでやるので綺麗なすごろくの形にはなりませんが。これは以前『天然生活』がやっていた特集を真似しました。
この順番に読んでも、読まなくても、逆流しても、横から見ても下から見ても。暴力(DV、性暴力)虐待などへの言及、描写を含む本のタイトルの横には*(アスタリスク)をつけています。
1. 性自認、性的指向て何だ?
『百合のリアル』著:牧村朝子 星海社新書
性自認、性的指向について「一緒に考える」形式をとった本。今は「LGBTs」から「SOGI」(性的指向と性自認 Sexual Orientation and Gender Identity)へと言葉が移って聞いてるように思いますが、『百合のリアル』はこの時点からSOGIを意識して伝えていました。
↓悩み相談も交えて
『ハッピーエンドに殺されない』著:牧村朝子 青弓社
『百合のリアル』でデビューした著者のウェブ連載、『女と結婚した女だけど質問ある?』(※現在のタイトルは『ハッピーエンドに殺されない』)の書籍化。『百合のリアル』も「一緒に考える」形でしたが、本書の前半はジェンダーやセクシュアリティに関する悩み・質問に対し牧村さんが答えていく対話形式。鋭くも誰かを勝手にジャッジせず、面と向かい合っていない(見えない)相手にも語り掛ける文章にいつも気持ちがすうっとします。コラムも沢山載っていますが、大学生の時のことを書いた「メンチカツ食ってミス日本」が鮮烈です。
↓『百合のリアル』ができるまで
『同居人の美少女がレズビアンだった件。』著:小池みき 監修:牧村朝子 イーストプレス
『百合のリアル』は青海社が主催したコンテストの優勝を受け、著者牧村朝子さん、企画・構成を小池みきさん、編集を青海社の今井雄紀さん(現在は『ツドイ』代表)が担当し出版されたもの。小池さんが牧村さんと会い『百合のリアル』をコンテストに応募するまでとその後を綴ったコミックエッセイが本書です。シェアハウスで同居人となった二人が本を一緒に出版するまで……とストーリーだけでも面白いですが、小池さんの語りの切れがよく笑えます。「人は世界を救えないけれど、人は人を救えるよ」という言葉が印象に残っています。
昨年は新宿で3人のトークイベントが開かれました。もちろん行った。
2. フェミニストたちのエッセイ
『バッド・フェミニスト』* 著:ロクサーヌ・ゲイ 訳:野中モモ 亜紀書房
言わずと知れたフェミニスト、作家で大学教授によるロクサーヌ・ゲイのエッセイ。ジェンダーや人種からエンターテイメント、社会をドライさとユーモアでもって語っています。アメリカのポピュラーカルチャーに詳しくないと分かりにくいところもありつつ、ロクサーヌ・ゲイが語る「バッド・フェミニスト」の姿は勇気をくれます。特に映画『ヘルプ 心がつなぐストーリー』への鋭い批評は必読。
↓イギリスのフェミニスト
『説教したがる男たち』* 著:レベッカ・ソルニット 訳:ハーン小路恭子 左右社
女と見るや、「説教/説明したがる」男たち……著者自身の経験から始まり、「女性軽視」の態度は性暴力や殺人などの暴力まで繋がっている、その構造を鮮やかに鋭く指摘したエッセイ。
↓日常の違和感から
『ロマンティックあげない』著:松田青子 新潮社
特に「ジェンダー・フェミニズム」に限ったものではありませんが、世の中の「これっておかしくない?」を指摘する、間違いなくフェミニズムの姿勢のエッセイ。洋画・本、メイク、テイラー・スウィフトなど著者の好きなものがたくさん詰まった、ちいさな宝箱のようなわくわくさを持つ本でもある。
↓好きなものは最高の武器
『だから私はメイクする 悪友たちの美意識調査』著:劇団雌猫 柏書房
なぜメイクをするのか?どんなメイクをする?女性たちへのインタビューを基に作られた本書には、「会社では擬態する女」「あだ名が『叶美香』の女」などタイトルだけで引きつけられる話がたくさんある。「あなたらしく」という広告やインスタアカウントを覗かなくても、「メイクはこうであれ」という息苦しさに風穴を開けてくれます。「メイク」に戸惑っていたとき、「そもそもなぜ自分はメイクをしたいのか?」に目を向けられました。
3. 女性表象、文学とジェンダー
『お姫様とジェンダー アニメで学ぶ男と女のジェンダー学入門』著:若桑みどり ちくま新書
大学でのジェンダー学の授業を基に書かれている、女性表象について学ぶ初めにおすすめの本。ディズニーのプリンセス映画を基にジェンダーについて考えていきます。
↓「女性表象」を考える
『〈妊婦〉アート論 孕む身体を奪取する』編集:山崎明子・藤木直美 青弓社
話題を呼んだ菅実花さんによるアートプロジェクト『ラブドールは胎児の夢を見るか?(Do Lovedolls dream of Babies?)』。妊娠したラブドールのセルフポートレートは何を語るのか? この展示をきっかけに始まった本書は、マタニティフォトや文学、胎盤人形から「妊婦表象」を紐解いていきます。私は「マタニティ・フォトをめぐる四半世紀 メディアの中の妊婦像」(小林美香)が一番興味を惹かれました。広告や雑誌の写真はこんなにも意図が込められていて、私は意識的・無意識的にそれを受け取っている。
↓文学とジェンダー
『テヘランでロリータを読む』著:アーザル・ナフィーシー 訳:市川恵里白水社
著者はテヘランの大学で英米文学を教えていたが、国勢の悪化と増していく圧力の中大学を辞め自宅で読書会を開く。著者と教え子は、ナボコフを、ギャッビーをテヘランで読む。この抑圧は、形を変えて、あるいは同じ形で、どの国にも時代にも存在しているのだ。
かなり難解で私は理解しきれていないと思うのですが、英文学を学ぶと決める前に読んで良かったと思います。
『闘う姫、働く少女』著:河野真太郎 堀之内出版
『千と千尋の神隠し』や『おおかみこどもの雨と雪』をジェンダーから読み解く!社会学寄りだと思います。「ポスト・フェミニズム」「ポスト・フォーディズム」など耳慣れない言葉が出て来るも、おなじみの映画のジェンダー批評は新しい視点をくれます。好きな映画の批評こそ読もう。
↓よりエッセイ寄り
『ヒロインズ』著:ケイト・ザンブレノ 訳:西山敦子 C.I.P Books
『ヒロインズ』についてはこちらを
↓自伝的な小説
『ヴァレンシア・ストリート』* 著:ミシェル・ティー 訳:西山敦子
レズビアンでクィアでフェミニストの詩人・作家、ミシェル・ティー。文章も本人もかっこいい。
4. 小説とジェンダー・セクシュアリティ
『早稲田文学 女性号』責任編集:川上未映子
作家、エッセイストたちの文章が集結。私は山崎まどかさん『いかに私は心配するのをやめフェミニストになったか』と津村記久子さん『誕生日の一日』、多和田葉子さん(松永美穂さん訳)『空っぽの瓶(ボトル)』が好きです。
↓
『マリー・アントワネットの日記』作:吉川トリコ 新潮文庫
フランス王妃、マリー・アントワネットが現代語を駆使して21世紀の日本の女性に語り掛ける!鋭い発言に笑いながら、当時のフランスと今の日本の似通った部分に苦しくなり、マリー・アントワネットに思いを馳せる。現代をサバイブするお守りのような本。
↓現代の女の子たちに
『本屋さんのダイアナ』* 作:柚木麻子 新潮社
お守りと言えば柚木麻子さんの本はどれもそう。とりわけ『本屋さんのダイアナ』は本好きの2人の女の子ダイアナと文子を通し自分で、2人で生き抜くための方法が書かれています。
↓「女ふたり」
『レズビアン小説短編集 女たちの時間』訳:利根川真紀 平凡社
アメリカ・イギリスの作家を中心に「女二人」の物語を集めた短編集。その豊かさとのびやかさ。前にあるイベントにいったとき、そこで会った全員がこの本を読んでいた、ということがあった。
↓
『九時の月』* 作:デボラ・エリス 訳:もりうちすみこ さ・え・ら書房
イランとの戦時下のテヘラン、ファリンは転校生の少女サディーラに恋をする。カナダ人の著者がイラン人女性の経験を基に書いた小説で、性差別・レズビアンへの差別への怒りとメッセージがはっきり表れています。ただ、「イスラム圏の女性は抑圧されていて可哀想」というイメージだけになりかねないところもあり『テヘランでロリータを読む』とも併せて読みたいです。
↓性差別への怒り
『82年生まれ、キム・ジヨン』作:チョ・ナムジュ 訳:斎藤真理子 筑摩書房
言わずと知れた小説だけれどこれは載せないと。「女性」が一生の間に経験する理不尽さの多さに怒りが湧いてくる。
↓「家族像」を解体する
『幸福な食卓』作:瀬尾まいこ 講談社文庫『卵の緒』作:瀬尾まいこ 新潮社
「父さんは今日から父さんをやめようと思う」-その一言から始まる物語『幸福な食卓』と「卵から生まれた」僕の物語である『卵の緒』はどちらも「家族の理想」なんてどこかへ飛ばしてくれる。
↓夫婦像も
『ゴーンガール』* 作:ギリアン・フリン 訳:中谷友紀子 小学館
「アメイジング・エイミー」、ニック・ダンの完璧な妻は失踪した。夫の内面と残された妻の日記が交互に語る「告白小説」ともいえるが、果たして二人の語りは信頼できるのだろうか。ジェンダーとも絡めつつ、「語り」を使い何重にも脱構築した物語。映画版はこの構造を無視していると思います。
5. マスキュリティを考える
『BOYS 男の子はなぜ「男らしく」育つのか』著:レイチェル・ギーザ 訳:富田直子 DU Books
この本についてはこちらに
↓
『熊と踊れ』* 作:アンデシュ・ルースルンド&ステファン・トゥンベリ 訳:ヘレンハルメ美穂&羽田由 早川書房
スウェーデンで実際に起きた3兄弟による連続強盗事件を基にしたミステリ小説。兄弟(実際は4兄弟)の一人が作者として参加し、強盗団となっていく3兄弟の現在と過去を交差さえて描く。スウェーデンのミステリ小説界では、ルポライターや記者として社会問題を書いていた人がより問題への耳目を集めるため小説家になることも多いらしい。
『熊と踊れ』も強盗事件というセンセーショナルなテーマながら核はマスキュリニティと暴力にある。
6. 日本の性差別
『日本のフェミニズム since 1886 性の戦い編』編集:北原みのり 河出書房新社
ずばり、「日本のフェミニズム」。日本のフェミニズムの歴史やフェミニストたちのエッセイをまとめた1冊。柚木麻子さんの「シスターフッドを信じられない人へ」が名文……!
↓社会問題
『女子高生の裏社会 関係性の「貧困」に生きる少女たち』* 著:仁藤夢乃 光文社新書
10代の女の子のため、「バスカフェ」やシェルターで居場所・食事などを提供する「Colabo」の運営者仁藤さんの著書。「JKビジネス」やそれを「許容」する社会がいかに搾取の構造を作りだしているか見えてくる。
↓小説でも
『路上のX』* 作:桐野夏生 朝日新聞出版
JKビジネス、性暴力、貧困。仁藤さんが著書やその他のメディアでし続けてきている状態を本作は小説の形で炙り出す。桐野さんはインタビューで「書かれていることは実際に起こっていること」「現実の恐ろしさが小説を越している」と話していた。
↓
『AV出演を強要された彼女たち』* 著:宮本節子 筑摩書房
『日本のフェミニズム』にも書いている宮本節子さんのルポ。NPO法人『PAPS』には「AV出演強要」について多くの相談が寄せられる。AV業界が作る搾取と構造の問題点を指摘した1冊。
↓
『児童虐待から考える 社会は家族に何を強いてきたか』* 著:杉山春 朝日新聞出版
「家族」には「今」の「社会」が色濃く反映される。あとを絶たない児童虐待事件と「家族」像のいびつさが克明なルポにより浮かび上がる。
↓
つづく
このnoteは1月頃から少しずつ書いていていた。今は、本を読もうにも、本屋にも図書館にも行きにくく、本を手に入れるのが難しくなってしまった。それでも、『フェミニストとしておすすめする本屋』ともども、また見つけたら随時更新します。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

