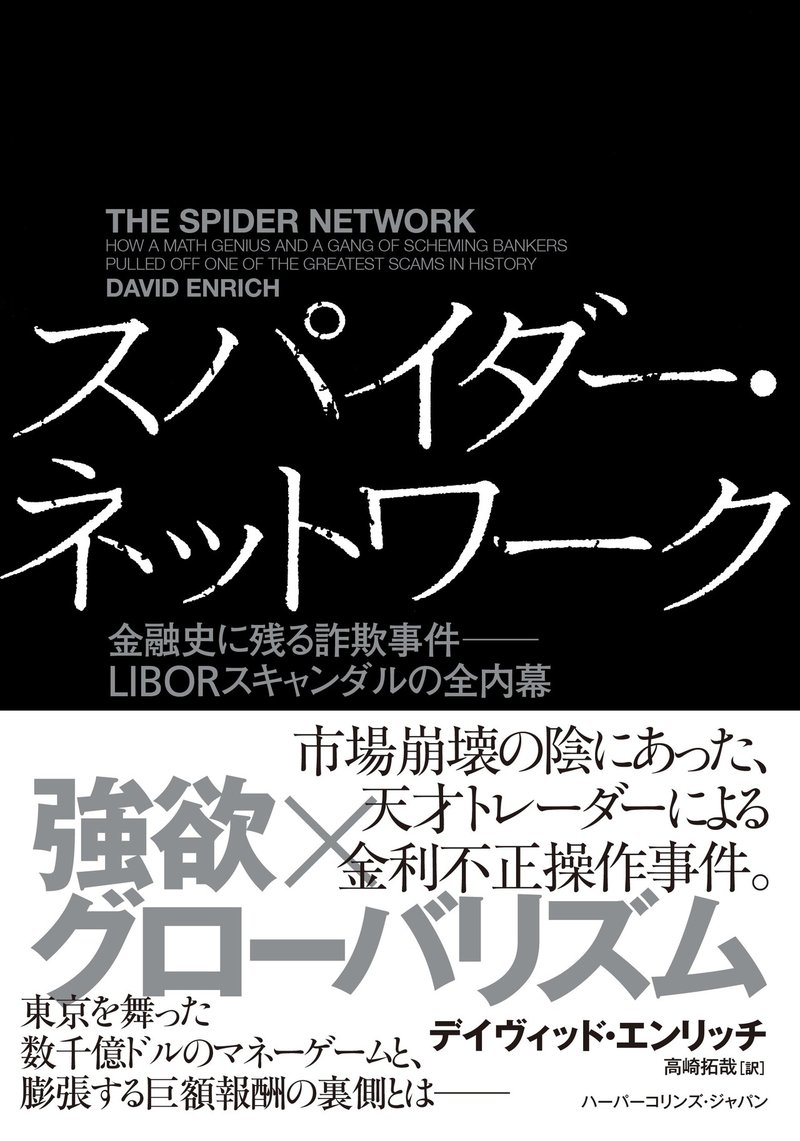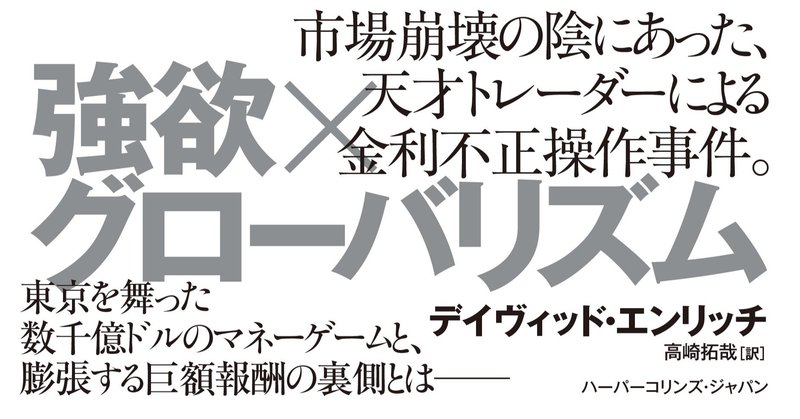
『スパイダー・ネットワーク』【試し読み】
『スパイダー・ネットワーク』
デイヴィッド・エンリッチ [著]/高崎拓哉 [訳]
(以下、本文より抜粋)
目次
本書に登場する人物
略語一覧
序
第1部 詐欺
第1章 戴冠式を見つめて
第2章 鏡の間
第3章 一流
第4章 絶頂
第5章 幸運の回転ドア
第6章 おべっか使い
第7章 メディアデビュー
第8章 モナコのヨット
第2部 包囲網
第9章 全員グルなら
第10章 ここだけの話
第11章 海神たち
第12章 フラッグ・ルームにて
第13章 軽いお叱り
第3部 もうひとつの詐欺
第14章 こいつがそうだ
第15章 蜘蛛の糸
第16章 第一級のペテン師
第17章 ステーキの単価
第18章 シャレード
第4部 勝利
第19章 箱船の中で
情報ソースに関する覚え書き
謝辞
訳者あとがき
原注
序
軽井沢の近く、山々のふもとに位置する小さなスキーリゾートは、家族連れに人気の日帰りスポットだ。しかし、日中は賑わうこの場所も、土曜の夜には閑散とする。この日は月が雲の衣を羽織っていた。
専用バスが、明かりのついたバーの外に停まった。雪がちらつく中へ、静けさを破るように、ビールのロング缶を手にした騒々しい銀行関係者が10人ほど現れた。ほとんどがすでに酔っ払っていて、足早に狭い店内へ向かった。
酔っ払いたちは、アメリカの銀行シティグループの職員だった。シティグループは世界最大級にして、とりわけやっかいなトラブルメイカーとしても知られる金融機関だ。一年前の2009年はじめ、倒れかけたこの巨獣を救うために、450億ドルものアメリカ国民の血税が注ぎ込まれた。ところが、その輸血によって救われたはずのシティグループがいま、投資銀行部門の職員10人以上を週末旅行に連れ出している。スタッフは、近くの高級ホテルにある和室に泊まっていた。
こうした慰安旅行が質素になることはありえない。目的は交流で、そして間違いなく友情は深まった。宴会は150キロほど離れた東京で新幹線に乗り込んだ時点で始まった。一行はスキーを楽しんだあとボウリング場へ案内され、そこで飲み、球を投げ、そしてまた飲んだ。そしてバスでバーまでやってきて、あとはやりたい放題だった。
乱痴気騒ぎの中心にいるのは、クリス・チェカレイという名の細身でカールした髪のアメリカ人だった。この日の振る舞いからうかがい知ることはできないが、生き馬の目を抜く東京の金融界でも指折りの切れ者だ。いまは亡きウォール街のリーマン・ブラザーズに長年勤めた毒舌のチェカレイは、日本へ来てまだ一年ほどだったが、早くもスタートレーダーのチームを結成していた。その目的は、もともとリスクに飢えているシティグループをさらにたきつけ、金融の新天地開拓へ乗り出させることだった。
もっとも、狙いはそれだけではなかった。雪の舞うこの夜、チェカレイは自分で飲むよりも、ある部下の喉に酒を流し込もうとしていた。部下はイギリスの冴えない30男で、名前をトム・ヘイズといった。身長180センチ近い長身瘦軀のヘイズは、たぐいまれな数学の才を持つ、東京きっての有能かつ積極的なトレーダーだった。チェカレイと同じで、こちらも見た目や行動から敏腕トレーダーだと察するのは難しい。オーダーメイドのスーツや高級シューズは身につけず、肩にはふけが落ちている。ビールよりもオレンジジュースやココアが好きで、昔は〝トミー・チョコレート〟のあだ名で呼ばれていた。
ヘイズはこうした社交の場が苦手……というより、苦痛に感じるタイプで、このときもそうだった。連れ出される前には、行きたくないと婚約者にこぼした。しかし、がまんしろと言われた。ヘイズは仕事人間で、シティグループは彼の新しい家族だった。ここで働き始めたのはほんの数カ月前だったから、仲間の心証をよくするためにも旅行は大切だった。しかしいまのところ、上首尾とは言いがたかった。新しい上司たちは称賛の言葉を並べ立て、シティグループの新たな財産だとヘイズを紹介する。バーに入るほんの数時間前、幹部のブライアン・マカピンはヘイズを「スター」と称し、巨大な東京部門の今後を左右する存在だと言った。そしてヘイズの飛び抜けた才能をフル活用していくと宣言した。確かに、報酬はスター級だった。前に働いていたスイスの銀行UBSでは、年収が10万ドル台で停滞していたが、シティグループに入ったとたん、およそ300万ドルの契約ボーナスが転がり込んできた。
シティグループの投資銀行部門のCEOを務めるマカピンは、その晩最後まで、チェカレイとヘイズとともに過ごした。イギリスの硬骨漢の街バーミンガム出身のマカピンは、背が高く、頰のたるんだ顔をしていた。少年時代は将来を期待される歌手で、友人とデッドラインという名のバンドを組み、自身の父親や、近くのロールスロイスの工場で働く作業員の集まるパブでライブを行うこともあった。デッドラインは解散したが、何人かのメンバーは残って新たにオーシャン・カラー・シーンというバンドを結成し、オアシスのツアーに帯同して一時有名になった。そのころにはマカピンはすでに脱退していたが、それでも酒が入ると、自分は超有名バンドのオリジナルメンバーだという自慢話が飛び出した。
このマカピンにとって、不完全燃焼に終わった音楽への想いを発散する道具が、大好きなカラオケだった。マカピンが熱唱するなか、ヘイズはチェカレイが勧めてくるイェーガーマイスターのショットを仕方なくあおり続けた。ハーブを使った甘みのあるリキュールに吐き気がこみ上げたが、ガキ大将のようなチェカレイのプレッシャーはすさまじく、ショットを空け続けた。上司をがっかりさせたくない一心だった。日中は、さほど難しいことはなかった。ヘイズはスキーがうまく、狂乱のトレーディング・フロアにいるときと同様、上級コースを果敢に滑りこなした。ところがいまは、頭皮から汗が噴き出し始めている。部屋がぐるぐると回りだした。ヘイズはトイレへ駆け込んで嘔吐した。それからパーティーへ戻った。
それから三年後の2013年1月、わたしはロンドンのクラークンウェルにある狭苦しいフラットのソファーに座っていた。ここは何百年も前、聖地を目指す十字軍遠征の騎士たちが拠点にしていた地区だ。その歴史を知ってか、わたしと妻が暮らす狭い通りには〈エルサレムへの道〉という名のベルギービールの店がある。一帯はしゃれたデザイン工房、寿司屋、画廊などで再び賑わい始めていた。
午後八時過ぎにiPhoneが振動し、見知らぬ番号からのメールが届いたことを知らせた。「明日会おう。あなたが信頼できる人間だということを確認したい」メールにはそう書かれていた。「この話はぼくの分をはるかに超えたもので、知る限りDOJ(米司法省)も全容はつかんでいない」
メールの送り主は恐怖に震える、完全にしらふのトム・ヘイズだった。
この連絡の二カ月近く前、アメリカのワシントンDCで、司法長官はヘイズを詐欺罪で刑事告発することを発表し、私腹を肥やすために無辜の民を多数犠牲にした強欲な二枚舌のトレーダーとの烙印を押した。地上最大の司法権を持つ男は、こう宣言した。やつは数百万ドル規模の大規模詐欺の首謀者だと。
複数のタイムゾーンにまたがる複数の土地で、銀行家とブローカー、トレーダーの集団が、数兆ドルのローンの根幹にして、金融システムそのものの背骨でもある金利を操作していた。その中心がLIBOR(ライボー)と呼ばれるもので、正式には〝ロンドン銀行間取引金利〟と言う。正確な額はわからないが、数十兆ドルにのぼる世界中の金融商品が、LIBORのほんの小さな動きに影響を受ける。アメリカでは、変動金利のモーゲージ債のほとんどがLIBORを基準にしていた。自動車ローン、奨学金、クレジットローン等々、固定金利でないほぼすべてのローンも同様だ。大企業による数十億ドル規模のローンの支払い額も、多くの場合、LIBORによって決まっていた。デリバティブと呼ばれる何兆ドルもの金融派生商品と連動したLIBORは、ほとんど誰にでも影響を及ぼす力があった。年金基金、大学の資産運用機構、大都市、小さな町、小規模事業、大企業のすべてが、LIBORを使って金利の変動を予測し、自分を守ろうとした。この本をクレジットカードで買う行為にも、LIBORが関わっている。同様に、書店を訪れるのに使った車のローン、不動産ローンや奨学金、市が道路舗装するのに受けた融資、あるいは債券を発行している会社で働いているなら、その仕事にもLIBORは関わっている。つまりLIBORに何かあれば、膨大な数の人が被害を受ける可能性があった。のちに明らかになるとおり、LIBORに異変が起こればすべてに異変が起こった。
LIBORを操作して収入をかさ上げするやり方は、ヘイズが思いついたものではない。それでも、彼はその手法を別の次元で実践し、そしてその倫理観にもとる行動が、何も知らない人たちに及ぼしうる被害にはまったく無頓着だった。そして当初はそのおかげで、金融というとりわけ稼ぎのいい業界のエリート層に昇り詰めることができたが、わたしと会った時点では、そのせいで三つの大陸の規制当局と検察当局に追い込まれていた。当局は、大量破壊の戦犯を躍起になって捜していた。
わたしは銀行とその難局について、『ウォール・ストリート・ジャーナル』等の媒体で十年近く文章を著してきた人間だ。それでも、これだけの惨事は記憶にない。表面的には目を惹くスキャンダルではなく、だからこそ詐欺の格好の温床になった。詐欺をはたらいた者たちは、ほとんど誰も目を向けない裏路地で策謀を巡らせた。しかしその影響は甚大で、ほんの少しの操作で数十万ドルという大きな利益を生み出すことができた。そしてそのあおりを食うのは、たいてい一般市民だった。
それでも、ヘイズと彼の共謀者たち──ある人物は「スパイダー・ネットワーク」と呼んだ──を捕らえることで明らかになったのは、近代銀行の土台を操作するスキームだけにとどまらない。今回の事件の根幹にあるのは、金融システム、あるいは業界を常に監視するはずのミニマリストで腰の重い規制当局の腐敗と破綻だ。確かにヘイズの倫理観はゆがんでいた。のちに診断が出たとおり、軽度の自閉症も理由のひとつだろう。ヘイズが人間関係を築くのが下手で、人間よりも数字に愛着を抱いていたのもそれが一因だ。それでも、事件を調べるなかで出会ったほぼ全員が、ヘイズと似た欠陥を抱えていた。数字と利益に執着し、自分が成果を上げるために他者を道具として利用した。負けている人々は犠牲者ではなく、食いものにされて当然のカモだと思い込んでいた。そして調べれば調べるほど、ある意味でヘイズ自身が食いものにされた側、金融業界全体の無秩序で無謀な振る舞いの全責任を負わされた不幸な男だと思えてきた。ヘイズの物語、そして彼を駆り立てた金融機関と業界の人間たちの物語が教えるもの、それは銀行業界が醜聞まみれで、その悪評をいつまでも払拭できない要因だ。
この続きは製品版でお楽しみください。
※本書の無断転載・複製等は、著作権法上禁止されております。
―――――――――――――――――――――――――――――――――
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?