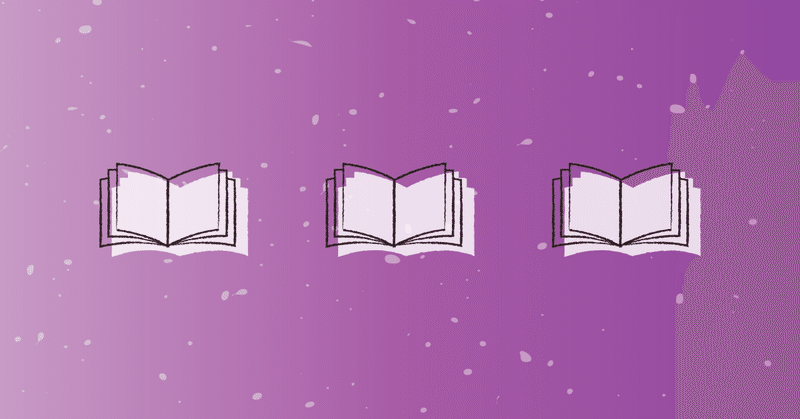
編集者のお仕事をのぞく/書く人の学校「#マーブルスクール」第5回講義録~編集講座~
本づくりのお仕事にあこがれを持ち、就職活動でエントリーシートを送った先はほとんどが出版関係でした。何年も残り、自分の知らない誰かに「言葉」を届ける力のある本というものを、編集者の立場で作っていけたらなんて素敵なんだろう。そんな風に願っていたことを思い出しながら、今回の講座を拝聴しました。
書く+αを学べるマーブルスクール。
第5回目となる今回からは、「編集」を学ぶタームに入っていきます。
(余談:何とか滑り込んだ本つくりの業界だったのですが、新卒で入った会社は入社後しばらくして民事再生法の破産手続きに入るという憂き目に…そんな話はまたいずれ?)
とはいえ、私が当時、編集者と聞いて頭にあったのは、あくまで書籍制作の現場の編集者。今回学ぶ、Webメデイアを運営する編集者とは、お仕事の内容はまったくもって同じなのでしょうか。
そんな疑問を持ちながら、今回からの講師・フリーランス編集者であり、現在複数のWebメデイアの編集長をも務めるえるもさんから、Webメディアにまつわる編集者のお仕事内容を学びました。
Webメディア編集のお仕事とは…?その内情をこれから少しずつ、理解して紐解いていきたいと思っています。
Webメディア運営に携わるさまざまな人たち
講義冒頭「Webメディアに関わる人ってどんな人がいると思いますか?」えるもさんからのこの問いかけに、私自身が思いついたのは…
・ライター
・編集者
・カメラマン
・会計担当者
・デザイナー…
これらの職種。しかし実際は他にも
・編集長
メディアの戦略や担当を決め、組織としての目標を管理する
・ディレクター
ひとつひとつの記事の進行管理や各所とのやりとり
・SNS担当者
メディアのSNS発信を担当する
・エンジニア
サイトの開発や改善、保守運用を行う
・その他
構成作成担当者さんや、入稿業務担当者さんなど
こういった方々がおおむね、ひとつのメディアに関わっていらっしゃることを学びます。さらに現場では、一人がいくつもの職域をまたいでお仕事をすることも往々にしてあるらしく(例:カメラマン×ライター=カメライター!)「これだけ」と思わず、いろいろな業務について広くアンテナを貼っておくのが、Webの世界で働く上では大事なのではないかと感じました。
その中でも編集者の仕事内容は?
さまざまな人が関わるメディア制作の現場で、編集者のお仕事とは具体的にどのようなものなのでしょうか。
講義中、こちらのnote記事を引用されながら、編集者の定義をされていました。
編集者:企画をし、プロジェクトを遂行する人
…記事(=プロジェクト)を企画して、立ち上げ、そのプロジェクト完成までに必要なメンバー(ライター、取材対象となる人、カメラマンなど)を見つけ、集め、記事を仕上げていく。目的に合ったコンテンツを作り上げる人。
ライター:カタチにしていく人
…記事のライティングをする人。メディアから発注を受け、取材をして原稿を作る人。
かなり雑な解釈にはなりますが、編集者はメディアそのものが有している、核とも呼べる「テーマ」を体現すべく、必要なコンテンツを企画するのがメインのお仕事なのかなと理解しました。ライターは、(企画立ち上げから携わることも多々あるようですが)編集者が立てた企画を、具体的なひとつの原稿に仕上げていくお仕事。そういう意味で、ライターは、イチから100にするお仕事と言えそうです。
◆ライターと編集者のお仕事内容違い
ライター
企画 ⇒ 取材 ⇒ 執筆 ⇒ 推敲
編集者
企画 ⇒(取材)⇒ 校正/校閲 ⇒ 編集 ⇒ 入稿/公開
上記、引用も踏まえてえるもさんは最終的に、編集者の定義をこうされていました。
ライターさんとともに、記事を作り上げる人
そう、編集者はライターとタッグを組んで、ひとつのコンテンツを作り上げていくお仕事。前職でお世話になった先輩編集者さんも、そのかたわらにはいつも著者、ライターさん、カメラマンさんなど、多くの人がいたなぁと思い出されました。
多方面とのやりとりをこなしながら最終的に〆切日までに原稿を仕上げ、入稿しないといけません。この間にあっては、
ディレクション(進行管理)やスケジューリング
コミュニケーション
このあたりのスキルも必須。講義ではこれらを円滑に進めるための各種デジタルツールも余すところなく紹介してくださいました。
ながた考察:えるもさんお仕事の流儀①編集者への道は〇〇が勝ち
みんなでひとつのモノを。個人プレイでは成り立たない、だからこその難しさと、逆に「面白さ」がこのお仕事にはあるんだろうとお話を聞きながら終始感じていました。あこがれもするし、目指してみたい。でも、具体的にその門戸はどこで、どんな風に開いているのでしょうか。
講義初回でありながら、ひとつの大きなヒントを提示くださったえるもさん。それは、「自分で(実績を)作ってしまうのがおすすめ」というもの。
例えば、ある程度ライターとして実績を積んだあたりで、自分ひとりが案件を担当するのではなく、そのジャンルが得意な別の、仲間のライターさんに声をかけてみたとします。
そういう状況を何件か用意できたなら、「一括で私にお仕事を投げてもらえたら、月〇本、割り振れます。」と言える。もちろん記事の内容は担保して、そうして実際にライターさんを手配し、お仕事を割り振って原稿を作り上げていけたとしたら、これってもう十分に編集者の領域です。
自分でやってしまうが勝ち。
そんな前向きで貪欲な姿勢が、編集の道を志すにあたっては必要かつ、とっても意味のあるものなのだと感じました。と、同時に、編集者という高いたかい頂にあったものが実は、「目の前のお仕事を丁寧に積み重ねていった先に出会えるもの」なのではないか、という風にも思えたのです。
実際にえるもさんが実践された実績の積み方はこちらのnoteにも詳しく書いてくださっています。
ながた考察:えるもさんお仕事の流儀②ライターさんの原稿は100なんです
先述したように、コンテンツ制作の現場では、編集者がライターに「この企画で書いてください。」と依頼する場面が多く、だからこそ、ライターと編集者の関係性においてはときに、「お仕事をあげる。」「お仕事をいただく。」そんな上下関係が出来上がってしまうこともあるようです。
知らず知らず、編集者サイドが上から目線になってしまう。
でも、それは全くの誤解で、えるもさんもこの点において
Web制作の現場において、上も下もありません。お金を払って、仕事をあげている発注側がえらいなんて言語道断です。
こう明言されています。ライターさんはイチから100を作る仕事。だから、ライターさんがあげてくれた原稿は100なんだ。ひとりひとりのライターに対する敬意を持ってお仕事されていることが、ひしひしと伝わって胸に迫ります…。
各方面とのやりとりを行い、チームを動かす編集者としての理想的な在り方が、ここにあるのではないでしょうか。すなわち、感謝と尊敬の念を持って、お仕事をする。
あぁなんでしょうか。大きな声を上げるでもなく、ただぽつりぽつりと愛の言葉を放つ。それがえるもさんなのかなぁなんて、感じています。今回の講義でえるもさんファンになった人は私だけではないはず。
今後、編集スキルもさることながら、チームの育て方、働く姿勢…などなども、えるもさんからは貪欲に学ばせてもらいたいな、とワクワクするのでした。
編集講義つづく…
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
