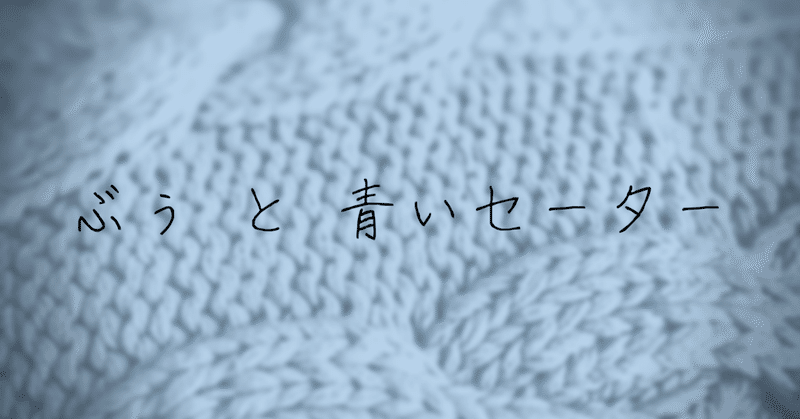
ぶぅ と 青いセーター
ぼすっ。
背中に軽く何かがぶつかった。毛からひんやりと冷たさが伝わる。雪だ。
むぅっと振り返ると小さな女の子がいた。どうやら、あの子が俺に雪玉を投げつけたらしい。
「うさぎが立ってるー!」
びっくりするほど大きな声でそう叫び、ザクザクと俺に近づいてくる。
もこもこと温かそうな赤いセーターが真っ白な雪に良く映える。めでたいというか、目が痛い。雪に足を取られ、ぼふんっと前につんのめる。なんだか、日の丸弁当に見える。腹が空いてきた。
もう、梅干しにしか見えなくなってきたそいつは、雪をかき分け、ずんずんと進み、やっと俺にたどり着いた。
「わー!ぶさいく!!」
失敬な!俺の顔を見るなり、開口一番にそれか!と眉間にしわが寄る。
「わ~、ぶさいく~。」
二度も言うな。眉間により深くしわが寄る。
「ねー、うさぎー。あなたはここでなにをしてるのー?」
俺はつい最近独り立ちをして、旅をしているのだ。1匹での遠出は独り立ちした大人兎の特権である。
「わたしはね~、雪でうさぎさんつくってたのー。ほら!かわいいでしょ~。」
ずいっと満面の笑みで雪の兎とやらを俺に突き出す。兎と言われれば、まあ、分からんでもないが、なんとも不格好な雪兎である。歪んだ顔が俺を見つめてくる。
「今、冬休みだから、おばあちゃん家にあそびに来てるの。ながーいお休みのときはいつも来るんだよ。今はおばあちゃん家のにわもまっ白だけど、春はお花畑になってきれいなんだよ~。」
庭と聞き、周りを見渡すと、かなり広い。どこまでが庭なのかよく分からない。俺の里よりも広いかもしれない。里の皆がこの庭に余裕で引っ越せる。俺の母さんは花が好きだから、お花畑に住めたらさぞ喜びそうだ。そんなことを考えながらぐるぐる見ていると、ポツンと赤レンガでできた小さな家が目に映った。もくもくと煙突から煙が出ている。何か作っているのだろうか。
「おやつだー!!」
女の子は叫んだかと思ったら、俺の目の前をバッと横切り駆けていった。どこまでも自由な奴である。走って行ったかと思うとキキキーッと急ブレーキのような音が聞こえてきそうなくらいの勢いで止まって、くるっと振り返り、ものすごい勢いで俺の方へ戻ってきた。
「あれ、おばあちゃん家!うさぎも来る?」
突然の誘いにポカンと固まってしまう。
「わたし、アミ!うさぎの名前は?」
俺の名前はジャック=ミッケルセンだ。
「分かった!『ぶぅ』ね!!」
なんでだ。
「わたしたち友だちよ、ぶぅ。よろしくね!」
そう言ってニカッと笑い、手を差し出す。
『ぶぅ』と名付けられ、納得できないが、自分に新しい友達ができることは嫌じゃない。俺は差し出されたその小さな手をきゅっと握った。そして、その手を握ったまま、友達のアミと一緒におばあちゃん家へと向かった。

「おばあちゃん、ただいまー。」
玄関で雪をはらい、アミはパタパタと家の奥へと進んでいく。
奥からパチパチと音がきこえる。暖炉でもあるのか、家の中は温かい。
おずおずとアミが向かった方へと進んでいくと、広い部屋についた。リビングであろう。部屋の隅にこぢんまりと暖炉がたたずんでいた。オレンジ色の火がゆらゆらとやさしく揺れていて綺麗だ。
暖炉の上に写真立てが三つある。一つは、小さい女の子がケーキを頬張っている写真だ。たぶん、今よりもう少し小さい頃のアミだろう。口の周りだけでなく髪の毛にまでクリームがべったりとついている。どんな食べ方をすればそんなところにつくのか分からないが、とにかく幸せそうである。その隣の写真は家族写真だろうか。アミのお父さんとお母さんらしき男女がアミを挟んで写っている。アミのぱっちりした目はお母さん、ニカッと歯を見せる笑い方はお父さん似だろうか。
「あら、かわいらしいうさぎさん。」
声が聞こえて振り返ると、腰の曲がった、なんとも優しそうなおばあちゃんがいた。手には小ぶりのバスケットを持っている。中から焼きたてのクッキーが幸せの香りを漂わせている。
「おばあちゃん!この子は友だちのぶぅ!ぶぅもいっしょにクッキー食べよう!おばあちゃんのクッキーは世界で一番おいしいんだから!」
ぐいぐいとアミに手を引かれ、テーブルまで案内されたというより引きずられていった。その後ろをおばあちゃんがよちよちと追う。
真っ黒なワンピースの上に色鮮やかな毛糸でカラフルに編まれたポンチョが歩く度にゆらゆらと揺れる。
引きずられて行かれたテーブルと椅子の脚には、これまたカラフルに編まれたキャップがつけてある。テーブルと椅子が靴下を履いているみたいでかわいらしい。
俺には少々高い椅子によじ登って座る。座ったはいいが、テーブルも俺には高く、結局椅子の上に立ってちょうど良い高さとなった。
焼きたてのクッキーの入ったバスケットがそっと目の前に置かれる。バニラクッキーとココアクッキー、ブロッククッキーにマーブル、チェリージャムのクッキーとどれもおいしそうで手を伸ばすが、どれから先に食べようか迷ってしまう。うぅむ。と迷っていると、クッキーの中にうさぎ型のバニラクッキーがあった。
「あら。ぶぅちゃんと同じうさぎさんね。」
おばあちゃんが紅茶を淹れながら微笑む。
サクッ。
一口かじった瞬間、口の中にバターの甘みが広がった。ほんのりとした優しい甘さに口角が自然と上がる。アミが言ったとおり、おばあちゃんのクッキーは世界で一番おいしいかもしれない。その一口から、バスケットへと手が止まらない。どのクッキーも絶品で、あっという間にバスケットの中は空っぽになった。
ふーっと一息つくと、ほわほわと湯気の立ったミルクティーを淹れてくれた。ぺこっと頭を下げると、おばあちゃんはまた、にこっと微笑んだ。優しい微笑みになんだか安心する。ちびちびミルクティーを飲んでいると、体も温まり、お腹もいっぱいになったからか眠くなってきた。うとうとと眠気と戦っていると、ゴッと横から何かがぶつかる音がした。びっくりして横を見ると、アミがテーブルに突っ伏していた。すーすーと寝息が聞こえる。
おでこ、大丈夫なのか?本当にどこまでも自由な奴である。

「ぶぅちゃん。」
おばあちゃんがちょいちょいと暖炉の方へと手招きする。暖炉の前のふかふかなソファにぽすんと腰かけ、ソファの下から箱を取り出した。パカッと蓋を開けると中には、色とりどりの毛糸玉がたくさん入っていた。赤、青、黄色、緑。庭に積もった雪のように真っ白なものから、暖炉の中で揺れる炎のような温かい橙色まで。きれいな色におおっと目を輝かせる。
「この中から、ぶぅちゃんの好きな色を選んでちょうだい。」
そう言われ、再び箱の中に目をおとす。
俺が好きな色・・・。
箱から毛糸玉をひとつひとつ取り出し、吟味した。そして、2つ、おばあちゃんに差し出した。
「この黄色と深い青色ね。ぶぅちゃんの好きな色。」
俺はこくん。とうなずいてみせた。
黄色は母さんが好きだった、たんぽぽを思い出したのだ。冬が終わって、花が咲き始め、たんぽぽを眺め、綿毛になると妹たちとフーっと飛ばした思い出がある。何より、強い花でどこを旅しても、春にはこのきれいな黄色があった。深い青色は俺の憧れで、俺が旅している意味でもある。俺は『海』というものが見てみたい。友達の渡り鳥のアウィスから聞いた話だと、海っていうのは青いらしい。広くて大きい、水溜りだと言っていた。この世界のほとんどが海らしい。俺は、その広くて大きな海というものを実際にこの目で見てみたいのだ。
「私の夫もこの青が大好きだったのよ。」
おばあちゃんは目を細めながら、暖炉の上へと目をやった。写真立てだ。3つある中のひとつにおばあちゃんが写っている。今よりも少し若いが優しい微笑みは変わらない。隣には男性がいる。おばあちゃんの旦那さんだろう。日に焼けた健康的な肌に爽やかな笑顔がよく似合う。一緒にいると心が明るくなりそうな人だ。
「彼はね、船乗りだったの。陽気でいつも鼻歌を歌っていたわ。私は若いときから体が弱かったから、彼と海へ出たことはないのだけど、彼の笑っている顔を見ると、広大な海とさんさんと降り注ぐ太陽の光のような明るさを感じたの。彼と一緒にいるだけで外に出られなくても楽しかったわ。」
肌が日に焼けているのは、船乗りだったからなのか。
おばあちゃんの視線が写真から、俺が選んだ青い毛糸玉へと移った。
「冬になると、やっぱり船の上も寒いから、セーターを編んであげていたの。何枚も何枚も飽きないように。いろんな色の毛糸で編んでいたのだけど、その中でも、この色のセーターは一段と気に入ってくれてね。そのセーターを着て、嬉しそうにまた船に乗っていったわ。」
話を聞きながら、旦那さんとおそろいの青いセーターで一緒に船に乗っているところを想像した。わくわくした。旦那さんに会えば、俺も海へと行けるのではないだろうか。
「彼、そのまま、遠くへ行っちゃったわ。青いセーターと一緒に。」
その言葉の意味を理解するのに、少し時間がかかった。
おばあちゃんはしわくちゃの手で青い毛糸玉を撫でた。愛おしそうに。しかし、その表情は切なげである。
「寒くなるとこうやって彼の好きな色で編み物をするの。もしかしたら、彼がひょっこり帰ってくるかもしれないでしょ?お部屋もあったかくしておきたいし、それに、ボロボロのセーターじゃいけないからね。」
俺の頭を優しく撫でる。いつも通りの優しい微笑みで。
この家が編み物であふれているのは、おばあちゃんが一つ一つ編んでいたのだ。旦那さんを待った時間だけ、ブランケットが、マフラーが、セーターが、押し入れに一枚一枚増えていくのだ。
「アミちゃんのお昼寝の時間も終わりね。これ以上寝たら夜、眠れなくなっちゃうわ。」
よいしょと腰をゆっくり上げ、眠れるアミ姫を起こしに行く。おばあちゃんに起こされ、眠り眼をごしごしとこするアミ。その半開きの口からはヨダレが垂れている。ずっと突っ伏して寝ていたせいで、鼻が赤い。お姫様には程遠い顔面である。

夜はおばあちゃん特製のクリームシチューをごちそうになった。俺の大好きな人参がごろごろ入っていて幸せだった。アミは自分の皿から俺の皿へ人参を移してくれた。引きつった笑顔で。その後、家に泊めてくれ、アミと同じベッドで寝た。俺は暖炉の前のソファがいいと抵抗したが、無理矢理ベッドまで抱きかかえられ、アミはそのまま寝やがったのだ。なんとも寝苦しい夜であった。世の中の可愛い可愛いぬいぐるみ達は毎晩、こんな複雑な思いで夜を過ごしていたのかと思い、同情した一夜であった。
寝苦しく、早朝に目が覚めた。幸い、アミは熟睡しており、俺はアミの腕から逃れることができた。リビングからパチパチと音がする。のぞいてみると、ソファにおばあちゃんが座っていた。手には、暖炉の上にあったおばあちゃんと旦那さんの写真。愛おしそうに旦那さんの頬をなでている。その横顔はさみしさに満ちている。
「ぶぅちゃん、おはよう。早起きさんなのね。」
にこっと微笑んでくれたその顔には、さみしさが残っている。きゅうっと胸が締め付けられる。俺はしわくちゃの手をそっと握った。
「あら。やーね。しんみりしちゃって。にこにこしてないと、彼が心配しちゃうわね。」
ふふっと笑う目元に涙が浮かんでいる。ソファによじ登り、おばあちゃんにぎゅうっとハグをした。
「ぶぅちゃんは優しい子だねぇ。」
ふわふわと俺の頭をなでる。
「そうだわ。ぶぅちゃんにプレゼントがあるの。」
そう言って差し出したのは、俺が選んだ毛糸で編まれたセーターだった。おばあちゃんの旦那さんも好きだった深い青色のセーター。リブがたんぽぽの黄色になっている。早速着てみるとサイズもぴったりである。温かくて、やわかくて、気持ちいい。尻尾がピコピコと動く。
「気に入ってくれたみたいで嬉しいわぁ。」
やっといつも通りの優しい笑顔に戻った。俺も嬉しくなる。
「おばあちゃん、おなかすいた~。」
アミが目をこすりながら起きてきた。髪には寝癖が盛大についていて、ライオンみたいである。
朝食はおばあちゃんがふわっふわの大きなホットケーキを焼いてくれた。バターとメープルシロップたっぷりで、アミと目をキラキラさせながら頬張った。お腹もいっぱいになり、ほぅ息をつきながらおあばあちゃんが淹れてくれたホットココアを飲む。窓の外を見ると晴天で、庭に積もった雪が太陽の光に反射して綺麗だ。この家にずっと居させてもらうわけにはいかない。天気がいいうちに出発しなければ。
ソファに座って編み物をしているおばあちゃんの膝をつんつんとつついた。そして外へ指を指す。
「ぶぅちゃん、もう帰っちゃうの?」
こくんと頷く。旅を続けなければ。海を見るために。
「えーっ!?ぶぅ、帰っちゃうのー?」
絵本からバッと顔を上げ、アミが叫ぶ。
「もっとここにいようよー。もう、住もう!ね!おばあちゃん、ぶぅここに住んでいいでしょ~?」
アミが俺をぎゅうぅっと抱きしめながらおばあちゃんに求める。苦しい。
「アミちゃん。」
おばあちゃんは優しく、そして諭すように口を開いた。
「ぶぅちゃんもきっとやりたいことがあるのよ。それをおばあちゃんとアミちゃんが引き留めるのは、ぶぅちゃんがかわいそうよ。」
「で、でもぉ・・・。」
アミの大きな目に涙がたまっていく。
「おばあちゃんと一緒にぶぅちゃんのやりたいことを応援してあげましょ?ね?」
「・・・・・・うん。」
よしよしとアミの頭をおばあちゃんがなでる。
「それじゃあ、ぶぅちゃん。出る準備をしましょうか。」
そうして俺は旅に戻る準備を始めた。
おばあちゃんがマフラーと袋を持たせてくれた。袋にはあの世界で一番おいしいクッキーがたくさん入っていた。
遂に2人とお別れである。今日からまた長い旅が続く。ドアを開けると冷たく澄んだ空気がスーっと鼻を抜ける。アミはブルルと震えた。
「ぶぅちゃん、気をつけてね。」
おばあちゃんが俺の頭をなでる。
「ぶぅ、もう会えなくなっちゃう?」
アミが今にも泣きそうな顔で聞く。
分からない。だが、また会いたいと思う。
「いつでも帰ってきておいで。ぶぅちゃんなら大歓迎よ。」
こくんと頷く。俺の旅がうまく進めば、海を見ることができたなら、またここへ戻ってこよう。2人にきゅっとハグをして俺はまた旅の続きを始めた。

今年の冬も寒く、今年は何を編もうかとわくわくする。
夕焼色のブランケット、若葉色のニット帽、アミちゃんにも真っ赤なセーターを編んであげなくちゃ。会う度に、身長が伸びる孫を見て、子供の成長の早さに驚くばかり。色とりどりの毛糸玉を取り出しながら完成を思い浮かべる。
「・・・深い青色。」
彼の大好きな色。そして、数年前に訪れた小さな友達の好きな色。たんぽぽみたいな黄色も好きだったかしら。
カランカラン
玄関のドアのベルが音を立てる。
「おばあちゃーん!来たよー!」
アミちゃんがパタパタとこちらへ駆けてくる。その手には小包があった。
「あら。郵便が来ていたかしら。」
「ううん。ポストじゃなくて、ドアの足下に置かれてたの。」
小包を受け取って見てみると、住所や名前も書かれていない。小包にはテープやのり付けもなく、簡単にハラリと開いてしまった。
「なあに?それ。」
中には小瓶が2つ。1つはたんぽぽの原毛が丸々一個入っている。春の花だけど、白くてふわふわしている様子が雪のようで可愛らしい。もう1つには。
「・・・まあ!」
中には小さな貝殻と海水が入っていた。頭に彼の眩しい笑顔が浮かんだ。そして彼とおそろいの青いセーターをうれしそうに着てくれた、小さな友達のことを思い出したのだった。
お わ り
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
