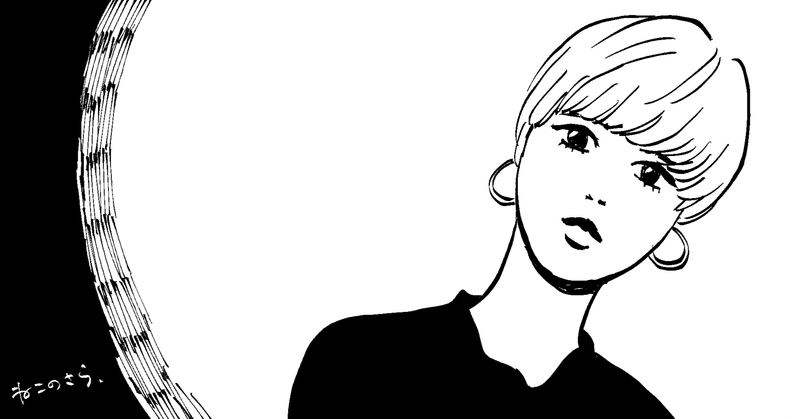
冬の列車
特急列車に乗っていた。
ゆうべ寝つけなかったせいか、さっき食べた駅弁のせいか、車掌が切符を点検しにくる前に、うっかり眠ってしまったらしい。誰かに一度、肩を叩かれたような気もするが、何もかもおぼろだ。
目が覚めた時には列車はもうずいぶん遠くに来ていた。
もう一度、自分のところに車掌はまわってくるだろうか。それともこのまま降りる駅に着いてしまうのか。だんだんと不安になってくる。
改札を出るとき、叱責されたらどうしようか。そんなことを考えていてたら、窓に自分の顔が映った。ああ、トンネルだ。どんよりした自分の目を見ていたら、また眠たくなってきた。
つぎに目が覚めると、まるで知らない駅に停まっている。目的の駅を行き過ぎたのか、まだなのかもわからない。私は今度こそ、車掌が来るのが待ち遠しかった。車内には誰もいなかったのだもの。
しばらくすると、連結ドアが開いて女の人が歩いて来た。
「降りないんですか」
「え」
「降りますよね」
女の人は少し怒ったように言った。
どういうことだろう。この人は、自分が降りる駅を知っているのか。そんなはずはない。それに、私が降りるのはここではないはずだ。
窓の外を見れば、ホームに乗客たちがぞろぞろと降りて行くところだ。
「じゃあ、私は先に降ります」
女の人は大きなバッグを抱えて降りて行った。
私はだんだん不安になって、ぜったい降りるはずのない駅に降りてしまった。もしかすると、私はずうっと先の駅まできてしまって、ここが終点なのかも知れない。
ホームには車掌がいた。車掌は一人一人の乗客の顔を見て、にっこりと微笑む。乗客はうれしそうに頷く。私の番が来ると、車掌が立ち止って不審そうな顔をした。やっぱり、私だけ切符を見せていないせいだ。急いでポケットから切符をとりだす。車掌はそれを制して頭を振ると、私を列車に押し戻してしまった。
ホームにいる人たちがこっちをじっと見ている。列車が動き出す。車掌がいないのにどうするんだろう。まさか自動運転なのか、そんなはずがないと思ったけれど、もう戻れない。
というところで、目が覚めた。ああ良かった。すべて夢だったんだ。
私は急いで切符を出すと、車掌がいつ来てくれてもいいように用意した。でも、その切符に刻印されていたのは半年前の真冬の日付だった。
空から白いものが舞い降りてくる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
