
普通教室のプロジェクター選びVol.2
Vol.1に続いて、プロジェクター選びの観点を紹介出来ればと思います。

「なぜ通常焦点モデルか」
いきなり焦点距離の話になってしまうのですが・・・
私の勤務校で出来たプロジェクター環境はVol.1で少し書いていますので、そちらをご覧ください。
自分たちは、現状あまり選ばれない通常焦点のモデルを選びました。
今の機種選定のスタンダードは、超単焦点をホワイトボードの上に設置する形かと思います。
通常焦点って、前に立つと眩しいし、影が出来たりと、デメリットが目立ちますよね。
じゃあ、なぜ?というところなのですが・・・
けっこう大きい違いなので、大事な2点を話させてください。
まず、価格です。
超単焦点モデルは高いです。
各校の超単焦点モデル選定理由はもっともなのですが、それは、業界の基準とか、電子黒板機能にこだわりすぎているんじゃないかなと思います。
ベンダーからのお勧めとかもあるのだと思います。
でも、それに頼らないこともとても大事で、
自分たちでちゃんと目的を定め、逆算して機器選定しましょう
。
工事後に後戻りできません。
通常焦点モデルにすれば、同じようなスペックでも
1台あたりのコストは相当抑えられるため、
2台構成が可能になります。
ここで安いモデル1台にケチらないことも大事なのですが、
超単焦点モデル2台は無理だというのは間違いないです。
「電子黒板の必要性」
プロジェクターの電子黒板機能。
いりますでしょうか?
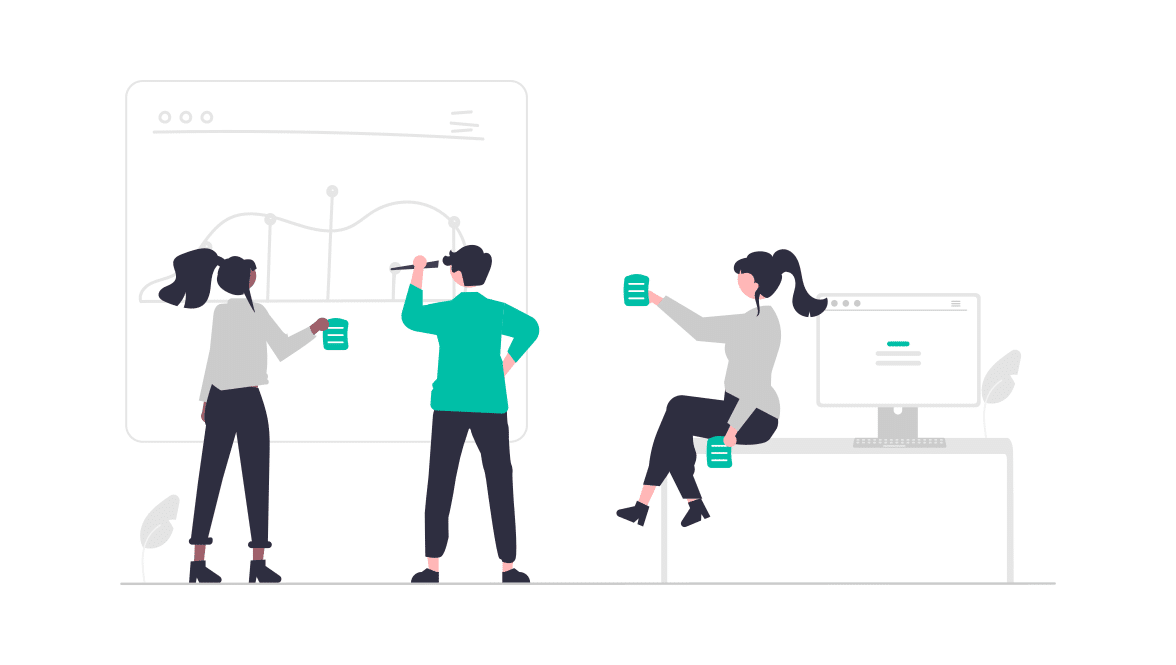
私はそもそも、昔からプロジェクターの電子黒板は必要ない派でした。
理由は簡単で、自分の授業の記録が
プロジェクターに依存してしまうからです。
次の授業ですぐ前回の授業の続きを表示出来る。これは良いのですが、
プロジェクターの電子黒板機能じゃなくても出来ます。
授業の書き込みとかを残したいのであれば、
端末自体のアプリで普段から操作するようにし、残すようにしましょう。
→こういったアプリは必須と言えます。また後の方で詳しく書きます。
つまりiPadなりChromebookなり、アプリで表示して授業展開し、ミラーリングさえ出来ればプロジェクターの役割はOKということです。
また、Vol.1で書いた機器が苦手な先生に対しても、
電子黒板機能をプロジェクターでやるとすると、
機器が難しく感じてしまいます。
これは間違いないです。
キャリブレーションを求められたり、自分の影の影響で
書きづらいというのもありますので。
通常焦点プロジェクターのデメリットである影の問題も、
電子黒板機能を使わなければほぼ解決です。
更に言うと、iPad上で記入して映すので・・・ホワイトボードの前に立たなくても板書き出来るんです。AirPlayですから。
机間巡視のように生徒の方に立ちながら書けたりもしますよ。
影はもちろん、プロジェクターの眩しさもそういった形で
少しデメリットが減りました。
ということで、Vol.2では”価格”と”電子黒板機能”から見た
通常焦点プロジェクターのメリットについて書かせていただきました。
Vol.3では、必要な入力についてや、あったほうが良い機能について触れたいと思います。
では。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
