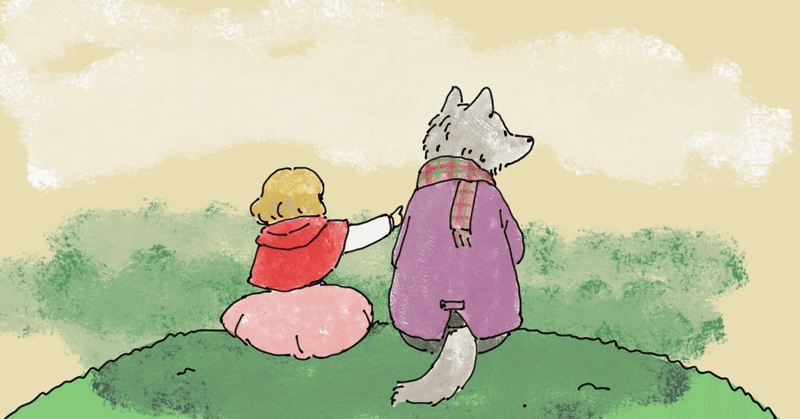
オオカミと狼伝説 【その1】 ミネソタの森で
文:ウィリアム・J・ロング(1867~1952年、アメリカ北東部で野生動物を観察して、多くの作品を書いた作家)
オオカミという生き物には、想像力をかきたてる何かが潜んでいる。そうでなければ、あれやこれやの逸話があるはずがない。
冬の夜、森を一人で歩いていたら突然、背後からオオカミの唸り声に襲われた、そういう経験がある人なら、その「何か」がわかるはず。
実のところ、そこにはなんの危険もないのだが。月に向かって吠え立てる犬と同じだ。しかし、影におおわれた森にいるせいで、あるいは昔話を思い出したことで、遠吠えが耳を震わせた途端、頭はオオカミへの恐怖でいっぱいになる。
だから、わたしがオオカミは人間を襲ったりしないと言っても、いやいやこういうことがあった、と反論するやつが必ず現われる。確かに、わたし自身、一度、シンリンオオカミの群れに追われたことがあるにはある。ただその終わりは、、、コメディだった。普通はその手の話の場合、むごたらしい終わりを迎えるものだ。
たとえば、オオカミの群れから命からがら逃れたある友人は、こんな風に話をする。
ある冬のこと、ミネソタでの話だ。俺はまだほんの子どもだった。その冬はひどい寒さで北から冷たい風が吹きつけていた。でかくて残忍なオオカミどもが、チャンスと見れば牧場の家畜を殺しにやってきた。夜になると、あいつらの遠吠えが聞こえてきた。森からの声が響き渡るのが恐ろしいのか、声がしない方がもっと怖いのか、何とも言えなかった。どっちにしても、あいつらがいることはわかっていた。その冬は、暗くなったら、誰も家の外には出ようとしなかった、そうせざるを得ないとき以外にはな。
このとき、わたしは熱心に耳を傾けてはいたものの、この手の面白い狼話というのは、いつだってこんな風に話されるものだ、ということを心にとめていた。こういう話はマスの卵と同じで、冷たい水の中でのみ孵化するのだ。
話のつづきを聞こう。
ある日の午後のことだ、ソリが壊れてしまい、父さんと俺は、家に帰るのが遅れた。家路につくときには、もう空は暗くなっていた。ひどくさびれた道だった。森がどこまでも続き、あたりは雪と凍った池ばかり、他には何もない。あとは途中に荒れ果てた小屋が一つあるのみ。森の道を8〜9キロ行ったところで、道を外れて湖を横切り、小さな森を通って、俺たちの農場がある草地に出る。あの夜のことはよく覚えてる。静まりかえった、月夜の晩で、冷え冷えとしていた。雪原をソリが走っていく音を聞いた。馬の息が白かったのを覚えている。
最初の大きな森を目一杯馬を走らせ、無事通り過ぎた。そしていとも容易く凍った湖の上に滑りこんだ。ウォーーーーーッ、そのとき、背後の森から、オオカミの遠吠えが聞こえてきた。俺は耳を澄ました。馬たちも同様だった。息を整える間もなく、毛が逆立つような恐ろしい鳴き声に包まれた。100頭のオオカミが一度に大声をあげているようだった。やつらは俺たちのいる道を、こっちに向かって走っていた。
父さんはパッと一度振り返り、馬にムチ打った。馬は神経を尖らせ、引き綱をグイと張って前に出ると、ソリを引いて飛び出した。ソリのスピードと幸運に恵まれて、なんとか転覆せずに走った。ソリを安定させるストックもなく、引き綱と緩んだチェーンだけで、狂ったみたいにズルズルと雪の上を這って進んだ。馬が蹴散らす氷のかけらが飛びちり、俺らの目をくらませた。その間、オオカミの鳴き声はどんどん近づいてきた。
やつらが氷の上を突進してくるのがわかり、毛が逆立った。だがその先で、さらに悪いことが待っていた。恐れていたことが起きたんだ。湖の端まで来たとき、岸の土手にぶつかった。馬はもう走れない、恐怖に陥った。ソリは宙を舞い、切り株に激突し、乗っていた俺らは跳ね飛ばされた。俺は頭から落下した。父さんはといえば、猫みたいにポンと宙を舞って馬具の上に落ちた。父さんも目一杯やられていた。立ちあがろうとしたら、父さんがこう叫んだ。「どこにいる、息子よ! ソリを外せ、ソリを外すんだ!」 俺らは素早く馬からソリを外し、その背に飛び乗って、死にものぐるいで馬を走らせた。俺が先頭を行き、次に父さんが続き、その後ろをオオカミの唸り声が追ってきた。
俺らは森を飛び出して草地に出た。柵を蹴散らし、納屋に突き進んだ。そこで納屋のドアを開けようとしたんだが、あわてているせいでうまくいかない。俺の馬は恐怖にとち狂っていた。なんとかドアを開けようとしていたところに、こいつが突進してきて俺を突き倒した。馬の後を追って父さんが納屋の中に走り込んだ。俺はもう中にいて安全だと踏んでいたんだ。父さんの姿が消えた瞬間、俺はまた極限状態になった。一人外に残されたとわかって、気絶しそうになった。で、俺はアビみたいに叫び声をあげた。すると父さんが飛び込んだとき以上のスピードで外に走り出てきた。父さんは俺をずた袋みたいに引っ張り上げ、納屋に走り込み、ドアをピシャリと閉めた。「だいじょうぶだ、もう、だいじょうぶだ」 父さんが言った。その声はかすれていた。
で、俺らはそのとき気づいたんだ、オオカミどもはもう声をあげてない。納屋の中では馬たちがゼーゼー息を切らせていた。納屋の外はといえば、何もかもが死んだように静まり返っていた。その静けさは何故かさっきまでの騒がしさ以上に恐ろしいものがあった。納屋のまわり四方八方から、オオカミは攻め込んでくるだろう。納屋の窓から外をのぞき、壁の隙間に耳を寄せて安全を確かめ、俺らは母屋に向かって駆け出した。
わたしはこの狼話の概要だけざっと話している。残念なことだ。友人の話はイキイキとして臨場感たっぷりで、スリリングなことこの上なかったし、ここまでのところ嘘はない。わたしはこの話にすっかり浸りきり、十分な関心を示したあとで、こう彼に尋ねた。
「その晩、きみはオオカミの姿を見たのかい?」
「いや」 友人は率直にそう答えた。「見てないし、見たくもない。遠吠えだけでたくさんだった」
「オオカミがいない」ということを除けば、まことに良くできた話と言える。翌朝、友人と父親が銃を手に昨日の現場に戻ると、置いていったソリのそばにはオオカミの足跡はなかった。そこから離れた遠い森の中で、真新しいオオカミの足跡がたくさん発見されたという。オオカミの遠吠え、それだけでこの親子は想像力たくましく恐怖に陥り、2頭の足の速い馬のおかげで自分たちはなんとか死を免れた、と信じるに至ったわけだ。
もう一人の友人の話をしよう。
+++
オオカミと狼伝説 【その2】 3月27日(水)公開
オオカミと狼伝説 【その2】 アラスカの鉱山技師
オオカミと狼伝説 【その3】 イタリアの村にて
オオカミと狼伝説 【その4】 雪嵐の森で
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
