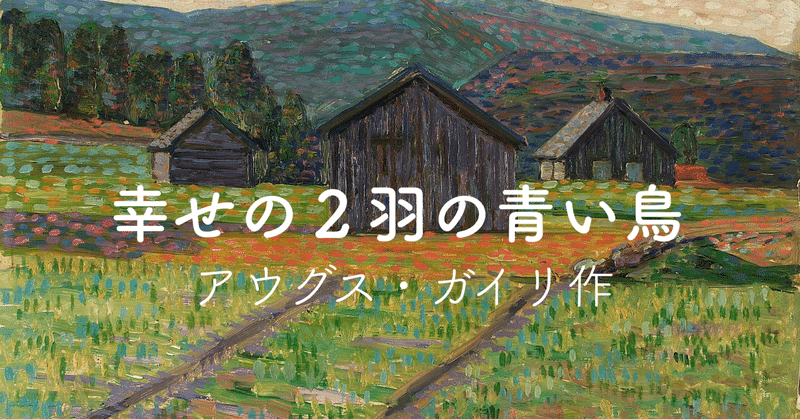
[エストニアの小説] 第6話 #3 ライ麦畑で最後の夜を(全17回・火金更新)
「母さんの目が光った。あたしはネズミみたいに部屋の隅で、じっと黙っていた。心臓がドキドキいうのを聞いた。『じゃあ、あんたには真面目な計画があるのかい?』 母さんはつづけて訊いた。『あんたはバカにするためにここに来て、若い娘をからかってるんじゃないと?』『そのとおり』とあんた。『将来、そういうことが起きるかもしれない。そう思ってる』『本当に?』 母さんは収まらない。するとあんたはしぶしぶ、ちょっと照れながらこう言った。『そういう風になることは、あり得ることだ、そうなんだ』」
「そのとき、あんたにはちゃんとした計画なんてなかった、でもあたしはあんたの手の内に、木から落ちた木の実みたいに収まった。あたしは一歩たりとも引き返さなかったし、ときにあんたの前に、ときに後ろについた。母さんはさらにこう言った。幸運の女神が微笑んでるよ、一生に一度のことだ、手放すんじゃないよ。だからあたしはあんたから離れやしない、ペンダントみたいにくっついてる。夜になって1日を終えると、あんたは農場のこと、牛や馬のこと、畑やそこで働く農夫や召使のことを話した。3人の農夫と2人の召使がいるって、言ったよね?」
ニペルナーティは握っていた手をカティから離すと、ため息をつき、父親のような調子でこう言った。「いいかい、カティ、わたしの言うことをそのまま受け取っていてはだめだ。わたしはあれやこれや言ったけど、農場に着いたら、君はがっかりするかもしれない。わたしが家を出たときには、確かに3人の農夫と2人の召使がいた。だけど今もいると誰に言える? わたしの留守中に誰かいなくなったかもしれない。わたしには知る由もない。近ごろは、農場の働き手がずっといることはない、そう思われている。1日、2日といて、飲んだり食べたりして、ぺッと唾を吐いていなくなる。あいつらはそうやって渡り歩く変人だ、国中を風が渡るように歩きまわってる。いいか、カティ、あいつらを扱うのは簡単じゃない。農場に住むようになったら、自分の目で確かめることができるよ。君の髪にはすぐに白髪が生えて、顔にはしわができるだろうね。農場を運営するのは、人が思うほど楽なものじゃない」
「あたしはやっていける」 カティが強い調子で言った。「それにもし、あんたが言うように、農夫の何人かがいなくなっても、他の人が助けてくれる。いまは畑仕事がいっぱいあって、大麦が収穫を待ってるし、カラスムギやじゃがいもだって。亜麻はすぐに収穫されて脱穀される。農夫なしには済まない。だけどなんとかやってみせる、そうできるさ。それにあんたには叔父さんがいるんだよね、そう言ってたよね。農場を監督するためにいる人だよ。その人は、あんたが変な女の子を連れて農場に帰ってきたら、びっくりするだろうね」
「そうだね」 ニペルナーティは素直に認めた。「きっとそうだ、わたしもそう思うよ」
「あんたは農場がどんだけ素晴らしいか話した」 カティは夢見るように言った。「あたしたちはあんたの言うことをじっと聞いていた、牧師がしゃべるのを聞いてるみたいにね。あんたをぐるりと取り囲んで聞いてた。それである日、あたしはあんたに言った、『トーマス、聞いて、あたしたちここにいてもしょうがない、早くあんたの農場に行こう』ってね。母さんもこう言った。『みんな、冬はもうすぐそこだよ、ツルだって南に飛んでいってる、巣にこもるときが来た』 でもあんたは聞いてやしなかった。あんたはあれやこれや、やるべきことに取りつかれていた。でもあたしはそのままにはしなかった、あんたを一人にはさせなかった、昼も夜もだ。『トーマス』 そうあたしは言った。『あんたの農場につれていって。見てわかるだろう、ここにはいる場所がないんだよ』『すぐだ、すぐだ』 あんたはそう言った、不機嫌そうにね。『今日なの、それとも明日?』 そうあたしが訊いた。『明日だ』 あんたはいやいやそう答えた。で、あんたの額に深いしわが100本くらい刻まれるのを見た。あんたは腰をかがめて、その目からは勇気や喜びが消えていた。あんたは急ぎたくはなかったし、もうちょっと考えたかったんだって、わかったよ。貧しい娘を自分の農場に突然、奥さんみたいにして連れていくのは簡単なことじゃない。まだ妻でもなく、そうなるかさえわかってない娘をね。だけど、次の朝早く、あたしは準備万端だった。前の晩、あたしは眠ることさえしなかった、荷物をつくって、頭にはスカーフを巻いて、あんたを待って小屋の前にすわってた。そしてあんたが起きてきた、眠そうでむっつりしてた。あたしのことを恐い顔で見た。それであたしはあんたに初めてのキスをした、嫌がらないでと頼んだ。母さんと小さな兄弟姉妹全員が出てきて、いい旅をと、また会いましょうと言った。で、あたしたちが少し家を離れたところで、みんなの声がはじけた。『雌牛をおくって、大きくて赤い牛だよ!」 そうピープが叫んだ。ヴォイリは馬がいいと言った。小さなマルは羊がいいと言った。だけどヤーンとヨハネスは雄牛を欲しがった。みんながそれぞれ欲しいものを言ったけど、母さんは黙ってそばに立って、涙を流していた。『結婚式に、あたしを呼ぶのを忘れないでね』 母さんは小さくそう言って、あたしたちを悲しげな目で見た。あんたは心を動かされて、あたしにこう言った。『みんな欲しい動物を手にしなくちゃね』 あんた、真面目に言ったんじゃないよね。雌牛に馬に雄牛に羊、あの子たち、馬や雄牛で何をしようっていうんだろうね。雌牛が1頭と子豚が2、3匹いれば充分だろうね、いたらありがたいと思うよ』
「ほんとうにね」とニペルナーティが同意した。「雄牛で何をしようって? これはきみと一緒にもう少し考えよう」
ニペルナーティはカティのまわりにライ麦の俵を集め、自分のジャケットで足をおおい、こう叫んだ。「ほら、もう夜だ、寒くなってきたぞ。なのにまだわたしは、君のベッドもつくれず、食べるものも見つけてきていない。神よ、君のくちびるは真っ青で、それに震えてる。ちょっとの間、君をここに置いていく、すわって、空で星がまたたいているのを見てるんだ。走っていって食べるものを手に入れてくるから。すぐだ、すぐに戻ってくるよ」
素早く、断固としてニペルナーティは立ち上がった。が、カティは自分も行きたいと言う。
「いっしょに行く」
「あー、バカだなぁ」 諭すように言う。「なんでわたしが君を置いて逃げるなんて考えるんだ? どうやってここから逃げられる、こんな見通しのいいところで、家から3日間も歩いてきて。どうしてわたしのことを信じてくれない」
「あんたはここのところ、気分がよく変わる、それが恐い」 カティが震えながら言った。「あんたの隣りで寝てるとき、半分眠った状態で、変な考えが浮かんでくるんだ。あんたには農場なんてない、家畜もだ、あんたはただの風来坊で、あたしをだましてる。それで涙をこらえなくちゃいけなくなる。あたしは小さな小屋で幸せで、そこにいることに満足していた。だけど、家にはお腹をすかせた子たちがいて、待っている。あの子たちは姉さんが幸せになることを信じてて、いい匂いのする焼きたてのパンや温かな肉の鍋を夢見てるんだ」
「あー、なんてことだ」 ニペルナーティはため息をついた。「なんで君はわたしのことを信じようとしない。何でだますんだ、一生の夢がよく肥えた雌牛だっていうチュンチュン鳴いてる小鳥を。君はそれを手に入れる、カティ、君の小さな兄弟姉妹の夢はかなう、そう誓うよ」
カティはにっこり笑って安心し、おずおずと言った。「あんたを疑ったりしてない、トーマス。ただ心の中によくわからない恐怖があって、どうしようもないんだ。だけどわかった、行っていいよ。お腹がすごく減ってるし、ここで待ってるから」
しばらくしてニペルナーティが手にいっぱいの食べものを抱えて戻ってきた。どこで手に入れたのか盗んだのか、神のみぞ知る。荷をほどくと、パンに肉、ミルク、ソリ用毛布などが出てきた。
「ここで食べものを得るのは難しくない」 ニペルナーティは嬉しそうに言った。「名前を言えば、ここの村の人たちは何でも差し出してくれる。わたしの農場までの道も聞いておいたよ。実際のところ、ここの森はずっと向こうまでわたしのものだ。疑うことなどない。食べるんだ、カティ、もう一晩ここで休むんだ、外でね、明日の朝には家にたどりつく。村の人たちはもう5キロもないって言っていた。君を抱えていくことだってできるよ」
カティが食べ終えると、トーマスはライ麦の俵二つでベッドをつくり、毛布でからだをおおってやった。そしてそのそばに座っていた。カティはすぐに目をつむった、長旅で疲れていたのだ。ニペルナーティは座って、そしてため息をついた。食べものには手をつけなかった。ライ麦の俵に寄りかかり、秋の空の流れ星を見つめ、またため息をついた。天の川がキリリッと青く冷たい空で輝き、燃えさしのような流れ星が落ちてきた。いくつかは空を横切っていき、長い長いしっぽのような火をたなびかせていった。フープ、フープ。フープ、フープ。ツルの鳴き声が夜の静けさの中で響いた。小さな雲みたいに森の上空にのぼっていき、夜の暗い空の中に消えていった。奇妙なほどに静かで平穏だった。ニペルナーティはライ麦の種が、俵の中で落ちて、雨粒のように地面を打つ音を聞いた。あちこちで靄(もや)が現れゆらめいて、タバコの煙のように、白い小さな塊となって地面をおおい始めていた。あたりは夜に満たされているのに、まだ脱穀機のうなり声が聞こえていた。
「ああ、困った」 ニペルナーティはため息をついた。「この子をどこに連れていったらいいのか、足を痛めたチュンチュン言う娘を。農場なんてない、家畜だって1匹もいない、小さな小屋すらもってない、お金も全部なくなった。この先どれくらい、この子を歩かせるつもりか、もっと嘘をつくのか、さらに約束をするのか。この3日間、この子はわたしの後を犬みたいにおとなしくついてきた。そして牛や馬のことを口にするたびに、目を輝かせている。ああ、神さま、誰からも求められていない男が、有頂天になって、自分のことを裕福な農夫と呼び、冗談半分に女の子に軽薄な言葉を吐いた。それ以来、火がついたみたいな事態になった。カティは寝ても覚めても、農場と家畜のことばかり口にしてる。そしてノリで貼ったみたいにこの男にひっついて離れない。で、男はこの子にこう言いたい、本当は農場なんてない、わたしたち二人がいるだけだ。心優しく幸運を願われて、家を出て、よい旅をと望まれた。いい旅を、でもどこに?」
'Two Bluebirds of Happiness' from "Toomas Nipernaadi" by August Gailit / Japanese translation © Kazue Daikoku
Title painting by Estonian artist, Konrad Mägi(1878-1925)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
