
17:「死」の恐怖より怖いもの。
こんにちは。
介護や認知症の悩み相談の
Haluhaave(ハルハーヴェ) MISAです
介護や家事、はたまた認知症の対応で大変な女性の力になれば、
との思いで活動しています。
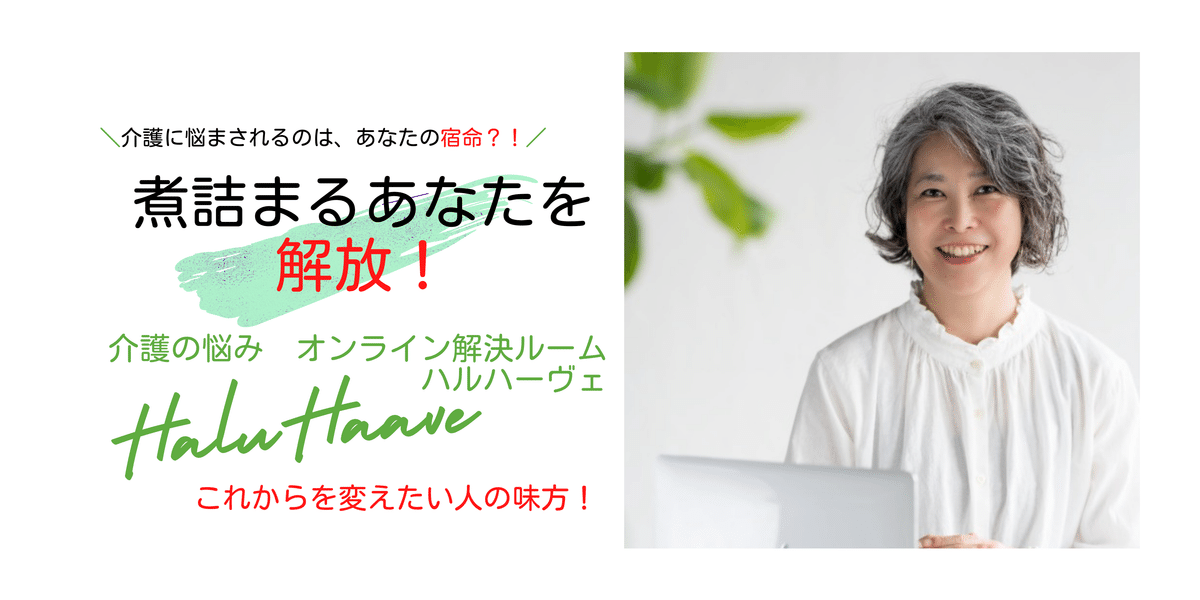
初めての方はこちら
↓↓
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ギョッとする題名ですね。驚かせてすみません。
怖い話ではありません。
今日は私の感想です。
「死」の恐怖より怖いもの・・・
それは、「そこに至るまでの孤独」。
そうかもしれない、としみじみ思いました。
普段、テレビはあまり見ないのですが、なんとなくつけた
NHKの番組。”あしたも晴れ!人生レシピ”。
初めて見ました。

内藤さんという女性医師の活動のお話でした。
在宅で最期を迎えたい方とその家族に寄り添った、医療サポートをされていました。
考え方や具体的な対応などを紹介されている中で、
「死」の恐怖よりそこに至るまでの孤独の方が、
人には恐怖。と言われていました。
一般的に、「死ぬのは怖い」と皆考えがちだけれど、
実は、「一人で苦しみながら世を去る」、「病気や不安を周囲に理解されず精神的に孤独」そんな状態で最期を迎えることの方が、恐怖なのだと。
亡くなれば、「恐怖」を感じる魂がないので、
そこに至るまでの方が大事なのかも、と納得。
「死」の恐怖、
「死に至るまで」の恐怖
どちらが怖いか、今のところ誰にも証明できないので、
正解はわかりませんが・・。
家族や色々な人と、日頃から交流を図り、互いに気にかけ、支え合えるような関係を作る。そうしておくことで孤独にならずに済むとアドバイスもされていましたね。
天涯孤独で独居だけど、ご近所さんや
馴染みのお店の方に支えられている。
そんな方と時折出会いました。
若い時ははちゃめちゃだったけれど、
晩年は周囲とうまく付き合って、支えてもらう。
不安もあったかもしれないですが、
見た目には穏やかに日々を過ごしている方が
多かったなあ、なんて思いました。
内藤医師いわく、人は一人で生きていく生き物ではないそうです
些細な日常、それがどれだけ貴重なことか。それを「幸せ」として噛み締めて欲しい。と言われてました。終末期が幸せな日々であれば、穏やかに最期を迎えられる、と。
普通の日常がとても貴重で幸せなことだった。そうコロナ禍で気づいた人も多いだろうから、些細な幸せも大事にしてほしいと話されてました。
何度となく来る震災、
身近な人の死
コロナ禍、
そんなことに出くわすたびに
日常は当たり前ではない
貴重な一日を大事に過ごそう
生きて起きられたこと、無事に1日を終えられたこと
周囲のみんなのおかげでやっていけていること
そんなこんなに感謝しなくちゃ!
そう思うんです。強く思うんですよ。
でもすぐ、忘れます。
とほほ。
「いっときそういったことが大事と思っても、人ってすぐ忘れてしまう。忘れず大事にしてほしい」と内藤医師は釘を刺されてました。
余談ですが、
私は腹が立ったり、ショックなことがあった時には、
明石家さんまさんの
「生きてるだけで丸儲け」を唱えるようにしてます。
自分の怒りや落ち込みが、些細なことだなあと切り替えができ
ます。
生きてるだけでもラッキー、奇跡。
毎日お風呂に入れて、暖かい布団で眠れて、
美味しい食事ができて、
ああなんて幸せ、
と穏やかさを取り戻せます。

注)理不尽な扱いを無理して我慢する方法ではありませんので
悪しからず。
最後まで寄り添った家族へのサポートも、感動しました。
ご本人は穏やかな気持ちで最期を迎えたとしても、残された側の喪失感や
悲しみについて、放置されたままではいけない、と。
献身的によく頑張られた、という声かけはもちろん
「なくなった方の人生の卒業証書」として、死亡診断書を遺族に渡す。
その人らしい人生を走り抜け、しっかり生き抜いた証。
死はそのゴール。
ゴールまでよく見届けられましたね、と伝える。
ゴールを見届けた、と言ってもらえることで、悲しみの淵にいても、
「ゴールまでの手伝いをやりきった」という達成感に変換できる。
そんな風に話されていました。
この声かけ、診断書の渡され方。悲しみより感動の涙が出そうです。
頑張った故人が主役だけど、私の頑張りも認めてもらえたんだ、って
思えますよね。
ただ、ご愁傷様、と渡されるより、絶対いいです。
気持ちとしておだやかに「死」を受け入れやすいと思います。
在宅で看取りをされているから、そういう配慮に余計に神経を
使っておられるんでしょうね。
在宅死を希望する人は50パーセントほどいるのに、自宅で実際看取られているのは10パーセント程度(数字はなんとなくです、すみません)とのこと。
病院での最期を希望する、それもありです。
治療を最後まで受けたい、医療の専門家に囲まれて
最後まで過ごしたい。そんな思いの方もあります。
死の間際に、本人又は家族が家での最期を迎えるのが怖くなる、
ということもよくあります。
※内藤医師も、
「在宅死が目的ではなく、幸せな終末期を過ごし、人生のゴールを穏やかに迎えることが大事」、と言われてました。
全く同感です。
現場にいた感覚で言ってしまうと、
在宅看取りを希望しても環境が整わない、というのが希望と実際の数字の差なのかなという印象です。
在宅看取りに協力してくれる往診医が近くにいない、ヘルパーさんの確保が十分できない、などなど
国も「在宅介護」や「在宅看取り」を勧めています。が、
誰もが安心して最期を迎えられるような制度や環境にはなってないと感じます。
「ご近所付き合い」は国も推奨する互助。大事でしょうが、これだけでは在宅見取りは成り立たないことも多いのが現実です。
内藤医師のような考えの方(医師に限らず)が増えると、
介護を受ける人もその家族も支援関係者も心強いなあ。
そう思った番組でした。
なんだか、つらつら書きましたが、
今日はこの辺で。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
介護が必要な方も、それを支える方も、楽しく豊かな生活ができることを願って・・・。
うまく行かなくても、落ち込んだりご自身を責めたりはしないでくださいね。
日々充分頑張っておられますので、そんな必要はないとわたしは思います。
責めたって良いことはありません。
「頑張ってるわ私!」と、ぜひご自身を褒めてあげてください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
