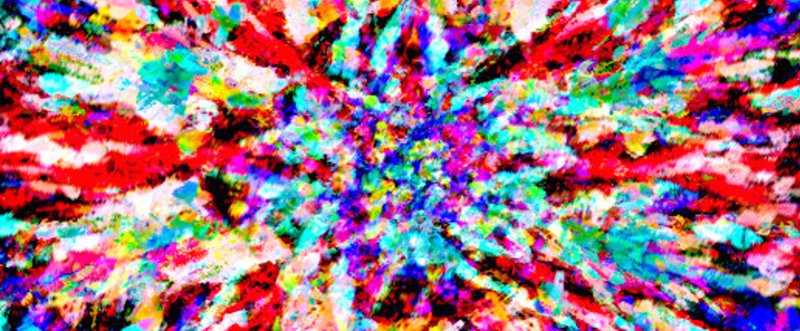
いとし君よ、百万年の愛の歌を
――遠い過去のことか、それとも遠い未来のことか、或るところに眠る機械人形が在ったらしい。
小さな古家に、植物が根差している。深い色をした緑の葉は、その古くなった壁のすべてを覆い、自らの命の力を誇っているようだった。天井まで届くその茎の先に、いくつもの蕾をつけたそれは、時折思い出したように花を開いて、鉱石のような輝く果実を実らせた。
その植物に囲まれた古家の中心で座るように眠るのは、遠目に見ると人間。しかし、近付いてみると、彼が機械人形ということに誰もが気が付くだろう。蕾が花を咲かせるのと同じように、彼も、鉱石の輝きにその身を守られながら浅い呼吸を繰り返し、時折薄目を開いて、またその瞼を閉じた。
……愛する者は、とうの昔に逝ってしまった。瞼を閉じると、その内側にちらつく面影のかがり火。そのあたたかい炎のせいか、機械の彼は深い眠りに落ちることもできずに、ただただ、自身の止まりかけた歯車をぬるい呼吸で回すことしかできない。
(この身体の……出来が良すぎる、というのも――)
最後に外へ出たのは、何年――何十――何百年――前なのだろう。最早自分がどのくらい此処にいるのかすらも分からない。ただ、ひび割れた壁の隙間から覗く斜陽が、世界は何も変わらずに廻っていることを彼に知らせた。
――おれは、いつまでこうしているつもりなのだろう。最初はこの両足で確かに立っていたはずだというのに、何故おれは今、こんなところに座り込んでいるのだろう。愛する者が死んだときの痛みを、今もまだ憶えている。あの裂かれるような痛みは、それまで経験したどんなものよりも激しく感じた。心が宿ったせいだ、心のせいだ、心がおれに在るせいだ。人を愛するということは、己の心を裂いてくれてやるのと同じことなのかもしれない。そうでなければ、こんなにも痛いはずがない。痛いはずがないのだ。
一度、歩いていた足を止め、座り込んでしまえば、再び立ち上がることはどうにも難しくなる。たいせつな者たちが逝き、なお、歩みを止めなかったこの機械人形は、一度この古家で立ち止まり、壁に形を変え生き続ける木を背にして座り込み、眠った。次に目を開けると、無意識の内に己の、地の魔力を注ぎ込んでいたのか、古家は植物に覆われていた。左手に絡まった蔓を眺め、そしてそのとき、彼は思ってしまった。おれには、立ち上がる理由がない、と。それから彼は立ち上がれずにいる。左手に絡まる蔓は、ただゆるく、彼の心を締め上げるばかりだ。
ふと、視線を上げると蕾が花を咲かせようとしていた。それを眺めながら、彼は自責の念にも似た気持ちを感じた。
自らが歩みを止めることなど、想像もしていなかった。機械のくせをして、心だけは人間のようなのだ。こんなにも人を愛するとは、それこそ、想像もできなかったことだというのに。
睫毛を伏せ、ゆるやかに呼吸をしていると、緑に覆われた古家の扉が、年季を感じさせる音を立てて開くのに彼は気付いた。そのことに内心驚きながらも、これだけ植物だらけなのだ、どんな者も奥までは入ってこないだろう、そう予想を立てて、彼は再び瞼を閉じる。
その予想とは裏腹に、緑をかき分け踏み拉く音は近くなる。その音が近付くにつれ、いよいよ彼は焦りのような気持ちを抱いた。まるではじめて目を開けたときと同じだ。どういう顔で、どういうことを言えばいいのか、彼にはまったく分からなかった。瞼の裏に、彼女の焔がちらつく。ついに足音が自分の目の前で止まっても、彼はその瞼を上げることができなかった。
虚を突くかのように、名前を呼ばれる。旧い名前だった。遠い昔に、たいせつな者たちから呼ばれていた、彼の名前。彼はないはずの心臓が飛び跳ねるような思いで、それを隠すこともできず、勢いよく顔を上げた。今、自分の名前を呼んだのは、目の前のこの少女だろうか。黒にも近い、深い青の髪をした少女を、彼は知らない。そうだ、知るはずもない。外に出たのはずっと前の話だ。ぐるぐると回る、不思議な思いを抱きながら、彼は言葉を発する。久しぶりに発したそれは、少しばかり掠れていた。
「……何故――俺の、名前を、知っている?」
そう問われた少女は、口元に手を当て、驚いたように笑った。
「知らん!――でも、知っていたから、知っているのだ。それよりおまえ、どうしてこんな処にいる? 動けないわけではないだろう?」
目の前の少女の物言いにたくさんの疑問を抱いていると、彼女の瞳に何かがちらついたのを彼は捉えた。それはいつも、彼が瞼の裏で見ていたものだった。少女の黒く、丸い瞳に、煌々と赤く燃える焔を彼は見たのだ。
鼓動の音が近かった。誰の心臓の音だ。彼は、訳も分からず心を打ち鳴らされている気分だった。目の前に極彩色が弾け、短い呼吸が繰り返される。そのたびに、天井に生った鉱石の実が緑の床に降り落ちた。
無意識に、彼もまた、旧い名前を口にした。遠い昔に呼んでいた、大切な者の名前を。少女は少しだけ目を見開き、喉の奥で笑った。
「なんだ。――おまえも、わたしの名前を知っているではないか。わたしを知っているのか?」
「……」
「わたしは、わたしのことがよく分からなくてなあ。目を開けたら、己の名以外はなんにも覚えてないとは!……いやはや、驚いた。けれど、何と言えばいいのか……此処に来なくてはならないような気がした。わたしは此処に――」
彼女が何かを言おうとしたのを遮って、彼は少女を抱き締めた。左手に絡まった蔓のことなどとうに忘れ、それを引き千切ったことにも気が付かず、彼は少女を抱き締めた。機械の喉が、灼けるように熱い。それでも彼は、ほとんど嗚咽のような声で言葉を紡いだ。
「――ずっと……ずっと、お前を待っていた」
「……泣いておるのか?……機械も泣くものなのだなあ……ほら、泣くな。ああ、まったく訳が解らん!――でも、おまえ、あったかいなあ……。おまえがわたしの忘れものだったのか、そうなのだろう? わたしは忘れものを探していたんだよ。なあ、おまえのことなのだろう?」
彼は長く息を吐くと、少女の肩を抱いていたその両腕を離した。そうしてから、震える左手で緑に覆われた床に触れる。すると、古家を覆っていた植物たちは淡く光を発しながら、大地に還っていくかのように静かに消えていった。彼の琥珀の色をした瞳がちかりと輝く。立ち上がると、視界が広がった。今まで忘れていたことだとはいえ、この古びた家は、随分と狭く見える。
止まりかけた歯車が、再び廻り出す気配を彼は感じた。また、少女も、何か幻を掴みかけたような気分だった。想い出さなければいけないことがある。少女のその様子に、機械人形の彼は少しだけ微笑んで、その手を取り古家の入り口へと歩を進めた。扉を開ける手前で少女を振り返り、まるで今までの、終わりを待つだけの生を忘れたかのようなやさしい顔で言葉を発した。
「俺のすべてをお前にやる。だから世界を――世界を、見に行こう」
少女が何かを言う前に、彼は扉を開いて外へと滑り出た。風が優しく、彼の髪を通り抜けていく。変わらず、この世界は美しい。おれが立ち止ろうが、歩き出そうが、この世界は変わらない。
彼は瞼を閉じた。彼女のかがり火が瞳の奥でやさしく揺れている。すべて、心のせいなのだ。この世界を美しいと思うのも、このかがり火を愛しいと思うのも。背後にいた少女が、彼の隣に並び、地平へ向けて手を伸ばした。すべて、心のせいだ。少女が笑ってから、世界が少し優しくなったような気がすることも、こうしてまた、歩き出そうとしていることも。それでよかった。それが、よかったのだ。おれの心は此処に在る。何もない方がよかったとは、今はもう思わない。おまえの瞳を見て、何かを想わないということは、きっと哀しいことだから。心が在れば、何度でも歌えるのだ。愛していると、何度でも、愛していると。
「なあ、何処から行く?」
不意に少女が、彼の琥珀の目を見つめながら言った。
「――ああ、風の吹く方へ行こう」
光の眩しさに目を細めながら、彼は風の向かう方向へ左手を伸ばした。それを眺めながら、少女が小さく笑う。
「……わたしには想い出さなければならないことが、どうやらたくさんあるらしい。どうする?」
「そうだな、歩きながら考えればいい。――想い出せなかったとしても、俺は隣にいる。今は……久しぶりに踊りたい。一緒に、踊ろう」
「……わたしは踊れないぞ」
「ああ、知っている」
長い旅路のはじまりを告げるかのように、何処かで汽笛の音がした。まるで急かすかのように音を立てるそれを聴きながら、しかし、急ぐ理由はないのだと、二人は心の奥で思った。時々は花でも摘みながら、ゆっくり歩いていければ、それでいい。きっと、それだけでいいのだ。不意に強い風が吹いて二人の服を揺らした。それにつられるようにして空を見上げれば、空は青く染まり、高く高く、何処までも高く、澄み渡っていた。
20160125
シリーズ:『貴石奇譚』〈太陽のための月〉
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
