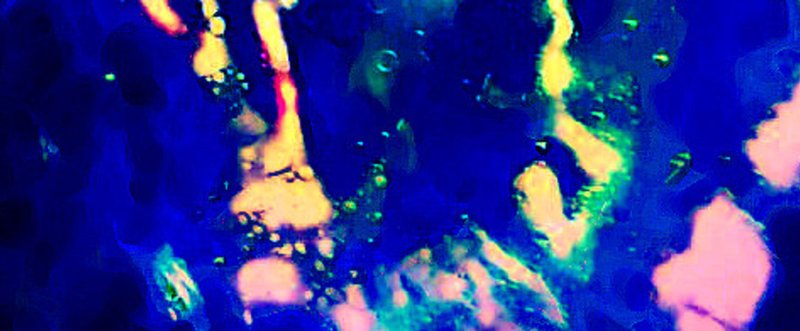
ライクアチャイルド
息を吸い込むと、花と草のにおいが身体を満たした。それらはやさしい色を纏っている。だが、この青年にとっては、夜空よりも黒に溶けた瞳の彼にとってそれらは、ただ、それだけのものだった。草花のにおい、やさしい香り、ただそれだけのもの。
彼が送っている生活は、生きている、そう言えるものなのだろうか。
夜明けの星を見送り、昼まで眠る。そして目覚めれば雑に作った料理を食べ、夜になるまで特に読みたくもない本を読んで過ごす。愛を忘れた少年の物語、星を深追いし過ぎて崖から落ちる老人の物語、恋やら愛やら希望やらの物語、彼の中には入っていかない物語。彼の目は文字の上を滑っていくだけだった。それもそうだろう、そんな物語たちのことなんて、彼にはどうでもよかったのだから。
彼は死んでいない、だが、生きてもいないようだった。
夕陽の赤と橙が、村全体を照らしている。大きな樹の下にいる彼も例外なく、この陽に照らされた。その眩しさに思わず目を瞑れば、瞼の裏にあの日の彼女の姿が浮かんだ。眉間の間に皺を刻みながら、彼は頭を振って再び目を開く。いつまでも彼女の影に囚われている自分が、どうしようもなく情けなかった。
はあ、と溜め息を吐いて彼は手元の本に目を落とした。そこではた、と気付く。
どこまで読んだのかが分からない。それどころか、本の内容すら彼には分からなかった。
今、主人公が何をしようとしているのか。どうしてそこにいるのか。物語がまったく、その一欠片すらも頭の中に入っていない。もう、この本の半分を読み終えていたというのに。
またか、と心の中でぼやいて彼は再度溜め息を吐いた。ゆるやかな苛立ちと己への嫌悪、そして言いようもない虚しさが心臓の奥で広がる。斜陽の鮮やかな色が、それをより一層深いものにした。
ふと、彼の背後から声がした。
「――その本、面白いよね」
反射的に振り向けば、そこには先日彼に空き家を譲り、自らを村長と称した少女が人懐っこそうな笑みを浮かべて立っていた。彼は表情を変えずに――彼にはそういうつもりはなかったのだが――ほとんど突き放すような言い方で呟いた。
「別に……何とも」
「えっ、そう?……あ、まだ半分じゃない。面白いのはね、この先だよ」
冷たいとも捉えられる彼の物言いを気にした様子もなく、少女はいつの間にか彼の前に回り、彼が持っている本を指差した。彼は読みながらもまったく内容が頭に入っていないその本を一瞥して、頁の間にある栞を抜き取り、特に躊躇いもなくその表紙を閉じた。少女の天色の瞳が疑問の色を浮かべたが、彼はそれに気付かないふりをした。
「読まないの?」
「……もう、星が出る時間なので」
彼の言葉は嘘ではなかったが、彼は星にもさして興味はなかった。だが、追いたくもない物語を追うよりは。捕まえる気のない物語を追うよりは。そんな風な気持ちで彼は毎晩星を見上げていた。星を見ていると、何となく、隣に彼女がいる気がするのだ。流星を待ったあの日のように。
読みたいわけでもない本を読むのは苦痛に近い。しかし、何もせずに呼吸だけを続ける、それはもっと痛かった。息を吸うたびに、彼女の笑顔を想い出す。息を吐くたびに、彼女の白くなった肌、死人の骨の色を想い出す。それらを想うたびに喉が渇き、肺は痛み、心臓は冷たく軋んだ。震える手で耳を塞げば、情けない自分の鼓動が近く聴こえて、その音にすら吐き気を催した。
嫌なことを思い出した、と彼は心の中で目の前の少女に悪態をつく。気を抜けば、自分の理不尽な心の矛先がこの少女にも向いてしまいそうだった。それを何とか心の中に押し込める代わりに、彼は何度目かの溜め息を吐いた。遠くで輝く一番星を眺めている少女がちらとこちらを振り向いて問いかける。
「――星が好き?」
彼は答えに詰まった。好き。星が、好き。好き? その答えを返せない彼と、小さな光が煌めきはじめた空を見上げる少女の間に沈黙が流れる。
その問いに知らないふりを決め込むこともできた。だが、どうだろう、彼は少女のこの問いからは逃れられないような気がした。もしここでこの問いかけをなかったものにしたとしても、彼はこの問いにずっと心を揺さぶられるだろう。
呟くように彼は言った。
「好き……では」
「じゃあ――星が見たい?」
「見たい……というか……幼馴染が、いえ、死んだんですけど、そいつが星……好きで――流星群が見たい、って――だから、何となく」
何を馬鹿正直に。彼は喉の奥で自分を罵った。短く息を吐いて見上げれば、空はもうほとんど夜の色に塗れている。星のよく見えるこの村の空は、今日もたくさんの瞬きを湛えて輝いていた。
「――星がもっと綺麗に見える方法、教えてあげよっか」
「……いや、興味ないです」
「まあまあ。聞くだけ聞いてよ」
空気は少しばかり冷たさを孕み、しかし澄み切っている。草花のにおいが風に漂うのを感じながら、この土地の空の高さと星の瞬きを眺め、彼は少女の言葉の続きを待った。
「しばらく目を閉じていて。……昔……って言ってもそんなに前じゃないけど、そう、もっと夜が深い土地へ行ったときにね、教えてもらったんだ。〝夜の闇に一度身を浸せ、そうして再び目を開いたとき、おまえは夜の光の煌めきを知るだろう〟――って。本の一文らしいけどね。……ああ、まだ目を開けないで」
彼はとりあえず言われるままに目を閉じていた。瞼を閉じると、やはりそこには彼女のやさしい面影がちらつく。これならば、何も見えない方がましだった。いいや、何も見えない方が良かったのだ。彼は溜め息に似ているがそれとは違う、溜め息よりも細い息を地面に落とした。
夜の闇に一度身を浸せ。それが自分にできるとは到底思えなかった。自分はただ、ちらつく彼女の姿を振り払い振り払い、心の中からどうにかして押し出そうとするばかり。ほんとうに自分の心の中から彼女が去っていくことが、彼にはいちばん恐ろしいことだというのに。自分の中で何かが変わる、それが彼にとっていちばん恐ろしいことだというのに。
「――空の方向いて、目を開けてみて」
そう声がかかり、彼は目を開けた。刺すような瞬きたちが彼の瞳を支配する。
いつの間に、こんなにも多くの星が出てきていたのだろう。それとも、見えていなかっただけだろうか。見ようとしていなかっただけだろうか。それらはさながら光の海、遠い街の輝き、砕けて散った真珠の無数の欠片。目を閉じて、また開く。そんなもの、まるで子どもの考えだ、そう喉の奥で小馬鹿にしていた彼は驚嘆まじりに短く息をついた。
「瞼の裏には何が見えた?……きっと、たいせつなものだよね。夜の闇に身を浸す……ってきっと、何も見えないようにするってことじゃないと思うんだ。たぶん――自分の影と、暗くて弱い部分と向き合う――みたいな意味なのかなって」
少女のその言葉に彼は心に冷たいものが帰ってくるのを感じた。今、星に見惚れて一瞬忘れていたもの。彼女の面影、あの日流れなかった星、一億年前の光、白い骨の色が。
「分かったようなことを言う……大事な人を亡くしたことなんて、あんたにはないだろ」
言い切ってから彼は、はっとして少女の方に顔を向けた。右手で拳をつくって力を込める。冷ややかに己を責め立てる自分の心と、怒りに身を任せている自分の心が、己の両こめかみで音を立てて弾けるようだった。
……おれは自分の滅茶苦茶な心の矛を、この人にまで向けてしまった。
その悔恨をこめかみの赤い光が叩き潰す。
……だが、そんな風に言わせたのはこの人だ。ああ言って何が悪い、何が悪かった。おれは悪くない。おれのことなんて放っておけばいいのに、口を出したこの人が悪い。なあ、そうだろう。そうじゃないか。
泣くか怒るかするだろう、と彼は少女の方を見て身構えていたが、その思いとは裏腹に少女は彼の方へ首だけ振り返って、困ったように笑うだけだった。
「あるよ」
「え?」
「たいせつな人を亡くしたこと、あるよ」
そう言うと少女は星空の方へ視線を戻した。彼はまるで氷水を顔にかけられたような気分で、少女の後ろ姿を見つめた。何も言うことができず、こめかみで暴れた赤い怒りを心の中で罵り、早くも帰ってきた後悔の念を抱えながら。
「たいせつな人を失って悲しいっていうのは分かるんだ……たぶん。でも、ずっと誰かの死を悲しみ続けること……それってきっと、悲しいことだよ。――知ったようなことを言うけど――幸せだったよ、その幼馴染さん。きみにこんなに想ってもらえて――そう、今も」
少女の言葉を聴きながら、彼は思う。
おれは、彼女の死を悲しんでいたのだろうか、ほんとうに?――おれが悼んでいたのは、彼女を失ったおれ自身ではないのか。おれは、おれのことしか考えていない。そうではないか?
寒気が背筋をのぼってくるのを彼は感じた。今度は腰に氷を直接当てられたようだった。
「……あの」
「ん?」
「すみません、いろいろ……」
「ううん」
彼が謝るとは思っていなかったのだろう、少女は可笑しそうに笑った。そうしてから樹の下に座っている彼の隣に自身も腰を下ろす。少女の青空を映した瞳が、彼のどこか虚ろな黒をしっかりと捉えた。
「――ねえ、だいじょうぶだよ」
言い切った少女に、何が、と彼は問わなかった。ただ、今日の斜陽よりもやさしい光で、身体のあちこちに当てられていた氷が溶けていくのを彼は感じた。
だいじょうぶ、そう言われたのは彼女を失って初めてだったかもしれない。ああ、何だ、おれはこれだけで良かったのか。何て――何て馬鹿々々しい。そう、そうなのだろう。おれは馬鹿なのだ。どうしようもなく、どうしようもなく馬鹿なのだ。
心の中で自分自身に悪態をつきながら、彼は瞼を閉じる。瞼の闇に、彼女の面影が浮かんだ。それは変わらないもので、いつまで抱えていくことになるものなのか彼には分からなかったが、そのやさしい彼女の面影を見ても、不思議といつもの痛みが襲ってこないことに彼は気付いて、喉の奥で少しばかり笑った。
ああ、確かに。確かに、おれはだいじょうぶらしい。
少女が彼の手によって地面に置かれた本の表紙を撫でる。
「ね、この本面白いんだよ、ほんとうに!」
どこがどう面白いのかを、少女がとうもろこし色の髪を揺らし手を振り、何とかこちらに伝えようと奮闘した。その様子を見て、彼はまた少し笑った。そして、自分が栞を抜き取ってしまった本を地面から拾い上げ、また自らも立ち上がり、少女に声を掛けることもなく自分の家の方へ歩を進めはじめた。その背を少女の声が追いかける。
「読んだら、感想! 感想ね!」
彼は歩きながら思う。どうせなら、あの少女に恋ができれば良かった、と。陽の光を纏い、花のにおいがする、やさしいあの少女に。少女の隣にいると夜の闇が冷たくない、そう思った。それは、彼がこの村に来て初めてのことだった。馬鹿みたいに恋を、そう、心臓の中に在る彼女のことを忘れるほどに恋ができれば。そこまで考えて、彼は短く息を吐く。そして頭の上に瞬く星の海を眺めた。どうやらおれはあの少女に恋はできないらしい。それは最初に会ったときから分かっていた。おそらく、少女もそうだろう。理由など、ごくごく単純なもの。彼女はまったく好みではないのだった。そう、それだけだ。ありふれた理由、それだけのこと。
だが、空っぽの心で読んでも内容がまったく入ってこなかったこの本。彼が自ら栞を抜き取ってしまったこの本。少女が面白い、と勧めてきたこの本。これは確かに面白いものだった。家に帰ると、彼はまずこの本の表紙を再び開いた。少女と話した後に読むこの物語は、前開いたときとまったく異なる物語のように感じ、彼は眠るのも忘れ、ただ、この本に紡がれた物語を追った。
本を読み終え、久しぶりに空腹を感じた頃にはもう、朝陽が顔を出しはじめていた。しかし、彼がそんな風に夢中で物語を追ったこと、それはこの本と、彼自身しか知らない秘密となったのだった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
