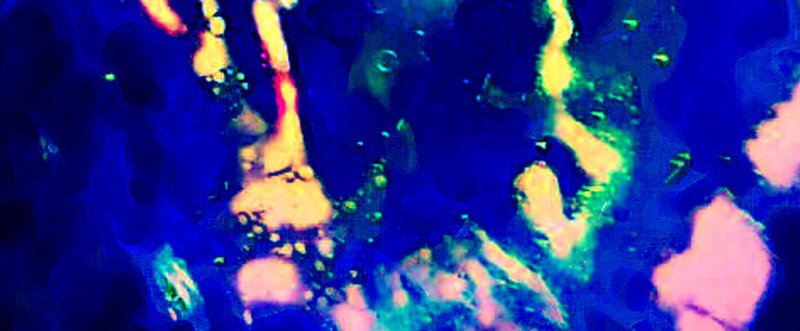
ひこばえを食むけもの
流れていく雲を眺める、その瞳をただ見ていた。
柔らかな黒色をした彼女の瞳が、ゆっくりと流れていく白色を眺めるのを止め、こちらを見た。さらさらとした緑の草の上に寝転んでいる彼女の前髪が風に揺られ額の上で遊んでいる。色とりどりの植物が所狭しと生い茂る道、街中ではあまり香らないが不思議と心が落ち着く香りのする白い小道を抜けた先に、この小さな丘は在った。街を歩いていて偶々見付けた小道、その先の丘、そこで二人はただ何となく空を見上げている。緑に染まったこの丘は確かに街の中に在るはずなのに、まるで別の世界に来たかのように新鮮に感じられた。
「……今日は読みたかった天文書が手に入ってよかったよ」
そう言って彼女は、自分の横に置いてある本の入った紙袋を腹の上に乗せて軽く叩いた。
「ヨタカはほんとうに好きだな、星がさ」
「それに付き合うアトリも相当じゃないかな。それとも単に私のことが好きすぎるだけ?」
「――どうかな……」
アトリはほとんど溜め息に近い笑いを吐き出し、遠くで漂う雲を眺めた。
「ヨタカは将来何になりたいんだ? やっぱり、天文学者?」
「うん……? 将来の夢、かぁ。それはあんまり考えたことがなかったよ」
「え――そうなのか」
ヨタカはどこか眩しそうにアトリの夜色をした瞳を見つめてから、青い空へと視線を移した。
「そうだよ。今まで君に聞かれなかったし――何より、今が楽しいから」
「……そう、か」
「ね、此処って何だか……秘密基地みたいだね」
言われてアトリは辺りを見回した。小高い丘から見えるのは一面の緑色、草原だ。此処は、ほんとうに街の中なのだろうか。通ってきた、色が生い茂るあの道は街の外に繋がっていて、此処は何処か遠くの外れに在る草原なのではないだろうか。だとしたら、通ってきた小道からあまり離れた場所へ行くべきではない。アトリは起き上がり、後ろを振り返った。どうやら、通ってきた道はまだ近くに在るらしい。だが、とアトリは心の中でかぶりを振る。だが、別に帰り道を見失っても構わないのだ。たとえ帰れなくなったとしても。此処にヨタカがいるのなら、それだけでいい。おれが何を失ったとしても、此処にヨタカがいるのなら。馬鹿げている、と己に指を突き付けて笑い出したくなった。けれども、この馬鹿げた想いは確かに本心なのだ。そうだ、それだけだ。アトリはぽつりと言葉を零した。
「此処で星を見たら、綺麗だろうな……」
ヨタカも起き上がり、アトリの言葉に頷いた。
「そうだね……また、来れるかな」
「来れるだろ、来れたんだから」
「――うん」
そう言って目を細めたヨタカの睫毛が、どこか寂しげなものに見えたのは気のせいだろうか。この草原への道を覚えていられないかもしれない、ヨタカはそれを不安に思っているのだろうか。アトリは目元を柔らかく緩め、それから少しだけ笑い、ヨタカに言った。
「だいじょうぶだよ、道なら俺が覚えとくから」
それを聞いたヨタカは一瞬その黒い瞳を丸くさせて、予想外といったような顔をしてアトリを見た。何呼吸かの間が空いた後、ヨタカは漏らすように笑い、困ったね、と頭を左右に振る。アトリは何か間違えただろうか、と少しばかり困惑したが、ヨタカが笑っているのを見てそれも最早どうでもよくなってしまった。ヨタカは目を細めてアトリを見た。太陽の白い光に照らされて、彼女の睫毛が星のように輝いている。その輝きに先の寂しさは見られなかったが、寂しさよりももっと深いものがそこには見え隠れしているのをアトリは感じ、どこか虚を突かれたような気持ちになった。
「――君は――どうして私を好きになってしまったんだろうね」
何故だかアトリは、その言葉には動揺しなかった。ただ、夜の光に落ちていくかのような、どこか優しくそして哀しい、そんな気持ちになるばかりだった。アトリは一瞬空を見上げ、それから瞼を下ろした。
「……どうしてだろう、な……」
言いながら、簡単だ、と思う。おれがおまえを好きな理由など、そんなものは一つに決まっている。おれがおれで、おまえがおまえだから。おれがおれだから、おまえがおまえだから、おれはおまえが好きなのだ。けれど、こんなこと、彼女に言えるはずもない。この恋は叶うことのないものだ。理由など知る由もないが、これは彼女への恋心を自覚したときからずっと感じていたものだった。それでもいい。それでもいいのだ。今、彼女が此処にいてくれるのなら、それだけで。
「……あのさ、ヨタカ」
「うん」
「今は……そばにいてほしいんだ。俺は、まだ……子ども、だから。その内きっと、大人になって……一人でも立てるようになると思うから。そのときには、おまえも俺も――きっと自分が進みたい道が見えてる、から。たぶん、進む道は別々だよ。それでもいいんだ……そのときは、自分の道を往こう。それがきっと――大人になるってこと、だと思うから。だけど、今は――」
言ってから、急にヨタカの顔を見るのが怖くなってしまった。閉じた瞼を押し上げて、彼女の顔を見ることが。今、ヨタカはどんな顔をしているのだろうか。少し冷たくなってきた風が吹く。その風に運ばれて、ヨタカの小さな答えが耳に運ばれてきた。
「……今は、いるよ。今は、此処に」
アトリは目を開けて、ヨタカの方を見た。吹く風が、彼女の長い黒髪を揺らしている。無遠慮に触れることができればどんなによかっただろう。けれどやはり、自分には触れることができない。理由はない、しかし触れれば、そこからすべてが砕けて壊れるような気がしているのだ。揺れる髪を見つめながら、少しだけ掠れた声でアトリは口元に言葉を乗せた。
「――ありがとう」
空を見上げる。そこには少しばかり傾いだ太陽の光と、流れていく白い雲が在った。ああ、と想う。ああ、何もない一日だ。今日は何もない一日だった。ただ、ただ恋をしただけだった。それだけだ、それだけだった。太陽の眩しい光が瞳を刺す。今日は何もない一日だった。けれど何故だか、少しだけ涙が出た。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
