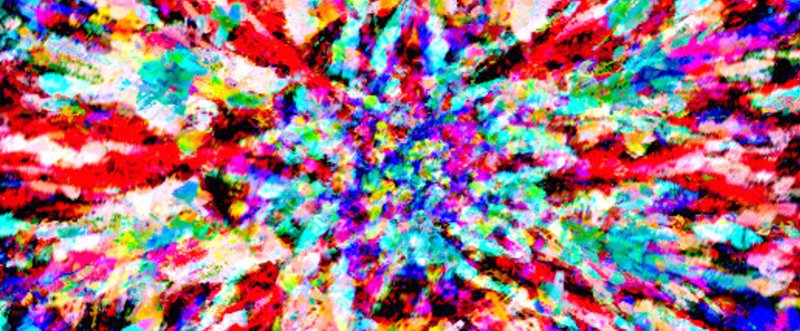
白い孔雀
――妖精が踊っている。
それがはじまりだった。
歯車が回る音が聴こえる。
機械仕掛けのこの街では、歯車と歯車が組み合わさる音、機械が忙しなく動く音、誰かの運ぶ部品が地面を転がる音、そういった音ばかりが耳に入ってくる。その、自然ではなく人々がつくり出す音たちが彼は好きだった。彼――スケッチブックを持って足早に街を歩いている、カルトという名の少年は、こんにち、忘れられないものに出会った。
(ああ、今日は調子が悪い……)
そんな風に口の中だけで呟きながら、カルトがいつものように工房の外で新しい発明の構想を練っていると、大通りの辺りから聴き慣れない音が流れてきた。それは音、というよりは楽の音だった。この街では聴き慣れない曲調が身体に入っては出ていく内に、その音楽を奏でている者の正体を知りたくなって、カルトは音のする方へ歩を進めた。
大通りを進んで広場に出てみると、そこでは小さな劇団が音楽を奏でながら公演をしている最中だった。その周りに集まる人はまばらだったが、宙を飛んだり跳ねたりする楽しげな音が、いつも聞いている街の音とはまた違う風に心地好く、カルトは少し遠巻きにその公演を眺めることにした。
「ここまで観てくれてどうもありがとう。――次で最後の演目になります、どうぞ最後までお付き合いくださいね」
その言葉と共に新たな音楽が始まる。何人かの少女たちが舞うようにして音楽を奏でている楽団の前に現れ踊ったが、その瞬間カルトの周りからすべての音がかき消えた。カルトは踊り子たちの中心で踊る、或る少女に目を奪われたのだった。
――妖精が踊っている、と思った。
少女の長い月白の髪が、踊る彼女に呼応するかのように揺れ動いた。額のサークレットが月のように輝いている。踊る彼女が手を伸ばすと、カルトはそのまま自らの心臓を掴まれるのではないか、そんな風に必要のない心配をした。
もう少し近くで少女のことを見てみたかった。だが、カルトの心とは裏腹に、彼の身体は言うことを聞かなかった。どうにも足が動かない。じりじりと灼ける心を持て余しながら、カルトがその場で動けずになっていると、こちらに視線を向けた少女の瞳と彼の瞳がかち合った。
彼女の瞳は、沈む太陽の色だった。
完璧だ、とカルトは思った。カルトの瞳に映る彼女は、何もかもが完璧だった。
そこから演目が終わるまでカルトはただじっと彼女の演舞を見つめていたが、やがて劇団が撤収していくのを見届けると彼も立ち上がり、足早に広場を後にした。
彼は速る動悸と気を抜けばもつれそうになる足を心の中で罵りながら、視界に映った手ごろな路地裏に滑り込んだ。滑る、というよりは転がるようだったが。とにかく彼は、何でもいいから静かなところに行きたかったのだ。
カルトは片手に抱えたスケッチブックを膝の上に広げ、腰の革袋から鉛筆を取り出すと、さながら嵐のような勢いで先ほど踊っていた彼女を描いた。そして三枚ほど彼女を素描したかと思えば、次のページにいきなり設計図のようなものを書き殴り始めた。
「――それ、私?」
カルトの筆が段々と静かになっていくのを見計らってか、何処だろうか、上の方から声が降ってきた。
はっとしてカルトが上を見上げると、あの踊り子の少女が陽光を背負って屋根の上に座っていた。それを見たカルトは鉛筆が手から転げ落ちるのにも気付かず、慌てて立ち上がって叫んだ。
「あ――危ないよ!」
「……そう?」
鈴の鳴るような声で少女は返した。カルトは、屋根の上へ向かってまた声を上げる。
「そう!」
それを聞くと彼女は、路地裏に連なる家々の壁を蹴るようにしてカルトの前に降りてきた。それがまるで、羽が生えているような身のこなしだったものだから、カルトには妖精が踊るようにして目の前に降りてきたようにしか見えなかったが、よく見ると彼女は、魔法で足に風を纏わせながらこちらへ降りてきたらしかった。
ぼんやり自分を見ているカルトを見て、少女はにんまりと笑い、彼の持っているスケッチブックを指差した。
「これで満足?……で、それ、私?」
うまくかわせたと思った話題を再び引っ張り出され、カルトは唸った。やっぱりこんなところで描くんじゃなかった、一度工房へ戻っておけばよかったんだ、そんな風に後悔の念が彼を責め立てたが、後悔したところで逃げ道が姿を見せるわけではない。カルトは観念して、少女とは目線を合わさずに頷いた。
「そう――だけど……」
「へえ! 上手いものねえ……。あなたのこと、最初は画家かと思ったんだけど――ただの画家だったら声はかけなかったんだけどね――どうやら違うみたいだから、つい。びっくりした? でも私もびっくりしたわ。あなた、発明家でしょう!」
そう言った少女はカルトの手からスケッチブックをふんだくり、設計図が描き殴ってあるページを彼に突き付けた。彼女の夕陽にも似た瞳がきらきらと輝いているのを見て、カルトはたじろいだ。
「――ま、待ってよ。発明家って言っても僕は親の工房で手伝いとかしてるだけの、卵……見習いみたいなものだし。それに発明家なんてこの街にはたくさんいるだろ? 別にそこまで珍しいものでも……」
カルトが何かもぐもぐ言うのを遮るように少女が口を開く。
「あなたが? 珍しくない? あんな小さな劇団の公演を真剣に眺めてたあなたが? 今にも走り出しそうな勢いで路地裏に入り込んで、何やら私の絵を描いていたと思ったらよく解らない設計図をめちゃくちゃな勢いで描き殴り始めたあなたが、珍しくないですって?」
彼女の怒涛の勢いに気圧され、カルトは両手を顔の前に上げて押し黙った。少女が月白の髪を揺らしながら、長く息を吐いた。
「これ、何?」
少女は言いながら、彼の描いた設計図をまじまじと見ている。カルトが頬を掻きながら、その問いに答えた。
「――機械人形、だよ。えっと……たまに見かけないかい? あれは魔法で動いてるものが多いんだけど……僕は魔法の力に頼り過ぎずに、自分の技術で機械人形を造ってみたいんだ。動力部分――人形の心臓は魔法じゃなくて、機械で動かす。人形を動かすにあたって、魔法に頼らなきゃいけない面も多いだろうけど、それでも僕はすべてを魔法に頼らなくても動ける機械人形を造りたいんだ」
それを聞いた少女は勢いよく設計図から顔を上げた。彼女の瞳がより一層輝きを増す。彼女はカルトのスケッチブックを掲げて、その場でくるりと回ってみせた。
「ほら、やっぱりあなたは発明家よ! ここに描いてある機械人形は男の子よね? でもそのモデルは私なんでしょう? なんて面白いの? 最高よ! 今、最高に楽しいわ!――ねえ、あなた、名前は?」
楽しそうに笑い声を上げながらくるくると回っている彼女が、カルトの方を振り返った。その笑顔が劇団で踊っているときのものとはまた違って見えて、カルトは目の前で光が弾けたように思った。
「――カルト。カルト・エクレール。……君は?」
「私、韻響。よくキョウって呼ばれるわ。ねえカルト、さっき私、あの劇団――トルメンタ一座って言うんだけどね、辞めたのよ」
「えっ?」
想像もしていなかった彼女――韻響の言葉に、カルトの言葉が詰まった。では、もう彼女が踊るところを観ることはできないのだろうか。熱かった血管を巡る血が、ゆっくりと冷えていくのを彼は感じた。その様子を見て、韻響がけらけらと笑う。カルトは怪訝な顔をして彼女の方を見た。
「踊り子を辞めたわけじゃないわ。あそこがちょっと肌に合わなかっただけ。まあ――踊り子稼業も、姉が、母が、祖母が、みーんな踊り子だったからやってるだけなんだけど」
「え――あんなに綺麗なのに?」
つい口を突いて出た言葉に、カルトはしまった、と口を押さえた。韻響がからかうように笑っているのを見て、顔に熱が集まっていくのを彼は感じた。
「ありがとう。……私、カルトの造った機械人形となら踊ってもいいって思ったわ。それってすっごく、面白そうでしょ?」
「……君は、僕がこれを完成できるって信じてくれるのか」
「ええ。だってあなた、自分のことを信じてるでしょう。自分なら、造れるって」
カルトは照れ臭そうに頷いた。その瞬間、身体が前に引っ張られるような感じを覚える。それは、韻響がカルトの手を引いて路地裏を抜けようとしているからであった。韻響に連れられて路地裏を抜けると、広い道に出た。空を見上げると、分厚い雲の隙間から青色が顔を覗かせている。韻響が両手をカルトの方へ差し出した。
「ねえ! 世界を見に行こう! 知りましょうよ、歴史を、技術を、世界を!」
その言葉にカルトは肩を揺らして韻響の方を見た。彼女の月白の髪が、沈む太陽の瞳が、すべてが、太陽に照らさせて煌めている。
この手を取らなければならない。自分の心がそう言っているのをカルトは感じた。世界を見る。それがどういうことで、そのためにどうすればいいのか、今のカルトにはまったく見当もつかなかったが、そんなこと、どうでもいい。それでも自分はこの人の手を取るのだ。そう言うかのように、彼の心臓が強く彼を打ち付けた。彼は目を瞑り、一呼吸だけ置いてから口を開いた。
「――うん、世界を見に行こう!」
そうして彼は、彼女の手を取った。それは当たり前のことだった。何故なら彼は、彼女に恋をしたのだから。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
