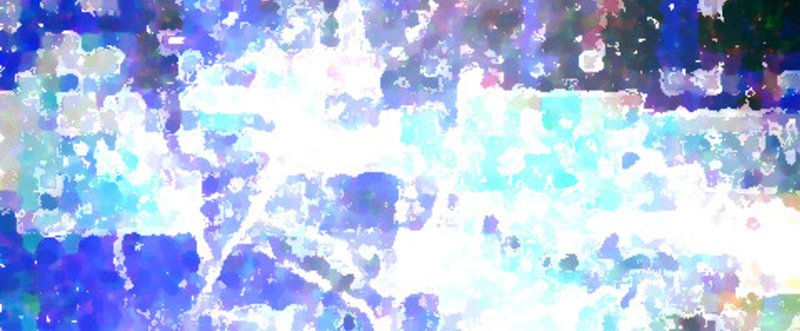
太陽のことわり
足枷は外された。
だが、それでも、この身体に翼はない。
人々の足音と共に歯車の音が、その存在を主張して鳴り止まない機械仕掛けの街に降り立ってから半日が過ぎた。ジークはそこかしこで回る歯車を見るともなくぼんやりと眺めながら、腕を組んで浅く息を吐いた。
(……アルは何処に行ったのやら……)
少し用があるからと言って街の奥へ急ぎ足で消えていったアベルを、することもないので大通りの端で待ちながら、ジークはぼんやりと思考を巡らせていた。
(五年、か……)
アベル・メリアスに拾われ、共に空へと飛び立ち、空賊団〈ムートン・ヴォルゲ〉を結成してからもう五年の月日が経った。
痩せっぽちだった自分の身体も、まともに食事を摂るようになってからはかなり丈夫になり、身長も年相応に伸びてそれなりに見えるようになった。奴隷時代、短く切られていた髪は襟足だけを長く伸ばして、人にはあまり見せたくない己の首筋を隠すようにしている。ジークの襟首には消えない焼印、奴隷のしるしが残っているのだ。
ジークはその焼印を右手の指先で触れ、澄んだ水面の瞳に影の色を宿す。
五年前、アベルに拾われてからの数週間は毎日悪夢を見た。飛空艇の寝台に横になるたび、〝あれ〟――もちろんジークを己の物としていた奴隷主のことだ――の太い指が自分の焼印に触れてきた感覚がよみがえり、ぞわぞわと吐き気のする悪寒を呼び寄せる。悪夢の中ではいつも同じように、〝あれ〟が気色の悪い笑みを浮かべていた。〝あれ〟が関わるすべての記憶は、どれもこれもがジークにとっては汚らしいものだった。思わずジークは顔をしかめる。
或る日には宝石のように愛でられ、或る日には動く道具として扱われた。〝あれ〟は男色家だったのだ。
少しばかり静かなところへ行きたくなったジークは、大通りを抜けて路地の前で立ち止まった。――路地。アベルに拾われてから数日後、目まぐるしく変わる己を取巻く環境に少し慣れ、思考も段々と冴えるようになってきた頃だ、こうして或る小さな街の路地を眺めていたことがあった。
そう、今聴こえているような歯車の音ではなく、冷たい鎖の音を聴きながら……
(自由……俺は今、自由……なんだ……)
アベル・メリアスと人通りの多い道ではぐれてしまったジーク・ブレッカーは、狭い路地の手前で立ち止まり、そうして自分の思うように行動できることへ何となく違和感を覚えていた。
自由になったら、と考えたことは何度もある。だがそれはどれも、もしもの話だった。こうしてほんとうに自由となった今、自分は何をすればいいのか、何をしたいのか、ジークはそれがいまいち分からなかった。
浅くかぶりを振って、大人しくアベルのことを探そうとジークが思ったそのときだった、路地の奥から何やら金属が何かと軽くぶつかる音が聴こえてきた。ジークの足の指先から頭のてっぺんまで、ほとんど恐怖に近い悪寒が込み上げる。そしてその、ひどく覚えのある感覚がジークのここ数日で緩みかけた思考を強く張り詰めさせ、かえって彼の思考を鋭く尖ったものにした――それこそ、毎日生と死の境にいたときのように。
それが彼の普通だったはずなのだ。ほんの数日前までそうだったというのに、どうしてこんなにも気を緩ませていられたのだろう。ジークは唇を引き結んだ。
この奥では奴隷市でもやっているのか、それともあの鎖の音はただの幻聴なのか、ジークは思考を巡らせる。どちらにせよ、何か意味があるはずだ。そう思いながら、いつも肌身離さず持ち歩いている赤い石へと無意識に手を伸ばして、ジークははたとする。
(そういえば上着、着てこなかったんだったな……)
赤い石はジークがいつも着ている上着の内側に仕舞われている。ただ、その上着――ジークの身に付けていたものはすべて奴隷が着るものであり、昼間の街を歩くにはあまりにみすぼらしく見えた。見かねたアベルが飛空艇の中にあったという古い服をとりあえずとジークに渡し、ジークもそれに袖を通したが、そのおかげで赤い石の入った上着は今、飛空艇の中に置き去りとなっているのだった。
ジークは家壁に背をつけて地面に座り込み、石のことは今は忘れようと更に思考を深めていく。
(いつか……自由になってもならなくても、〝あれ〟を殺してやると思っていた……そのいつかは、今なんじゃないか……?)
右の手のひらを強く握る。手首の先から、しゃら、と鎖の音が響いた。今度のこれはまごうことなき幻聴だ。しかし、聴こえている。外れたはずの鎖の音が聴こえているのだ。それに、夜になれば悪夢さえ見る。〝あれ〟の手からは逃れられたはずだというのに、〝あれ〟がにたにたと笑っている悪夢を毎夜見るのだった。
結局、自分は逃れられてはいないのか。未だ〝あれ〟に囚われ続けているのだろうか。どうすれば悪夢を見なくなるのだろう。どうすれば、悪夢は終わるのだろう。ジークは目を瞑った。
(やはり、そうだ……〝あれ〟がこの世にいる限り、俺は……)
しかし、どうすればいいのだろう。今さら〈ラピスラズリ〉に戻りたいと言っても、アベルに不審に思われるに違いない。それにあの男のことだ――見たところ十七か十八か、自分とあまり年齢は変わらなそうだが……と、言っても自分の年齢もはっきりとは分からないのだが――妙に鋭いところがある、こちらの考えていることなどすぐに気が付いてしまうかもしれない。
それはだめだ、とジークは溜め息を吐いた。これは自分の問題なのだ。アベルまで巻き込むわけにはいかなかった。
やはり、今すぐには無理かもしれない。こういうことをするのには、何かと準備が必要だと考えられた。
(だが、必ず……俺が生きている内に必ず……)
一度計画を頭の中で練ろうとしたそのとき、人の気配を感じてジークは素早く顔を上げた。そこにはここ数日でよく見知った顔があったが、その人物の白群色の髪の中にジークは何か違和感を覚え、眉根を寄せる。そして数呼吸おいてからその違和感の気付き、ジークは思わず上擦った声を上げた。
「ア――アル、お前、それ……角……」
「おう。こういうの、ア・シンメトリーって言うんだろ? どうよ、格好良いか?」
そう笑って片手を額の方にやったアベルを見て、ジークは言葉を失った。
アベルの額にそびえていた一対の角、鬼族の証、その片方がまるで木を切り倒したかのようになくなっている。冬の空色をした前髪の隙間から切り取られたアベルの角が切り株のように見え隠れしているが――そして彼のこの態度、つまりはそういうことなのだろう――アベルは己の角を切り落としたのだ、己の意思で。
ジークが何故、と口にする前にその疑問を感じ取ったのかアベルが先手を打った。
「手持ちが底を尽きたからな。金なんてほとんど持たずに出てきちまったから、家。……鬼族の角はけっこう高値で売れるって小耳に挟んだことは何回かあったが、こんなに高く売れるとは思ってなかったぜ。まあ、相手はメリアス家に繋がりのある商人だったから高く買ってくれたのかもしれないが……家がだめになったって向こうは知らないらしかったから、危ない橋を渡ったことになるんだけどな。はは、近い内にばれるだろうよ。悪いことしちまったなあ、悪党になろうってやつがこんなこと言うのも変だけどさ。……うん、まあ、しばらくはこの金でやっていけると思うぜ」
赤虎眼石の瞳を細めて笑うアベルに、ジークが言いたいことは山ほどあったが、とにかく彼はいちばん最初に疑問に思った点を少々掠れた声で口にした。
「……鬼族の角は、何度も生えてくるもの……なのか……?」
「人によっては生えてくるやつもいるんじゃねえの、俺は違うけどさ。たぶん生えてこない――何となく分かるんだよ。もし生えるとしても、そりゃえらく時間がかかることだろうよ」
「じゃあ……だって……! アルの角、それは鬼族の証だろ! お前……お前には、誇りというものがないのか!」
立ち上がってそう叫んだジークに、アベルの瞳が白い光に閃く。口元は弧を描いていたが、軽く笑い飛ばすような雰囲気は彼の周りから取り払われていた。
「あるさ」
「なら、どうして売ったりなんか……!」
「だから売ったんだよ、高く……な。持っていても金にはならない誇りさ、だけど俺にはけっこうたいせつな誇りだったんだ……だから、それに見合う金と交換したのさ。……あの商人からこの金を盗むのはたぶん、簡単だ。けどな、昼間の地上にいるときは……ただのアベル・メリアスでいたいんだよ。だって――悪いことっていうのは、夜にするものだろ?」
そう言われても納得のいかない表情をしているジークを見て、アベルは軽く笑った。それから首を横に振り、ジークの頭を軽く叩く。
「だいじょうぶだっての。角を一本失っても、アベル・メリアスって男はけっこう二枚目ってやつだからさ。な、そうだろ? ジークがそうやって怒ってくれるのは嬉しいけど、悪いことなんて別にないんだぜ。金もたんまり手に入ったし、誇りって言っても角は割と邪魔だって思うことも多かったし――何ならもう一本売ってもいいかもな」
「……笑えないぞ」
「……だよなあ。悪い悪い、冗談だ。俺なりに場を和ませようとしてみたんだよ」
ジークはそう言って頭を掻くアベルを拍子抜けや呆れや、その中に理由もない哀しみが入り混じったような気持ちで眺めていたが、ふとアベルの左手に赤く瞬く何かを見付けて軽く目を見開いた。
「それ……」
「うん? ああ、そうだった。お前の魔法石、ちょっと借りてたんだ。換えた金で魔法道具に……って言っても、見た目はただのイヤリングだけどな……したんだけど、あー……いや、でも……勝手にしたらまずかったよな、悪い」
先ほどとは打って変わって自信なさげな顔をしているアベルから飛空艇に置いてきたと思っていた赤い石を受け取りながら、ジークは手のひらに乗った石が淡く発光していることに気が付いた。しばらく手のひらに乗せて眺めていると、その淡い光は少しずつ薄れていき元の赤い石へと戻ったが、確かに、赤い石が魔法道具に加工されたらしいことが知識の少ないジークにも理解できた。
「イヤリング……というのは?」
「ああ、耳につけるんだよ。風の力を吹き込んでもらったから、つけても石自体はそんなに重くないと思うぜ。それにたぶん、風の魔法を使うのが得意だろう、お前は? 身のこなしが軽いように見えるし、何よりお前が操縦する船は速い。それに……無意識か? お前の周り、よく風が吹くんだぜ――ほら、な」
アベルがそう呟いた途端、イヤリングを耳にしたジークの周りから風が勢いよく立ち上ってアベルの白群の髪を乱し、その風は高い空へと駆け抜けていった。赤い石が再び淡く発光し、今度はその光がジークの身体の中へと入り込んでくる。熱を含んだ風が血液中を駆け巡り、目元では鋭い風があっちこっちへと吹き荒れた。そうして一通りの嵐が過ぎ去ると、ジークは自身の身体がさながら羽のように軽くなっていることを感じ、驚いた。
「それはお前の力になるはずだと思ったんだ、ジーク。どうせいつも持ち歩くんだったら、役に立った方が断然得だと思ってね」
「ああ――いや、驚いたな……すまない、ありがとう、アル。有り難く受け取るよ、ほんとうに身体が軽い……」
ジークは路地の方へ目をやり、無意識に口を動かした。それは音にはならなかったが、アベルはそれを目敏く拾い上げ、先ほどまで浮かべていた人懐っこく見える笑みを顔から消してジークに声をかけた。
「〝これなら〟……何だ?」
ジークはアベルの表情を見て、一瞬言葉に詰まる。
この男は笑っていると人当たりのいいお調子者に見えるのだが、一旦その表情を陰に潜めると、その顔は人が思うよりも精悍で顎の形も目の形も鋭く、ほとんど冷たい氷のような印象を与えるのだった。
それは彼が鬼族で、見た目は人間に近いが、人間ならざる者であるからなのか、それとも彼特有のものなのかは今のジークには分からなかった。
「……何でもない」
「なら、いいけどさ」
あからさまな態度に対して、さしてそれを深く問う様子も見せないアベルにジークは驚きながらも拍子抜けをし、浅く息を吐いた。しかしアベルは何かに気付いたのだろう、路地の方を見ながら少しばかり自嘲的に笑い、呟いた。
「なあ、ジーク。何かを得るためには、何かを失わないといけないんだな……」
「え?」
「――その覚悟、できたら言えよ」
アベルはそれだけ言うと、戸惑うジークに踵を返して街の出口へと向かっていった。いつまで経ってもジークが追ってこないのを不審に思ってか、アベルは道の途中で振り返り、ジークに向けて手招きをする。ぼうっとしていたジークはそれを見て意識を地面に下ろし、アベルの後を追った。
自分の隣まで走ってきたジークを見て、アベルがあの人懐っこい笑みを浮かべて言う。
「なーあ、ジーク。アイスって喰ったことある?」
「アイス……?」
「そう。甘くて美味いんだよ、これがさぁ。な、ちょっと喰ってから行かねえ?――急ぐ旅でもないんだしさ」
「――おい、ジーク? 聞いてんのか?」
「……え?」
瞼を開けると、目の前には白群色の髪。そのよく見知った色が自分の前にあるのを見て、ジークは自分がいつの間にか壁を背にして軽く微睡んでいたことに気が付いた。両目の間を軽く指で押さえて、ジークは困ったように笑う。
「すまない……軽く寝ていた」
「立ったままか?……なんつうか、器用だなぁ」
「少し考えごとをしていたんだ――と、言っても……大分昔のことだが」
「考えごと、ね。ま……用も済んだし帰ろうぜ、考えるのは船でもできる」
自分の隣に在る路地に、あの街の路地を重ねながらジークは音を立てずに溜め息を吐いた。
(結局、いつも、俺は俺のことばかりでいっぱいになってしまう……昔も、きっと今も……)
アベルのように自分の誇りを差し出して、それを金に換え、その金で誰かのために何かをするということなど、自分にはできやしないのだ。遠くにいようが、近くにいようが、やはり自分の目に彼は悪党として映らない。
だが、そういうアベルを身近にし、彼を見ていると時折ひどく哀しくなるものだ。
それは彼への劣等感からか、それとも彼の抱いている、人には見せない悲しみからか、それとも彼がこちらへ抱いている違う形の劣等感からか。船にいる連中も、そういう風に感じることは少なくないだろう。
生きていくということが、ある種哀しみを帯びていることを、迷い羊たちはあの飛空艇の中で暮らす内に知っていくのだ。だからこそ、あの船の中――アベル・メリアスという男のつくる空気の中は心地が好い。それは、彼がひたすらに生きているからだった。
「なあ、ジーク」
路地を見つめているジークを横目に、アベルが呟いた。
「覚悟――できたか」
こちらを振り返り、笑みを潜めてそう問うアベルに、ジークは自嘲気味に笑ってかぶりを振った。
「いいや……結局、俺は臆病者だよ」
「はは、よかった」
「え?」
「……実はさ、俺もけっこうびびりなんだよ」
そう言って目を細めるアベルにジークは、やはり自分はこの男のようにはなれないのだと感じながらも、その小さな痛みに似た感情を厭だとは思わなかった。そう、敵わないのだ、結局。あの船に集まる連中、その誰もが最初にアベル・メリアスに盗まれるもの……
「びびりなのさ、だからこうして群れてんだ――あのさ、ジーク」
「うん?」
「覚悟、できなくてもいいぜ。……ずっと」
「〝心盗んでも、命盗むな〟?」
「――ああ、そういうこった!」
この身体に翼はない。
だが、それでも、足枷は外された。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
