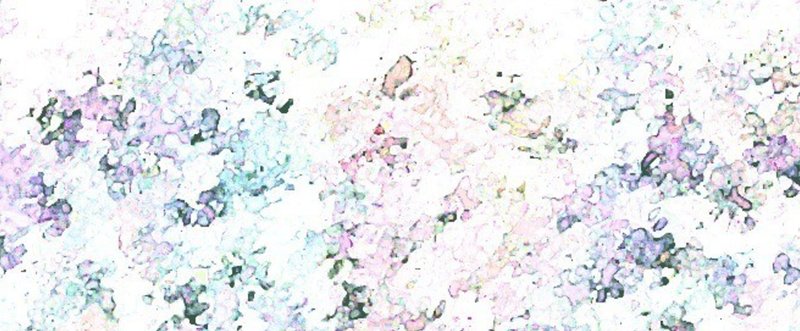
光の城
あの日のことを想い出していた。
雨の中、彼と笑い合ったあの日のことを。
そう海岸に立つ彼女の髪を、白い月が照らしている。深海の色をしたそれが、潮風に誘われて揺れた。
あの日、まだあどけない少女の姿をしていた彼女は来年で二十歳を迎える。
彼女のやさしく強い、心に剣を携えていた祖父は先日、息を引き取った。
死の根が彼女の心に這い寄ったが、彼女はそれを、母のときよりは幾分か優しい気持ちで受け入れることができた。それは紛れもなく、祖父のあたたかい意志と彼のやさしい心が、父に自分の心を裏切られ、母を失った彼女のことを何年もの間包み込んでくれたおかげであった。それは彼女も分かっていた。
彼女は優しく微笑みながら、自分の後ろで自分と同じように海を眺めている彼を振り返った。彼女の笑顔はもうあの頃の少女が湛えるものではなかったが、つられて笑った彼の顔はあの頃となんら変わってはいない。
クコ、と彼があの日と変わらぬやさしい声で呼びかけた。
クコと呼ばれた彼女は、彼の卵色に輝く髪に目を細める。
――彼は、変わっていない。
いつまでもやさしい心、魔法のかかったような声、輝く卵色の髪、若草の瞳、少年の笑顔。
そう、変わっていないのだ。
わたしの身長は伸びた、自分が思っていたよりも高く。わたしの声は変わった、自分が思っていたよりもやさしく。
それでも彼は変わっていない、何にも。すべて、あの日のまま。
「――クコ、往くんだね」
気が付くと、彼の若草色がこちらの瞳を覗き込んでいた。ゆるりと頷いて肯定の意を示す。
「もっと広い世界を見たくなったんです。イルカくんのおかげ」
「ぼくだけじゃないよ。お祖父さんのことも忘れないで」
「もちろん」
彼の背丈はあの頃のまま、伸びても縮んでもいない。あの日は同じくらいの背格好だったイルカを、今ではクコが見下ろす形になっているが、彼女にはそれすらも愛おしく感じた。
「クコが往くなら、ぼくも往かなくちゃ」
「……何処へ?」
クコの問いかけが、まるで聞こえなかったかのようにイルカは続けた。
「そういえばクコ、君ってば何にも言わないけどさ、ぼくのこと変だとは思わないの」
「……あなたは最初から変よ。初めて話した日に――明日、海に行こう……だとか、言い出して」
「そうじゃなくてさ」
「イルカくんが幽霊ってことについて?」
そう言い放つクコに、イルカが困ったように笑った。
「気付いてたんだ」
「何となく――妖精にしては人間味があり過ぎる気がするし、幻にしては本物っぽいから」
言いながら、クコは何とも形容し難い気持ちに駆られた。
いつまでもやさしい心、魔法のかかったような声、輝く卵色の髪、若草の瞳、少年の笑顔。
彼のすべてがたいせつで堪らないというのに、なんということだ、彼は死んでいる!
言葉にしたら、それがみるみる現実味を帯びる気がして嫌だったのだ。変わらない人間はいない。けれど彼は変わらなかった。それもそうだ、彼は幽霊なのだから。
怖くはない、ただ少し、哀しく思った。
「死んでるんだ、こうして見ることも、話すこともできるのにね」
「ええ」
「考えることもできるのに」
「ええ」
「触れることだって、できる」
「――ええ」
彼の冷たい指が、彼女の頬をやさしく抓った。
波が静かに打ち寄せる音を耳が受け入れる。ふと視線を空へ向けると、夜が朝に溶け始めたようだった。
「足もあるし、身体も透けてはいないよ」
今は。イルカがそう言ったような気がしたが、彼女は小さく微笑み、彼のつめたい指が此処に在ることを感じようとするだけであった。今だけは。
「クコ、寂しいね。ぼくら一緒には往けないんだ」
「あたし……あなたと初めて話したときから、たぶん、分かってた」
小さな川が、イルカの指を濡らす。滲んだ視界で彼の姿が子どもにも見え、大人にも見えた。
「ずっと君に会いたかったよ。君を待ってたんだ」
「……何年くらい待ちました?」
「分からない。百年くらいかな――ほら、泣かないで」
「あなたも泣いてるのに?」
彼の涙からする海の香りに、彼女は産声を上げるかのように泣いた。彼の首にしがみついて、羊水に帰りたがる胎児のように泣いた。
そうして自身の首元に、彼の真珠が零れ染み入るのを感じ、それが温かいことに彼女は安堵する。
「何処へ、往くの」
「そうだなあ。朝を越え夜を越え、星も月も越えて――海へ往きたい」
「ねえ、きっと世界は広いのね。あたしが思っているよりも、ずうっと」
「そうさ。ぼくが思っているよりもずうっとね」
月がゆるやかに息を潜め、白い地平線に燃える太陽が顔を見せた。同時に、彼の足が金色の光を発しながら空へ還っていく。
はっとしてイルカの首元から腕を離し、彼の顔を見た。
若草の瞳は海から生まれた光に照らされて、命の輝きに満ちている。
彼と彼女は笑っているような泣いているような表情を浮かべながら、互いの手のひらに互いの手のひらを合わせた。
「――言いたいことがたくさんあるんだ」
「ええ、聞かせて」
「クコ、大きくなったね。綺麗だよ、すごく。ああ、でも、君は髪……短い方がぼくは似合うと思うなあ。ぼくさ、君の泳いでる姿を見るのが大好きなんだ。人魚みたいだよ、本当にね。白いワンピース、似合ってるよ。やっぱり君には白が似合う。――おかしいな、今日は上手く言葉が出てこないや。ねえ、ねえ――泣かないで、大好きだよ、大好きなんだ――ぼくの大切な友だち……」
クコは砂に雫を落としながら、それでも笑ってみせた。その笑顔はあどけない、あの日の少女のものだった。
「あたしも、ひとつだけ――いい?」
「もちろん」
「――あなたの名前を、教えて」
金の光に包まれたイルカが笑ったのが分かった。もうほとんど消えてしまいそうな身体をこちらに寄せ、彼は耳元で何かを囁く。
それが、彼の最後の言葉だった。
「次、会えたときに」
――朝陽がクコの深海色を照らしている。
彼は此処にいない。
彼が空に還ると、彼女の涙はぴたりと止んだ。まるで彼の星の砂が、彼女の涙ごと空へ攫っていったかのようだった。
大切な友だち。
彼のその言葉を口の中で反芻する。
彼への想いの中には、友だちのそれとは違った何かも在ったような気がするが、それはひとまず涙と共に流してしまったことにしよう。
彼は此処にいない。
けれど確かに、此処にいたのだ。
誰が信じなくとも、わたしはそれを知っている。
消えない幻のような、解けない魔法のような彼。手のひらには、未だ彼のつめたい温度が残っている。それでも、此処にいた彼はもういない。彼がいなくても、朝陽はわたしを照らした。
そろそろわたしも往かなくちゃ。まずは――そうね、髪を切ろう。
そうして彼女は、一度空を仰いでから一歩を踏み出した。広い世界の前では取るに足らない一歩、けれど彼女と彼に取っては大切な、ひどく愛おしいその一歩を。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
