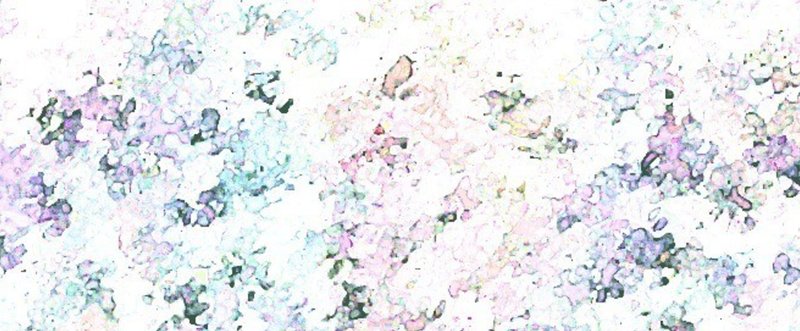
呼び水、汽笛、舟の色、白いるかの泪
――ずいぶんと永いこと、夢を見ていたような気がする。
うっすらと若草色の瞳を開けた少年は、目の前に広がる海の輝きに目を見開いた。
海とは、こんなにも美しいものだっただろうか。
(……ぼくがうたた寝してる間に世界が変わっちゃったのかな)
少年は自身が座っていた砂浜から立ち上がると、ぐ、と背伸びをした。そのあと小さな欠伸も一つ、宙へ浮かべる。
まさか何百年もうたた寝をしていたわけではないだろう、そう少年はポケットの懐中時計――祖父の部屋からこっそり借りてきたものだ――を取り出して時間を確かめた。
(なんだ、十分しか経ってないや)
それにしても、と少年は思う。
それにしてもずいぶんと永いこと、夢を見ていたような気がする。それは何分、何時間、そんなちっぽけな間じゃない。そう、何年、何十年――いや、何百年、それほどの時間を漂っていたような、そんな気がする。漂う、なんてのはおかしいな。だってぼくは此処にいるのだから。此処で生きて、地面に足も着いているのだから。
夢の内容はほとんど覚えていない。ただ、あの場所――白い砂浜に、カモメがよく鳴く海――どこかこの場所にも似た、夢の中では、海がひどく美しいものに見えた。ちょうど今のように。うたた寝から目覚めると少年は、今まで見落としていたものがしっかり見え、聴こえるようになっていたのだ。
波の音、その奥で歌う貝殻の声が聴こえる。これまで聞くともなく聞いていたカモメの声、あれは彼らの故郷を想う歌だった。遥か昔、己が生まれた海へと捧げる歌だった。
水面は白く輝きながら揺らめいている。その中に一点、小さくちかりと光るものすらも少年の瞳に捉えられた。少年が駆け寄ってその光を掬い上げると、その手に残るのはシーグラスの欠片。少年はそれを太陽の光に翳して見つめた。淡く光るシーグラス、少年はそれを海の宝石だ、と心臓の奥で想い、たいせつにポケットの中へ仕舞った。
大きく息を吸い込む。肺いっぱいに潮の香りを詰め込みながら、少年は想う。香る潮はどこか血のにおいにも似ている、と。海の香りは、今の少年にとってまったく命のにおいと同じだった。
波の音、水面の輝き、潮の香り、それらの秘密を少年は今すぐ誰かに伝えたかった。その反面、自分だけの秘密にもしたかった。少年は心臓に手をやって、瞼を閉じる。暗闇の中でも波の音は聴こえる、水面の輝きも感じる、香る潮はやはり、血のにおいをはらんでいた。
この秘密は。そう、この秘密は自分のたいせつな人だけに教えよう。
少年は心臓の奥深くでそう想い、その想いは心臓の中で緩やかに溶け、血に混じり、彼の身体中を巡った。
そのあたたかさを感じながら、少年は瞼を開く。開けた目に飛び込んできたのは、深い青色の宿る二つの丸い瞳。それがこちらの顔を不思議そうに覗き込んでいる。少年が驚きの声を上げると、二つの瞳の持ち主――見たところ彼と同じくらいの少女である――は首を少し傾けた。
「目を瞑ったりして、何をしているの?」
絹のようなやさしい声。少年は、少女から発せられた声のやさしさに再び驚きながらも返事をした。
「海を見てたんだ」
「見てた?……目を閉じていたのに?」
「うん。ぼくも驚いたけどね、目を閉じるとけっこう――かなりかな、見えるよ。海の姿が」
それを聞くと少女は海の方へ向き直り、少年が先ほどやっていたように目を閉じてみせた。それから数呼吸すると少女は瞼を開き、再び少年の方へ向き直った。
「あんまり良く見えないみたい。きっとあなたが特別なのね」
そう言って柔く笑った少女の顔に、何故だか少年は見覚えがあった。少女の髪は柔らかい灰の色、瞳は海の深いところにあるやさしい闇を湛えている。少女と会ったことはない。それは確かだった。しかし、その髪や瞳、声のどこかに懐かしさを覚える自分もいる。それも確かなことだった。さっきまで一緒にいて、さっき別れたばかりのような、そんな懐かしさをこの少女には覚える。少年はほとんど囁くような声でひとりごちのような問い掛けを自分と、少女に向けて言った。
「――夢で、会った……?」
夢、と少女がおうむ返しをした。それから少し笑って、ゆっくりと左右に首を振る。
「会ってない。あなたが会ったのは、わたしに似てる人よ、きっと。そう、わたしじゃないわ」
「……ごめん、変なこと言ったね」
「わたしは嫌いじゃないよ、そういうの。それにね、夢で会ったことはないけど――わたしはあなたを知ってるの」
「ぼくを?」
少女は頷き、白い砂浜を数歩進んだ。波打ち際で少年を振り返り、やさしく笑う。潮風が少女の灰の髪を揺らし、命を称えながら少年の横を吹き抜けた。
「あなたはいつもここで海を見ているでしょう。わたしも、そこの坂の上から海を見ているの。気付かなかった?」
「ぜんぜん……」
「だと思った。海を見るのが、好き?」
そう問われると、少年は海の方を向き、右手を伸ばした。指の間で、水面がきらきらと輝いている。
「ただの暇つぶしだったんだ、今日までは。でも、今日……初めて、海が綺麗だと思ったよ。何で今まで気が付かなかったんだろう、ぼくは今までどこを見ていたんだろうね。君は好き? 海を見ること」
少女は緩やかに否定の意を示し、少年と同じように右手を海の方へ伸ばした。
「わたしもただの暇つぶし、今も。あなたには先を越されてしまったみたいだね」
そう言って笑う少女に、血に溶けた想いが淡く光るのを感じた。カモメの歌も、シーグラスの光も、命のにおいも、今はすべてが遠い。今、少年の目の前にあるのは、自分の鼓動の音、そして少女の絹の声だけであった。
「――ねえ、君は明日もここへ来る?」
「明日?……晴れたら……きっと」
「ぜったい、にして」
「……晴れたら、ね」
血に溶けたこの秘密を、この少女に伝える日がいつかはくるといい。揺れる灰の髪と太陽の光に輝く青の瞳を見て、少年はそう想った。そして、少女の血に溶けているであろう命の秘密もいつかは知りたい、そんな風にも想う。
だが、少年が今それよりも強く想うのは、明日も会いたい、その願いだけであった。
「ぼくは君と、一緒にいてもいい?」
「……それは、晴れなくても」
ずいぶんと永いこと、夢を見ていた気がする。
あれは誰の夢だったのか、ぼくの夢だったのだろうか、それともぼくではない誰かのか。ああ、でも、それはもうどうでもいい。もう、夢は覚めてしまった。夢は覚めて、海を知り、きみに出会えたのだ。それだけあれば、ぼくにはもう十分だった。夢の中で出会った、ぼくに似たぼくではない人と、きみに似たきみではない人へ心の中でさよならを告げる。波の音が、カモメの歌が、水面の輝きが、シーグラスの光が、潮の香りが、命のにおいが、この言葉を遠い彼らまで届けてくれることを願う。
そして、どうか、明日は晴れますように。
その小さな願いだけを少年は声として心臓から外へ送り出し、海に伝える。
それに応えるように、何処までも柔らかな風が、二人の髪をやさしく揺らしていた。
20160229
シリーズ:『仔犬日記』〈白いるかの泪〉
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
