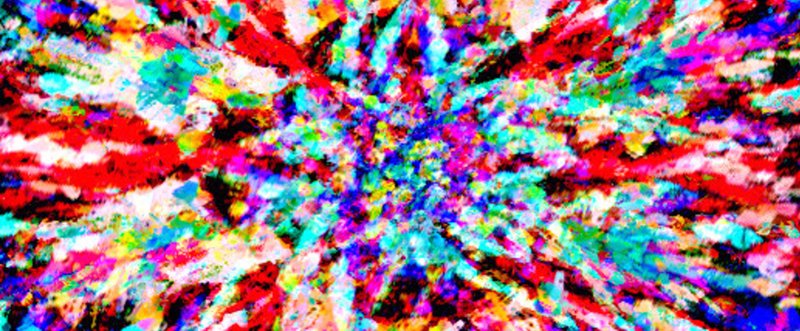
輝脈
その人は、燃え滾る焔のような髪に黄水晶の瞳をもつ。
身体には黒地に揺れる炎が描かれた赤の浴衣を纏い、背には大きな団扇を背負っている。焔の髪は後ろで無造作に結わえられているが、それでもその人は不思議な色香を放っていた。そしてその人は、左目を覆うようにして前髪を垂らしている。時々ちらつく左の黄水晶が、その人の秘密をまたひとつ増やした。
――小町薫子。それがその人の名前だった。彼女のことを一口で表すのは難しい。人は誰しも秘密を持っているものだが、彼女の場合、彼女に何か秘密があるのかすらも、多くの人には分からなかった。彼女にはどこか、掴めない鬼火のようなところがあるのだった。
薫子は火のメイジ、いわゆる火を扱うのが得意な魔法使いである。
メイジとは、魔法を使い、生計を立てる者。彼女には食い扶持が多い。自身の生まれであるワノ国〈紅玻璃〉で魔法の宿った硝子細工を売る工房を営んだり、その高い魔力を生かして廃墟や遺跡に赴き、そこで手に入れた財宝などを売ったり、はたまた商人の護衛をしたりと、彼女の収入源は非常に様々である。腰を落ち着け、硝子工房の収入だけでも十分食べていけるというのに、彼女は一定の場所に留まるのを嫌い、店を長期間空けることが多かった。
……彼女の瞳が炎の光に揺らめく。彼女の黄水晶の奥にはいつも、たいせつな人と交わした約束、〝世界を見る〟という約束だけが煌々と燃えていた。その約束は彼女の黄水晶の瞳を一層強く輝かせる一つの種火だった。その約束のことを知っているのは、彼女と親しいたった数人だけなのであるが。
彼女はたった一人、その身一つで旅をすることが多かった。一人でいるのが特別好きなわけでもなく、他人が嫌いだったわけでもないが、ただ、一人でひたすらに旅を続けていた。しかし、いつからか彼女の隣には一人の青年が付き添うようになっていたのである。
――その青年の名前は犬童。インドウ。彼は自らでそう名乗った。驚くべきことに、彼は人ではない。魔法の力を借りて動く機械だった。機械人形。それは、世界的に見ても比較的珍しい存在である。
その姿は胴体や腕の水色に光る結合部分を除けば、人間とほとんど変わりはない。簡潔に言うならば彼はエキゾチック――どこか異国風な風貌をしていた。
彼――犬童は、輝く銀色の髪に琥珀の瞳をもち、紫の生地に白で模様が描かれている踊り布をいつも首に巻いている。右耳には羽のようなピアスを着けており、首から下げている紐が長めの大きな三日月のネックレスは、中心に光を吸い込んで輝く硝子のようなものが取り付けられていた。それはどこか、サン・キャッチャーにも似ていた。先端が翼のようになっている金色の短槍も、彼が護身用としていつも身に着けているものである。
戦い、踊る機械人形。それが犬童だった。彼は機械人形であり、青年であり、踊り子であり、そして薫子の弟子なのだ。
「カオル、これは何だ?」
機械人形である犬童は、自身の知らないことを何でも知りたがった。生まれたての頃、彼はほとんど無知であった。それは純粋な赤子のように。そしてその水晶のように透き通った純粋さは、時を経てその形を変えたが、それでも消えてしまうことはなかった。
犬童の主と薫子は彼に惜しみない知識を与えた。犬童の主は薫子の古くからの友人だった。彼は犬童のことを造った張本人であり、犬童にとって父親のような存在である。彼も犬童のことを実の子のように愛していた。
その主が犬童に与えた知識は、文字の読み書き、生きる術、自分らしく在ることの大切さ、愛情だった。文字の読み方を覚えた犬童が、彼の書庫を蹂躙し貪るように本を読んだため、片付けにほとほと手を焼いたことは未だ彼の記憶に新しい。
「――わっちのことは師匠と呼べと言ったであろう。……それは魔物か何かの化石じゃなあ」
薫子はまだうら若い女性であるというのに、このような変わった話し方をする。師匠と呼べ。薫子は苛立たしげにそう返した。それはほとんど彼女の口癖のようなものであり、それを聞いた犬童が苦々しげに、師匠、と呟くのが二人の間の定石であった。
見た目から判断するのならば、小町薫子という女は犬童の舞踏の師のように見えるのだったが、その見た目とは裏腹に薫子は彼の武術の師なのである。犬童は踊ることに特化してつくられた機械人形であるため、舞踏に関しての師を彼は必要としなかった。
そんな薫子が犬童に知識として与えたのは、武術のいろは、命の脆さ、生の輝き、そして、世界の広さだった。
「化石?……化石か。俺たちもいつか化石のようになるのだろうか」
「さあ……なあ。わっちはいつか白い骨になるだろうが、おまえはどうなるやら。確かに長いこと経てば化石のようになるかもしれんがなあ」
「主やカオルと違う姿になるのは少し寂しいような気がする。……俺にも心の臓があれば同じになれたのだろうか」
「師匠と呼べ。……そうでもなかろうよ。骨も化石もさして変わらぬ。おまえはそうしてすぐに心臓に拘るなあ、おまえの欠点じゃよ」
今、二人は或る遺跡で過去の歴史に触れていた。遺跡を探索することは知識欲が底を知れない犬童のお気に入りであり、薫子も古いものに触れることは好しとするため、互いが共に行動していないときでも犬童と薫子、二人が二人とも遺跡に赴くことも多々あった。
「お前――師匠も世界という言葉に拘る。それと俺のこれは違うのか」
その言葉は、犬童が化石を引っくり返しながら何の気もなしに呟いたものだったが、寸鉄が人を殺すように、壁の文字を指でなぞっていた薫子の動きを一瞬止めた。
「……いいや……同じだろうなあ。わっちはどうも過去に囚われるたちらしい」
犬童と最初に出会ったとき、薫子が彼に向けて最初に発したのは、世界を見に行こう、という言葉だった。それは、自分が死んでも生き続ける犬童に一人で生きていく能力を身に付けてもらいたい、という彼の主の願いを、薫子が汲んで発したものであったが、彼女の瞳の奥は何か別のものを爛々と燃やしていた。
「ただ、何かに拘るというのは魂が在る証じゃよ。……おまえには心があると、何度も言うておるのに」
「心の臓がないんだ。心というものはそこに宿ると聞く。だから、俺には心というものがない……何か、間違っているのか」
「おまえもなかなか頑固じゃなあ。何でも信じるくせをして、これだけは信じてくれぬ」
「――難しいことは分からない」
犬童がそう言ったのを聞くと、薫子は短く息を吐いて彼の手にしている化石を指差した。
「過去に囚われるというのは、ちょうど、こんな感じじゃよ」
「……つまり? 分かるように言ってくれ」
薫子は視線を地面に落とした。彼女の黄水晶が溜め息と共に閉じられる。
「――恋の話をしても?」
「関係があるのか?……言われても、俺にはよく分からない」
「分からない方がよいこともある」
犬童は怪訝な顔をして薫子を見たが、彼女はそのまま話を続けた。
「わっちのこの執着はもう動くことのない化石を愛しているのと同じようなものでなあ。もうこの世にはいない者の、もう叶わない約束を――ずっと心で想っているのじゃよ。……恋心と言うより、ほとんど風化した感傷に近いのだろうが。いやはや困ったことにな、彼女はわっちに〝一緒に世界を見に行こう〟、と言った。……旅の途中で彼女は病を患い、そのまま向こうへ逝ってしまったが。……軽率なことを言うものではないなあ」
そこまで言って薫子は、自身も犬童に同じことを言ったのを思い出したのだろう、視線を犬童の銀色に向け困ったように笑った。
「……おまえにも同じことを言ったのだった。〝世界を見に行こう〟、と」
「ああ。だからこうして、此処にいる」
彼の琥珀が薫子の黄水晶を見据える。彼のそれが怒りを孕んでいるように見え、彼女の瞳は揺れた。
「なんじゃ、犬童。そのような顔をするな、ちと……怖く見えるぞ。怒っているのか?」
「いいや……。ただ、お前がお前を否定しているように感じたから、少し」
「ああ――そうか。わっちがわっちを否定するということは、おまえを旅に出した、おまえの主も否定することになってしまうからなぁ……」
「それもある。だが……お前が俺に、世界を見に行こう、と言ったことを、俺は間違っているとは思わない。……軽率とも。もしお前が死んでも、思わない」
彼のその揺れない瞳を、薫子は見据えた。彼女は自分の喉がぐつぐつと煮えるのを感じ、その熱さを抑えきれず、ついには笑い声として外へ追いやった。そこで初めて犬童の琥珀が揺れるのを彼女は感じ、一息おいてからまた話し始めた。思い出したように、師匠と呼べ、と呟いてから。
「ああ、分かっておるよ。おまえはそういう奴だからなあ。真っ直ぐで結構、結構。と、いうか……わっちがそう簡単に死ぬわけなかろう。わっちを誰だと思っておる? 小町薫子、おまえの師匠だぞ?」
「ああ……そうだったな、師匠」
そろそろ話も探索も切り上げて、一度遺跡を出る頃合いだ。薫子がそう思うのと同時に、いつの間にか化石だけでなくいろいろな石や植物を収集していた犬童が口を開く。
「そういえば、その化石の人は……一体、どんな人だったんだ?」
化石の人、それが恋慕の情を抱いていた彼女のことを指しているということに気が付くのに、薫子は少しばかり時間がかかった。
「……犬童、主のことを父親と思うことは?」
「……いつも、そう思っているが。主には言わないでくれ」
「なら、わっちが好きだったのはおまえのお母さんじゃよ、犬童」
犬童は石を拾う手を引っ込め、薫子の方を向いた。そして、ひとつ溜め息を吐いて、柔く笑う。
「お前は時々、少女のような顔をする」
「……師匠と呼べ」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
