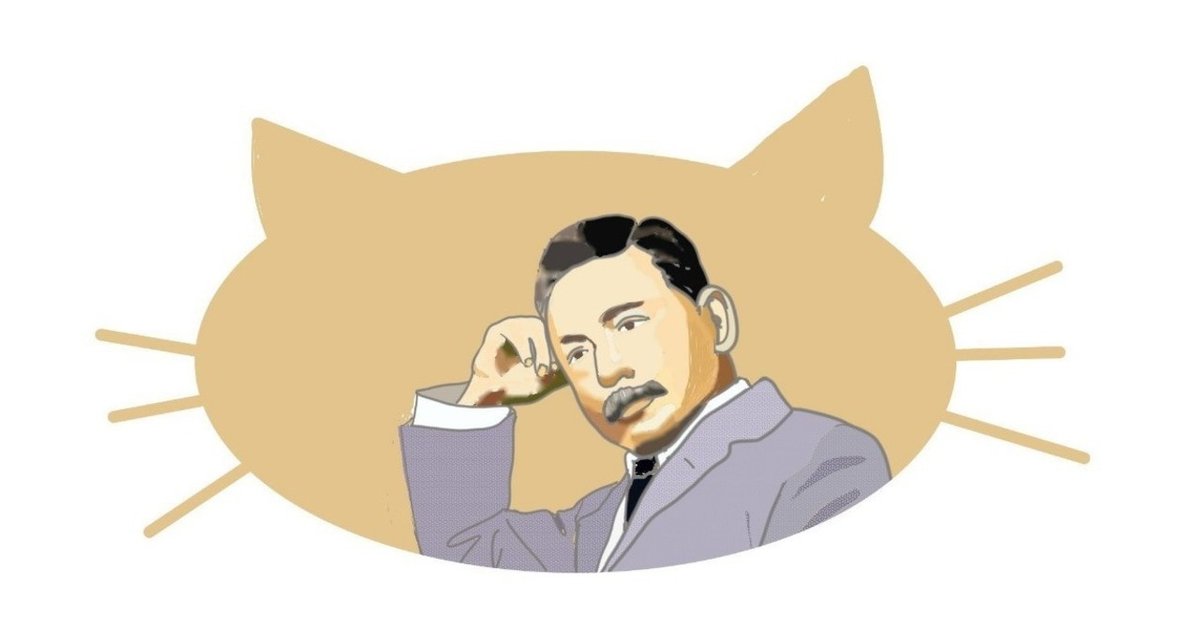
夏目漱石の「こゝろ」を読んで
とある読書がテーマの小説を読みました。そこで採り上げられている作品の中に夏目漱石の『こゝろ』があり、どんなお話だったか内容を思い出してみたのですが、教科書にも採用されよく知られている【下】の部分くらいしか記憶がありません。『こゝろ』は高校生の時に通読したはず……と思って書棚を漁ってみると三十年以上前の文庫が出てきたので、この機会に再読してみることにしました。
教科書以外では『こゝろ』に触れたことが無いという方に説明しますと、この作品は【上・中・下】の三部構成となっており、その内の【上】と【中】は「私」という青年による一人称の語りなのですが、最終章である【下】の部分は「私」が「先生」と呼んで親しくしている人物から受け取った手紙の内容(過去の告白)になっています。【中】の終盤で「先生」からの謎めいた手紙を受け取った「私」が、汽車の中でそれを読んでいる……というのが作品の全体像だと考えてよいでしょう。
さて、いざページをめくると最初から違和感を覚えます。主人公の学生「私」は鎌倉の海水浴場で「先生」と知り合うことになるのですが、当初「私」の目を引いたのは「先生」その人ではなく、そのときに「先生」と一緒にいた西洋人だったというのです。
漱石が、本編とは一見なんの関係も無いようにも思える描写にかなりの行数を費やしているのは不思議ですが、問題はそれだけに留まりません。なぜならば、その西洋人がとりわけ主人公の目を引いた理由とは「彼が他の西洋人たちと違ってパンツ一丁だった」からというのです。主人公は、「先生」をオマケとしてしか認識していなかったことになるわけですが、ちょい役の西洋人と重要人物の「先生」とのバランスを考えると、なぜこのような描写が必要だったのだろうかと首を傾げてしまいます。
この出会いの後、東京に戻った主人公は「先生」の自宅に親しく行き来するようになります。教養はありそうだけど特に仕事もせず過ごしている不思議な「先生」に、主人公はなぜか惹かれていくのですが、自分自身は田舎の両親から受ける期待に応えられないまま卒業を迎え悶々とした日々を過ごしています。良い就職先も見つからないうちに父親の持病は次第に悪化してゆき、いよいよ今日か明日がヤマというその日、主人公の元に「先生」から一通の長い手紙が届きます。それが「先生」の遺書であると気付いた主人公は、今まさに息を落とそうとしている父親を放り出して東京行きの汽車に飛び乗ってしまうのです。
その列車の中で読んでいる遺書の内容が前述した【下】であり、この中に「先生」の過去が告白されているのですが、しかしこれもちょっとおかしな話ではないでしょうか? 既に死んでいるかもしれない知人の安否を確かめるためだけに、危篤の父親を放って遠くに出かけるものかなあと。ちなみに主人公はこの後、作中には一切登場しません。つまり彼や病気の父親や実家の家族がどうなったのかを、読者は全く知ることなく物語を読み終えることになるわけです。あまりにも不親切で投げやりにも思える展開ですが、漱石はなぜこんな形で作品を綴り終えてしまったのでしょう。
多くの読者にとって『こゝろ』といえばやはり、「先生」が友人「K」と下宿先の「お嬢さん」を巡って繰り広げる三角関係のドラマ、というイメージで捉えられているのではないでしょうか。その印象があまりにも強烈なので、【上】【中】の語り手である「私」の存在が軽くみられがちな傾向があるのは事実でしょう。特に【中】は、「先生」という人物について説明することはほとんどなく、また中途半端なまま終ってしまうので、「作者が構成を誤ったのではないか」と受け取る読み手もいるようです。
通読してみると、【上】や【中】には先述の西洋人の件のように、不可解にも思える展開や描写がいくつか存在しています。【下】だけでも小説として成立しそうなお話に、なぜ導入部が必要だったのかを再考してみる余地は十分残っているような気はします。日本近代文学を代表する作家の一人と言われる漱石が、そのような無駄にも思えるようなことをするものでしょうか。
実際に『こゝろ』を精読すると、その全編を通じて「親子」という関係が細かく配置されていることに気付きます。
冒頭の第一章では主人公を海水浴に誘ったという友人が登場するのですが、彼はかねてより気の進まない結婚を親から迫られています。この友人は「母親が病気になった」との電報を受けて急遽帰郷してしまいますが、その彼自身、おそらくそれは自分を誘い出すための口実であろうと予想しています。しかし本当に病気なら無視することもできないため、仕方なく鎌倉から遠路はるばる中国地方(西日本の)まで帰ることを選択するのです。
同じく【上】の二十三章では、田舎に一時帰省した主人公が父親と将棋を指す場面が描かれます。このとき主人公は、父親と「先生」を比較し、肉親である父よりも他人である「先生」のほうに深く繋がっている現在の心境を認識します。これを伏線として展開される【中】では、タイトルの『両親と私』が示すとおり、主人公とその両親の話に終始します。
また【下】の主要登場人物である「先生」、K、お嬢さんの三人も、それぞれ肉親との関係が詳しく描かれており、それらは皆、この章を構成する重要なパーツとなっています。例えばお嬢さんの場合を見てみますと、彼女は(本人の意思は別にして)母親の了承というプロセスなくしては結婚を認められない存在なのです。「先生」が結婚を申し込んだのは当のお嬢さんではなく母親であり、その母親いわく「本人が不承知のところへ私があの子をやるはずがない」というのです。仮にこのような母娘の関係が存在せず、「先生」が直接お嬢さんに交際や結婚を申し込むような、つまり現代のような環境だったならば、Kとの間にあの悲劇は起こらなかったかもしれません。
「先生」が人間不信になってしまったのも、Kが常に意固地になっているのも、彼らとその肉親の間に複雑な過去があったからです。おそらく『こゝろ』を読み解く鍵のひとつは、この「親子の関係」なのではないでしょうか。
改めて登場人物たちの親子(肉親)関係に着目してみると、お嬢さんの例のように、親が子の人生について絶対的な強権を持っていることがわかります。一方で、子供世代の側はそれに反抗を挑んでいることも伺えます。
主人公を海水浴に誘った友人は、親の押し付けに反発しながらも抗えずに帰省しました。Kは親の言うことに従わず、しまいには勘当されて健康を害するまでになり、そのあまりの頑固さから姉や友人に心配をかけています。「先生」は叔父の強権的やり口(自分の娘と結婚させようとしていた)に反抗し故郷を捨てましたが、恋の苦しみに際して、かつて嫌っていた絶対的強権(親の決定権)を利用してお嬢さんを手にいれました。
では主人公の「私」はどうでしょう? 彼は田舎の実家と東京にまたがって、どっちつかずの存在なのではないでしょうか。死の病に冒されている父親は、息子に独り立ちして欲しいと願っている半面、彼が遠くへ去っていってしまうことに寂しさも感じています。主人公自身も両親を放っておくことはできず、さりとて都会の生活を知ってしまった身では、田舎で家を守って余生を過ごすこともしたくはないのです。
この肉親関係の中に描かれているのは、旧来的な価値観と新たな価値観の葛藤です。
【上】において主人公は、地方でいまだ確固として存在する伝統的価値観としての血縁より、「先生」との親交を通じて結ばれた新しい価値観のほうに重きを置くようになっていきます。そしてこの伏線はやがて、先に問題として取り上げた【中】のラストへとつながっています。
なぜ主人公が危篤の父親を放り出して汽車に乗り込んだのかというと、それはこの「新旧の価値観の問題」こそが作品のメインテーマだからなのではないでしょうか。ここはおそらくとても重要なポイントになっていて、最終的に【下】で「先生」が「明治の精神に殉死する」という難解な主題にも関連しているのではないかと思います。
ここで一旦【上】の第二章に戻って、例の西洋人に注目してみましょう。
主人公は「先生」たちに出会う日の二日前に、他の浜辺で西洋人の団体客が海水浴を楽しむ様子を目撃したと書かれています。その団体客たちは身体の大部分を覆い隠すような水着を着ていたのですが、「先生」と連れ立っていたあの西洋人だけは、彼らと違い肌をほとんど露出していたわけです。
当時(一九二〇年頃)の西洋的な道徳観では、人前で腕や脚をさらけ出すのは恥ずべきこととされており、実際に二十世紀の半ばくらいまではTシャツ一枚で外出することさえもマナー違反でした。
つまり、「先生」と同行していたその西洋人は、当時においてかなり(というか飛びぬけて)新しい価値観の持ち主だったことが分かるのです。
十九世紀のドイツで新しい哲学を提唱したフリードリッヒ・ニーチェという思想家は、一神教的な神様やあるいは理想や真実といった「絶対的な価値」によって生き方を決定される人間を厳しく批判しました。この主張は、発表当時ほとんど支持されなかったものの、彼の死後になって見直され「実存主義」という新しい思想の発展に結びつきます。
実存主義の内容をごく簡単に記すと「自分自身の生き方を自ら創造する」ということです。ニーチェによって批判されたような絶対的価値観は、『こゝろ』の中でKや「先生」が悩まされ影響を受けていた田舎の伝統的な価値観とも重なっています。
ニーチェの提唱する哲学は、このような旧来的な観念から逃れ、新たな時代に人間たちがどのように自らの生きる価値を創造していくかに主眼を置いているのですが、面白いことにそれは『こゝろ』のストーリー展開と相似形を成しています。ニーチェによると、神や理想などの絶対者に従属していた旧時代の人々の存在意義とは、「新たに出現する人類たちの踏み台となり、彼らを飛び立たせるために滅んでいくこと」であるというのです。
余談ですが、この思想をテーマにして作られたのが、イギリスの作家・アーサー・C・クラークによる『地球幼年期の終わり』『二〇〇一年宇宙の旅』といったSF小説です。ご興味のある方はぜひご一読いただければと思います。さらに余談なのですが、アニメの『機動戦士ガンダム』もまた、この思想がベースとなっている作品だと考えられます。ガンダムに登場する「古い地球人」は、宇宙を活動の舞台とするニュータイプたちにとっての踏み台です。無印ガンダムで黒い三連星のリーダーであるガイアが「俺を踏み台にしたぁ?」と叫ぶシーンは有名ですが、あれも実はガイア=地球を、アムロ=ニュータイプが踏んでジャンプしていくというイメージの表現なんじゃないかなあと勝手に思っています。
『こゝろ』に話を戻します。
「先生」とは、自らが旧来の価値観と共に滅んでいくことにより、新しい価値観に憧れ飛び立とうとする主人公の「私」を、田舎や肉親という呪縛から解き放つ存在です。だから主人公は、危篤の父親を放り出して東京へと向かい、「先生」は明治の精神に殉死するのです。
明治とは、開国によって新たな価値観(個人主義)が西洋からもたらされ、それが人々の意識に浸透し憧れを集めた時代でした。しかし、リアルにその価値観が移り変わる時代を生きた人々にとっては、旧来的価値観という鎖から真の意味で脱却することは恐らく難しかったであろうと思われます。漱石の感性が捉えた明治時代とは、「大正」という更なる新時代を前にして日本人が巣立ちの準備をするために存在した、束の間のひと時だったのでしょう。そしてそれは、漱石本人の人生とも完全に重なっていたのです。
(漱石とニーチェ哲学については浅学ゆえにその関連性を確信するには至らないのですが、処女作『吾輩は猫である』の中には既にニーチェについて言及した箇所があり、漱石が著作を読んでいたであろうことは窺えます)。
【中】の九章では、病床の父親が主人公に向かって「(俺の病気のために東京に戻れないお前は)気の毒だね」とつぶやく場面が描かれます。主人公の父親の病気が、お嬢さんの母親が罹ったという病と同じものであったという事は、おそらくとても重要な意味を持っています。「先生」は【上】の二十四章で、この病気(腎臓の病)について次のように語ります。
「自分で病気にかかっていながら、気がつかないで平気でいるのがあの病の特色です」
おそらく漱石はここで「病気」という言葉を用いて、「親の絶対的な強権(=昔は良いとされていたもの)」が、これからの新しい時代に生きる若者たちの幸せとは両立しない、いわば「呪い」のような存在になっていることを提示したかったのではないでしょうか。それは、明治の日本に新しくもたらされた個人主義が、エゴイズムというそのままの意味で行使されたことによる悲劇的対立だとも言えるでしょう。Kや「先生」も、この呪いによって知らず知らずのうちに拘束されていたのです。
しかしお嬢さんを巡る葛藤とKの自殺によって、自らも病に冒されていたことを気付いてしまった「先生」は、旧時代が残した呪いを一身に抱き、新しい人間(主人公)を飛び立たせるために世界から消えていくのです。それはイエス・キリストが人々の罪を背負い、自ら進んで磔台に上った事にも似ています。キリスト教を信仰としてではなく敢えて文学的に解釈するならば、イエスとは、それまでの怒れるユダヤの神と人類とをとりなすためにこの世に産まれ、キリスト教という新しい価値観をイスラエルの人々に残して去って行く英雄としての存在なのです。
『こゝろ』の【中】があの展開で終ってしまうのは、そこがすなわち物語のゴールであることを示しています。つまりこのお話は、
「先生」が恋の葛藤とその後の決断によって苛まれる人生の苦悩を描いたものではなく、主人公が「先生」の死によって旧来的価値観の呪縛から解き放たれるという物語
だと考えられるのです。パンツ一丁で登場するあの西洋人は、意味無くそう描かれているのではなく、そういった主題を象徴するものとして意図的に冒頭に配置されています。一方、観察の比較対象とされた西洋人の団体客らは「(道徳という)絶対的価値に従属する旧人類」を表しているのでしょう。
物語の終盤では、この冒頭部に対応する象徴的な事件が起こります。それがすなわち「乃木将軍の殉死」です。明治天皇は日本人の旧来的価値観における絶対者のシンボルとして描かれ、乃木将軍は従属者の役割を表しているのです。
冒頭の西洋人によって表されるような新しい価値観を身辺に漂わせ、主人公を新しい生き方へと導いて自らは滅んでゆく存在、それこそが、漱石が示したかった「先生」というキャラクターなのだと思います。
一読すると無理やりな描写に思えるような箇所には、その中にこそ物語の本質が隠されていたりするので、文学作品を読む際には特に注目したいポイントです。作家の平野啓一郎氏も著書『本の読み方 スロー・リーディングの実践』の中で同様のことを指摘しており、そういう不自然な描写というのは「作者が無理をしてでも伝えたいこと」である場合が多いのだそうです。
このように『こゝろ』を読んでみると、ともすれば「構成のミスなのでは?」と思われてしまうような【上】や【中】にも、きちんと役割があると意味づけることができます。
もちろん、これが唯一の正しい読み方であると断言するつもりはありませんが、ここまで見てきたように『こゝろ』の魅力は必ずしも【下】の中だけに存在するのではありません。むしろ作品全体を通して深く読み込むことで、今まで気付かなかった【下】の面白さを発見できる可能性があるのではないでしょうか。
本稿では、紙面の都合で採り上げるポイントが限られてしまいましたが、作中には他にも不思議な描写がいくつもあり、おそらくはこの先にもっと深い理解が隠されているであろうことをお伝えしてこの小論を閉じたいと思います。
(了)
Written by : M山
