
心の傷を乗り越えるために、私たちには何ができるか?『トラウマとレジリエンス』試し読み
4/16(火)発売の白揚社新刊『トラウマとレジリエンス:「乗り越えた人たち」は何をしたのか』より、プロローグの試し読みをお届けします。
著者はコロンビア大学で「喪失・トラウマ・情動研究所」所長を務めるジョージ・A・ボナーノ教授。トラウマやレジリエンス(自ら立ち直る力)研究の第一人者です。
本書でボナーノは、「同じようなつらい体験をした人でも、トラウマに長く苦しむ人もいれば、すぐに日常を取り戻せる人もいるのはなぜか?」という疑問に取り組みます。
早期に回復できた人たちには、それを可能にした「能力」がもともと備わっていたのだろうか? それとも、周囲の支えなど、「環境」が大事だったのだろうか? はたまた、その出来事のあと、どのように「行動」したかが決め手だったのか――?
数々の事例を紐解きながら、今もトラウマに苦しむ人たちは、心の傷を乗り越えるために何ができるのかを探っていきます。
お届けするのは、本書の冒頭部分となる「プロローグ」の全文です。
※本稿には交通事故の描写が含まれます。フラッシュバックなどの心配がある方はご注意ください
■ ■ ■
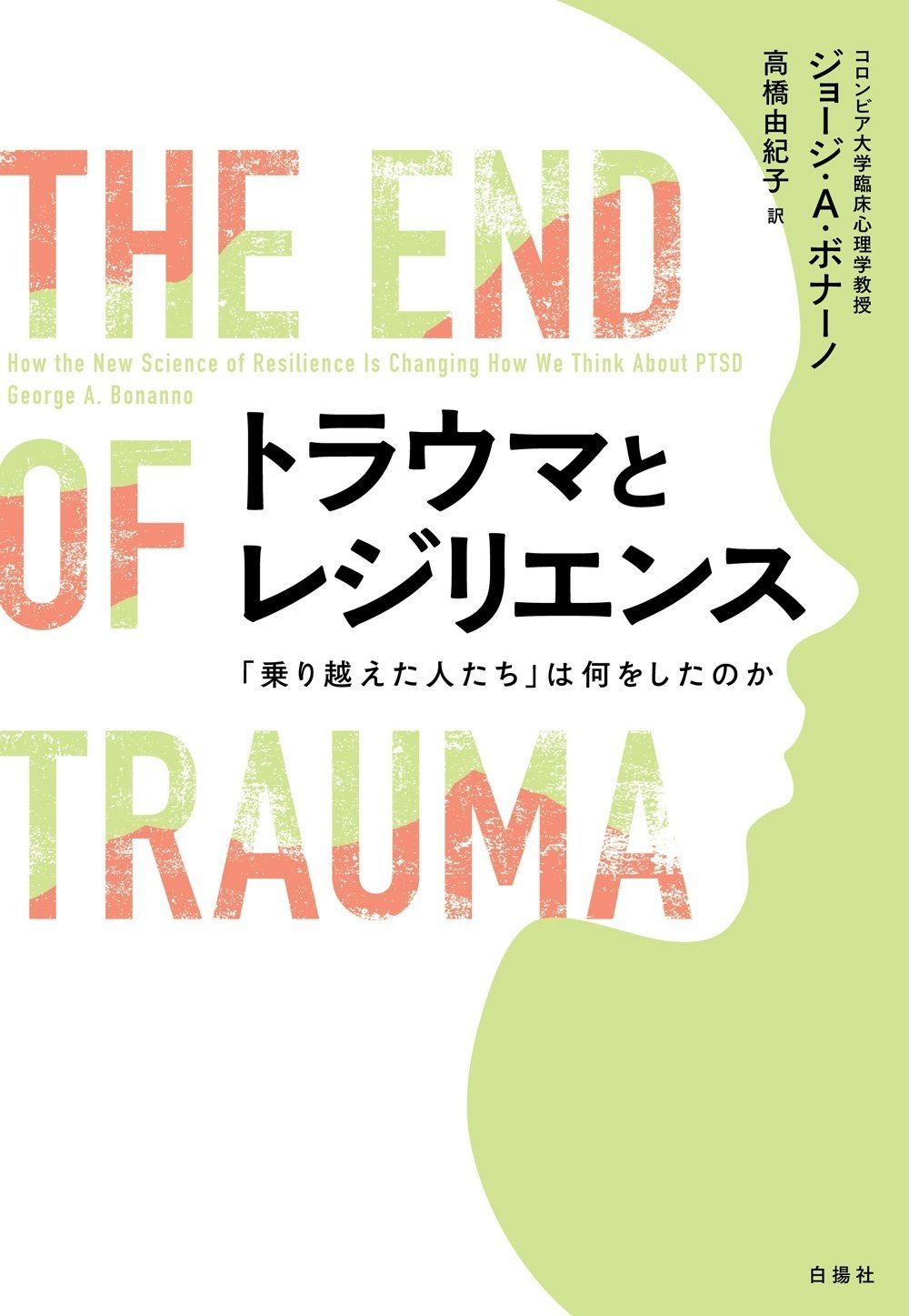
プロローグ 自分はなぜ大丈夫なのだろう?
ジェッドと最初に会ったのは、私が教授をしているコロンビア大学ティーチャーズ・カレッジの、臨床心理学博士課程の面接の時だった。その日面接に来た多くの候補者と同様、ジェッドもきちんとした服装でオフィスに入ってきた。しかし私には、彼が歩いて入ってきたという事実が驚きだった。彼が悲惨な交通事故に遭って、もう少しで命を落とすところだったと知っていたからだ。再び歩けるようになるかもわからないと聞いていた。
ジェッドはその日、事故のことはあまり語らなかった。それより他に話すことがたくさんあったからだ。起きたことの全貌を知ることができたのは、それからかなり経ってからだった。
ジェッドは五年前まで、ニューヨークでミュージシャンとして身を立てようとしていたが、それは容易なことではなかった。「食べるために仕方なくウェイターをやっているミュージシャンでした」と彼は言った。彼はニューヨークの一流レストラン、グリニッジ・ヴィレッジの「バッボ・リストランテ」で働いていたが、生き方を変えたいと考えていた。恋人のメーガンと暮らし始めたからである。彼女は看護師の勉強をしていた。ジェッドは以前から興味のあった心理学を学ぶことを考え始めた。都心から少し離れた場所にあるシティ・カレッジでいくつかクラスを取ったところ、非常に面白く、次学期には本格的に勉強を始めるつもりだった。
一二月二一日の夜、店での長いシフトが終わった時も、彼は将来に思いを巡らせていた。店を閉めた時、時刻はすでに午前一時三〇分だった。ソムリエが家族へのクリスマスプレゼントにワインを持って帰っていいよと言ったので、彼はそれを取りに地下室に行った。いいワインを四本見つけてバックパックにしまい、出口に向かった。
その夜は非常に寒かった。ジェッドはフードを目深にかぶり、西八丁目の交差点に立って信号が変わるのを待っていた。「歩行」を示す信号の白い光が凍った舗道の上に揺らめいたのを見て、彼は横断歩道に踏み出した。突然、ごみ収集車が猛スピードで角を曲がって突っ込んできた。あっと思う間 もなく彼ははじき倒された。
「すべて、ありありと覚えています」と彼は言った。「フロントバンパーに叩きつけられ、前輪に巻き込まれてトラックの下に引きずり込まれたんです。左に寄って倒れたんで、左脚が外に出ていて前輪に轢かれました」
トラックの前輪はジェッドの脚を踏み砕いた。それから一秒か二秒の間があって、次に二重車軸の後輪が彼に襲いかかった。
「二五トンのトラックが……僕を轢いていったんです」
バックパックに入っていた四本のワインが壊れなかったのが不思議だった。ジェッドの左脚と腰の一部は完全に潰れ、辺りは血と骨の海となった。想像を絶するむごい事故だった。彼は狂ったように悲鳴を上げ続けた。
最初に現場に到着したのは、消防署から駆けつけた緊急対応チームだった。非常に素早い対応で、事故の五分後には到着していた。
副隊長のエイドリアン・ウォルシュは、ジェッドを見つけるとその手を取った。
ジェッドは、自分がどれほど危険な状況にあるかをよくわかっていた。
「生きるか死ぬかの瀬戸際だとわかっていました。なぜか意識を失わなかったんです。ただ悲鳴を上げていました。長いこと悲鳴を上げ続けたことを覚えています」
それから、聖ヴィンセント病院に彼を連れていくはずの救急車が遅れていると知らされる。病院はわずか六ブロック先なのだが、渋滞に阻まれているというのだ。待つ時間は耐えがたいものだった。
「次第に恐怖がつのってきました。消防隊が到着して一帯を封鎖しました。自分を轢いたゴミ収集トラックが停まっていたのもよくと覚えています。倒れていた所から、道路を封鎖する様子が見えました。いまもまざまざと思い出すことができます」
救急車が到着するまで、できることは何もなかった。いったい救急車はどこにいるんだろう。
「そこら中で人が叫んでいました。ウォルシュ副隊長の叫び声も聞こえます。彼女は何とかして僕を早く病院に連れていこうとしていたんです。みんな焦っていました。彼女が消防車を指さして『なんでこれに乗せて聖ヴィンセントに連れていけないの!』と消防隊員に怒鳴るのが聞こえました」
一分、二分と時間が経過するにつれ、ジェッドはさらに危険な状態になっていった。大量の血液がすでに失われていた。ウォルシュはのちに、あの忌まわしい夜に彼にとって何らかの幸運があったとすれば、凍りついた舗装道路の上に横たわっていたことだったと言った。低温が失血を遅らせたのだという。それにしてもジェッドの出血は大量だった。救急医療隊員は、通常の輸血量の五倍近い五〇単位もの輸血をしなければならなかった。
救急車が到着するまでの耐えがたい二五分間が、ジェッドには気の遠くなるような長い時間だった。だが耐える以外、彼にはどうするすべもなかった。
「道に横たわったまま、一種の瞑想状態というか、ゾーンに入ったというか、ただ呼吸を感じていたのか……何をしていたのかよくわかりません。ショック状態でした。周囲には怒声が飛び交っていました。『バスを急がせろ!』と叫ぶ声。バスというのは彼らの言葉で救急車のことです。ウォルシュ副隊長は優しい女性で、僕の手を握って落ち着かせようとしました。僕はトランス状態でいるだけで精一杯でした」
ようやく救急車が到着した。ジェッドは一瞬ホッとしたのもつかの間、恐ろしいことに気づいた。
「この身体を動かされるんだと思ったんです。自分では動けないから、他の人たちがこの耐えがたい苦痛を生じている身体を動かすわけです。彼らは僕を引きずって持ち上げ始めました」
ジェッドはこの間もずっと意識があった。「でも意識が混こん濁だくするほどの苦痛でした。目の前が真っ白になって。おそらく病院に着くまでかなり大声でわめいていたと思います。それからすべてが薄れ始めました。痛みのために気を失ったようです」
救急車はあっという間に聖ヴィンセント病院に到着した。猛スピードで彼を運んだのである。ジェッドは痛み止めをくれと叫んでいたが、苦痛を和らげるものは何も与えられなかった。それより病院に着く方が早かった。
「救命救急士が『少し待って。病院に着いたら痛み止めを打つから』と言ったのを覚えています」
病院に着くと、医者たちがジェッドを囲んで質問を始めた。詳細な情報が欲しかったのだ。ジェッドの答えははっきりしていた。「痛み止めをくれ。そしたら答える」
それから、ジェッドの意識は遠のいたり戻ったりした。しかし一つの記憶だけははっきりしている。恋人のメーガンの顔を見たことだ。彼女はブルックリンのアパートでジェッドの事故の知らせを受け、すぐに病院に駆けつけたのである。
「メーガンがいて心配そうにしていたのを覚えています。辛い記憶です。彼女は取り乱して泣いていました。僕は無力感を覚えました。大丈夫だと言って彼女を安心させたかった。手術室に運ばれる時には、自分は大丈夫という自信があったのを覚えています。僕は彼女に『向こう側でまた会おうな』と言って手術室に入りました」
その夜ジェッドが覚えていたことは、そこまでである。
手術台の上でもジェッドの出血は止まらず、整形外科医たちは、彼の潰れた脚をどうしたら残せるかを慌ただしく話し合っていた。そこに血管外科長が到着し、整形外科医たちをどかしてジェッドを見た。後で聞いた話では、血管外科医は「相談ばかりしてたら、この男は助からない。まず出血を止める方法を見つけなくては」と言って、整形外科医たちを手術室から追い出したそうだ。
ジェッドは生死の境にあった。容体を安定させるのにどれくらい時間がかかるかも、脚を残せるかどうかもわからなかった。医者たちがメーガンと彼の家族に容体の重篤さを説明し、助からない可能性もあると警告したことを、もちろんジェッドは知らなかった。
外傷センターでの最初の夜、ジェッドは何時間も手術室にいた。医療チームは彼の命を救おうと懸命だった。身体の各部分がどれほどの損傷を受けたかが明らかになるにつれ、複数の手術が必要になることがわかり、それらを最も安全に行うには、彼を治療のための人工的な昏睡状態にする必要があると医者たちは決断した。そして事故から三日後、ジェッドの左脚を救えないことがはっきりした。左脚のすべてと股関節が切除された。さらにまだいくつかの手術が予定されており、ジェッドはもうしばらく昏睡状態でいなければならなかった。
人工的にもたらされる昏睡というのは、事故などで起きる昏睡状態、たとえば頭部の外傷によって脳が腫れた時や、脳への酸素供給が断たれた時などに起こる昏睡状態と似ているようで違う。人工的昏睡は、あまり多くない量のバルビツール酸系の催眠剤、たいていはペントバルビタールとかプロポフォールを使うことによって、意図的に導入される。これらの薬は脳内の代謝を抑え、患者を一時的に、麻酔下に近い深い無意識の状態にする。
この人工的な昏睡の間、脳の活動は減少するが、認知プロセスはある程度働く。患者はしばしば昏睡中に、狂気じみた夢を鮮明に見る。これらの夢は、昏睡中に周辺で生じた音とか、医療行為や介護のために触られたり動かされたりした時の感覚と関係している場合もある。
ジェッドは夢の中で味わった落下する感覚がいまだに消えないという。肉体から遊離していて重さがない。だがどこまでも落ちていく。あまり気分のいい感覚ではない。
「オープンカーみたいに上が開いた飛行機のようなものに乗ってて、人間の身体を持っていない。そして落ちていく。流れ落ちる滝に沿ってまっすぐに。すごい速さで左右に揺れながら落ちる。飛んでいるんじゃなくて落ちる。制御がまったく利かない。あいまいな記憶の中ではっきりしているのは、フリーフォールの感じです。果てのないフリーフォール。恐ろしい感覚です」
「どのくらいそれが続いたのかわかりません。ただひたすらどこまでも落ちていく。ずいぶん長い間だったようです」
「それから……ヒュウッと音を立てて……着地したんです」
「かなりの衝撃だったけど何かが壊れるほどじゃなかった。『あ、自分の身体に戻った。もう落ちてない。身体が戻った』という感じでした。やっと終わった。僕はあの……何といいましたっけ……そうそう『リンボ』だ。天国と地獄の中間地点。そこまで行ってから戻ってきたんです」
「それから、奇妙な話ですが、以前にネイティブ・アメリカンの儀式小屋みたいな所で会ったことのある呪医の声が聞こえました。『お前には呪いがかかっていた』とか『家族に呪いがかかっていた』とか言うんです。それから『これで貸し借りなしだ。この後はよくなる』って」
ジェッドは笑いながら「サイコ的な変な夢ですよね」と言った。さらにまた別の夢では、有名な料理人のマリオ・バターリが、ジョー・バスティアニッチとともに、彼を尋ねてきたという。二人はバッボ・リストランテの共同経営者で、ジェッドは二人とも知っている。彼らは実際に、昏睡状態のジェッドを見舞いに来ていた。母親が、「お二人が見舞いに来てくれたよ」と言ったのをはっきり聞いたか、あるいは聞いた記憶があるのだろう。だがバルビツールの影響下にあったジェッドの脳は、二人に会ったのは消毒薬の匂いのする病室ではなく、「どこか南部のヴァージニア州辺りの、春の緑の野原」だったと感じていた。マリオとジョーの訪問時に耳にした会話はまったく覚えていない。ただ彼らがいたことと、その時の穏やかな感じだけを感じ取っていた。
この「牧歌的な場所」というテーマは、彼の昏睡時の夢によく現れた。
「快適な長期ケア病棟で回復期を過ごしていた間に、こんな夢の中の現実が作られたんだと思います。そこにはあずま屋となだらかな丘があって、陽光に満ち、温かく快適です」
そのあずま屋は、彼が生まれ育った小さな町にあったあずま屋を思い出させた。別のいくつかの夢にも、このあずま屋は出てきた。また彼は、メーガンと結婚した夢を何度も見た。これら結婚の夢は、時に非常に奇妙なものだった。
「最初の夢は、ものすごく変でした。姉のボーイフレンド──いまは義兄ですけど──がネットで、韓国のアンダーグラウンドの何かを検索している。メーガンのためにヴィンテージ物のドレス、ビートルズが活躍した一九六〇年代のドレスみたいなのを探してるんです。それから僕たちは車に乗り、丸い形の山をうねうね登って、頂上の丸天井のあずま屋に着きました。乗っていた車は赤いコンバーチブルのスポーツカー。メーガンは嬉しそうでした。何もかも六〇年代初めのヴィンテージ。ヴィンテージ結婚式なんです」
「結婚式の詳しい場面は出てきませんでした。でも僕たちは結婚式をやり直さなければいけなかった。メーガンの父親が、何かに不満で、最初からやり直すはめになったんです。そんなわけで僕たちは、二回結婚しました」
入院中の彼の夢はたいてい奇妙なもので、なかにはいくつか非常に不快なものがあった。それらの多くは偏パラノイド執的で、何かの過ちに対する罰のような要素を含んでいた。彼はこれらを「歪められた夢」と呼んだ。
「潜水艦の中に二週間閉じ込められたこともあります。僕はコックで、ずっと料理をさせられていました。何かの過ちに対する罰、何か無作法をしたための罰のようでした」
また別の夢では、看護師か付添人に体毛を剃られていた。これは実際の手術の準備の一環で、おそらく現実の記憶が残存したのだろう。だが夢の中のジェッドは、その様子を離れた所から眺めていた。体毛を剃られる自分がいて、しかもそれが非常に痛い。看護師がわざと自分に罰を与えていると感じ ていた。
「まったく奇妙でした。自分が悪い子みたいにひどい目に遭わされる内容なんです。彼らが何を言ったか覚えてませんが、明らかに怒っていて僕を罰していました」
なかでも恐ろしかったのは、農場にいる夢だったという。「回復期を過ごす気持ちのいい場所ではありません。『肥満農場』と呼んだ方がいいような、ともかくひどい所でした。この施設もまた南部のどこかだと思います。患者たちはみなベッドから溢れそうに……恐ろしく太っています。まるで人 間フォアグラを作る恐ろしい農場みたいで、でも病院なんです。患者たちは点滴で栄養を与えられる。僕もベッドで点滴につながれていて、やはりものすごく太ってる。ベッドから溢れそうでした。飼育されてたんです」
*
こういう悪夢の心象にどんなメカニズムが働いているのかについては、驚くほど何もわかっていない。また人工的昏睡時に、こういうことがどれくらい頻繁に起きるのかもほとんど解明されていない。だが人工的昏睡状態にあった患者の多くが、奇妙な幻覚を伴う夢を見たことを報告している。
そういう夢は、不気味で恐ろしいものだったと訴える人が多い。暗く邪悪な「存在」に取り囲まれ、「さまざまな場所」に連れていかれ、「恐ろしい出来事」を経験するという。人工的な昏睡状態によって悪夢はさらに不快なものになる。なぜなら夢に終わりがないからだ。このような昏睡状態は非常に長く続くことがある。通常の夜の眠りの中で見る夢と違って、昏睡中の夢は、睡眠と覚醒のサイクルで途切れることがない。延々と続くことがある。以前に一人の患者が、「目覚めることのできない持続する悪夢」と表現したことがある。また「永遠に続くように思える悪夢……恐ろしいことが次から 次へと途切れなく続く」と言った人もいる。
夢がいつまでも続くために、「信じがたいほどまざまざと詳細に」感じられ、ハイパーリアリティのようになる。人工的昏睡を経験した人の多くが、昏睡から覚めた後に、夢で起きたことが現実ではなかったとわかるまでに数日を要したという。さらに困るのは、意識が戻った後も、昏睡時の夢が消失しないことだ。トラウマ的記憶に近いものが残っていつまでも付きまとう。
以前に診たある患者は、「昏睡中に見た悪夢がいまもまだ続いていて、まるで現実のように思えるんです」と話していた。
患者によっては、負傷そのものより、昏睡中の悪夢の記憶の方がさらに辛かったようだ。「身体の回復よりも、悪夢からの回復の方が困難でした」「怪我が治るよりも、昏睡状態の中で見た夢から立ち直る方が、はるかに長い時間がかかりました」などと彼らは語った。
こういう回想的記憶をどう解釈すべきなのか、これまで誰も体系的に研究した人がいないので、はっきりしたことはわからない。最もひどい反応を経験した患者たちだけが、その経験を語っているとも考えられる。実際に、すべての昏睡経験者が悪夢を報告しているわけではない。昏睡中の夢を何も覚えていないと答えた人たちもいる。
しかしながら、近年のある調査によると、集中治療室(ICU)で治療を受けた患者たちが、これと非常に似通った経験を報告している。ICUの患者は、幻覚を経験することがめずらしくない。一つには向精神薬の影響が考えられる。「ICUサイコシス(精神病)」という言葉さえあるほどだ。そ の調査では、面談した患者の八八パーセントが、ICUにいた間に幻覚や悪夢の侵入記憶(突然襲ってくる不快な記憶)を経験したと回答した。看護師によってゾンビにされたとか、銃撃を受けて血が飛び散ったとか、鳥たちが互いを笑い合っていたなどというものもあった。また彼らは、退院後も数か月にわたって、それらのイメージが意識の中に侵入し続けたと語った。
*
こういう事実は、ジェッドのその後に暗い影を落とした。彼は想像を絶する悲惨な事故を経験したばかりではない。事故の一部始終──車輪が脚を踏み潰したこと、自らの悲鳴、溢れ出る血、凍てつく舗装道路、切り裂かれるような痛み、メーガンの頬を伝う涙──のすべてを覚えている。それらすべての記憶に加え、不気味に「歪められた」昏睡夢の消えることのない記憶をこの先も抱えていかねばならない。またそれに加え、いずれ昏睡状態から目覚めた時には、左脚が腰の一部を含めてすべてなくなっているという現実を知ることになる。
ジェッドの家族は非常に心配していた。六週間の長きにわたり昏睡状態に置かれていた間、彼の身体は切り取られたり、配置を変えたり、つなぎ合わされたりした。さまざまな手術が、計二〇回にも及んだ。脚の切断に加え、気管切開、結腸の経路変更手術も行われた。意識が戻った時、何が起こるのだろう。何を覚えているだろう。脚を失ったことにどう反応するだろう。家族はどう説明すればいいのだろう。これほど悲惨な出来事によるトラウマに、彼はどう対処するだろう。
だが誰もが驚いたことに、昏睡から覚めた時、彼はすでに脚がないことを知っていた。どうやって知ったのかわからないと自分でも言っていたが、なぜか知っていた。昏睡状態でも、医療チームが周りで話していることが聞こえていたのかもしれない。あるいは医療行為を感じ取ったり理解したりしたのかもしれない。また単に、自分の脚が受けたダメージがあまりに大きいことを理解していたのかもしれない。
「脚はメチャメチャだと感じていました」とジェットは当時を振り返って言った。「道に倒れていた時、脚が見えてたんです。命すら危ないと思った。だからある程度知ってました。脚はもうないだろうと思いながら目を覚ましたので、驚きませんでした」
人工的昏睡からの覚醒プロセスは、ゆっくりと数日かけて行われる。そうすることで、意識が現実の場所と時間に戻ってきて、脳も身体のコントロールを取り戻すことができる。また、見慣れぬ場所で突然目を覚ますことのショックを軽減できる。ジェッドも、昏睡から覚めながら、周囲を「切れ切れに」認識していったと言った。「『あ、僕はICUにいるんだ!』とか、そういう感じじゃなかったですね。じりじり少しずつ理解していった感じです。脚のことは知っていました。でも自分の身体を見下ろした時、腹の一部に穴が開いていて、身体中にたくさんチューブが入っていて、どこも傷だら けだと思った覚えがあります」
その後は、付随して起こるいろいろな状況が彼を悩ませた。「目が覚めて、ものが言えないことに気づきました。そばにいた人が、『呼吸器にチューブが入っているので、抜くまでは話せないですよ』と教えてくれました」
話ができるようになったのは、目が覚めて五日後だった。それまでは身振り手振りか、短いメモで意思を伝えるしかなかった。気道に挿入されたチューブのせいで喉が激しく渇いた。
「意識が戻って一番苦しかったのは、喉が干上がっていたことでした。喉がカラカラなのに何も飲ませてくれない。まずちゃんと呑み込めるかを確認しなければというんです。呑み込み支援のスタッフが次々に来ました」
意識が戻った後には、元気づけられることもいろいろもあった。彼はともかくメーガンに会いたくて仕方なかった。彼女の存在がどれほど心を慰めてくれたかを、彼はいまも覚えている。
しかしそのあと、記憶は次第に辛いものになっていく。ジェッドは自分がどのように脚を失ったのかに向き合い始めた。二、三日もすると、頭は事故の記憶でいっぱいになっていた。
「その時はまだ、口がきけない状態でした。そして記憶が一気に襲いかかってきたんです。頭の中で事故を繰り返し再現していました。記憶には強い誘発性がありました。トラウマ的な誘発性です。『これに対処しなくてはならないのか!』と僕は思いました」
昏睡時の夢の記憶もまた、彼を悩ませ始めた。これは事故の記憶と同じか、あるいはそれ以上に苦痛だった。
「夢の内容を考えまいとする時間の方が多くなりました。実にまざまざと蘇ってくるんです。夢のテーマは主に、妄想症、暴行、罰、環境への不信などで、どれも強烈なものでした」
ところが数日経つと、自分でも意外だったが、それがぱったりと止んだ。
意識に侵入してきていたイメージは、薄らいできたと思うと、すっと消えてしまった。その後も事故の詳細は思い出せるし、悪夢の内容もありありと思い出せるが、これらの記憶は意識に侵入してこなくなった。フラッシュバックが起きなくなり、恐ろしいイメージに付きまとわれることもなくなっ た。思い出そうとすれば記憶を呼び起こせるが、考えたくないと思えば考えないでいられた。
「最初の二日くらいは、本当に記憶の洪水の中で溺れているみたいでした。しかしその後、記憶が後退していきました。すごく速やかでした。あれほどはっきりしていた記憶が薄らいだことも、昏睡から覚めた時のような強い反応を起こさなくなったのも、なんとも変な感じでした」
ジェッドにとって、この変化は非常に大きな意味を持っていた。
「僕には理解に苦しむことがありました。なんで自分の精神がもっとひどい状態になっていないのかということです。それが何より不思議でした。悲惨な目に遭った人がみんなPTSDになるなら、なぜ自分は平気なのか。それが疑問でした。なんで僕は大丈夫なのかって」
*
なぜジェッドは大丈夫だったのか。
これほどの過酷な経験をした人間が、どうして平気でいられるのか。
この疑問は重大ではあるが、答えが得られない問いであるように思われる。
だが実は、答えはある。もちろん、この苦難が彼の精神に傷を残さなかった理由を、絶対的な確信をもって知り得るとは思えない。彼がこれほど長い間昏睡状態にあったことで、その経験の少なくとも一部は謎で覆われている。しかしそれ以外の部分に関しては、ジェッドに限らず、多くの人の悲惨 な体験について以下のように説明することができる。
それは、トラウマをどのように捉えるかというところから始まる。従来の考え方からすれば、ジェッドは精神的に完全に打ちのめされたはずである。一見速やかな回復と見えたものは幻想にすぎず、心の奥底に潜む重篤な心理的外傷を一時的に否認しているにすぎないということになる。こういう考え方は、ここ半世紀のほとんどの期間、我々のトラウマ理解を支配してきたもので、嘆かわしいほど不十分だ。
最近まで、トラウマについて我々が知っていたことのほとんどは、心的外傷後ストレス傷害(PTSD)など最も重篤な症状の研究から得た知識だった。もちろん、重篤なトラウマを理解するためにあらゆる努力をしなければならないのは当然だ。ただ問題は、その目的ばかりに集中して、激しい反応を示さない人たちのケースを見落としてしまうことにある。その結果、重い症状が出るケースについてはたくさんの知見が得られるが、問題のないケースについてはろくに学ばないということが起きる。そして残念なことに、ものごとは常に悪い方に向かうとか、トラウマになるようなストレスを受けると、必ず長びくトラウマやPTSDが生じるなどということを、人々は次第に信じるようになっていった。
こういう考え方は「本質主義」と呼ばれる。トラウマを引き起こす出来事はいわば「自然種」で、目に見えない不変の「本質」を持っており、人々に特定の感情や行動を起こさせるという信念に根差した考え方だ。PTSDはこのように考えられる傾向がある。PTSDの本質を捉えようとした時、私たちは、それは人が発明したり創出したりしたものではなく、もともと存在するもので、人は単に発見したにすぎないと考えてしまった。本質主義者たちの考え方が必ずしも間違っているわけではない。犬は猫とは違うし、石は水とまったく異なる。しかし、本質主義的な考え方は時に的を外すことがある。特に精神状態に関してはそうだ。そして、この後見ていくように、従来のトラウマに関する考え方はひどく的外れだった。トラウマもPTSDも、静的で不変のカテゴリーではない。あいまいな境界を持つ動的な状態で、しかも時とともに展開し変化するものだ。
もちろんPTSDや、少なくともそれに近い症状が生じることはある。そして残念ながら、そういう場合には、心身の健康が著しく損なわれることが多い。しかしPTSDのような激しい反応は、トラウマ的出来事に遭遇すれば必ず即座に発症するようなものではない。暴力的ないし命に関わるような出来事が非常に大きな衝撃を与えるのは当然だ。そしてほとんどの人が少なくとも何らかのトラウマ的ストレス反応を経験する。放心状態になることもあれば、不安に取りつかれることもある。忌まわしい思考、イメージ、記憶に苦しめられることもある。これらの反応は人によっても、出来事によっても異なるが、たいていは一時的なもので、二、三時間あるいは二、三日で消えることもあれば、二、三週間続くこともある。このように一過性である限り、トラウマ的ストレスは完全に自然な反応である。PTSDではない。
PTSDというのは、トラウマ的ストレス反応が消失せず、悪化して増大し、最終的に持続的な苦悩として定着してしまうものだ。だがこのような結果になるケースは、一般に考えられているよりはるかに少ない。これまで数十年間にわたる調査の結果、暴力事件あるいは命に関わる出来事に遭遇した人の大半は、PTSDを発症していないことが明らかになった。つまり、出来事そのものが「本質的にトラウマを引き起こす」ものではないということだ。どんな出来事でも、暴力事件や命に関わる出来事でさえも、「本質的にトラウマを引き起こす」ものはない。そういう出来事は単に、「トラウマを引き起こす潜在的可能性がある」にすぎない。それ以外の大部分は、それぞれの当事者にかかっている。
その「それ以外の部分」は、トラウマについて一般的に考えられているよりも、はるかに多様性がある。ほとんどの人々はPTSDを発症しないが、その中には別のさまざまな形で苦労する人たちもいる。二、三か月ないしそれ以上トラウマ的ストレスで苦しめられ、その後徐々に回復に向かう人もいれば、当初ストレス反応はそれほどひどくないが、時間とともに少しずつ悪化していく人もいる。だが、そのように多様なパターンがあるにしても、圧倒的多数の人々が、トラウマ的ストレスに何とかうまく対処できる。トラウマを引き起こしかねないような出来事に遭遇した人々も、そのほとんどは、比較的速やかに普段の生活に戻ることができ、長期にわたる苦悩を覚えることがない。大多数の人は、立ち直る力を有している。つまり「レジリエント」なのだ。私自身も何度も調査を行ったが、繰り返しこの結果が現れた。他の研究者たちの研究の結果も同様である。これまでに行われたあらゆる種類の研究──非常におぞましい出来事やトラウマを引き起こす可能性のある出来事に関する研究──を調べてみても、最も一般的な結果は、人々が示すレジリエンスであった。
だが、「人間は非常にレジリエントだ」ということが研究の結果明らかになったとしても、まだ大きな疑問が残る。恐ろしい出来事が起きた時、人はなぜこれほどうまく対処できるのだろうか。どうして恐ろしい記憶を振り払って生活を続けていけるのだろうか。どうやって、それほどレジリエントになれるのだろうか。
皮肉なことに、これが従来のトラウマ理論の欠陥が最も際立つ箇所である。もしPTSDが単にトラウマ的出来事のせいで起きるというならば、同じ本質主義的な論理に従えば、ほとんどの人がトラウマに対してレジリエントであるのは、単に彼らがレジリエントだからということになる。つまり従 来の見方に立てば、レジリエントな人々には彼らを損傷から守る何かが本質的に備わっていると考えざるを得ない。
みなさんが目にするレジリエンスに関する記述のほとんどが、この固定した本質主義的考え方にはまり込んでしまっている。レジリエントであるためには正しい資質──つまり非常にレジリエントな人々が持つ五つないし七つの特質──を備えている必要があるというのだ。このリストに挙げられている特質を備えていればレジリエントで、備えていなければレジリエントではないという。こういう単純明快さは、非常に人を惹きつける。またこういう特質を獲得する努力をすれば、レジリエントになれるという期待を抱かせる。
しかしよく見ればこの論理には欠陥がある。リストに載っている特質の数が問題だというのではない。私自身の研究でも、レジリエンスに関係する特質をたくさん特定することができたし、今後さらに見つかることは間違いない。したがって数は問題ではない。問題は、このようなフリーサイズの服みたいな特質リストに頼っていては、目的を達成できないということだ。私はこれを「レジリエンスのパラドクス」と呼ぶ。レジリエンスの統計的相関関係を見つけることはできる。つまりいわゆるレジリエントな人々がどういう特質を持っているかということだ。しかし逆に、何か悪いことが起きた時に、その相関関係を基に誰がレジリエントで誰がそうでないかを実際に予測することは難しい。
その理由は、レジリエンスもトラウマと同様に動く的だからだ。トラウマになりかねないような出来事によって引き起こされたストレスは、時間とともに展開していく。何とか制御しようと努力する間にも、動いたり形を変えたりする。トラウマ的出来事は生活自体に影響を与えることも多く、そのためしばしば新たなストレスや問題を生み出す。たとえば身体的損傷が残っていることもあれば、一時的に仕事や住居を失うこともある。こういったショックに適応するには時間がかかる。いくつかの持って生まれた性格によって対応できるものではない。
実際に、多くの研究が示しているのは、何か一つの特質、あるいはいくつかの特質だけでは必ずしも効果がないということだ。後ほど説明するが、どんな特質にも行動にも、プラス面とマイナス面の両方がある。簡単に言えば、ある状況におけるある時点で功を奏したものが、別の状況や別の時点ではうまく働かず、かえって害をもたらすことがある。明らかによいように見える特質や行動、たとえば感情を表出することや、他者に助けを求めることでさえ、いつ何時でも有効とは限らない。場合によっては、一般的に問題が多いと考えられている特質や行動、たとえば感情を抑圧することなどが、まさにその人が必要としている行動だったりする。これはまさに、人は苦悩と闘いながら、その時その時で一番良い解決法を考え、さらに微調整を繰り返していかなければならないということを示している。言い換えれば「フレキシブル」でなければならないのである。
こういうと単純なことのように聞こえるが、この「フレキシビリティ」には重大な意味がある。人が逆境に適応する過程でこれは重要な役割を果たすので、私はこの点を説明するのに多くのページを割くつもりだ。まず、フレキシビリティというのは、受け身のプロセスではない。トラウマになりかねない出来事は、辛く不快なものであるから、普通は何をおいてもそれを思考の外に追い出したいと思う。だがその出来事に適応するためには、自分がどんなことを、どういう理由で経験しているのかについて、自ら進んで体系的に考えなければならない。それを効果的に行うには、モチベーションと熱意が必要だ。私が「フレキシビリティ・マインドセット」と呼ぶ気持ちの持ちようが重要になる。
このマインドセット、つまり信念を持つことができると、試練に向き合うための基本の行動に移行できる。そして私が「フレキシビリティ・シークエンス」と呼ぶ一連のステップを始めることができる。このステップを辿っていくと、自分に何が起きたのか、それに対して何をしたらいいのかを理解できるようになる。また調整のための大事なステップもあり、ここでは選んだ戦略がうまく行っているか、別の戦略に変更すべきかを判断する。この一連のステップを辿ることにより、手持ちのツール、つまり自分が使える特質や行動やリソースをフレキシブルに活用して、効果的に状況に適応しながら前進できる。ここでぜひ指摘しておきたいのは、これらが決して特別な能力ではないということだ。単にあまり意識されないヒトの心の特徴だというだけで、育成も改善もできる。
この考え方について公の場で講演を行うと、「トラウマに関する従来の理論がそれほど間違っていたなんて到底信じられない」と言う人が必ずいる。みなさんもまた、そう思っているかもしれない。それも無理はない。いま述べてきたような考え方の多くは、みなさんがこれまで教えられてきたことと相反するからだ。そしてもちろん、従来の理論にはまったく根拠がないと言えば、それも間違いになる。これまでの考え方、特にPTSDの概念は、トラウマを理解する長い道のりにおいて、なくてはならない重要な段階だった。しかし我々はいま、はるかな道のりをここまで進んできた。そしてこの後すぐに述べるように、その間に発見された洞察やエビデンスは、疑いの余地を残すことなく、従来の考え方がもはや生き残れないことを示している。
この後の各章で、より筋の通った新しい枠組みを示していこうと思う。レジリエンスやPTSDなど、トラウマによって生じるさまざまな結果を説明できるだけでなく、これらの異なる結果がどのように展開していくかも説明できる枠組みである。新しい考え方を導いた疑問や考えを深く探求し、それを支えた研究のいくつかを詳しく見ていこうと思う。ここで紹介したジェッドには、今後もいくつかの場面で登場してもらって、その様子をチェックするつもりだ。また他にも、重大な苦難に遭遇した人たちのさまざまなストーリーを紹介する。だがその前に、まずそもそもの始まりからスタートしなければならない。人間が最初にトラウマを理解しようとした時点に、戻ることにしよう。
■ ■ ■
本書の目次
プロローグ 自分はなぜ大丈夫なのだろう?
パートⅠ 三分の二
第1章 PTSDの発明
第2章 レジリエンスの発見
パートⅡ ストーリーと予測
第3章 外からうかがい知ることのできない世界
第4章 レジリエンスのパラドクス
パートⅢ ゲームを主体的にプレイする
第5章 フレキシビリティ・マインドセット
第6章 相乗効果
パートⅣ 基本的な仕組み
第7章 フレキシビリティ・シークエンス
第8章 フレキシブルになる
パートⅤ リピート・アフター・ミー
第9章 自分自身に語りかける
第10章 そして世界的パンデミックが起きた
謝辞
註
著訳者紹介
■著者
ジョージ・A・ボナーノ
コロンビア大学臨床心理学教授。
同大学のカウンセリング・臨床心理学部長、喪失・トラウマ・情動研究所所長を務める。
愛する人の死やトラウマ的出来事に直面したときに発揮される「レジリエンス」研究の世界的権威。科学的心理学会(APS)、国際トラウマティックストレス学会(ISTSS)、国際ポジティブ心理学会(IPPA)より、それぞれ Lifetime Achievement Award(生涯功績賞)を贈られる。これまでに何百もの論文を発表しており、その多くがネイチャー誌、JAMA(ジャマ)誌、アメリカン・サイコロジスト誌、アニュアル・レビュー・オブ・サイコロジー誌などの一流雑誌に掲載される。世界で最も引用された科学者のトップ 1%(ウェブ・オブ・サイエンス)。その研究は、ニューヨーク・タイムズ紙、ウォール・ストリート・ジャーナル紙、ニューヨーカー誌、サイエンティフィック・アメリカン誌、アトランティック誌、ロサンゼルス・タイムズ紙、ローリング・ストーン誌、NPR 、CBS 、ABC 、CNN ほか、数多くのメディアで取り上げられている。著書に『リジリエンス-喪失と悲嘆についての新たな視点』(金剛出版)がある。
■訳者
高橋由紀子
翻訳家。慶応義塾大学文学部卒。『幸福優位7つの法則』(ショーン・エイカー著)、『今ここに意識を集中する練習-心を強く、やわらかくする「マインドフルネス」入門』(ジャン・チョーズン・ベイズ著)をはじめ、ポジティブ心理学、社会心理学、マインドフルネス関連の訳書多数。
最後までお読みいただきありがとうございました。私たちは出版社です。本屋さんで本を買っていただけるとたいへん励みになります。
