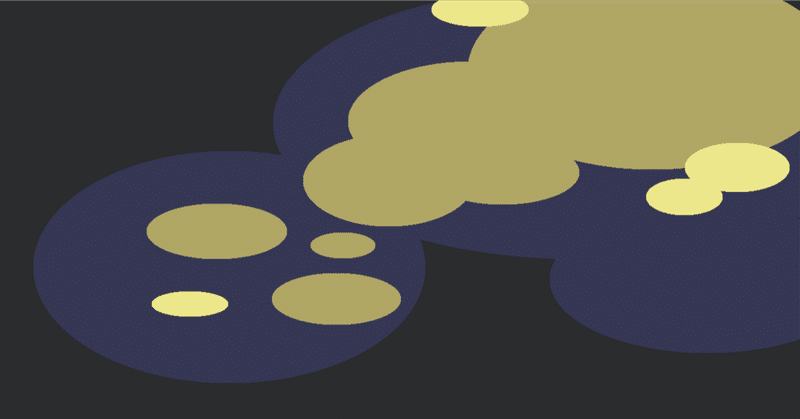
【怪奇小説】オドイト【第一話③】
【前回】第一話② https://note.com/haizumisan/n/n64b348f24bde
苦しい。彼女が恋しい。いずれ忘れるその感情を、僕は手の中で慈しむように撫でまわした。
彼女が、特別な一人から、かつて知り合いだった他人になるまで、いや、そうなった後だって、今の僕の気持ちが本物であるということには変わりないのだ。
薄情だ。どうしてそうも割り切れるものだろう。こんな紙切れで別れを告げるなんて。
僕は、受験の失敗と、初めての恋人との別れを思い出していた。それらを思い出しても、僕の心が痛むことはもうないが、どんな種類の痛みだったのかは、なんとなく思い出せる。
その記憶は、今の僕の痛みをより早く過去のものにするのに、役立つはずだ。
要は、経験が大切なのだ。人は、道の痛みを恐れる。それがどのくらい痛くて、どれだけ続くのか分からないからだ。
オドイトは、過去から共感というものを切除し、参照可能な情報にする効果がある。記憶の引き出しに保管した痛みの情報は、新しい痛みに対して、それがいずれ褪せて力を失っていくものだと教えてくれる。
不安を抱かずに生きることはできない。だけど、不安を予習して、いくらかの安心をお守りにすることはできる。
オドイトは、人類が終わりなき不安を克服するための進化の過程で生まれた、叡智なのだ。
力を失うと分かっている、彼女の喪失という痛みを、できるだけ綺麗な形で引き出しにしまいたい。そうすることで、僕はより安心に生きることができるのだ。
僕は手近にあったウィスキーの瓶を無造作に開け、彼女と親しくなるきっかけになったCDを再生した。彼女と趣味の話で意気投合したのは、このアーティストが、お互いにお気に入りだったからだ。
僕はソファに身をうずめて音楽を聴きながら、酔い潰れるまで酒を飲んだ。酩酊は、痛みに身をやつす儀式だからだ。
翌朝、二日酔いの嘔吐がおさまった頃に、僕はオドイトを吐き出した。
洗面器の中でのたうつそれは、今までで一番大きく、醜かった。
オドイトの姿は、個体ごとに違う。排泄も繁殖もしない、生まれながらに生き永らえないことが決まっている。未熟で、か弱く、グロテスクなものである、ということが共通している。
オドイトの体表面に付着した成分が、不快な粘りと味を口内に残している。
僕はアズレン入りの洗浄剤で、何度も口をすすいだ。洗面器に横たわるオドイトは、僕が吐き出す洗浄液が跳ねる度に身をよじらせ、苦しんでいるようにも見えた。
前に2回吐いたオドイトは、洗面器のゴミ受けを取り外して、洗浄液と一緒に押し流した。しかし、今回のは洗面器の排水口には大きすぎる。
こういう場合、人目に触れないよう紙に包むなどして、可燃物と一緒に廃棄することになっている。
しかし、僕はこの醜いものに触れる気になれなかった。
洗浄液を再び口に含み、オドイトの全身にかかるように狙って吐き出した。すると、オドイトは一層に身をよじり、のたうち、段々と弱々しくなり、やがて動かなくなった。
僕はその場に座り込み、しばらくうなだれていた。オドイトを吐き出した後の身体は、倦怠感に襲われるのだ。
僕は書斎に行き、机の引き出しからライターオイルを取り出した。
(続く)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
