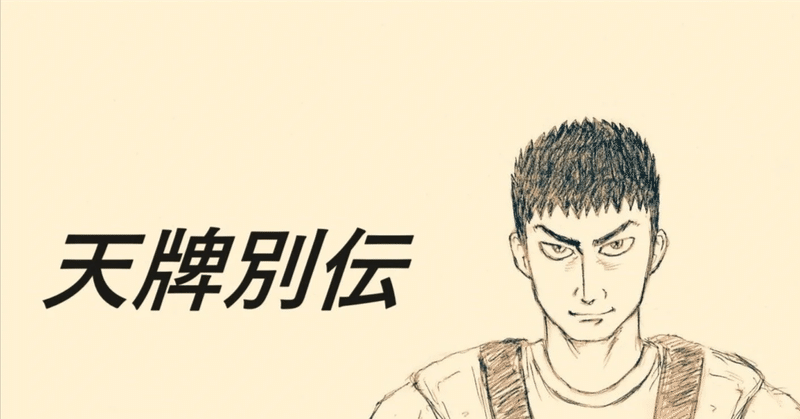
天牌別伝 二
二
カレーは、やはり一日置いた方がうまい。
少し早めの昼食をとると、すぐに星野源八は台所で食器を洗った。
めずらしく、今日の『いこい』に客はいない。いつもなら、誰かしら寝転がっているか、人数が揃えば卓を囲んでいるが、今日は全員が仕事にありついて外に出ている。
ドアが開いた。
風とともに、人が入ってきた。菊多賢治。肩にかけた上着と垂れ下がった前髪が、風に靡いている。
「めずらしいな。だいぶ暖かくなってきたが、まだ風は冷たいだろ」
「ああ……。今日は、これから、赤坂へ行く。なんとなく、立ち寄ってみた」
よろめくように、菊多は一番近い卓の席に座った。
「そうか。もう、一年になるんだな……。腹、減ってないか? カレーライスならすぐ出せるが」
「気持ちはありがたいが、胃が受け付けん……。白湯を、くれないか」
「わかった」
星野は、白湯を注いだ湯飲みをサイドテーブルに置いた。
両手で湯呑みを抱える菊多の仕草は、まるで老人のようだ。頬の肉は削げ、目は落ちくぼんでいる。それでも、菊多の双眸には炎が宿っていた。麻雀に対する、狂気とも言える執念の炎だ。
「今日の対局は、津神も行くのか?」
「いや……。やつは、新満氏の一周忌だからといって、行くような男ではない。まあ、俺も興味があるのは、集まる打ち手の方にだが」
「なるほど。それにしても津神は、なにを考えてるのかわからないやつだ。いずれまた、裏社会を巻きこんでの大きな争いが起きるかもしれないな……」
「その時は、またあんたの出番が、来るかもしれない」
「勘弁してくれ。俺は、この雀荘や、この雀荘を愛してくれる連中を守るので精一杯さ」
「そうか……。そろそろ、行く。邪魔したな」
「ああ。気をつけてな」
ふらつきながら立ちあがり、菊多は入口へ歩いた。昨年よりも痩せ細った菊多の姿に、星野は胸を衝かれた。
「できれば、またあんたと打ちたい」
ふり返って、菊多が言った。
「いつでも来いよ。胃にやさしいもの作って、待ってるぜ」
口の端に笑みを浮かべ、菊多は出ていった。
しばらくして、車の走り去る音がした。どうやら菊多は、表でタクシーを待たせていたようだ。
星野は窓を開け、空を見あげた。雲ひとつない、澄んだ空だ。
青空を見あげながら、星野は菊多の口に合いそうなメニューをぼんやりと考えた。
* * *
チョコレートパフェを平らげた田浦海輝が、スプーンを置いた。
「ふぅ~、食べたなあ。ほんとにご馳走になっちゃっていいんですか、鳴海さん?」
「気にせんでええ。歳を取ると食が細うなるさかい、若いモンがうまそうに食っとるのを見るんが楽しいんや」
コーヒーを啜り、鳴海弘富は言った。
「そうですか……。ありがとうございます。ドリンク、入れてきますね」
グラスを手に立ちあがり、海輝はドリンクディスペンサーの方へ歩いていった。
テーブルにコーヒーカップを置くと、鳴海は窓の外の通りに目をやった。土曜の昼だけあって、行き交う人々は多い。このファミリーレストランにも、多くの客が入っている。
黒流会の三國健次郎と同様、鳴海も昨年の対局以降、一線を引いた。京都の『ウェスト』の店長だった天堂忍に経営を任せ、大阪の『ステップ』とともに統括してもらっている。
この一年、息子の晃の消息について多方面を当たったが、新たな情報はなかった。まだ生存を諦めたわけではないし、津神元に対する憎しみも、消えたわけではない。それでも、昨年の対局を境に、鳴海の心の中ではひとつの区切りがついていた。
海輝が戻ってきた。グラスの中身は、オレンジジュースのようだ。
「それ飲んだら行こか」
「はい」
海輝を見ていると、つい頬が緩んでしまう。鳴海にとっては、孫のような年齢だ。しかし、麻雀の才は目を見張るものがある。優勝した柏木、そして瞬や北岡。いずれも新たな時代を感じさせる打ち手ではあるが、海輝は彼らをも凌ぐ打ち手になるかもしれない。まだ子供だが、天才という言葉がこれほどふさわしいと思った打ち手は初めてだ。
鳴海はコーヒーカップを手に取った。空だということに気づき、腰を上げた。
「ワイも、もう一杯だけ飲もうかな」
「はい」
素直な子だ、と鳴海は思った。家庭の環境もあるだろうが、海輝の姉の家庭教師をしていた伊藤芳一の影響も大きいだろう。海輝にとって、伊藤は憧れの兄、ヒーローのような存在らしい。
聞くところによると、伊藤は東大生でありながら裏社会の麻雀に足を踏み入れ、惨敗したのち東大を中退し、京都の実家に戻ったのだという。いまは麻雀はきっぱりとやめ、再び医師を目指し勉強しているようだ。
海輝は、瞬のことも兄のように慕っている。そして、伊藤も瞬も、黒沢義明の弟子だったという。
(黒沢はん、一度しっかりと打ってみたかったわ……)
せめて、黒沢の弟子たちの行く末は、もう少し見守っていよう。
注がれるコーヒーを見ながら、鳴海は思いをめぐらせた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
