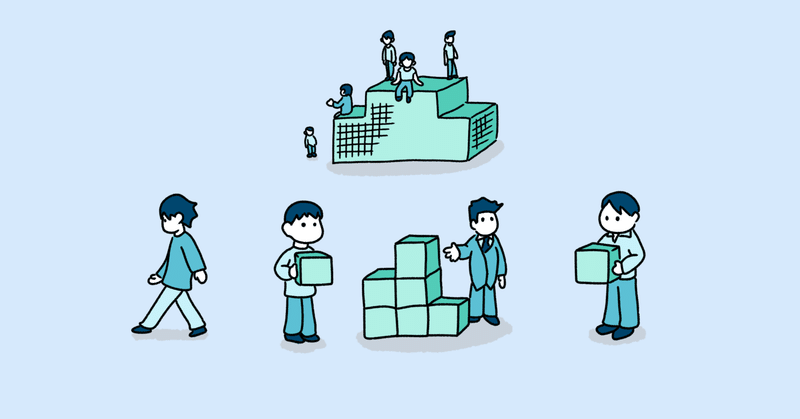
小笠原直著『監査法人の原点』を書評する(3/4)
この記事は前回記事の続きです。初めての方は第1回からどうぞ!
3-4.自由職業人
自由職業人という言葉は、定義が定まった概念ではない。本書の説明は監査論でいう「独立性」の概念に一見似ているが、「独立性」が監査に臨む際に保持すべき属性に留まるのに対し、「自由職業人」は「人」の属性として、「あるべき生き方」という意味まで含んでいる。例えば、「本来、公認会計士とは自己完結を旨とする…べき」(53頁)と述べられ、その生き方に相応しい組織の在り方、にも議論が展開している。公認会計士は「組織人にもともと向かない」(119頁)、また「全員がつながることがパートナーシップの原点であり、そしてそれこそが、自由職業人の組織を意味するものだと思っています」(163頁)などの表現もある。この辺りの記述には、波頭のプロフェッショナル論との共通性が見て取れる(波頭 2006)。
しかし、監査業務には、本書が示唆するような「自由」な判断は求められていない。本書は「組織である以上、またルールを遵守することがあくまでも重要な職業ですが、だからといって、自主規制や自己保全的ルールという型にはまった行動規範や思考基準は、自由な判断の妨げになるだけです」(56-57頁)と主張する。しかし監査という業務は、単に各会計士がプロとしての経験に照らして正しいと判断した、から信頼性を付与できるのではない。「しっくりくる」基準が各人違っていたら、財務諸表への信頼は高まらない。会計基準・監査基準という(原理的には専門家が中心となって暫定的に決めた)ルールに従う(言い換えると、判断を「自主規制」で自ら型に嵌める)からこそ、利用者は監査人ごとの判断過程や結論が大きくは違わないという安心を得ることができるのである。
この指摘は些末な言葉尻を拡大解釈していると思うかもしれないが、本書に登場する以下の主張を見てほしい。
「正しい情報に照らして、その情報にいちばんしっくりくる会計処理は何かを考えることがいちばん大事なのです。監査の仕事、会計処理の仕事は、それこそ当事者間の仕事であって、外野がとやかく言うことではない。インターネットでいろいろ調べてわかることではない。それが業界の風潮であるとすれば、その風潮はおかしい、間違っていると、声を大にして言いたい」
「外野がとやかく言うことではない」という記述は、「自ら縛る」ことの重要性、監査が信頼性付与につながるメカニズムを、本書が適切に認識していないことの表れであるように思われる。
また「自由職業人」論は、「雇用されないのが本来の姿」という主張も含んでいる。監査法人の組織形態については節を改めて論じるが、ここで指摘したいのは、「組織に縛られない」という意味での「自由」は、会計の専門知識を得たことで既に達成されているということである。専門知識を身につけたことで組織間移動の自由度は拡大しているのであり、本書が提示する「組織人」対「自由職業人」、という構図は成り立たない。そもそも、専門知識や資格を得たからといって、大きな組織で働くという職業選択の「自由」を捨てなければならない理由はない。
本書は、公認会計士の独占業務が監査業務である以上、非監査業務でなく監査業務と「自由職業人」の風土・気構えを両立させるべきだ、とも主張する(130-132頁参照)。しかし、これも「自由職業人」というレトリックに自ら引き摺られ、その機械的なあてはめによって監査業務の性質を見誤った主張であると考えられる。
このことを説明するには、法曹との比較が分かりやすいだろう。法曹・会計士ともにルールに関わる専門知識であり、ヒトとルールが関わる場面ごとにサービス/業務が生じる。大雑把には、(1)ルールの制定・改訂、(2)ルールの理解促進・活用、(3)ルール逸脱への対処(防止・摘発・認定等)、を識別できる。
法的サービスの場合はよく検察、裁判官、弁護士が主要なサービス領域として挙げられるが、前二者は(3)、後者は(2)あたりと主に対応している。(1)の領域でも審議会等で需要がある。一方、会計サービスの場合は(1)として審議会やASBJ、IFRS財団等への参画等、(2)としていわゆる非監査業務等、(3)として監査業務や証券取引等監視委員会・財務捜査官等が挙げられる。
各領域で求められる職業規範や標準的な組織形態・組織規模等は、主にそのサービス/業務の性質に規定される。例えば、「プロフェッショナル」の典型であり「自由職業人」である法曹も、司法機能を担う間は(雇用形態や職業規範上)「自由」ではなくなる。業務の性質上、組織に属し、利害関係者から自身を切り離し、(自分の信念とは異なるかもしれない)既存慣行との整合性をより強く意識して法的な判断を行うことが、制度上期待されているからである。同様に会計専門家も、保証機能である監査業務を行う際は、その性質上「期待される品質のサービスを提供できる組織体制を整える」「好みのクライアントに肩入れしない」「自らの判断過程を監査基準で縛る」などの「束縛」の受容が求められる。そのことは、会計の専門家であることと、何ら矛盾しない。
主に「業務の性質」に拠ると論じたのは、「独占業務かどうか」は、職業倫理や組織形態と直接の関係が無い、ということでもある。各領域で求められる機能が実際にどのように満たされるかの制度設計は歴史的・地域的にバラつきがあり、理論的に正当化しきれない偶然的な要素も多く含まれる。「独占業務かどうか」も、そのような制度設計の一側面に過ぎない。日本の税理士と会計士の並存は、このような偶然性の典型例といえるだろう。
しかし本書は、公認会計士が「自由職業人」であるという性質は、資格制度であることに由来する(56頁)と述べている。前述したように、会計士の「自由」は資格というよりも専門知識に由来する。公認会計士に「自由な生き方」を保証する目的で資格制度・監査制度が作られたわけではない。
ここまでの検討を踏まえて、本書の主張を改めて見てみよう。
「公認会計士の独占業務は監査です。その監査業務を捨てて立派に身を立てて…も、独占業務を捨てるというところに、公認会計士としての存在価値をどうみるのかという問題があることは間違いないと思います。…公認会計士である以上、やはりやらなくてはいけないのは上場企業の監査業務であると私は思います。それこそが公認会計士の表看板だからです。…あくまでも、監査業務を企業に提供することがわが国の公認会計士制度のそもそもの始まりだから、そこは優先しなければいけない」
現代日本では、会計の専門知識習得によって可能となるサービスのうち、(4)の一部(監査業務)のみが(公認会計士の)「独占業務」とされている。しかし繰り返すが、これらの制度設計は「たまたま」そうであるに過ぎない。著者は、仮に非監査業務も公認会計士の独占という制度の下なら、(より「自由職業人」的な働き方をしやすい)非監査業務を選んだのだろうか?
引用部分に現れた著者の思考過程は、会計の専門知識を得たことで拡がった業務の可能性を、国がたまたま監査業務のみを独占業務にしているという偶然的な外部要因によって狭める、「不自由」なものであるように思われる(ただし、それも含めて当人の自由選択であるので、この思考過程が「間違っている」わけでもない。本指摘の目的は、その特徴を可視化することだけである)。
なお念のため付言すると、これまでの議論は、「自由」でないから監査業務には魅力がない、という意味では全くない。再び法曹のアナロジーを用いるなら、裁判官が弁護士より「不自由」でも、裁判業務に大きな魅力と意義があることに変わりはない。各人が自分の好みに合わせてサービス領域を選べばよいのであって、監査業務と非監査業務との間に、一般的な優劣は存在しないと考えるべきだろう。
例えば、先にも紹介した浅野は、「『本来、会計士もビジネスロイヤーとして、基準文言に明記されていない部分も含め、クライアントの立場に立って条文解釈を行い提案することで、目の前のクライアントから感謝されるような専門家になりたい』と夢見ていましたので、大手の監査法人系事務所ではもはやそういった積極性やリスクを取る姿勢の仕事は実現できそうもないと判断し、独立に至った」(浅野 2019、17頁)と述べている。このような個人的好みを持つ者なら、非監査業務を選ぶのは自然な意思決定といえる。
一方で、例えば、自身の事務所やクライアントという私的利益に貢献し続ける業務を物足りないと感じ、違う種類の公益への「物語」を求める者もいるかもしれない。個人レベルではどのように考えようと問題なく、基本的には、各人の好みの問題ということになろう。
以上の議論をまとめる。公認会計士が「自由」であるのは専ら専門知識によるのであり、制度(監査業務の独占が国家に認められていること)によるのではない。会計士であるからといって、特定の雇用形態や業務領域が「一般的に」より正当とか望ましいと考える理由はない。
3-5.適正規模・組織形態
ここまで「公認会計士は自由職業人である」という言説の問題点について詳しく検討してきたが、本節では、前節ではあまり触れなかった「自由職業人」と「組織規模」との関係を取り上げる。
本書では、組織は公認会計士にとって必要悪かもしれないといい、少人数のパートナーの集まりを「自由職業人の組織」(163頁)として想定している。また、金融庁も「『公認会計士はリスクを背負う自由職業人である』前提で制度構築している」(55頁)のであり、公認会計士の「組織人化」に金融庁は困惑・失望しているはずだ、との認識を示している。
しかし、金融庁が望むこと(=制度趣旨)は、高品質の監査サービスが提供されることであり、そのために監査従事者の「独立性」が維持されていることである。ここで、「組織人」であること(大組織に属すること)と「独立性」の保持は矛盾しない。監査業務遂行に要求される「独立性」は専ら被監査会社との関係に注目した概念であり、監査従事者の雇用形態が「独立」かどうかとは論理的な関係が無い。監査手続を行うなら会計士資格に関係なく「独立性」宣誓書への署名等が要求されるので、公認会計士に限って要求されるものでもない。従って、金融庁が、会計士が「自由職業人」であることを前提に制度設計しているという本書の主張には、根拠が無い。
監査法人の組織規模・組織形態は専ら「高品質の監査サービスを提供できるかどうか」という観点から定まるべきものであり、企業活動が拡大・複雑化すれば、監査人側に必要な組織規模・組織形態も変わりうると考えるのが自然だろう。本書は、昔の公認会計士事務所・監査法人の組織規模や組織文化を、「天衣無縫」(157頁)などと肯定的に描写している。しかしこれらの特徴は、その時代に特有の、(時代によって変化するという意味で)偶然の産物に過ぎない可能性が高い。組織規模や組織文化に対する好みは各人で分かれるだろうが、その「一般化」は、主張の射程や前提条件の特定、背景となる規範理論の構築等、誘惑に比して議論としての難易度が高い(そして記事作成者のみるところ、本書も失敗している)。自身の好みを「もともと」「ピュアな」「本来の」「本質」「原点」等の形容詞で正統化・理想化するだけでは、説得力に乏しいのではないだろうか。
(続きます)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
