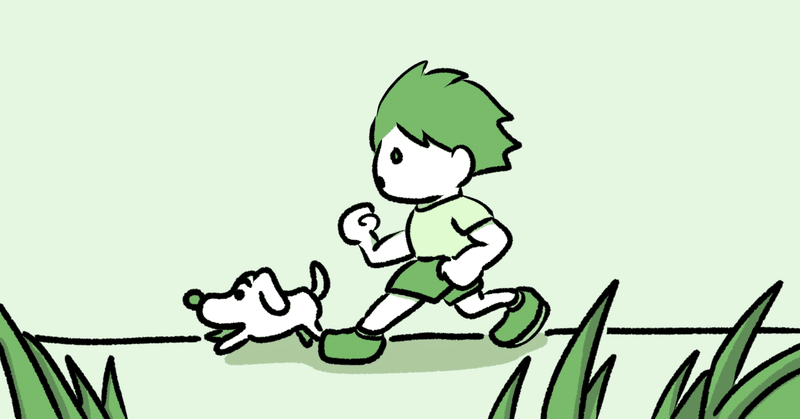
小笠原直著『監査法人の原点』を書評する(2/4)
※この記事は前回記事の続きです。初めての方は第1回からどうぞ!
3-1.「財務諸表利用者」の軽視(承前)
なお、前述のメカニズム(企業のパートナーを公言することによる、監査人としての信頼付与力の低下)が作動するにあたって、監査人の自己認識(独立性を保っていると自分で思っているかどうか)は、関係ない。監査人が「企業の戦略パートナー」というスローガンを繰り返せば、当該監査人の判断が全体として企業有利に歪んでいる可能性を示唆するものと、利用者が考えても不思議はない、ということである(外観的独立性の毀損)。そのような思考が利用者側に生じれば、仮に監査人が実際には公正な判断を行っていたとしても、当該監査人の信頼付与力は、低下する。
監査人ごとの財務諸表への信頼付与力の差は、いわゆる「監査品質」についても生じる。遵守すべき監査手続は監基報等に規定されているが、手続の遵守程度は、法人により異なると想定するのが自然である。各法人の「監査品質」を定量化するのは容易ではないが、一般に法人毎に「高い・低い」という評価の差は確実に存在し、実際に投資行動に影響を与えるのはこのような「イメージ」の方である。ここでも、監査品質が低いという評判の監査法人に監査を依頼した場合には株価がその分下がるので、企業は監査報酬の節約分との比較衡量で契約先を決める、ということになろう。
本書は、以上のような「情報の非対称性」に由来する企業・利用者・監査人間の相互作用を認識できていない。そのため、「企業の戦略パートナー」を正面から掲げる監査法人と契約すれば、会計判断が企業に寄り添うものになり、適切な指導も受けられるので、企業にとって魅力的である、という単純な推論に留まったものと推察される。
とはいえ、保守的な会計判断は企業を害する、というロジックに一定の説得力を感じる読者もいるかもしれない。そこで次節では、この点をめぐる本書のキーワード「意思決定のデフレ化」を中心に検討する。
3-2.意思決定のデフレ化
本書では、企業の事業計画に基づく見積り数値を適正と判断するかどうか監査人が迷う場面の記述が多く出てくる。そのほとんどが、保守的な判断について、保守的であること自体を批判するものである。以下、列挙してみる。
「人間、『×』をつけるのは簡単です。慎重で保守的な見解を述べれば、その時点では何であれ、真っ当そうな説明はできてしまうからです」
「もちろん、資産には計上できないという判断が正しい場合もあります。経営者の暴走を止めるのは公認会計士の務めです。ところが、『計上できない』といったときにはその会計士は判断しているようで判断していないことがあります」
「強調しますが、保守的に対処するのは簡単です」
「リスクを取りたくないからと、何でも批判的に判断して、ノーと言う。そうしたケースがあまりにも多いですが、実はそうした態度こそ、厳に慎まなければいけないのです」
一方、保守的な判断に肯定的な記述は、「減損処理をしたほうが望ましいという確固たる信念があれば、もてる引き出しを全部出し切ってでも説得する」(146頁)くらいしかない。ただし、これも楽観的な判断を戒める文脈ではなく、公認会計士にコミュニケーション能力が必要だと強調するための場面設定にすぎない。
このように、本書は保守的判断に極めて批判的である。しかし、「保守主義」(企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性のある場合に、それに備えた適当に健全な会計処理を要求する原則)は、企業会計の一般原則のひとつとして正面から認められている。そのためか、本書は「保守主義の原則」には全く言及せず、「意思決定のデフレ化」という表現を中心に用いている。そして、これは「組織人化」の弊害と結び付けられ、「組織人」と化した会計士が「リスクテイク」をしなくなったとの批判が展開される。
「リスクテイク」については次節で改めて取り上げるとして、ここでは「意思決定のデフレ化」の吟味を続けよう。
そもそも「デフレ(ーション)」は経済学の用語であり、会計学の専門用語ではない。喩え・レトリックであり、意味はなんとなく分かるものの、定義が与えられないので厳密な議論は不可能である。
一般に、専門的な議論には専門用語を用いるべきであり、読者への訴求力等の思惑があってもレトリックの使用はなるべく控えるべきだろう。本書の奨励する監査態度が保守主義の原則に牴触する虞をはらむのは明らかであるから、読者を丁寧に説得したければ、「デフレ化」ではなく「保守主義の原則」を正面から取り上げた上で、自説の妥当性を論証すべきだっただろう。鍵概念を専門用語でなくレトリックに頼るのは、本書全体に見られる、専門用語を正確に使って厳密に議論しようとする態度・実践の欠如(後述)の表れであるように思われる。
とはいえ、この指摘だけでは検討が終わってしまうので、以下「デフレ」を「保守的な判断」に読み替えて議論を進める。
前述のように保守主義は企業会計の一般原則(のひとつ)だが、一方で「過度に保守的な会計処理」も明示的に禁止されている(企業会計原則注解4)。あくまで会計基準内での保守主義が求められているのであり、実態に即した判断が求められる。単に保守的な、もしくは楽観的な方が望ましいという性質の判断ではないので、監査人を評価するにあたっては、いかに検証可能な形で検討を尽くしたか、という判断過程が焦点のひとつになるはずである。
しかし本書は、判断過程についての議論がほとんど出てこない。例えば、おそらく監査基準委員会報告書への言及は一回もない(ただし、「マニュアル」という表現は出てくる(53頁、130頁))。本書が専ら注目するのは(企業に好意的か否かという監査人の基本態度と)判断の結果であり、保守的な判断はそれ自体が適正な監査を行っていないものとして非難される。このような「判断過程の軽視」も本書の大きな問題のひとつであり、監査人の負うリスク・責任に関する本書の誤認識(次節)とも通じるところがある。
さらに、「デフレ」批判の仕方も、フェアなものではない。本書中に「デフレ発想の公認会計士」の思考パターンを例示し、批判する箇所がある。会社が3年目から黒字化する事業計画を立て、2年目まで予定通り赤字、業績はやや上向きになってきているという場合が例として挙がっている。この場合、「デフレ発想の公認会計士」は「いくら予定どおりといっても、実際に開業以来、二期続けて赤字であったことは間違いありません。減損会計の原則に照らせば、これは減損の兆候になる…2年目も赤字なのだから、いくら予定どおりといわれても、この赤字がずっと続く可能性のほうが高いのではないか」などと言い出す、その結果(減損損失計上を強要して)固定資産としての価値をゼロとしてしまう、と批判している(93頁)。
しかし、いわゆる減損適用指針(企業会計基準適用指針第6号)では、予め合理的な事業計画で当初より継続してマイナスになることが予定されていれば、実際のマイナス額が当初予定よりも著しく下方に乖離していない限り、「減損の兆候」には該当しないと明示されている(適用指針12項(4)、81項)。つまり、本書がここで批判したような公認会計士は、現行基準下ではそもそも存在できず、存在できない主張を叩いても会計判断の困難さや幅についての理解は深まらない。この部分は、著者が当該規定を知らなかったのであれば知識の不足、知っていたのであれば藁人形論法(相手を、論破が容易なように歪めて特徴付けた上での批判)である、という批判を免れないのではないだろうか。
なお、一定時期を境に監査がより「保守的」になった、という観察は本書に限られたものではない。例えば浅野は、「エンロン事件をきっかけに、監査法人のあり方は、訴訟リスクや金融庁からの行政処分を避けるがために、どんどん保守化・マニュアル化され、個人の裁量や意見の余地は極限までそぎ落とされ、独立性の維持の要求も一層厳格化されることになりました。当時、大手の監査法人に勤務していた筆者も、監査法人がどんどん保守的になっていく雰囲気を肌で感じとったのを鮮明に記憶しています」(浅野 2019、16-17頁)と回顧している。
変化の要因や程度については、同時期に会計ビッグバン等複数の流れがあったこと、論者のバイアスもかかっていること等を考慮し、浅野の見立てよりも慎重な見極めが必要となろう。ただ、何らかの変化があったらしい、ということは一旦受け入れても良いように見える。
その場合、変化の規範的評価には複数の選択肢がある(変化前のほうが良かった、変化後のほうが良い、どちらもOK、どちらもダメ、等)。本書は第一の立場に立つ(104-105頁辺り参照)が、その論証には、成功していないように思われる。詳しくは、そもそも何を良い状態と捉えるべきか、という観点から後述する(「3-5.適正規模・組織形態」辺りを参照)。
最後に、筆者が前提としているようにみえる、「保守的な判断は企業にとって不利である」という議論も、疑わしい言説であることを付言しておく。例えば、いずれ必要になる減損なら費用の期間配分に過ぎず、投資期間全体の利益は変化しない。適時に減損を計上しないことで、後に二進も三進も行かなくなったときに累積分まとめての計上となり、市場にネガティブなサプライズとなって株価が余計に下がる可能性もある。また、いったん減損を(過度に)保守的に計上することで、その後の「V字回復」を演出する利益調整を意図する可能性もある。
もちろんこれらの指摘は可能性に過ぎず、一般化や条件特定にはより詳細な吟味や実証が必要だが、少なくとも「保守的な判断=企業に悪」という単純な図式は、成立しない。
3-3.結果責任・リスクテイク
次に、「結果責任」をめぐる本書の議論を検討する。関連する「リスクテイク」についての議論も合わせて論じる。
本書には、公認会計士が「結果責任」を負うという指摘が繰り返し出てくる。たとえば55頁では、「私たち監査法人は、プロセスを評価される立場の人間ではありません。結果評価がすべてです。結果が悪ければ、その責任から逃れられない。それはリスクです」と述べている。また73頁では、「公認会計士は経営と向きあい結果責任を負う立派な仕事と思います」とも主張する(124頁、138頁も参照)。
リスクについても、例えば212頁から始まる項のタイトルは「リスクテイクこそ私たちの役目、誇り」となっている。公認会計士には「常に判断が間違うというリスク」があり「そもそもリスクフルな職業」なので、「公認会計士はリスクを取るのが前提です。だからこそ信頼も得られるし、社会的にも認められる存在なのです」(213頁)と述べられている。
しかし日本の制度上、公認会計士・監査法人の責任は、結果責任ではない。結果責任は、法的にはいわゆる無過失責任を指す。監査人は、誤った意見を表明した結果として投資家が損害を被っても、故意又は過失が無ければ損害賠償の責任を負わない。過失があったかどうかは、監査がGAAS(一般に公正妥当と認められた監査の基準)に則って行われたかどうかで判断される。このように、監査人はいわゆる過失責任のみを負う「プロセスを評価される立場の人間」である、というのが正確な理解である。
また、監査人が財務諸表の「作成責任」を負わないことは監査基準や監基報で繰り返し強調される点であるし、監査報酬の面でも業績との連動は禁止されており(倫理規則22条)、この意味での結果責任も負わない。サービス提供を完了する責任、自身のサービスに対する道義的な責任や評判低下のリスクは会計士に限らず行為主体全てに伴うものなので、取り立てて「結果責任」と呼ぶことはない。
従って、本書で重要な位置を占める、公認会計士は結果責任を負う存在である、という言説は、誤っている。また監査人への信頼の源泉も、リスクを取ることにあるのではない(後述)。リスクテイクに関する言説も、もっともらしい見解を述べているようで、実は標準的な監査理論から大きく外れている。
ただし、ある会計処理が虚偽表示にあたるかについて確信が持てないときに、「認容した会計処理が後から重要な虚偽表示との認定を受け、さらに監査手続の過失も認められたために、損害賠償責任を負うリスク」は存在する。この場合、「念のため」減損等を被監査会社に要求する、という場合があるのかもしれない。このような限定的な意味では「リスクを回避すべきでない」という言説が成立するようにも見える。
しかしこの場合も、「監査人はリスクを取るべきだ」という結論が支持されるわけではない。会計基準に従う(「過度に保守的な会計処理」の強要は会計基準違反)こと、正当な注意を払ったといえるだけの監査手続を尽くすこと、各人の会計判断の能力を高めること、で対応可能な問題である。監査人の基本姿勢(企業に好意的か否か)、判断結果(保守的か否か)、リスク選好(リスク回避的かどうか)等を直接問題視する必要はないし、逆にこれらの点で特定の立場を監査人に要求すれば、監査意見の歪みをもたらす副作用が生じる。
(続きます)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
