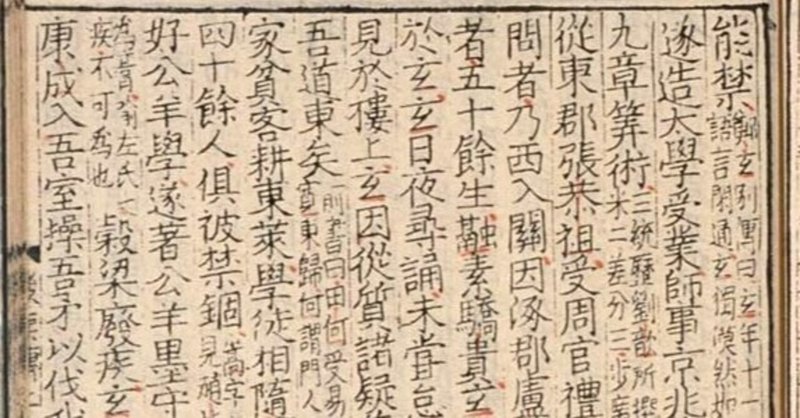
後篇・第七章「現代の視点」
鄭説の意義
後の歴史の展開を見ると、第四章の終わりで述べたような矛盾は内包しながらも、鄭玄はその後長く受け継がれる体系的な礼制度の構築に成功したと言えます。これが経学においてどのような学術的役割を果たしたのかという点について、最後に考えることにいたしましょう。
何度も述べたとおり、経書はもともとがバラバラに成立したもので、全体量も多いですから、様々な内容を含んでいます。極端に言えば、「AはBである」ということもあれば「AはCである」ということもあり、「ⅩとYは同じ」とあることもあれば「ⅩとYは異なる」とあることもあります。
ここから「経書の内容は無茶苦茶なものだ」というマイナスのイメージを受けるかもしれませんが、むしろ「古典」として人々に受け入れられるに当たっては、積極的な作用を果たしたとも言えます。相矛盾するほどに非常に幅広い内容を含み、様々に解釈される可能性があったからこそ、普遍性を獲得し、二千年以上に亘って漢字文化圏の全体で「古典」として重視された、とも考えられるからです。
説明だけでは分かりにくいと思いますので、簡単な例を示しておきましょう。『論語』の陽貨篇には、以下の二つの文章が続けて収められています。
子曰、性相近也、習相遠也。
孔子は「(人はみな)生まれ持った性質は似ているが、教育・習慣によって大きな差が生じる」と言った。
子曰、唯上知與下愚不移。
孔子は「優れた智者と劣った愚者は、変わることがない」と言った。
一見して、逆のことが書かれているように見えないでしょうか。前者は、人間は先天的な能力には差がなく、後天的な教育や習慣によっていくらでも変わり得る、という内容。一方後者は、優れた人間である「上知」と愚かな人間である「下愚」は、決まりきったもので変化しようがない、という内容。少なくとも、方向性としては正反対の主張ですね。
仮に、「教育によって治安を改善しよう」と訴えたいのであれば、前者を引用し、「教育によって人々の性質は変えることができると孔子が仰っています」と言えば、説得力が増します。
一方、「悪い奴は悪くて更生のさせようがありませんから、厳罰を与えましょう」と訴えたいなら、後者を引用すればよいわけです。つまり、矛盾する内容を含むということは、それだけ豊かな方向性を持つということでもあり、多くの場面に通用する普遍性を獲得するということでもあります。
しかし、経書解釈の営み、つまり「結局孔子は何を言いたかったのか?」ということを考える上では、上のような矛盾をそのままに放置しておくわけにはいきません。
上の二条の場合であれば、人間を「上・中・下」の三等級に分け、前者はこのうち「中」の人間だけの話をしたもの、後者は「上(聖人)」と「下(大悪人)」は変化しようがないことを言ったもの、というようにして矛盾を解決し、孔子の主張を明らかにしようとします。
さて、それでは、経書に書かれている矛盾する事柄を、現実の政治制度として利用する場合、どのような方法が考えられるでしょうか。または、学術的にその内容を把握しようとしたら、どのような方法があるでしょうか。
少し思考実験をしてみましょう。例えば、「AはBである/AはCである」という矛盾する記述がある場合にどのように解決するか、考えてみます。
まず、簡略化するなら「Aは、BかつCである」としたり、「AはBである/AはC(これはBの誤り)である」とする方法が考えられます。逆に、複雑化するなら、「AはBである/A(このAは実はDを指す)はCである」などという方法が考えられます。前者は区別を減らし統一する方向、後者は区別を増やし分類する方向、とも言えます。
仮にAという制度を現実世界で実現させようとする場合、どの方法が楽でしょうか。当然、前者のように簡略化していく方法が楽です。様々な記述を「まあ似たようなもんでしょ」と合わせていくことにより、その制度を現実世界で実行するときに、大きく手間を省くことができます。
では、経学という学術世界の発展を考えた時、どちらが便利でしょうか。そもそも、学問の根本原理は、「分類」することにあります。雑多な事象を細かな小概念に分けて検討し、その連関や位置づけを探るという学問営為は、自然科学・人文科学・社会科学といったあらゆる分野に通用するものです。一旦細かく分析して最小の単位を認識することによって、その後の議論をスムーズに行うことができます。経学の場合もこれと同じで、複雑化・分類の思考が、経書を学術的に分析していくためにはマッチしています。
鄭玄の学問は、どちらの特徴に近いでしょうか。第六章で紹介した、鄭玄・王粛の学問の方向性の相違を思い出してください。「郊」祭と考えられる経書のたくさんの記述について、細かな区別を設けて新たな概念を作ったのが鄭玄、ちょっとした矛盾には目を瞑ってまとめて解釈するのが王粛、という対比でしたね。
ここから、大雑把に振り分ければ、鄭玄は後者(複雑化)、王粛は前者(簡略化)という傾向にあるといえます。もっとも、王粛も結局は経学者であり、あまり型にはめて理解するのは危険なのですが、大まかな傾向としては、間違った分類ではないでしょう。鄭玄によって徹底的に細かく分類・整理がなされ、礼説の全体像と各説が示されたことによって、初めて経学・礼学を議論する全面的な土台が整えられたと言えます。
以上、鄭玄の学問は「分類」を指向し、これが学術的な色彩を帯びるものであると示しました。とすると、これが「現実」から乖離したロジックの遊戯という印象を受けるかもしれませんが、そういうわけでもありません。ひとたび「分類」が進み、事柄の最小単位が認知されると、実践の場においてもこの道具を使わずして議論することは不可能という状況になります。実際、王粛の議論でも、鄭玄の礼説が逐一引用されながら議論が進んでいました。鄭説が一定の地位を得てからというもの、礼学に関する議論では、学術的文脈・政治的文脈を問わず(そもそも古代中国ではこの両者は峻別できないものですが)、鄭玄の学説は用いずにはいられないものになります。「経学」が、その後に二千年近くの展開に堪えうる学術性を備えるにあたって、鄭玄が大きな役割を果たした、と言えるわけです。
なお、一つ断っておくと、ここまで鄭玄が経書解釈を行う際に、分類と体系性の営みを中心に据えたことを述べてきました。ただ、これは決して、鄭玄が「完璧な」一貫性のもとに体系化を成し遂げたというわけではありませんし、またその分類が「完全に」噛み合うように作られているというわけではありません。鄭玄は長い期間を書けて執筆していますから、その過程で対立する説が提出されていることもありますし、後篇・第四章で述べたような(鄭玄本人さえ既に気が付いていた)矛盾もそこかしこにあります。つまり、鄭玄の意図として体系化の方向性はあったことは言えますが、決してこれが完璧に実現したわけではありません。
ここから先は
¥ 100
ぜひご支援お願いいたします。いただいたサポートは、図書購入費などに使用させていただきます。
