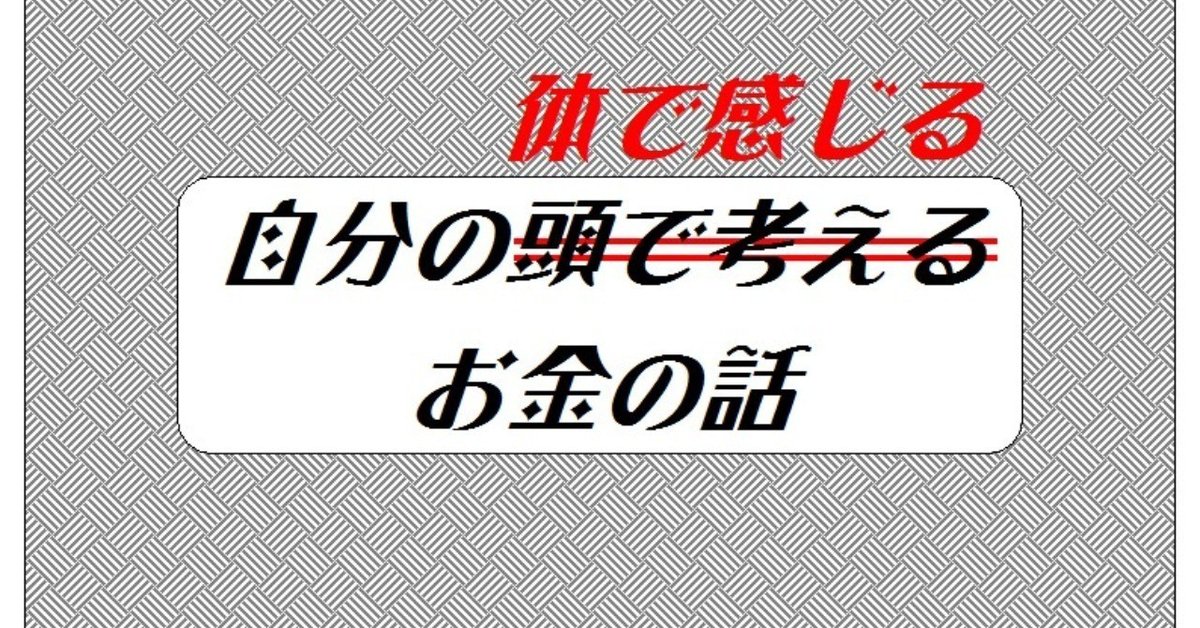
自分の「体で感じる」お金の話
「自分の頭で考えるお金の話」の、「その3」です。
⇒ その1~「インフレーション」を考える
⇒ その2~「自分の頭で」を考える
『その2』でお金は感情情報であるとしましたが、そこのところをもっと突っ込んで考えてみようというわけです。
† お金の「超越性」
湯浅赳男著『文明の血液』。1998年発行。
今でこそお金とお金の歴史に関する本はたくさん出版されるようになりましたが、そうしたブームの先駆けともいえる書籍です。
貨幣の歴史が一つの時代を終わって、新しい局面に入ったことは、どうやら確かなことのようである。ここで言う一つの時代とは貨幣と貴金属が結びつけられていた時代である。これまでの事実の故に、日本語では貨幣をオカネと言い、金銀を意味する「黄白」は貨幣を意味し、フランス語でも銀を意味する言葉が貨幣をも意味するわけである。
言うまでもなく、文明社会において、これまで人間をもっとも夢中にさせてきた財は、権力とともに貨幣ではなかっただろうか。ひとたびその味を覚えたとき、貨幣を求めて人間は奮励努力するばかりでなく、友を裏切ったり、人を殺すことすらあえてした。自らの生命を危険にさらすばかりでなく、死後に地獄に落ちることすらも辞さなかった。この貨幣の魅力はそれ自体の有用性によるものではない。それは、この、有用性を拒否することによって他のあらゆる財と交換される可能性を持つという超越性にあるのであり、そこからくる魔性は今後も無くなるとは考えられない。しかしながら、この貨幣に対する渇望は決して人間の本性といったものではないということを忘れてはならないだろう。むしろそれは貨幣が金銀と結びついて以後のものなのである。
お金には有用性を超越したものがあるという指摘。平たくいうならば、
役に立たないことが役に立つ
お金そのものは何の役にも立ちません。だからこそ、他の財やサービスと交換するにおいては純粋に役に立つ。
財やサービスの有用性を「使用価値」というなら、お金にあるのは「交換価値」で、しかもお金はなによりも流動性が高い。流動性とは、「具体的には役に立たないからこそどんなものとでも交換できる」ということです。
† 感覚と世界
というように「お金には超越性がある」と言ってみても、それはすこぶる抽象的で、感覚的にはなんとなくわからなくはないけれども、雲をつかむような話にしかなりません。
なので、もっと具体的に感じられるように、「感じること」を考えられるように話を進めていきたいと思います。
どんな生物には感覚があります。植物は日の光を感じてその方向へ葉を伸ばそうとするし、それ以前に重力を感じて、重力に逆らって空へ向かって伸びようとする。根は水や栄養分を吸収しようと地中に伸びていきますが、「吸収しようとする」ことは「感じようとする」ことだと言ってもいい。
ぼくたちに人間は動物で、一般的には五感があると言われています。視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚です。
これらの感覚は、いうなれば有用性を感知するためのものです。身体外のモノの有用性に関する情報を収集するための装置が、感覚装置です。その情報の種類が5種類あるということ。
こうした考え方を環世界といったりもします。
環世界(かんせかい、Umwelt)はヤーコプ・フォン・ユクスキュルが提唱した生物学の概念。環境世界とも訳される。
すべての動物はそれぞれに種特有の知覚世界をもって生きており、その主体として行動しているという考え。
すべての動物は環世界の中で主体的に生きている。人間もそうであるはずなのですが、人間だけ(と言い切れるかどうかは微妙ですが)は、環世界とはべつの別の世界を持つ。すなわち、“内面”だとか“精神世界”だとかと呼ばれる世界です。
環世界とは異なった「世界」を持っているということは、そこに知覚があるということです。知覚があるということは感覚がある。
では、内面世界を知覚する感覚とはなにか?
それは、ことば。言語です。
† 言葉は二次の感覚である!
言葉が感覚であるという言は、これまた感覚的になんとなくは理解できるだろうと思います。けれど、やはり抽象的で茫漠としたところはあります。
ここの茫漠としたところを具体的に説得力ある説明をしてくれているのが養老孟司さんです。具体的な本の名前は忘れましたが、以下のような説明。
・言葉は視覚と聴覚の複合感覚である。
・人間は赤ん坊の頃には絶対音感があるが、成長に従ってなくしていく。その理由は言葉を発達させるため。絶対音感があると他者の発声を聞き取るのに邪魔になるから、人間は音感を成長的に退化させていく。
・視覚は言語の習得に伴って、モノに「輪郭に見える」ように発達していく。
・視覚の発達と聴覚の退化がマッチしたところで言語が生まれる。
言語とは、環世界からモノの有用性に関する情報を収集する一次の感覚のうち、視覚と聴覚(と触覚)とが複合して生まれた二次の感覚。
一次の感覚は〈いきいき〉としています。食べ物の美味しそうな匂いを嗅ぐと、身体が反応してお腹が空いていることが自覚される。この自覚は感情を伴います。親しき者の穏やかな声を聞けば安心し、険しい表情を見れば不安になる。人間にとってスキンシップは安心を得るのに欠かせない。
一次の感覚装置で収拾される一次の情報の有用性は、感情となってモニタリングされています。
二次の言語も〈いきいき〉していると言えます。が、その〈いきいき〉は、一次に比べると若干〈いきいき〉度は下がるはず。「はず」というのは、文明が進むと、二次の感覚の方により〈いきいき〉を感じる個体も出てくるようになるからですが、動物としての人間という存在の機序からいえば、一次の方が〈いきいき〉として、より有用性は高いはず。
というのも、一次の情報は、個体の生存に直結する情報だからです。
二次の感覚(言語)によって感知される有用性には、特別の言葉があります。それは「価値」と言います。一次の感覚で「価値」に相当する言葉は見当たらないので「アフォーダンス」という言葉がジェームズ・J・ギブソンんによって造語されました。
アフォーダンス(affordance)とは、環境が動物に対して与える「意味」のことである。アメリカの知覚心理学者ジェームズ・J・ギブソンによる造語であり、生態光学、生態心理学の基底的概念である。「与える、提供する」という意味の英語 afford から造られた。
† パロールとエクリチュール
「パロールとエクリチュール」といえばジャック・デリダですが、そちらへ入っていくと話が込み入るので、我流に簡単に話をしてしまいます。
要するに。
二次の感覚はまず「話し言葉(パロール)」です。
「書き言葉(エクリチュール)」は、パロール習熟後に確立される、言わば二・五次の感覚。
読者の方には、ここで立ち止まって自身の感覚を省みていただきたいのです。感覚と有用性の関係について。
一次の五感で得られる感覚から得られる有用性は、すこぶる具体的・直接的で、〈いきいき〉としています。
二次の言葉から得られる感覚になると、一次の感覚と比較すると、間に一枚「なにか」が挟まっているような感覚――内感覚とでもいうべき感覚。シュタイナーなら自我感覚というか?――あります。この「なにか」こそが価値であり、一次にはその「なにか」がないからこそ「価値」に相当する言葉がないわけです。
それがさらに二・五次のエクリチュールになれば、「なにか」の存在感が一段と大きくなる。この「大きくなる感じ」が「超越性」というものなのですが、、、、いささか抽象的に過ぎますね、、、(汗)
† お金は三次の感覚である!
言葉で追いかけると抽象的になりすぎるので、「自身で(自身を)感じる」ことを是非していただきたい。
話を続けます。
お金とは、この「なにか=価値」そのものです。
お金を価値そのものだと断言してしまうと、多くの人は感情的反撥を覚えると思います。どこかのCMではないけれど、「プライムレスな価値はある」と。
感じて欲しいのは、それが「反撥」だというところです。素直に飲み込めない。素直に飲み込めないのは、それが、もともとの動物としての(アフォーダンスな)人間の感覚を損なってしまうという感覚を感じるからです。
そして、この「反撥の感覚」を感じさせるという事実こそが、実はお金そのものも感覚であることの証明になっている。人間をして矛盾の感覚を生じせしめるだけの存在感がお金にはある。
この矛盾の感覚が、超越性です。
「役に立たないからこそ役に立つ」という矛盾が感覚的に成立してしまうからこそ、超越性が生まれる。
言葉としての超越性ということでいえば、連想するのは創造神でしょう。世界を創造したとされるけれど、だとすれば、その神はいったいだれが創造したのか? 考えれば考えるほど、疑問は遡っていきます。果てしなく遡ることができる無限性が超越性ですが、お金にも同じようなところがあります。なぜお金に価値があるのか? 考えれば考えるほどわからなくなる。
けれど、それは感覚だとしてしまえば腑に落ちます。感覚に根拠や理由はない。感覚は「(生物学的に)そのように生まれた」としかいいようがないものです。
人間の場合、元々持って生まれた(アフォーダンスな)感覚を複合させていってより高次な感覚を生成して能力がある。
お金とは人間の感覚生成能力が生みだした文明的歴史的な感覚
です。
高次の感覚であり、〈生き生き〉度でいえば一次の感覚よりも劣るはずのもの。劣るはずと誰もが感じるから、昔から金もうけのための商業行為は卑しいものだとされきた。このことも歴史的感覚で展望すれば、感覚的に理解ができるはずです。
現代はしかし、本来は劣るはずの感覚を感じ取ることが優位になってしまうような社会環境になっています。多くの人が感じてしまう【生きづらさ】というものの根っこは、端的に言うならば、人間が高次の感覚を生成していくことによって生じた矛盾にあると考えます。
感じるままに。

