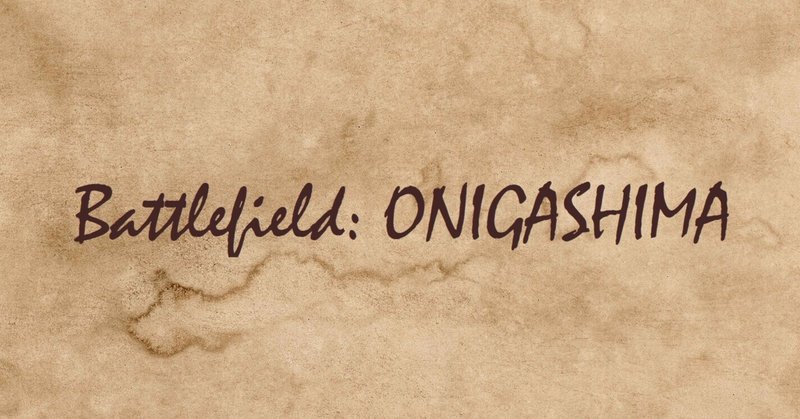
バトルフィールド鬼ヶ島
「今ここにいる中で、いちばん強いのは、どいつだ?」
というのが、俺たち傭兵の溜まり場にずかずか入り込んできたその男の最初のセリフだった。
「仕事を頼みてぇんだ。強い奴じゃなきゃ、ダメなんだ」
「それじゃ、おまえが探してるのは俺だな。話、聞かせろよ」
俺がそう言ってやると、周囲の他の傭兵どもから、面倒くさそうな抗議や反感の声があがったが――表立って挑んでくる奴はいない。俺の強さが知れ渡っているせいかどうかはわからないが、確実に言えることは季節は夏で、時刻は真昼近くで、この辺り一帯の傭兵が集まってきてる古寺のお堂は日こそ入らないものの風通しは皆無に近くて――要するに、無駄な喧嘩をするには暑すぎる、ということだ。肢で触れるほど濃い湿気が毛布みたいに暑苦しく俺たちを包んでいた。喧嘩どころか、動くのもおっくうだ。たいていの奴は灰色近くに変色した古畳に長々とのびている。
仕事は欲しい。喉から肢が出るほど。それはみんな同じだ。
圧倒的な兵力を誇り、この大陸で優勢を占めてる髀刀族は、常に仲間割れを起こしており、長年にわたり傭兵の良いお客だった。ところが数年前、西方にある凶という都で新しい強力な王が即位してからは、戦乱はぱったりと止んでしまった。ヒトの世は完全に平定されたのだ。平和な世の中――それは、俺たちにとっては、食いっぱぐれを意味する。
だから、こちらとしても、あまり仕事は選んでいられない。金になる話ならたいていは乗る。
にもかかわらず、この髀刀族の顧客の奪い合いにならなかったのは、金を持ってるように見えないせいだ。まず第一に、年が若い。たぶん十六、七ってとこだ。
「強ぇのか、おまえ?」
男は頭をめぐらし俺を見た。くしゃっと笑みくずれたその顔は、絵に描いたようなバカ面だ。
俺は尻尾を軽く振って、肯定の返事に代えた。
「そいつはただの狂犬だ。イカれてンのさ」
と誰かが言った。
【続く】
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
