
我々の教科書
企画: 05. 我々の教科書
言葉を使って表現をするわたしたちは、言葉を通して自らの生存を形作ってきました。そんなわたしたちの教科書と言える作品を紹介いたします。
今津 祥
『プレーンソング』保坂和志
『ガラスの街』ポール・オースター
『夢判断』フロイト
深夜の間違い電話をきっかけに私立探偵になる『ガラスの街』の主人公は、次第に依頼の目的から脱線し、NY という都市の迷宮の中で自己を解体させてゆく。フロイトは精神分析治療の実践の中で発見した、無意識が蠢く夢を、『夢判断』で分析した。『プレーンソング』では、主人公がカメラのような役割を担い、奇妙な共同生活をする周囲の人間を観察するようにして、小説が紡がれる。
いずれの本も、わたしたちがつい前提にしてしまう「私という仮定」が、いかに意味のないものであるかを教えてくれる。平成元年生まれの私は、「個性」というものに付き纏われてきた。時代もまたそれを意識させる時代だった。「特別な自分でなければならない」「個性を持たなければならない」そんな強迫観念が、時代に行き渡っていたし、今も少なからずそうだろう。しかしむしろ「個性」を意識すればするほど、「個性」はなくなっていくという逆説があるのではないか。「個性」なんか意識しないくらい好きにやっていたら勝手に出てくるのが「個性」なのだから。
『ガラスの街』は、そんな「私」の脱構築を、『夢判断』は「私」という存在の複雑さを、『プレーンソング』は「私」の外にある世界の豊かさを、それぞれ私に教えてくれた。
Archipelago ~群島語~
隙間 (今津祥)
墓地に囲まれた町 (今津祥)
たまり なおこ
特定の書籍をあげることができなくてすみません。自分の外側にあるもの、自分以外の外界がすべて、教科書です。
五感をつうじて自分の体(=有機体)が受け取るもの、それが教科書です。
木々をゆらす夏の蒸した熱風、信号待ちするときに見えた街路樹、交差点に止まる車のナンバープレート、夕立のあとの水たまり、
ひとつひとつが役割をもって社会を形成していて、それはまるで生き物のようで、外界じたいが、有機体。
自分は有機体であり、外界も有機体。
自分=有機体=外界。
教科書=外界=自分。
自分が自分の教科書であるために、何をすればいいのか、ふんわりと、考える日々です。
近藤真理子
『枕草子』清少納言 /『むかし・あけぼの』田辺聖子
『地図のない道』須賀敦子
「春望」杜甫
『枕草子』は、きらきらしている。清少納言は宮仕えでのあれこれを楽しんで、いとおしんで、野暮ったい人たちや自分のことすら面白おかしくして、中宮定子と定子その人がもたらすかがやきと柔らかさを描き出す。彼女はこれを宮仕えの日々の中で日記のように書いただけではなかった。自身が敬愛したものすべてが、影にのまれ失われた後に、追想しながら書いたりもしたらしい。意識して読むと、当時徐々に迫っていた沈淪と崩壊の兆しがちゃんと書き込まれている。
この不穏さは、読者の同情をひくための演出として利用されているわけではない。彼女が受け取った美しさは、頑ななほど彼女が受け取ったように書かれる。そのことに、わたしはいつも胸を打たれる。有名な「春は、曙…」や「にくきもの」のような章段も、おそらく胸の中にふっと去来したもので、彼女だけの真理だろう。でも『枕草子』のページを閉じて目を上げると、世界はもう「そう」なっているのだ。それは、彼女自身が、自分の感覚や感じ方によって捉えられた世界を、楽しんでいとおしんでいたからではないか。
美しさを見出す目を持って世界を見ること。自分が見つけた美しさの強度を信じ、余計な装飾をせずプレーンに描く/ 書くこと。古典の教科書で出会ったときから、ずっとわたしは清少納言になりたがっている。
『枕草子』は、田辺聖子の『むかし・あけぼの』から読むと入りやすい。
ほかにも、冷静で厳しいがやわらかい視線を持つ須賀敦子。杜甫の「春望」は、起承転結という構成のお手本として、よく声に出して唱えている。
Archipelago ~群島語~
雲居島 (近藤真理子)
桃食まぬ子ら (近藤真理子)
高橋利明
「姉ちゃんの詩集」サマー
『るきさん』高野文子
『小さいことばをうたう場所』糸井重里
高校生のころから、10年間くらい、眠る前にひとりで本を音読していた。ニートだったころは、岡本太郎を音読して、自分を鼓舞していたし、ニートの自分がいったい何を鼓舞していたとのだろう、と、いま思うと謎だけど、岡本太郎は良い。一連の本(「強く生きる言葉」等)は、botなき時代のbotとして、とても役に自分を鼓舞するのに役立つっていた。(だから、なんの役に立ってたんだって)文章の本だけではなく、マンガも音読していた。主には、高野文子。「るきさん」「棒が一本」「黄色い本」、高野のマンガは、時代を追うたびにむずかしくなってゆく。何回読んでもわからない。読みなおせば読みなおすほど、読めてなかった事が実感できる。そんなマンガを読んでいる自分をエライと思っていた。そんな自分を高等遊民っぽくてカワイイなー、と思ってくれる人いないかなー。養ってくれる御曹司とか。居ないですかね?居ないか。さておき、糸井重里の<気付き>を綴った短文集(「小さいことばを歌う場所」「思い出したら、思い出になった。」)も、よく音読していた。今となっちゃー、糸井重里が好きだって公言するのは恥ずかしい事だが(誰に対して恥ずかしいか知らねーが)、当時はイトイがオレのアイドルだったのだ。震災のあとは、すがるようにイトイのTwitterを見ていたし、吉本隆明の音声アーカイブにも大変お世話になった。最後に、サマー著「姉ちゃんの詩集」。これはサイコー。「2ちゃんねる」発の書籍の中でも。これだけはガチ。死んだら棺桶に入れてくれ、ってレベルで好きだ。他にも、大好きなものは沢山ある。例えば彼女のクリトリスとかね。でも、彼女のクリトリスをここで紹介することは出来ない。何故かといえば、このスペースは本を紹介するスペースだからである。そう、クリトリスは本じゃないのだ。
坂野晶
カーソン・マッカラーズ『結婚式のメンバー』(村上春樹訳)
ディーノ・ブッツァーティ『タタール人の砂漠』(脇功訳)
ユクスキュル/クリサート『生物から見た世界』(日高敏隆、羽田節子訳)
「たびたび読み返す本」という括りで3冊を選んだ。
▷カーソン・マッカラーズ『結婚式のメンバー』(村上春樹訳)
アメリカ南部に住む12歳の少女フランキーが、夏の間じゅう、歳の離れた兄と兄嫁の結婚式に恋い焦がれるという話。麗しい兄と兄嫁と一緒に、夢のような結婚式のメンバーになれれば、フランキーは生まれ変われると信じている。マッカラーズは一貫して孤独について考えた作家だったらしい。こういう小説が読みたかったんだと読み返すたびに思う。
▷ディーノ・ブッツァーティ『タタール人の砂漠』(脇功訳)
辺境の砦に配属され、タタール人の襲撃に備える任務を任された軍人ドローゴ。だが実際に砦に勤めてみると、タタール人は本当に攻めてくるのか、そもそも存在するのかもあやしい。いやそれでもいつか戦争が起きて、この時間が報われる日がくるはずだ、いやでも……という、「人生」を描いた作品。描写は幻想的なのに、想起される不安はこの上ないリアリズムに溢れている、ブッツァーティの小説はおもしろい。
▷ユクスキュル/クリサート『生物から見た世界』(日高敏隆、羽田節子訳)
初めて読んだときに瑞々しい文章に魅了された。世界観がこつこつと組み上げ直される感覚。
「環世界は動物そのものと同様に多様であり、じつに豊かでじつに美しい新天地を自然の好きな人々に提供してくれるので、たとえそれがわれわれの肉眼ではなくわれわれの心の目を開いてくれるだけだとしても、その中を散策することは、おおいに報われることなのである」(7項)
秋山拓
氷室冴子 「海がきこえる」(小説-文庫版)
高野文子 「るきさん」(漫画-文庫版)
今まで一番読み返した本と聞かれてこれだと言えるものはいくつかありますが、今もまだ手元に置いて読み返すものはこの二冊くらいだと思います。
・氷室冴子 「海がきこえる」(小説- 文庫版)
・高野文子 「るきさん」(漫画- 文庫版)
「海がきこえる」
高知と東京、高校時代と大学時代を行き来する本作はアニメやドラマにもなり、私自身ドラマは未履修ですが、連載版、単行本版、文庫版、そしてアニメ版との間で生まれる差異は物語というものが作り手や時代、状況で変わることを私に教えてくれました。と、語りつつ本当に語りたいのはそんなことではなくて、私がこの本を今も読むのはこの物語に通底する世界の明るさがあるからです。それは出版時期、舞台共にバブル期であるからかも知れないし、主人公の若さやそれゆえの葛藤、先の見えなさという現実が風景の持つ共感作用で包まれているからかも知れません。知らない時代の話なのに知っているような、こんな景色の中に自分の日常を置けたらと思わせてくれるような、そんな魅力がこの物語にはあります。
「るきさん」
今では当たり前になったような半径数メートルの範囲で展開される日常の話ですがここまで軽やかで、フィクションなのにどこか近くに彼女がいるように感じさせるリアリティは今においても読んだ記憶がありません。例外的にエッセイ漫画というジャンルがありますが、「るきさん」はフィクションだからこそ素晴らしいと感じます。実際はどこにもいないからこそ、るきさんは全ての読者にとってどこかにいるかもしれないリアリティがあるのだと思います。
並べてみるとどちらも私が体験していないバブル期終盤〜崩壊後の作品です。だから好きなんじゃないの?と言われるとそうかも知れませんが、だとしても私は自身にまつわる物にささやかでもこの二作に通じるような明るさや軽やかさ、それを伴うリアリティを与えたいと思い何度もページをめくってしまうのです。
Archipelago ~群島語~
分かれる水の岸辺より (秋山拓)
東京のアパート(最寄駅:牛込柳町) (秋山拓)
小映
John Berger “Way of Seeing”
山本浩貴(いぬのせなか座) 『言語表現を酷使する(ための)レイアウト 第0部 生にとって言語表現とはなにか』
Jon Krakauer “Into the Wild”
John Berger “Way of Seeing”
どんなに未熟であるにせよ、心情を抱えまなざしを放つのであれば、見えるものは見える。それら見えるものの中で、何が真であるわけでも、どれが確実なわけでもないだろう。ただ人は、目に映るものをどう受け入れるのか。目を通し心へ入り込んでくるものに、どう応えるのか。わたしはわたしなりのやり方で、存分にこの世界を見、その中にあるわたしを見る。そうした見ることの集積がわたしの世界を形作り、わたしの一部となってゆく。
大学初年度4月の必修レポート課題で本書の邦訳版が示され、提出期限は翌5月だったけれど2 年後に提出した。原書にあたり、思春期末期のあれこれをこなしつつ仕上げた提出稿は制限字数の数十倍となり、受け取ってはもらえたが教授室へ呼び出された。淹れてくれたお茶と提出物とが置かれた応接テーブルを挟んで向き合った先生は、十数分にもわたり終始無言であった。謎時間に耐えられず「読んでどうでしたか」など拙い質問を幾らか試みるも無言。無言だけれど時折ニヤける。意味はわからない。今でもわかっていない。半年ほどたって彼に師事する院生から、ゼミの呑み会で「小映君は才能がある」って褒めてたよ、と聞かされる。なんの才能だかわからない。が、一歩前へ進めた実感が湧く。卒業後風の噂で、先生が自死したと耳にする。
山本浩貴( いぬのせなか座) 『言語表現を酷使する( ための) レイアウト 第0部 生にとって言語表現とはなにか』
生きることと書くことを恐ろしく生真面目に、そして先鋭的に捉え直す試み。
「共通の友人の死」が彼ら“いぬのせなか座”を結びつけ、本書を育んだ思考/運動へと駆り立てる様に幾度か言及されるのも印象的。けれど本当は「友人の死」に仮託された別の何かがそこには潜んでいて、その気配に薄々気づいている。死は誰のものか、どう扱い得るかというのは切りのない話だけれど、そういう風に第1部以降が展開したらいい。
Jon Krakauer “Into the Wild”
アラスカの森奥で息絶える青年の道行き。読みだしたばかりだけれど、Sean Penn監督作の映画版が好きなので結末は知っている。生きてるうちに読み終えたい。
カルヴァンの紅い灯 (小映)
輝けるプリズンホテルと再監獄化する世界 (小映)
小瀧忍
深澤直人 『ふつう』
岸本佐知子 『死ぬまでに行きたい海』
嶋稟太郎 『羽と風鈴』
ひょんなことから手に入れる本がある。その本や著者に対する知識が無くても、
棚に並ぶその本のたたずまいが僕の右手を引き寄せる。なんらかの情報を持って手に入れた本より、そんなきっかけで手に入れた本の方が自分にとって大切な本になっている気がする。
『ふつう』は富山のD&DEPARTMENTに立ち寄ったときに出会った。薄い水色の布張り表紙は裏面まで続く両面貼り、12x16cmの文庫本よりやや大きめのサイズはその厚さもあり小振りな辞書を持つような感触。
その時僕の右手がこの本に手を伸ばしたのは、コロナ禍の先の見えない、目に見えない、世の中がそんなものに不安を抱えた時だからその「タイトル」に惹かれたのか、若しくはその手触り、箔押しのタイトル、本文の心地よい天地余白という「本の手触り」だったからなのか今はうまく思い出せないが、それから3年が経ち、僕が「ふつう」からちょっと離れてしまった時に「ふつう」へゆっくりと戻してくれる「とくべつ」な本である。
『死ぬまでに行きたい海』は、雑誌『MONKEY』で連載されている出不精な翻訳家がどこかへ出かけて何かを書く、「非日常的な日常」をまとめたもの。著者の他のエッセイに見られるクスッとする点は抑えられつつ、記憶と描写を深めた文章に感情は揺さぶられる。そしてここにもなんでもない「ふつう」を感じる。
自分にとって「なんでもない」ものを深めていったらどんなことばが生まれてくるだろうか。基礎科と演習科の1年間を経て『三月の水』という小冊子を勢いで作った時、上記2冊が傍らにあった。土地の話と写真、文字の大きさ、本の手触り。完成度は別として、この二冊によって目を向ける方向は見えてきた気がする。
そして基礎科で出会った「短歌」という形式に引き込まれ、作歌を試みるようになった。これも歌人の知識ゼロでふと本屋で手に取った『羽と風鈴』は、いつか辿り着きたい境地である。
Archipelago ~群島語~
見知らぬ土地からの手紙 (小瀧忍)
泣けるキウイ (小瀧忍)
草村多摩
ルシア・ベルリン 『掃除婦のための手引き書』
リン・ディン 『アメリカ死にかけ物語』
中島らも 『今夜、すべてのバーで』
ルシア・ベルリン 『掃除婦のための手引き書』
「それからは何週間も処女懐胎を冗談の種にした。『ちょっとコーヒーをいれてくれない? 起き上がれなくって。処女懐胎だもんだから』」
どこにでもいるような人々の生の一幕が、特別な物語になって現れてくる。テキサスやニューメキシコが大切な場所になり、愛すべきアル中のママや祖父に会いに行きたくなる。ほんの数ページに、途方もない時間も空間も広がっている。具体的な手触り、ユーモア、驚き、ことばのかっこよさ。からっとしながら切なく、弱くて強い人々。書くべき人や物語がすぐそこにあることを、そこからどこへでもいけることを気づかせてくれた。
リン・ディン 『アメリカ死にかけ物語』
「はじまりも終わりもない、誰からも見放された道でも、人間味あふれる物語がひっきりなしに生まれる」
アメリカの冴えない町の、酔っ払いたちの声。バーや路上の、どこへも行けないような人たちの人生からこぼれる魅力が、町々を移ろいゆくアメリカ育ちベトナム人の視点で淡々と描かれる。問題とたくさんの思い出を抱え、しぶとく生きる人びとを、愛を込めて。そこにある物語が、わたしにはすごく普遍的なものに見える。
中島らも 『今夜、すべてのバーで』
「ああ。アル中にはマンドリンが一番なんだ。手がふるえて、いいトレモロが弾けるからな」
アル中で入院する主人公は、アル中に関する本を読んで勉強している。本で得た知識を検証するように、自分の身に起きる症状を冷静に分析し、屁理屈を並べ、飲みながらユーモラスに展開される物語。救いようのないアル中的思考で交わされる、主治医や他の患者との会話。酔っ払いたちへの愛と、その一人として自分を観察する主人公の可笑しさ。乾杯。
ぱっと抜き出した三冊は、どれも酒飲みの話だった! 都合が悪いことだらけの世界に愛をもって対峙する眼差しで切り取られた美しい世界。それと、時に、いやほとんど? 意味のない可笑しさが溢れる文章。むしろこちらが作られたお話なんじゃないかと思ってしまうような現実に朦朧としている中で、本当の世界に触れた気がする文章。飲み過ぎて大切なものを忘れてばかりいるけれど、愛と笑いを、わたしも書いていきたい。
樋口貴太
滝口悠生『愛と人生』
保坂和志『未明の闘争』
J・ケルアック 青山南訳『オン・ザ・ロード』
滝口悠生『愛と人生』
「つまりはその満ち引きを私たちは結局自分の人生であるかのように見はじめ、聴きはじめてしまい、となるとそのひとつの波の打ち寄せが人生であるようにも思えるのだったし、引いていく波こそが人生であるようにも思えたし、その無限の繰り返しが人生そのものであるようにも思えたし、同じ繰り返しのようでいて二度と同じ波はないのだというそれが人生であるようにも思え、しかし人生は人生であって波ではないのだということに気づくのだった」
保坂和志『未明の闘争』
「富士山は頂上が白く、稜線が長くきれいに伸びている。裾野に並んでいる家がミニチュアのように小さくて現実感がない。しかしミニチュアのような家のすべてに人が暮らしている。その中には空き家もある。稜線は意外にも歪で右が出っぱっている。富士山のまわりには何もない。向こうは空だけしかない。雲は今は少しある。稜線はどこまで伸びてくるのか。自分が今いるここも稜線の延長に違いない。サンシャイン60や住友ビルや東京タワーから見える富士山がこの富士山と同じなのは形だけだ。富士山のこの大きさを知らなくても東京で富士山が見えて、「富士山だ!」と感動をこめて声を出すのは、私もそうだがどういうわけだ」
J・ケルアック 青山南訳『オン・ザ・ロード』
「目を覚ますと、太陽が真っ赤。まさに異常な人生の瞬間で、あんなにも奇妙な時間は空前絶後で、自分がだれなのかわからなかった――家から遠く離れて、旅にさまよい疲れて、見たこともない安ホテルの部屋で、外の蒸気のシュッシュッという音、ホテルの古木のキュッキュッという音、階上の足音、ありとあらゆる寂しい音を聞きながら割れ目の走った高い天井をながめている、しかし自分がだれなのかわからない奇妙な十五秒間。恐くはなかったが、別なだれかに、見知らぬ他人になっていた。人生がなにかに憑かれたようなものに、幽霊の人生になっていた。アメリカを半分ほど進んできて、ぼくの青春の東部とぼくの未来の西部の分かれ目にいたから、あんなことが、あんなに奇妙な真っ赤な午後がいきなり出現したのか」
斌
『数学を志す人に』岡潔
『音楽』岡野大嗣
『エクソフォニー-母語の外へ出る旅-』多和田葉子
『数学を志す人に』岡潔著
自分は指針にしている本や参考にしているもの、このように書きたい、と言った本はないので、自分のバイブルとしている本を紹介します。
流れる小川のようなさらさらとした文章で、頭に一切のストレス(負荷)を感じないのは今までで岡潔さんのご著書だけです。
自分にとって必要不可欠な一冊です。
『音楽』岡野大嗣著
短歌のバイブル。自分にとって岡野さんの短歌はなくてはならない、ずっと聴いていたい音楽のような、常に持ち歩きたい歌集です。多くの人が目にしたことのあるような光景や、身近な出来事を、多くの人が、自分も含む、気づかなかった視点から詠まれている。情景が浮かんでくるような短歌ですが、読むたび情景が変わる。自分も創作では、自由に読み取ってもらいたいと思っており、様々に受け取れる作品を書きたいと思っています。
お守りのような一冊です。
『エクソフォニー-母語の外へ出る旅-』多和田葉子著
多和田葉子さんのエッセイ本も自分にとってのバイブルです。
ことばの学校基礎科の第一回目の佐々木敦先生の講義でとりあげられたもの。
自分は日本語が母語だし、と、どうしても外国語は第二の言語、いわゆる「勉強」となり、いつまでも身につけることができない、と悩んでいた自分にとって、「二つの言語を持つ」という、新たな考え方、ものの見方を与えてくれ、自分の世界が広がりました。この本を教えてくださった佐々木先生に感謝するとともに、なくてはならない一冊です。
林恭平
『慣れろ、おちょくれ、踏み外せ 性と身体をめぐるクィアな対話』森山至貴、能町みね子
「結婚の奴」能町みね子
「大都会の愛し方」パク・サンヨン
「慣れろ、おちょくれ、踏み外せ 性と身体をめぐるクィアな対話」は、社会学者の森山さんと文筆家の能町さんが最新のクィアトピックや体験談などについて、軽妙に対話する本だ。性的少数者の歴史における、二つの側面が浮かび上がる。
一つはL、G、B、Tなどと特性に名前をつけて結束し、声を上げる運動のこと。もう一つは、そのラベルからもこぼれ落ちる一人一人の個性にプライドを持ち、体制には屈しないとする反骨精神のようなスタンスだ。
昨今のLGBTブームとも言える急速な機運に乗れない気持ちに言及したかと思えば、先達が勝ち取ってきたラベルの上に成り立つ今があると、敬意も忘れない。わかりやすい答えは明示されず、絶えず議論は行ったり来たりを繰り返す。
体力テストの反復横跳びを思い出した。運動音痴の私は息も絶え絶えになりながら、それでもたどたどしいリズムでの往復運動に、奇妙な心地よさを感じるのだ。
そんな往復にこそ、クィアという言葉の本質はあるのかもしれないと読後に思った。対談は少子化やクローン人間の是非にまで発展し、刺激的だ。枠に収まらない他者の個性を想像する欲求に満ち、足を踏んでくる権力に中指を立てる準備も万端。本を読んで終わり、ではない。この先も絶えず迷い続け、考え続け、文章を書き続ける自分でいたいと、そう思わせてくれる本だ。
能町さんのクィアな実践を綴った「結婚の奴」も面白い。彼女が恋愛対象ではないゲイのおじさんと同居を始めて、家族のようなものになっていく日々をまとめたエッセイだ。丁寧な自己分析や経験の言語化で、結婚という過剰に意味づけされた制度が解体されていく。世間をおちょくるような勇敢さが、かっこいい。
丁寧な言語化と優しいユーモアが、「大都会の愛し方」にも共通する。韓国のゲイが主人公のこの作品を読み、こんな小説が書きたいというあこがれと、先に書かれてしまったというおこがましい嫉妬が混じり合った。
開け放つ準備を (林恭平)
二〇二〇年九月八日@函館 (林恭平)
磦田空
川上未映子『水瓶』
初めてこの作品のことを知ったのは、マームとジプシーという演劇団体が2018年に上演した『みえるわ』という作品で扱われているのを見てのことでした。
公演には友達に誘ってもらって行きました。当時は詩をまったく読まなかったのですが、声を耳で、字幕を目で追って、帰ってから本を買って読み進めていると、このようなことばがあるのか、こんなにことばは知らないほうへと開けているものだったのかと目が開くような気持ちになりました。それから今わたしが持つことばへのささやかな関心が始まっていったように思います。
教科書というには感傷的すぎるかもしれませんが、ほとんど最初にことばに驚いたときの気持ちを何度でも思い出せるようにしていたいと思っています。



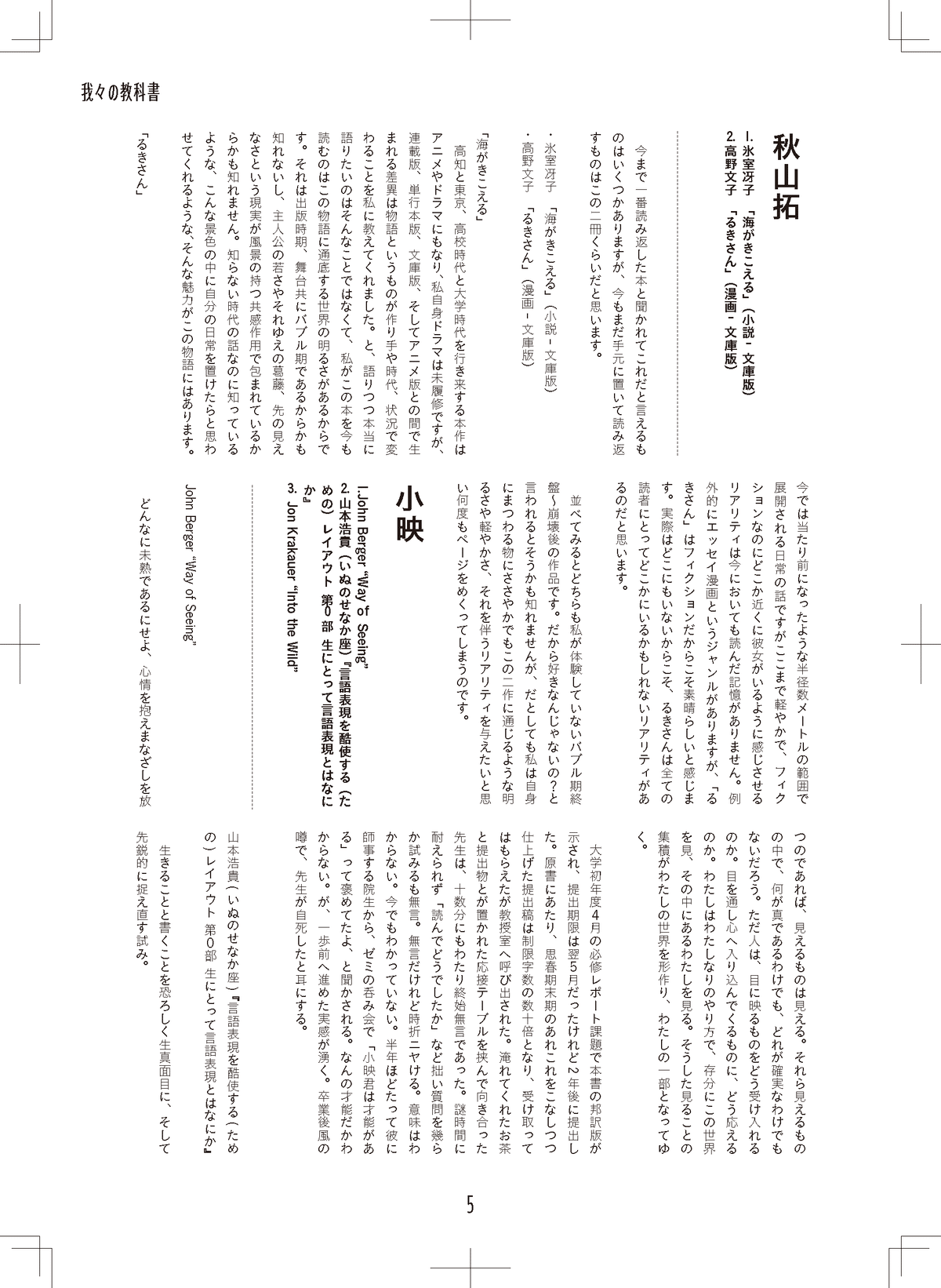
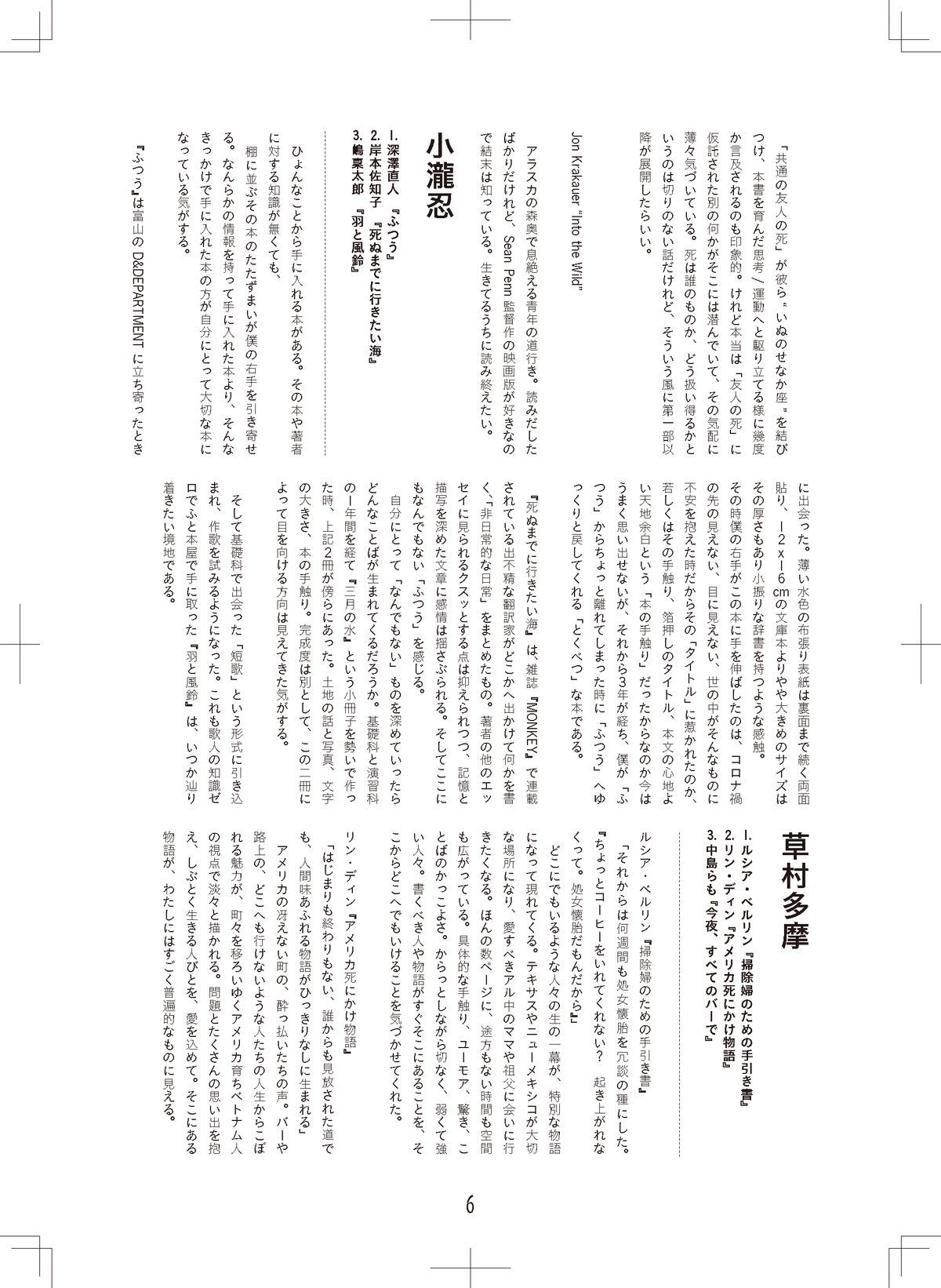


修了展示 『Archipelago ~群島語~』 について
佐々木敦が主任講師を務める、ことばと出会い直すための講座:言語表現コース「ことばの学校」の第二期の修了展が開催された。展示されるものは、ことば。第二期修了生の有志が主催し、講座内で執筆された修了作品だけでなく、「Archipelago ~群島語~」というコンセプトで三種類の企画をもうけ、本展のための新作も展示された。2023 年8 月10 日と11 日に東京都三鷹のSCOOL で開催。
『Archipelago ~群島語~』展示作品はこちらからご覧ください。
「群島語」について
言葉の共同性をテーマとし、言語表現の新しい在り方を試みる文芸誌『群島語』
2023年11月に創刊号を発表。
今後の発売に関しては、X(Twitter)や Instagram で更新していくので、よければ是非フォローお願いいたします!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
