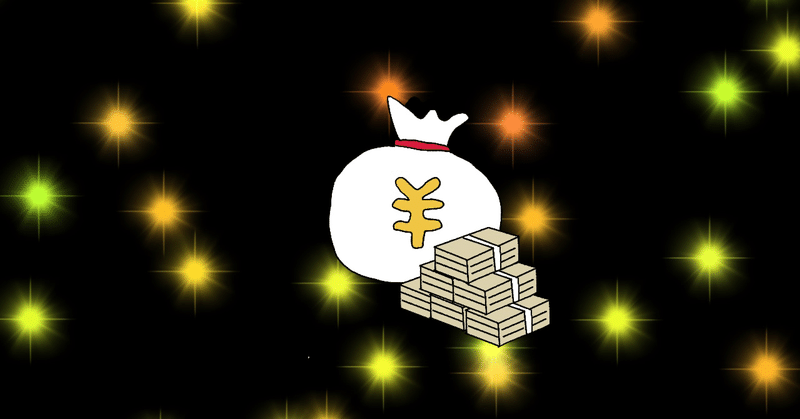
どんな場合に出資法の違反になるの?【解説】
皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、どんな場合に出資法違反になるの?というお話をしたいと思います。
弁護士に相談したい方はこちらから
出資法ってどんな法律?
この出資法ですが、「お金を集めたり、資金調達をする場合に何となく出資法ってかかわってくるのではないですか?」というご相談を受ける事があります。でも実際には「出資法ってよく分からない」「出資に関する法律なので、何かしら資金調達をする時に全部ダメになるのかな?」というイメージがあるかと思いますが、この出資法自体は具体的に何がOKで、何がダメなのかというところをご説明していきたいと思います。
元本保証はNG!
出資法の第1条に出資金の受け入れ制限というものがあります。例えば、「元本保証」や「必ず儲かる」といったうたい文句で出資を集めると、これは出資法違反になります。なので、「元本保証ですよ」という表現は当然ダメです。
次に第2条に預り金の禁止というものがあります。これも同じ様な形ですが、不特定多数の者から元本の返還が約束されている状況で金銭を預かりますといったものです。とりあえず金銭を受け入れて、「預けて下さい、必ず返しますから」「元本は保証しますから」と言ってお金を預かる事はダメです。
高金利の禁止
この他にも第3条、第4条とありますが、第5条では高金利の利息について制限がされています。年109.5%を超える利息の契約、貸金業者であれば年20%を超える利息の契約をすると、これは出資法の違反になります。利息制限法というものがありますが、これはその超えた利息分は無効になるというものなので、いわゆるお金の問題、民事上の問題となります。しかし、この109.5%を超える場合は刑事事件になります。なので、相手が同意していようが同意してなかろうが、年109.5%を超える高金利の契約をしてしまうと、当然無効となり、処罰される可能性もあります。
出資法は刑事罰もある
罰則としては刑事罰があります。先ほどご説明した、元本保証をしてお金を出資してもらう、預かるといったケースであれば3年以下の懲役、300万円以下の罰金となりますし、年109.5%を超える高金利の契約をしたケースであれば、5年以下の懲役、1000万円以下の罰金となり、結構重い罰則となります。
出資法はこういった法律となっているので、お金を集める方法については注意をし、「元本保証は当然言わない」「高金利な契約はしない」といった事が必要かと思います。
弁護士に相談したい方はこちらから
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
