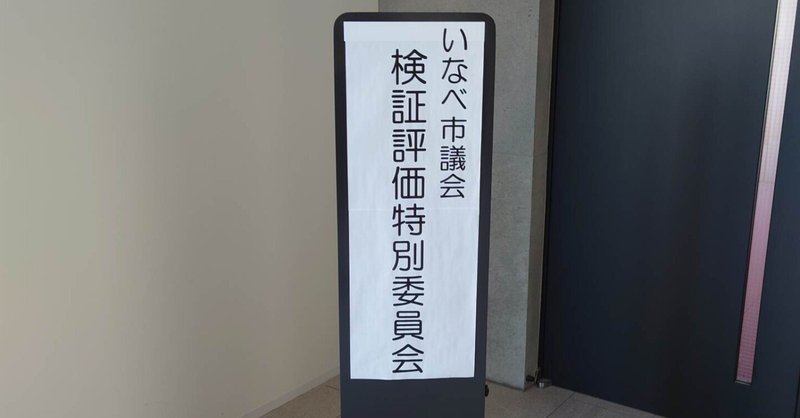
2日間の議員研修会で、成熟度評価モデル計16項目についてグループワークを実施――三重県いなべ市議会
三重県いなべ市議会は2022年12月、(公財)日本生産性本部が作成した地方議会成熟度評価モデルを実装化することを決め、議会検証特別委員会を設置した。すぐに議会プロフィールの一部作成に取り組み、2023年3月28日~29日には、成熟度評価モデル5つの視点・計16項目についてグループワークを行った。同市議会では案段階で市民の意見を聴き、今年10月までに評価モデルを完成させる予定だ。
■議会基本条例に基づき、施策評価及び事務事業評価を実施



三重県最北端に位置するいなべ市は2003年12月1日、員弁郡北勢町・員弁町・大安町・藤原町の4町合併で誕生した(人口約4万3000人)。市議会(議員定数18人、現員17人)では2017年3月24日の本会議で議会基本条例を制定(同年4月1日施行)。条例に基づき、決算審査における施策評価及び事務事業評価を行うなど積極的に議会改革を進めてきた。
いなべ市議会では議会改革のバージョンアップに向け、地方議会成熟度評価モデル導入の機運が高まり、2022年10月25日に全議員を対象とする議員研修会を開催。江藤俊昭・大正大学教授の二つの講演「地方議会改革の到達点と課題~『住民自治の根幹』としての議会の作動」「議会からの政策サイクルの展開と議会評価~『住民自治の根幹』としての議会の作動の豊富化」、グループごとに講演を聞いての感想共有・意見交換、日本生産性本部による地方議会成熟度評価モデルの説明などが行われた。
■市制施行20年の節目に、「より一層充実した議決機関」に

この研修会が、評価モデル導入のいわばキックオフ。同年12月13日には今期の第1回議会検証評価特別委員会(清水隆弘委員長、議長を除く全議員16人で構成)を開催し、検討のための体制やルールなどについて議論した。
2023年は合併し、いなべ市の市制施行20年の節目の年。小川幹則議長は「この節目に、いなべ市議会を、より一層充実した議決機関としていく」とのメッセージを寄せた。
特別委員会では、同モデルの実装化で先行している長野県飯田市議会を参考に、1グループ5~6人のワーキンググループを三つ設けて議論する体制を決定。そのリーダー・サブリーダーはファシリテーションのスキル向上などをねらいとして期数の若い議員を選出した。
また、ルールについては特に要領を定めず、「全て『合意形成』により運営する。不備が生じた場合も『合意形成』により解決を図りたい」と清水委員長が述べた。
■「リーダー・サブリーダーの役割・期待」を確認


2023年1月18日には、第2回議会検証評価特別委員会を開催。議会プロフィールの作成や成熟度評価を実施する目的、手法、流れ、留意事項などを確認した。また、日本生産性本部の田中優磨研究員が、合意形成のベースとなる「対話」のあり方について解説。最後に、いなべ市議会の現状についてグループごとに意見交換を行った。
特別委員会終了後には、第1回リーダー会議を開催(特別委員会の正副委員長と3グループのリーダー・サブリーダーの計8人で構成)。「リーダー・サブリーダーの役割・期待」として次の項目を確認した。
①討議の目的、着地点を理解する
②発言しやすい雰囲気をつくる
③発言者の意図と発言の趣旨の理解に努める
④時間調整を行う(独壇場にならないように)
⑤合意形成を図る
また、各種会議の段取りや情報共有のあり方などを定めた「地方議会の成熟度評価を円滑に運営していくための申し合わせ事項」を確認した。
■ビジョンは、「市民に期待・信頼される議会」
その後、1月26日に議会プロフィールの「議会に期待される役割」と「議会が実現すべき理想の姿」についてグループワーク。2月2日と17日のリーダー会議で、グループワークで話し合われたことをまとめ、3月28日に開催した議会検証評価特別委員会で報告、全議員の了承を得た。
現段階の「議会に期待される役割」と「議会が実現すべき理想的な姿」は次の通り。
【議会に期待される役割(ミッション)】
(1)執行機関を監視・評価
(2)市民意見・要求・要望の把握
(3)政策提案・提言
(4)市民への説明責任
【議会が実現すべき理想的な姿(ビジョン)】
議会に期待される役割(ミッション)を踏まえ、いなべ市議会が実現すべき理想的な姿(ビジョン)は以下のとおりとし、今期議会議員任期満了となる令和7年には、このビジョンに近づき、議会基本条例制定10年を迎える令和9年にはビジョン到達を目標に取り組む。
いなべ市議会が実現すべき理想的な姿(ビジョン)は、「市民に期待・信頼される議会」とし、以下の3項目を明記する。
(1)市民の声を反映する議会
市民の意見を聴く機会を増やすことにより、施策及び事業の監視、評価の視点とするなど議会活動に反映。
(2)合意形成ができる議会
議員間討議を積極的に行い、合意形成を図り、議会の意思を示す場面を増やす。
(3)政策提案及び提言を実現できる議会
社会の変容に即した提案及び提言を図り、市政に反映。
■市民意見を踏まえ、10月までに評価モデルの完成を




3月28日~29日の議員研修会では、成熟度評価計16項目について5つの視点ごとに個人検討、グループワークを重ねた。研修時間は両日で計5時間にも及んだ。
グループワークでは模造紙に評価結果とその理由を書くグループもあれば、ワークシートの用紙に各議員の意見をびっしり記すグループも。すべての議員が意見を述べ、制限時間が過ぎても白熱した対話が続いた。複数の議員が「この議員はこのように考えていたんだ、と思った」と感想を話し、グループワークによって多くの気づきを得たようだ。
29日のグループワーク終了後には、各グループで合意できた事項や感想などを情報共有。「議員間討議のとらえ方に温度差があった」「ざっくばらんな話し合いができて有意義だった」「みんなで情報を共有して、少し先が見えてきた」など。最後に清水委員長が「8月下旬を目途に市民のみなさんに(評価結果の案を)示し、10月までに評価モデルを完成させたい」と今後の予定を話した。
*
いなべ市議会は、評価モデルの実装化で先行する飯田市議会や福島県会津若松市議会に比べ、1年弱という短期間での完成をめざしている。それだけ各議員や議会事務局職員の負担も大きいが、対話の素地があり、バージョンアップに向けた熱量を感じさせる議会だけにその成果が楽しみだ。
(文・写真/上席研究員・千葉茂明)
〇日本生産性本部・地方議会改革プロジェクト
https://www.jpc-net.jp/consulting/mc/pi/local-government/parliament.html
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
