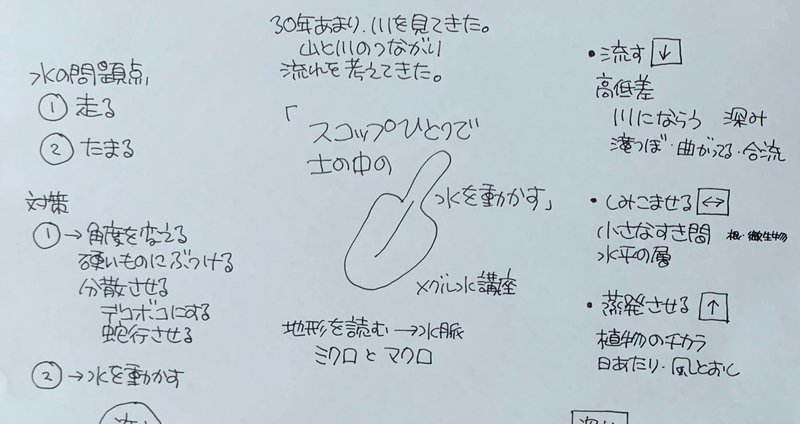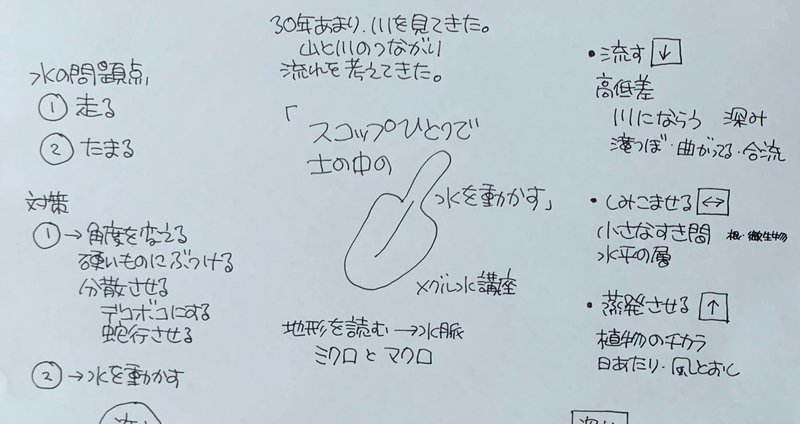溝で浸透しやすい形状にする
雨どいがあるものの、水が停滞しやすい雨落ち付近で水が浸みこみやすくなるように作業した。
軒下にコンクリートが敷かれていて、コンクリートの脇に水が停滞しやすい。斜面変換線となるコンクリートと土の間に溝を掘って、しみ込みやすくする。
コンクリートにあたった水が、とどまりやすい地形となっている。水が地中へともぐっていきやすい状態にするのが作業の目標。
① コンクリート脇の斜面変換線となる部分に溝を掘る② 溝が埋まらないように炭と枝を入れる。枝はゆらゆらしない程度に密着させ、菌