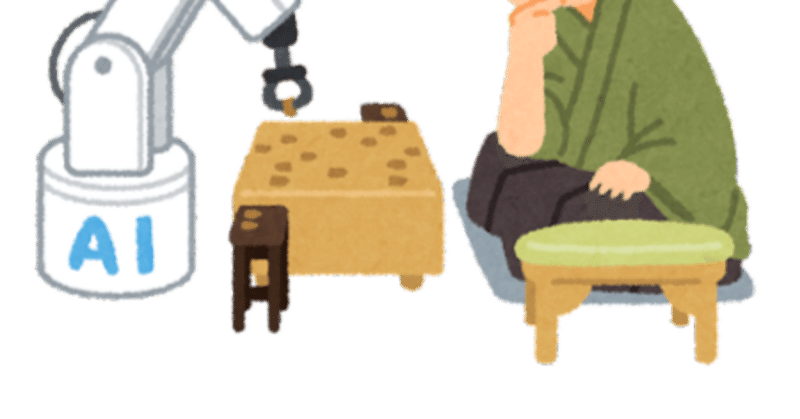
小説「けむりの対局」・第13話
勝つのは、どっちだ? 升田幸三 vs 人工知能
時刻は、午前零時に近い。
対局は終わっても、二人の対話は続いていた。
「面白かったろう」
と升田。
「はい、とても。将棋を、こんなに夢中になって指せたのは、まだ教わったばかりの小学生のとき以来です」
と早見。
「将棋は人間どうしで指すもの。力士を相手に、相撲のロボットを作って勝ったとしても、面白くも何ともなかろう。それと同じよ」
「はい。陸上選手に、クルマが競走で勝っても、何の自慢にもなりませんから」
二人は、声をそろえて笑った。
升田は言った。
「人間が仕事に役立てようとして作った機械が、逆に人間から仕事を奪っておる。操ろうとした機械に、逆に操られ、時間の過ごし方まで押しつけられたままに、人間は日々を送っておる。まっこと、おかしな世の中じゃ」
その言葉に、しばし黙りこみ、それから早見は口をひらいた。
「僕はもう、コンピュータ将棋の世界から手を引こうと思います。ちゃんと人間の役に立つ、情報工学の研究を、これから始めたいと思います。戦友はもう、お蔵入りです」
ややあって、升田が訊いた。
「ところで、ワシの戦友は元気にしとるかな?」
「え……」
「早見善介。ポナペ島の守備隊員として、死と隣りあわせの毎日をともに生きぬいた、ワシの戦友よ」
「…………」
「黒目勝ちの、大きくてまるい目が、おじいさんにそっくりじゃ」
「…………」
「その顔立ちから『メメクロ』と呼ばれていた善介に、お孫さんの俊介くんはよう似とる」
その言葉に、つぐんでいた口を、ようやく早見はひらいた。
「ご存じだったのですね……」
升田は、うなずいて、言った。
「戦友というソフトの名前も、ワシとメメクロの仲を言い表したものではないのかな。ワシら二人は、大の仲よし、強い絆で結ばれた戦友どうしだったからな」
早見は、驚いた顔をした。そうして答えた。
「何もかも、お見通しなのですね。あれは僕が中学生になったときでした、祖父から戦争の体験談を聞かされたのは。お前も良い友人を持つのだぞと、祖父はそういう気持ちだったのでしょう。ミクロネシアのポナペ島に送りこまれた自分たちの任務は、滑走路を作ることだった。やってくるはずもない味方の飛行機を迎えるためだった。そこへ毎日のように敵機が飛んできて爆弾を落としていった。滑走路だけではなく、自分たちの宿舎も爆撃を受けた。空襲警報が鳴るたびに、全員が壕のなかへ避難していった。ところがある日、自分だけが逃げ遅れてしまった。もう駄目かと観念したそのとき、爆撃のなかを一人の男が宿舎に飛びこんできた。それは、升田幸三だった。自分を助けにきてくれたのだ。升田は自分を背負うと、ガレキのなかを走っていった。『それ行け、やれ行け、もっと行け』と歌いながら、ガレキの山を一つずつ飛びこえていったのだ。升田のおかげで、自分は助かった。升田は、まさに命の恩人。祖父は僕にそう言いました」
早見の話をなつかしそうに聞いたのち、升田は言った。
「終戦の年の十二月十八日、アメリカ軍の輸送艦で運ばれ浦賀の港に着いたとき、メメクロとワシは手を取りあって喜んだものじゃ。やっと日本に帰れた、とな。メメクロとは将棋も指した。これが、まったくのヘボ将棋でな。飛車と角行、それに左右の桂馬と香車を落としても、このワシには一度も勝てんかった」
早見は、くすっと笑った。それから、だんだんと顔を曇らせた。
「小学三年生の僕の、手を取りながら、駒の動かし方の一つひとつから祖父は教えてくれました。とても優しい祖父。いまでも大好きな祖父です。だけど、祖父はもう、生きているのかどうか、僕には分かりません。この十五年間、ずっと眠りつづけているのです」
重く沈んだ早見の言葉に、
「おじいさんは、生きておるよ」
と、升田。
「えっ……」
と、早見。
「先ほどの対局の間、言魂を、何度か飛ばしてきた」
「言魂……?」
怪訝な面持ちの早見に、
「あれを見い」
そう言って升田は、対局場外のディスプレイを指さした。
その画面には、依然として電人戦の生放送が映し出されており、対局場から中継スタジオの場面に切りかわって高段棋士と聞き手による大盤解説が行われている。
そこへ、視聴者からのコメントが次々と流れている。
「やはり升田先生は強かった。まさしく将棋の鬼!」
「いや、鬼ではなく、将棋の神!」
「神は人類を救い賜うた!」
「早く記者会見が見たいよwww」
「それ行け、やれ行け、もっと行け。メメクロ」
「あのコメントは……」
驚く早見に、升田が言った。
「ま、まさか。祖父はパソコンなど使える状態ではないのに……」
戸惑う早見を、
「機械など使わずとも、魂は飛んでくる」
升田が諭した。
そして、
「行こう」
と、立ち上がった。
そのとき、テーブルの側から、にこやかな顔をして朝比奈会長が近よってきた。
「升田先生。それに早見さん。こんなに遅くまで、対局お疲れさまでした。恒例の記者会見の準備がようやく整いましたので、二階のプレスルームまで、お運びいただけますか」
升田は言った。
「記者会見など、せんでよい」
「えっ……」
困惑顔の朝比奈に、
「このワシは、いずこともなく漂うけむりのようなもの。この対局も、また、けむり。すべては、けむり、まぼろしよ。そんなけむりやまぼろしに、記者会見など要らぬだろう」
そうして、升田と早見は、対局場を出ていった。
升田の座っていた、座布団のそば。大きな灰皿に残された、八分咲きの菊の花。
それを、じっと見つめているうちに、あの対局が現実だったのか、それとも幻であったのか、松下春菜には、もはや分からなくなっていた。
(14)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
