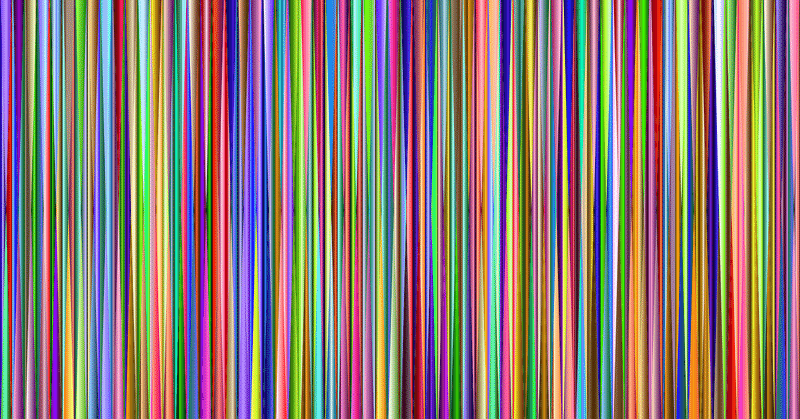
短編小説『クレイジー・ストライプ』
1
動物園でシマウマが殺された。
テレビのワイドショーは、国会前で機動隊と揉み合う動物愛護団体を映している。怒号と悲鳴、人間と人間の肉体がぶつかる鈍く不穏な音。それらが響くリビングには、トースターで焼いたばかりの食パンの香りが充満している。窓からは穏やかな陽が差し込み、いたって平和だ。今回のことに限った話ではない。どんなに悲惨な事件や自然災害が起きても、僕らの生活圏に及ばない範囲での出来事なら、それが揺らぐことはないのだ。
寝起きの僕は、温かいコーヒーを飲みながらパンを頬張り、テレビを見ていた。けれど、普段通りの朝食に変化をもたらしたのは、息子であるケイの表情だ。眉間に皺を寄せ、ちぎったパンを握る拳に力が入っている。おいおい、せっかくのパンが。ひどい職業病のせいか、パン屋の僕はパンの身を案じてしまう。
「どうして、シマウマが殺されなきゃいけないの?」
「殺されなきゃいけないの?」という言い方に激しい怒りが込められているのを感じる。この春、ケイは小学2年生になった。幼稚園に通っている頃なら、大人が答えにくい「なんで?どうして?」攻撃をあしらうことはできたけど、ケイはケイで小学校低学年ながら独自のコミュニティで情報を得ている。何かしらの根拠をもって、誰かを責めているのだ。
「シマウマのしまもようがいけないんだって」
自分で言っていて、意味がよくわからないのは自覚している。でも、それが本当のことだった。この国で、しまもようは暗黙の禁忌になってしまっている。
事の始まりは今から3年前。この国で初めて発生した大規模テロだ。首都を襲った地下鉄爆破テロ。ラッシュ時を直撃し、その被害は甚大なものだった。僕らが住んでいるのは、郊外の田舎町。テレビの映像がセンセーショナルすぎて現実感は乏しかった。それに、まだ幼いケイの心の成長に予期せぬ影響があるといけないから、テレビは消していることが多かった。
国中の悲しみが癒えないうち、またしても爆弾テロが起きた。今度は、首都ではない地方の都市で。しかも、遠く離れた2つの街で同時に起きた。都会で暮らす人たちはパニックに陥り、街中が混乱した。次はどの街が狙われるのか、みんな疑心暗鬼になり、心身ともに疲弊している様子がテレビやネットを通じて伝わってきた。僕が住む町は大丈夫だろう。そんな楽観的な思いは僕だけのものではなかったはずだ。都会から疎開してくる人たちがたくさんいたから。
政府はテロを防ぐことに躍起になった。同盟国の支援も受けてテロ組織を撲滅するまで3年かかった。その間、テロは小さなものを含めると5つも発生していた。そんな悪魔たちのトレードマーク。それが、しまもようだった。
テロ現場には、しまもようのマークが意図的に残されていた。人々を嘲笑うかのように。もう見たくもない。嘘偽りのない人情というものだ。その人情が、シマウマを殺した。
「トラもしまもようじゃん。なんで、シマウマだけ殺されるんだよ?」
最近、ケイは口が悪くなってきている。男の子だから、ある程度は仕方ない。
「シマウマのしまもようは目立っているからじゃないかな」
もうわけがわからない。当然、ケイは納得していない。頬っぺたを膨らませ、口を尖らせている。
「ケイ、大人の事情よ。大人になればわかるから」
僕とケイとのやり取りにしびれを切らしたのか、キッチンから妻のカリンが口を挟んできた。
「早く用意しなさい。学校に遅刻するわよ」
ケイはオレンジジュースを一気飲みすると、パンを残してプンプンしながら洗面所に行った。
「あなたもPTAの会合に遅れるわよ。客商売なんだから、評判を下げるようなことはしないでよね」
カリンはテレビを切った。僕は急いでパンを食べる。「あぁ、言っちゃった」と思う。「大人の事情」って言葉、それを使うのは本意ではない。あれを言っちゃうと、どんなことにも蓋をしてしまえるから。でも、あのままケイに追求されていれば、僕も口にしてしまっていたかもしれない。だって、シマウマが殺されたのは、大人の事情でしかないから。そして、とりあえずトラが生かされているのも、大人の事情でしかないから。
2
学校に到着すると、いつものようにケイの教室の前を通る。窓から覗くと、ケイは真剣に授業を受けていた。感心だ。クラスメイトが僕に気づいて、ケイにサインを送ってくれる。「パパが来てるぞ」と。でも、それを受け取ったのにも関わらず、今日のケイはそっけなかった。
たまたま目が合った担任のジョン先生に会釈だけして、会議室に向かった。ドアを開けると、黒板を背にして座っていたPTA会長のブラントンが腰をあげて迎えてくれた。
「やぁ、お店がお休みの日にわざわざ申し訳ない。今朝もお宅の食パンをいただきましたよ。妻が買って来てくれるのですが、毎日食べても飽きない。実においしい。今度、私もお店に伺います」
僕は恐縮しながら軽く握手を交わすと、空いている席に座った。今日の出席率はまずまずといったところか。やはり、最近の状況に親として多少の危機感を覚えているのかもしれない。定刻になり、会合が始まった。大柄のブラントンがのそのそ立ち上がり、挨拶をする。
「今日はお忙しいところ、お集まりいただき、ありがとうございます。本日、会員の皆さまに諮りたいことは、子どもたちの服装についてです。ご存知のことと思いますが、昨日、動物園でシマウマが殺処分されました。大変痛ましいことです。ですが、国民感情を考慮すれば、致し方のないことのようにも思います。都会では、しまもよう狩りなるものまで行われているとかで。しまもようがデザインされた広告が駅で破壊される事件もありました。そんな中、我がPTAとしては子どもたちにしまもようの服装を禁止する決定をしたいと思いますが、いかがでしょう? シャツもキャップもスカートも靴下も、しまもよう禁止です。もちろん、心苦しいです。しかし、子どもたちの安全には代えられません。私は、何としても子どもたちを守りたい。その一心です」
冷房が効いた会議室で汗を流しながらブラントンが話し終えると、拍手が聞こえた。小さく鳴り、渦を巻くように大きくなる。僕も、その中にいた。ひとりの女性が立ち上がり、声をあげた。
「私は、ブラントンさんから今回の提案が無いとガッカリしていたことでしょう。大賛成です。子どもたちの身が心配ですし、私自身も今はしまもようを見る気分にはなれません」
「そうだ、そうだ」という独り言が重なる。ブラントンが、また口を開いた。
「ご賛同、感謝いたします。もし、こちらで反対が出なければ、採決したいと思いますが、よろしいでしょうか?」
誰も異を唱えない。僕も、唱えるはずがない。全会一致だ。
「今年のPTA会員の皆さまは実に素晴らしい。こんなに一体感を持てることは近年ありませんでした。心強いこと、このうえない。早速学校に伝え、速やかに実施してもらいます。では、解散」
重さを感じさせない軽い足取りでブラントンは出て行った。会員たちは帰り支度をしながら「よかった」と口々に安堵している。「ブラントンさんは対応が早いし、実行力があるわね」と、さっきの女性は赤いフレームの眼鏡を指で上げて満足気だ。ブラントンは今度の町の選挙に出馬するらしい。この調子なら当確ランプが灯るのも早いだろう。
予想通り、学校はこの日のうちにすぐに動いた。もう子どもたちは、しまもようを着られない。
「なんで? どうして、しまもようの服を着ちゃいけないの?」
僕は、この話を切り出すタイミングをうかがっていた。せっかくの休みの日、家族との夕食は幸せなものであってほしい。カリンが作ってくれたパスタとサラダ、アクアパッツアは今日も絶品だった。デザートにジェラートを食べ、ケイのお腹が満たされたところで話し始めたが、すべてを台無しにするほどケイは不機嫌になった。
「あなたたちのためよ。しまもようを着ていたら誰かに叩かれたり、もしかしたら石を投げつけられたりするかもしれないのよ」
僕の隣に座ってジンジャーミルクを飲むカリンがケイを諭す。
「知ってるよ。しまもようの人たちが悪いことをしたからでしょ。でも、それって関係あるの?」
「ケイやお友だちを守るためなんだよ。わかってくれないかな?」
「だからさ、どうしてしまもようを着ているだけで叩かれたり石を投げられたりしなきゃいけないの? 僕たち、何も悪いことしてないのに」
子どもの質問というのは、本質を突いてくる。そこに忖度なんてない。だから、答えれば答えるほど大人は苦しくなる一方だ。追求されると、まず理論的には勝てない。
「それはケイの言う通りだ。でもね、今は世の中がそうなってる。しまもようは悪いもので、みんなでそれを無くそうとしているんだ。そうだ、ケイはジョン先生から『みんなと仲良くしましょう』と言われていないかい? みんなで決めたことだから、ケイもそうした方が僕は良いと思うんだ」
我ながら良い例えが思いついたように思うが、どうなんだろう。ケイがじっと僕を見る。僕は息子の顔から目をそらした。
「じゃ、公園に遊びに行ったり、サッカーの練習に行ったりするときは着てもいい?」
「……それも駄目なんだ」
やっぱりこらえていたみたいだ。ケイの瞳が涙で覆われた。
「新しいのを買ってあげるから。服もキャップも」
カリンはケイの気を引こうとするが、彼女も僕も知っている。大好きなヒーローが映画の中で実際に身に付けていたキャップ。抽選で当選し、つばの裏にはサインが書かれてある。それは、忌まわしいテロが起きる前のこと。幼稚園だったときにもらって以降、ケイはしまもようのロゴが入ったキャップを宝物のように大切にしてきた。外で被っては、誇らしそうに。キャップという言葉が引き金になったのか、ケイはテーブルにうつ伏して泣いた。胸が痛い。おそらくカリンもそうに違いない。ジンジャーミルクを飲み、ため息をついた。
「でもね、仕方ない。決まったことだから。しまもようは、もう駄目なのよ」
テロを起こした奴らが憎い。あいつらがずっとまとわりついている。
3
それから数日して、店内に流れるラジオがニュース速報を伝えた。
「動物愛護団体幹部を逮捕」
夕暮れ時、僕の小さなパン屋には翌朝のパンを買い求めるお客さんが数人いたが、一瞬の静寂の後、誰もが好意的な反応を示したのは驚いた。公務執行妨害ということらしいが、真実はわからない。それなのに。
「しまもよう、見たくないものね」
「自分たちのエゴで勝手なことするからこうなるのよ」
「自業自得ね」
「良い迷惑だもの」
動物愛護団体を非難する声も耳に入ってきた。僕は、ブラントンの素早い決断に改めて舌を巻いた。彼は、この町にもいずれ波が訪れることを察知していたのだ。ケイら子どもたちにしまもようの服装を禁止しておいてよかった。カリンの危惧は、おそらくケイへの脅しに近かったと思うが、そうとも言えない状況になってきているのかもしれない。
店じまいをしようとしていると閉店間際にひとりのお客さんが店に入ってきた。ブラントンだった。
「やぁ、こんばんは。この前の約束通り、買いに来ましたよ。今晩は妻も娘も出かけていましてね、夕食にパンを食べたい気分になりました。もうすぐ閉店ですのに、申し訳ない」
「いえいえ、ご来店ありがとうございます。残っているパンが少ないのですが、ゆっくりお選びください」
「ありがとう」
パンを見定めながら、ブラントンはのそのそと店内を歩き回った。トレイには、ハムとレタスを挟んだクロワッサンとカレーパンが載っている。クリームパンにトングを伸ばそうとしたとき、その手が止まった。
「これはいけない。このパンは危険ですよ」
じろりとこちらを見るブラントンの顔からは笑みが消えていた。とても不気味で、脇から汗が垂れる。
「そのクリームパンが何か?」
「その隣です」
ブラントンがトングで指したのは、僕の店の名物「サンロード」というメロンパンだった。真ん中にオレンジ色のメロンクリームが縦にあり、その両側をホイップクリーム、さらに外側をメロンジャムが……まさか。
「しまもよう、じゃないですか」
「いや、ただのメロンパンですし、さすがにこれは大丈夫じゃないですか」
僕は笑っていた。怒っても良かったはずなのに、笑うしかなかった。それも必死に。なんだか、とても悪いことを隠しているような、そんな気分にもなってきて。
「私は、あなたのことを友人であり、同じPTAの同志だと思っています。そのうえで、これは危険だとお伝えしています。しまもようを毛嫌い排除する風潮は、この町にもやって来ています。そのことはあなたも理解しているでしょう」
僕は頷くしかなかった。
「何よりもケイくんのことが気がかりだ。それに、このようなパンがある町だと他に知られれば、町全体の治安にも関わる。どうか、善処いただきたい」
子どものことを持ち出されると親は弱い。
「少し考えさせてもらって良いですか?」
「わかりました。早期にご対応いただけること、期待しております」
そう言うと、ブラントンは結局クリームパンもトレイに載せ、合計3個のパンのお金を払って店を後にした。表情は戻り、いつものやわらかさをまとっていたが、帰り際にサンロードに目をやる顔つきは厳しいものだった。
僕はカリンに電話し、新作パンを考えたいとの理由で帰りが遅くなる旨を伝えた。サンロードの去就について、ひとりでじっくりと考えたかった。もし、他のパンならすぐに製造や販売をストップしていたかもしれない。けれど、僕の中でサンロードは別格だ。
4
20代前半、学校を卒業した僕はある商社に勤めていたけれど、激務に耐えられずに退社した。辞めてしまうと身体は楽になったが、すぐに自己嫌悪に陥った。これからどうすれば良いのか、途方に暮れた。
そんなとき、テレビを見ていると、ムートンという名のパン職人のドキュメンタリーが放送されていた。当時80歳。まだ現役で、一生懸命に生地をこねている姿に、僕はどういうわけか泣いていた。雷にでも打たれたショックを受けた僕は、何か憑き物が落ちたように清々しい気分になり、その人を訪ねることを決めた。こういう行動力が自分にあったのが今も信じられない。飛行機に乗り、ムートンの店に足を運んだ。
テレビの影響か長い行列ができていたが、僕は最後尾に並んで待った。徐々に進み、ガラス越しに中を覗くと、いた。腰は曲がっているが足取りはしっかりしていて、お客さんひとりひとりとの記念撮影に応じている。ようやく店内に入ると、名物のメロンパンを買い、ムートンに直接手紙を手渡した。そこには「弟子にしてほしい。閉店後、ほんの少し時間をください」と書いていた。
店を出て、僕は近くの広場のベンチに座った。「時計塔跡」と書かれた小さな碑が建っていたが、この町にとって大切な場所ということはまだ知らなかった。そこで、買ったばかりのメロンパンを食べた。口と鼻に甘さがいっぱいに広がる。こんなにおいしいメロンパンを食べたのは初めてのことだった。知らない土地で、パンを食べながら涙を流した。不審者に思われたかもしれないけど、周りを気づかう余裕すらないほど夢中になるやさしい味だった。
夜、店に戻った。誰かもわからない人間からの手紙だ。無視されることも覚悟していたが、ムートンは笑顔で待っていてくれた。そして、弟子になることを快く許してくれた。後から聞いても「ただの直感だよ」としか教えてくれなかった。ムートンは、あまり多くを語らない。でも、心が大きな人だった。そんなムートンから伝授されたのが、サンロードのベースになったメロンパン。僕の人生を変えたと言っても過言ではないメロンパンだ。
2年間の修行期間を終え、僕が生まれ育った故郷、今も暮らす町に帰る前日、ムートンは坂の上の教会に連れて行ってくれた。ムートンは何も言わない。二人で街を見下ろしていると、ちょうどその先に夕日が沈んできて、教会までを一本の光が結んだ。
「お前のこれからは明るい」
これだけで、もう僕は十分だった。
故郷に戻り、3年ほど隣町のパン屋に勤め、カリンと出会って結婚して店を構えた。メロンパンをアレンジした看板メニューを作りたくて、あの日に見た景色を表現しようと思った。サンロード、すなわち、太陽の道。サンロードは、師であるムートンとの絆の証であり、僕という人間の象徴だ。
これを手放すのか。ムートンの写真を指で撫でたまま、夜を明かした。
5
太陽が昇り、僕は一睡もせずに開店に向けて準備を始めた。今日は日曜日。カリンもケイもまだ寝ているはずだ。帰っていないと心配するかもしれないから、もう少ししたら電話をしておこう。窯に生地を入れて焼く。朝一番の香ばしいにおいはパン屋だけが嗅ぐことのできる特権だと思っている。けれど、さすがに気分は晴れなかった。焼きあがったパンを窯から取り出し、フルーツを乗せたり、クリームを挟んだりする。昨日、あんなことがあったけど、もちろんサンロードも作った。メロンパンに切れ目を入れて、メロンクリームとホイップクリーム、メロンジャムを流し込む。たくさんのサンロードが朝日に照らされてキラキラと輝き出す。見ていられなかった。他のパンを作ることに集中し、店頭に並べていった。
開店時間を迎え、シャッターを開ける。すると、何人もの人が店の前に群れていた。ただ、パン欲しさに開店を待ち望んでいるような雰囲気ではない。殺伐としているから、それはわかる。ひとりの女性が僕の前までツカツカと歩いてきた。赤いフレームの眼鏡。この前のPTAの会合で、ブラントンを絶賛していた女性だ。
「そちらでは未だにしまもようのパンを販売されているようですね。どういうおつもり?」
僕は絶句するしかなかった。
「しかも、あなたはPTAの会員さんでいらっしゃいますよね? あまりにも意識が低いというか危機感が無さすぎるんじゃありません?」
「昔から販売しているパンなんですが……」
なんとか声を絞り出すも、逆効果だった。
「そんなことは百も承知です! ですが、世の中の流れというものがあるでしょう。そもそも、しまもようの服装を子どもたちに禁止しておいて示しがつかないとは思いませんの?」
後ろにいる何人もの人から「そうだ、そうだ」と同調する声が飛び交った。その人たちも追従するように迫ってくる。人間が押し寄せてくる圧の怖さに僕は震えた。
「お待ちくださーい!」
遠くから叫び声が聞こえた。その方を見ると、ブラントンが巨体を揺らしながらこちらに走って来る。赤い眼鏡の女性と僕との間に割って入ってきた。
「はぁはぁ、みなさん、落ち着いてください。実は昨日、私も懸念をお伝えしたんですよ。なので、おわかりいただいたはずです。しまもようのパン、販売は中止されますよね?」
「あら、そうだったの? ブラントンさんがお話しいただいたのなら安心ですわね」
息を整えながら、ブラントンは女性に向かって親指を立てた。
「中止されますよね?」
念を押すようにブラントンが僕に尋ねる。でも、即答はできなかった。
「どうして黙ってるんですか!」
赤い眼鏡の女性が金切り声をあげた。僕は思わず耳を塞いだ。ブラントンが女性を制止する。
「事態は一刻を争うものです。この町の安全と平和のためなんです」
太陽がまぶしい。ヒーローのようにブラントンは胸を張った。僕は心を落ち着かせたかった。お辞儀をして店の中に戻ろうとする僕に罵声が飛んだ。
「しまもよう反対!」
「しまもようをやめろ!」
「さもなくば、この町から出て行け!」
振り返ったところで容赦はない。これがシュプレヒコールというものか。テレビで見ていただけのものが僕を取り囲んでいる。ブラントンが後を追いかけてきて、そっと耳打ちされた。
「こういうことを言いたくはありませんが、このままでは何が起きてもお守りすることはできませんよ」
それには応えず、僕はシャッターを閉めた。今日は臨時休業だ。シュプレヒコールはしばらく鳴りやまなかった。
店に入ってすぐ、カリンから電話がかかってきた。
「今、店に……」
「うちにも来たわよ」
「自宅にまで!」
「えぇ。とりあえず夫に伝えておくと言って帰ってもらったけど」
「ケイは?」
「ちょっと怖がっちゃって部屋にいるわ」
「今日は一日、外には出ないほうがいい」
「わかった。ケイにも強く言っておく。あなたは?」
「誰かに見つかると面倒だから夜までこっちにいようと思う」
「サンロードはどうするの?」
頭が痛い。
「もう、無理かもしれない」
眩暈がした。でも、カリンを不安にさせるわけにはいかない。
「また別のパンを作れば良いだけさ」
そう言って電話を切った。シュプレヒコールはもう聞こえない。サンロードは、今も変わらず輝いている。僕はひとつを手に取り、齧った。我ながら、おいしい。なのに、どうして。浮かんだのは、ケイとカリンの顔。二人を危険に晒すわけにはいかない。サンロードが載ったトレイを持ち上げた僕は、目をつぶってゴミ箱に捨てた。
「何してるの?」
僕は心臓が止まりそうだった。
「ケイ、どうしてここに?」
「パパが心配で家を抜け出してきたんだよ」
ケイは怒っているような、悲しんでいるような、そんな顔をしている。
「どうして、パパがパンを捨てなくちゃいけないの?」
すがるように聞いてくる。辛い。どう答えたら良いのか、わからない。黙っていると、ケイも黙ったまま。お互い、もう何も言わなかった。
6
次の日から、僕はサンロードの販売を中止した。その決定が小さな町中に届くまで、そう時間はかからなかった。すぐにブラントンが店に来て「ご英断に感謝します」と握手を求めてきた。
一日経ち、二日経ち、日曜日の喧噪が嘘だったかのように、やがて日常の風景が戻ってきた。僕の決断は、間違ってはいなかった。僕は、この町で暮らしていかなければいけない。家族を養っていかなければならない。あのままサンロードを売り続けていたら、店は潰れていたことだろう。これでよかったんだ。
けれど、ケイとの関係はギクシャクしている。サンロードを捨てたあの日から、ほとんど口をきいていない。食事のときに顔を合わしても無言で、何か話しかけても何も言わない。学校でイヤなことでもあったのか疑ったが、ジョン先生いわく思い当たることはないらしい。あんなことがあったからイジメにでも遭っていないか心配だが、ケイに聞いても何も返ってこないので、確かめようがない。カリンも困っていた。
「反抗期じゃない?」
「そうだと良いんだけど」
そうであってくれれば御の字だと僕は願った。
それから、町からしまもようが次々に消えていった。果物屋からスイカが、ケーキ屋からショートケーキが、魚屋からは鯛が消えた。どこかでシュプレヒコールが聞こえるたび、何かが町から失われていく。そうして平穏は保たれていた。
ある夜、店で帰り支度をしていると、突然、ケイがやって来た。カリンはいない。僕は戸惑った。親子なのに、あの一件以来、僕の方が距離を感じてしまっている。
「どうした? 夜に危ないじゃないか」
ケイは肩にかけたバッグから大量の紙を取り出し、僕に突き付けた。
「何? ママにテストを隠してたのか?」
冗談で和ませようとしたが、失敗。笑ってはくれなかったケイがつぶやいた。
「しょめい」
しょめい? 中身を見るまで、それが指し示すものをイメージできなかった。
『サンロード、だいすきです』
『あまくておいしいサンロード、またたべたいです』
『かぞくみんなサンロードがたべたいといっています』
『サンロードつくってください。おうえんしています』
『ケイのパパ、がんばれ!』
たどたどしい文字。ケイの言う「しょめい」は子どもたちからの「署名」だった。
「これは……」
ケイは恥ずかしそうに下を向いている。
「先生には内緒で、クラスのみんなに書いてもらった」
一枚一枚に目を通すと、目の裏が熱くなる。でも……もう無理なんだ。情けない父親で御免。心の中で謝る。
「僕、明日からあのキャップを被っていくから」
「えっ?」
僕は、また言葉を理解できなかった。
「ひとりじゃないよ。ボブもマリーもお気に入りのTシャツとかワンピースを着るって。どれも、しまもよう」
ケイはニヤッと笑った。反乱のつもりなのか、そんな単語を知っているかどうかもわからないけど、さもそれを楽しんでいるかのように。僕は頭の中が混乱していた。
「と、とりあえず今日は一緒に帰ろう」
ケイは自転車を押しながら、僕のそばを歩く。帰り道、ケイは一言だけ僕に言ってくれた。
「サンロード、僕も大好きだよ」
とても、とても嬉しかった。
7
翌朝、玄関でカリンが僕を抱きしめてくれた。勇気をもらった気がする。店に着き、窯に火を入れ、パンを焼く。香ばしいにおいはパン屋の特権だ。誰にも邪魔はさせない。
焼いたばかりのメロンパンに切れ目を入れ、真ん中にメロンクリーム、その両側にホイップクリーム、さらに外側にメロンジャムを流し込んだ。それを何個も何個も作る。開店時間、ムートンの写真に手を合わせてからシャッターを開けた。昨夜作っておいたポスターをガラスに貼る。
『サンロード、まさかの復活』
その上には大きくキャッチコピーを添えた。
『しまもように狂うな!』
もう聞きつけたのか、ブラントンが暴れ牛のように店になだれ込んできた。目が赤く充血している。
「はぁはぁ、いったい、何を考えているんだ!?」
「ポスターに書いてあるとおり、サンロードを再開します」
「頭がおかしくなったのか?」
「どう思っていただいてもかまいません」
「どうなっても知らんぞ……」
「パン屋は辞めるかもしれませんが、僕はサンロードを作ることを止めません」
「もう勝手にしろ!」
お尻を振りながらブラントンは出て行った。店に来る人全員が目を丸くし、店内には入らずに去っていく。
これから大変な日々が始まる。僕たち家族は覚悟したんだ。ケイは、しまもようのキャップを被って登校しているところだろう。カリンが付き添ってくれているが、二人も冷めた視線に耐えているに違いない。
でも、ケイには仲間がいる。
きっと、いつか僕にも。
fin.
★関連作品 短編小説『スマバレイの錆びれた時計塔』
★Kindleにて小説「おばけのリベンジ」発売中!
よろしければ、サポートお願いいたします!頂戴しましたサポートは、PR支援や創作活動の費用として大切に使わせていただきます。
