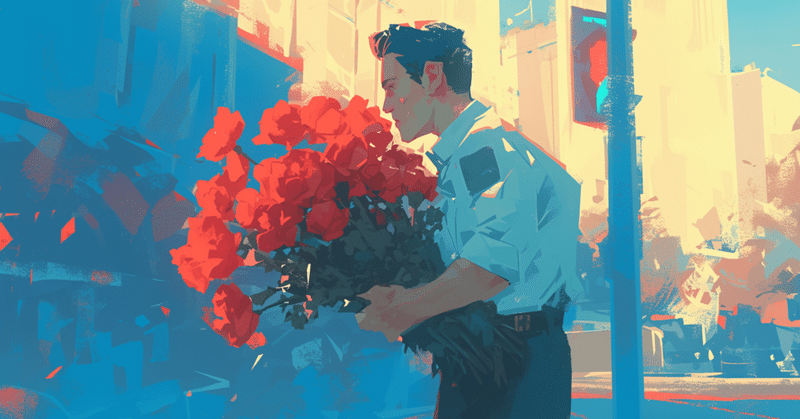
哲学の勉強 霧を掴むがごとく
相変わらず哲学の輪郭をつかむのに苦戦している。哲学という総体を追い求めているが、この姿勢がよくないのだろうか。哲学という個別の領域に見える思考とは、哲学者個人の経験や思考、感性に由来するものであって、哲学という大枠など存在しないのだろうか。哲学的思考様式が存在することを過程にして勉強を始めたが、ここにきて方針転換が必要なのだろうか。儒教や仏教の類推で学ぼうとする姿勢がよくないのだろうか。儒教、仏教の知識が薄いが故に、類推がうまく働いていないのだろうか。よく物事を理解することを霧をつかむがごとくと表現したりするが、哲学を勉強することに、これほど適切な表現はないのではないかと思われる。自分の身に蓄積されず、ただ吸って吐いてを繰り返しているような、奇妙な時間が過ぎ去っていく。だが、自分の中でこうではないかという姿が見えている気もする。見えているのは所詮自分の願望であって、真実ではないのだろうか。相反する考えが脳の中央幹線道路を高速で行ったり来たりしている。
うだうだと自分の中で繰り返されている迷いを吐き出したが、文字にしている作業の中で天啓のように降ってわいてきた、学んだことを次々とそのまま吐き出すとよいという観念に従ってこれからの作業を進めるとするか。別に特別頭のさえない人間には愚直におそらくこっちであろうという方向に進んでいくこと以外に方法はないのである。それ以外にないのなら、作業仮説やらはいらないのである。少なくとも有力な作業仮説を構築できるようになるために必要な知識量が足りていない。地力を鍛えるには、地道な読書と書き出しを繰り返すしかないのである。筋トレやら野球やらで実感していたではないか。体をうまく動かすことと同じように、思考も量が必要である。運動量が足りすぎているくらいに達して初めて、精度が磨かれていくのである。それを忘れてはならない。とにかく近道はないのである。
木田元さんの著書を最近読み、ソクラテス以来の王道的な哲学と、それに反旗を翻すような反哲学の運動が19世紀末、20世紀にニーチェとハイデガーを代表として始まったことを知った。となると今、哲学と呼ばれる営みは、それまでの哲学を批判し、吟味し、また超越する試みだけではなく、場所すら超越した、一般化の極みを目指しているらしいことを知る。そうなってくると覚えるべき事柄が多いな本当に。簡単にはいかないことを何となく悟ってたはいたがこれから大変だ。
とりあえず自力で自分流、西洋哲学史をざっと書き上げて、そこから反哲学の潮流を汲んだ現代思想に入っていければなと思う次第である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
