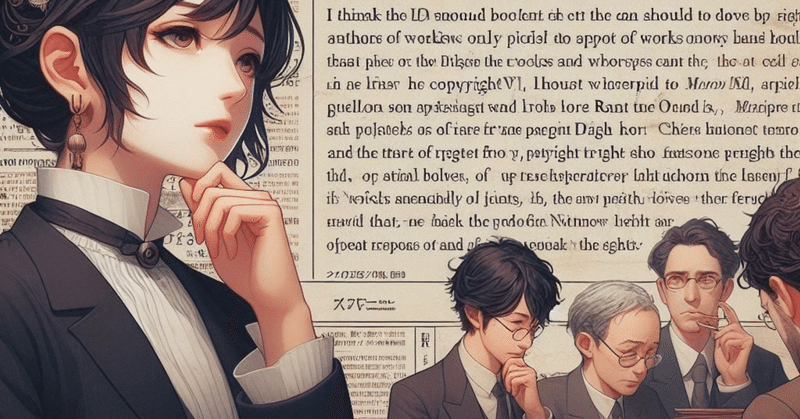
なぜ人間は何もしていないときに苦痛や不安を感じるのか? 思考の断片メモ
暫定的個人的見解
内面化した社会との苦悶の対話が勝手に始まってしまうから
社会=高度消費社会、情報社会、大衆的な倫理、法による秩序
人間は何もしていないと苦痛を感じるようにできているというが、私はこれは違うと思う。何もしていないという状態が苦痛を喚起するのではなく、何もしていないと己との対話が始まってしまう。これが苦痛なのだ。己との対話に終わりはない。己が常に変化するからだ。己はある時は自らの欲望に、またある時は他者の欲望としてふるまう。自らの欲望も他者の欲望も、姿をとらえたと思ったら形を変える。一度つかんだその姿から変わらないものはないとも言ってよい。その時の正解は一瞬のうちに不正解になる。
己の欲望が横を向くと、それに相対する欲望とが無数に平行に存在することがわかる。ある一定の立場を内面化し、一度はそれで割り切ったとしても、並行する欲望、思想とが投げかけてくる疑念の声は思考を続ける限り止まることがない。
自分と、自分が内面化した他者との対話を控えるには、それから目をそらすことしか有効なことはない。
自分ではないものへの集中、没頭以外にこれとの対決を避けることはできない。
あるべき人間像との乖離が苦痛不安を喚起するのだろう。
何もしていないという状態そのものが苦痛であることもある?
ただ時間が過ぎるのを延々と感じていることが苦痛?
個人的にはちょっとしか理解できない。ただ時間が過ぎていくことにもなんとなしに面白さを感じる。これはちょっと微妙かもしれない。ただ時間が過ぎていくkとには面白さを感じることはできないかもしれない。
常に何かをやってはいるかもしれない。何もしていない時間は意識して振り返ってもないかもしれない。
何もしていないこと=暇であることの苦痛についての考察が足りていない
科学技術が人間の在り方と思想を変える大きなファクターだろう。思想同士の対決も大きな要因ではあるが、21世紀は技術が思想を変革する要因だろう。果たしてそうか?それら科学技術産業すべての変革は資本主義がなくてはならなかった?
何もしていないときにすべての人間が苦痛を感じているとはかぎらない。一部の人間、特に現代社会に生きる人間の一部が、何もしていないときに苦痛を感じている節があるのではと仮説を立てる。
人間の思考は生活空間に支配されはしないが依存する。そのため生活空間たる環境がどのような特徴を持っているかを考える。
社会階級や個人的思想、精神状況によっても違うだろう。
違うだろうか?違うだろう!
個人的な経験によっても持つ思想は変わるだろう。
現代社会の特徴である高度消費社会、情報社会、グローバル化の特徴。
高度消費社会
高度消費社会とは、産業の発達により、消費行動が生理的欲求から社会的・文化的欲求へと変化する社会です。
高度消費社会の特徴は次のとおりです。
産業化の深化により、自らの再生産に不可欠な財への欲求がほぼ満たされる欲求体系の高度化とその商品形態による享受が日常生活のあらゆる局面にまで浸透する
他人との差を付けるという欲求によって消費行動が促される
大量消費社会では、ものを大切にするという意識がより薄れる
製品が壊れたり古くなった場合でも修理するよりか買い換えたほうが費用的に安価に済むような価格設定がなされる
大量消費社会においては、あらゆる製品が安価に手に入るようになることから、消費者は「豊かさ」を感じることができる
高度消費社会では、広告や販売術等の「依存効果」(ガルブレイス)を通じて、欲望は創出され続けると言われています。生活必需品の消費としての絶対的欲望に不自由を感じない若者の多くが、流行や新商品の巧みな演出によって、際限のない相対的欲望の渦中に巻き込まれていると言われています。
情報社会
information society. 具体的な物の製造や流通に価値をおく以上に,物や人に付随する大量の情報に価値をおき,それを収集,伝達,処理することを経済・産業や生活の中心に据える社会。 ほぼ同様の意味をもつことばとして脱工業化社会,脱産業化社会がある。
グローバル化(グローバリゼーション)技術革新や交通手段の発達などにより、国や地域の垣根を越えて、政治・文化・経済などが地球規模で拡大する現象です。
人・モノ・カネが活発に移動し、世界規模で資本や情報のやり取りが行われる。
国境の意義があいまいになり、各国が相互に依存し、他国や国際社会の動向を無視できなくなっている。
国境の垣根をできる限り引き下げ、ヒト、モノ、カネの流れを活発化させる現象、およびそうすべきだという考え方である。
グローバル化によって世界が一つの市場になり、安くていいものの競争が激化する。
労働者はより資本主義を内面化し、合理的、効率的にふるまえなければ競争から振り落とされてしまうという恐怖にかられる。
何もしていないことは労働者としての鍛錬を怠っているとしてこの社会からつまはじきにされてしまうと妄想する。
正解などといった割り切ったものを提示することが有効ではないかもしれない。
この世界には相反する価値観が並行して無数に存在する。
一つの人格は他者の集合体であるから。
ここまで考えてきたが己との対話が苦痛ではない、己の中の他者、自分を律する監視者、欲望対我々が受けてきた教育?視線?常識?他者の思想?
自分の欲望とはなんだ?
自分の欲望と他人の欲望との境界線はどこだ?
自分の欲望=他人の欲望?
赤ん坊は何も持っていない。そこにはただ学習能力だけがある。
赤ん坊は言語を吸収する。
言語はもちろん赤ん坊が生み出したわけではない。
他者が他者と通信するために生み出した精密なプロトコルだから。
赤ん坊が生み出す言葉もある。あーとかうーとか。言語水準未満。
赤ん坊はまず言語という他者を己として同化する。
そして同化した他者たる言語で、提示された他者の価値観を吸収していく。
最初は家族とか養育者の価値観を吸収する。
そのうち幼稚園とか学校に行くことになって、先生や同級生、上級生、下級生の価値観を吸収する。
今はインターネットもあるので、無数の人間の価値観を吸収することになる。
そのうち自我が芽生えある一定の価値観に反発することになる。
さてここでひとつ疑問。
この自我とは本当に私なのだろうか。
他者が作り出した言語で、他者が語った価値観を吸収して、ある一定の価値観を払いのける。
ここには無数の他者があるだけで、私がやったとといえばひたすら学習=吸収していただけだ。
ある一定の価値観を払いのけたのが私というにはまだ足りない。
ある一定の価値観を払いのける価値観を吸収し採用しているに過ぎない。
それが自我=私だといわれてもまた同じようなことが始まる。
ある一定の価値観を払いのける価値観を採用する価値観を採用しているに過ぎない。
自我=私=他者というまるで奇妙な図式である。
自分と他者との境界線は考え出すと危うい。
現実はほぼすべて己の欲望と他者との欲望の折衷案?
そもそも人間はひとりで生きていくには言葉を必要としなかった?
これは何もしていないと不安になるとは関係なし
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
