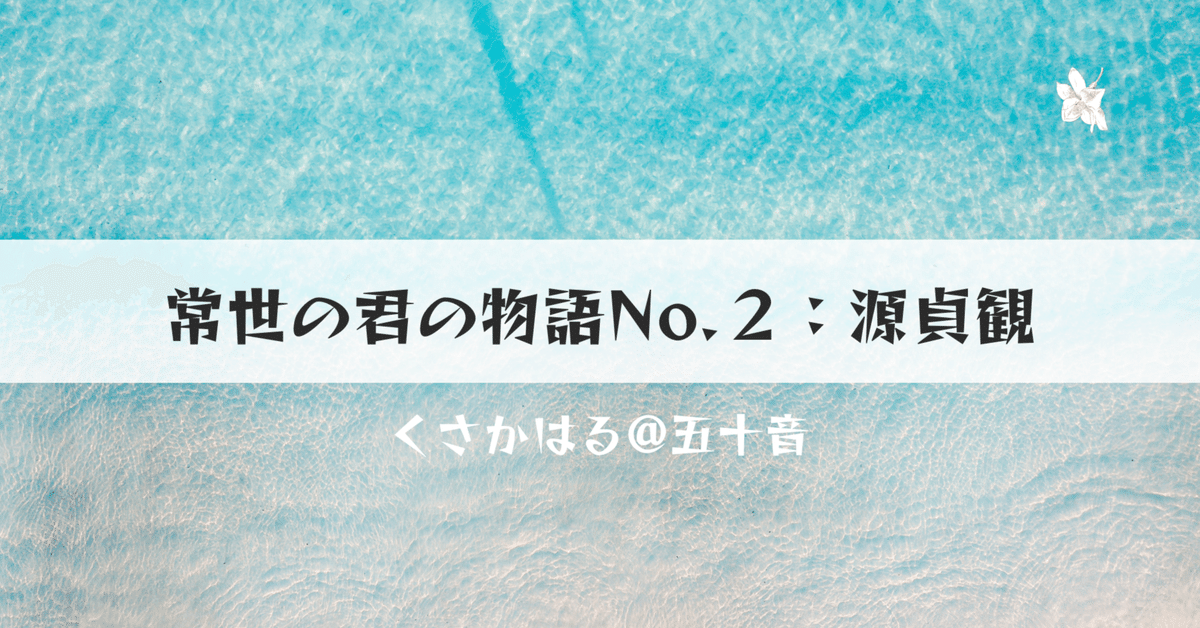
第一章:めんどうなことだ
一筋の涙が、頬をついと流れた。
どうやら眠っていたらしい。
源貞観《みなもとのさだみ》は、濡れた頬をぬぐうと、ぬっと起き上がり伸びをした。
自身が下敷きにしている影を確かめると、木漏れ日混じりとはいえ、おおよその太陽の位置が見て取れる。
それに加え、講堂の縁側にあって、今まさに正午の鐘の音が聞こえている。
その音を最後までじっくりと聞き取ってから、今一度、貞観はその場で大きく伸びをした。
「ねむ」
思わず漏れ出た言葉で、庭の手入れをしていた小坊主と目が合う。
貞観は思わず、はにかんだ。
ここは良願寺、大和国の東の端にある、和同の頃から続くゆかりある寺である。
かつて都のあったこの平城の地も、今ではもっぱら寺社仏閣のひしめくかび臭い一都市に成り下がり、長い時が過ぎていた。
都が山城国に移って、はや三百有余年になる。
そんなことは書物の中でしか知らない貞観にとって、良願寺は古ぼけた寺でしかない。
年輪の浮き出た太い欄干に体を持たれかけさせ、貞観はふうと、ひとつため息をついた。
季節は初夏、気の早い蝉が四方からその声を響かせている。
「またこんなところでさぼってやがる」
突如そんな声がしたので振り返ってみると、今ちょうど一人の僧侶が、縁側を伝ってこちらへやってくるところであった。
どかどかと、肩で風をきって歩いてくる姿は、実際の年齢よりも年嵩に見える。
「あらあら、目が覚めたよ、義円《ぎえん》」
そう言って、貞観はへらへらと袖を振る。
貞観と同じ十六であるため、もう少し若々しいところがあってもよさそうなものだが、義円という男は会う者すべてに二十後半に思われるほど老成していた。
対する貞観と二人で並んでいるところを見ると、なよとした貞観を女性と見間違え、男女が昼間から寺の境内で逢引きをしているふうにも見てとれる。
「そんなにさぼるとまた叱られるぞ」
「いいよ別に。構いはしない。それより毎日同じ時間になると始まる講義に出るほうが面倒というものだ」
はははと大きな口を開けて、義円は笑う。
いつ見ても、この友人の快活なさまは見ていて気持ちがいいものだと、貞観は思う。
「それより、こないだ言っていた女人はどうなった」
一転、真面目な面持ちをして義円が問うた。
「こないだの女人て、一体、誰のことだろう」
貞観は片手で指を折る動作をしてみせる。
「さすが、常時二十人以上と文を交わしている奴の言うことは違うな。ほら、半年前から文を送っていて、こないだから文のやりとりを始めたという」
「ああ、西三条の女御」
「そう、それだ」
義円はしたりと笑む。
「彼女ねぇ、今夜、伺うつもりだよ」
「今夜だと?」
ここでいう「伺う」とは、勿論、ただ顔を出すだけの意味ではない。
この時代、恋愛は、男性が女性の元へ通い事に及ぶことで成り立っている。
つまり、貞観は今夜、西三条の女御の元を訪れ、事に及ぶと言っているのである。
「ずいぶんと急だな」
「手がね」
貞観が己の手をひらひらとさせる。
「手?」
「そう。手っていうのは文面のことだけれど、彼女の文の内容がね、早く来いってせっつくんだよ。かねてから美人と名高い西三条の女御から、そんな文をもらった日には、行かない手はないだろう」
ここでも義円は、はははと笑う。
「というのは表向きの話で、僕は前を歩かれるのが嫌いなんだ。手を引かれるのも嫌い。誘導されるのも嫌い。せっつかれるのも嫌い。行動を強いられることに激しい怒りを覚えるたちなんだ」
「それは知っているが。それならなぜ」
ふふ、と貞観は笑む。
「この手合いの女人は、放っておけばだんだんと言動が極端になるものさ。早めに手を打って、しこりが出来る前にさよならするのが出来る貴公子というものだろう」
これには、義円は声を出して笑った。
「僧侶の俺には分かるまい」
「都から遠く離れた地とはいえ、こうして女人と遊び交わすことができるというのは、男冥利につきるものだよ」
「らしいな。さすが、『しなだれの君』は言うことが違う」
『しなだれの君』とは、貞観の女人と交わす文面や、そのしゃなりとした態度から名付けられたあだ名であった。
はじめは文の相手が面白がって呼んでいたものが、いつの間にやら大学の同僚たちの間でも用いられる名となり、今ではすっかり義円にも定着していた。
もっとも、女人とは異なり、同僚や義円は、このあだ名をもっぱら女遊びの激しい貞観を揶揄するために使うのであったが。
「僕の女遊びもいいけれど、そちらの男遊びはどうなんだい」
この時代、僧の男色というのも、珍しいものではない。
「まぁ、いろいろだ。適度に楽しんでいるよ」
それでも、寺内のことについては口がかたくなるのは、義円が任務に忠実な僧兵であるからでもあった。
「しかしまぁ、色々とめんどうなことだねぇ」
まるで生きることそのものに飽いているかのような貞観の物言いは、今にはじまったことではない。
「そのような態度が、女人をその気にさせるのだろうな」
義円は笑って言う。
「なんだい、そりゃ」
「あまり遊びが過ぎると、また『婆さん』にしかられるぞ」
義円の言う「婆さん」とは、貞観の家人で最も長く勤めている稲《いね》婆さんのことである。
いつだったか、貞観が、約束もないのに義円と夜通し飲み明かしたことがあって、その時は二人してしこたま叱られたのだっけ。
その時の記憶がどうにも抜けないらしく、以来、義円の中で稲は「婆さん」で定着している。
貞観は、言われてその時のことを思い出し、一拍遅れてはははと軽く笑った。
見ると、庭の手入れをしていた小坊主が、今度は通路となっている飛び石に水を撒いている。
太陽はいよいよ目に映るものすべてに、じりじりと熱を伝えている。
「大学へは、戻らんのか」
今日の今後の予定を、義円が尋ねる。
「ああ、もう自邸に戻ろうと思うよ。暑いしね、夜のためにも少し寝ておきたいから」
「そりゃあご苦労なことで」
面倒だけれど、と貞観は笑う。
「義円はこれから午後の読経?」
「ああそうだ。お前の分も読み上げてきてやるからな」
義円は胸の前で手を合わせて見せる。
それを見て、貞観はふふ、と笑う。
「じゃあ」
「それじゃあ」
そうして、太陽が最も高い時刻に、二人は別れたのであった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
