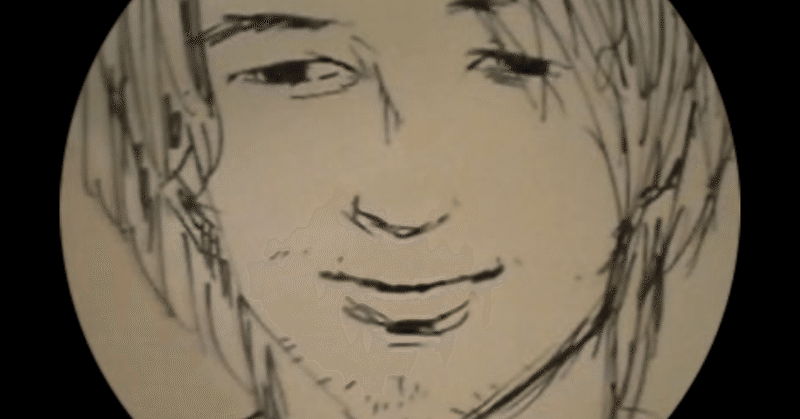
実演家印税と著作権印税に関する不条理について。
今日は日本の音楽家への利益配分の不条理をお話します。印税のお話です。
若い音楽家で著作権印税や実演家印税(アーティスト印税)についてよく分かって無い人、無頓着な人が多いと思います。ここでは出版社の手数料やジャケット代などの細かな数字は抜きにしてザックり話を進めます。インディーとメジャーでは実演家印税に大きな差がありますがここではメジャーでの話とします。CDの売り上げからの印税のお話です。
まず大前提として実演家印税は契約です。著作権印税は法律です。
実演家印税は1~3%です。それをバンドメンバーで分けます。バンドメンバーが4人て実演家印税が2%ならひとりの取り分が0.5%です。
著作権印税は6%です。法律で決まっています。出版社はたいていその半分の3%、残りの3%を作詞作曲者が取ります。
作詞作曲者のAさんは著作権印税収入の3%+実演家印税収入の0.5%、つまり3.5%が取り分です。
他の曲を作らないBさんの収入は実演家印税の取り分の0.5%だけです。
つまりAさんとBさんは同じバンドのメンバーでありながらCD売り上げの印税からの収入は7倍もの差があります。
そしてカラオケなど、原盤を使用しない際の印税収入は作詞作曲者のみです。何回カラオケで歌われようと他のバンドのメンバーには1円も入ってきません。
私が音楽業界に入った当初、上記のようなことを知りびっくりしたことを今でもよく覚えています。音楽業界では作詞作曲者ファーストです。バンドの他のメンバー、演奏者、編曲家、曲を作らないトラックメイカーにはとても不利です。現在の日本の音楽業界の構造はこうなっています。
日本ではかつて大手メジャーレコード会社は作曲家、作詞家と専属契約を結んでいました。専属作詞曲家と言われた時代です。曲を作る人が偉かったんです。曲を作る人は先生と呼ばれてました。歌手が先生から曲を頂く、そのような歌手と作詞曲家との関係がありました。時代が変わり、曲を自前で用意するアーティスト、バンドが多く生まれそのような慣習は無くなります。
とは言えいまだに作詞曲家とその他の音楽家の所得格差について日本の音楽業界は抜本的な改革をしようとしません。ではこの不条理をどうしてるのか?個別に緩和策を講じます。
シングルのB面にあまり曲を作らないメンバーの曲を収録する。サザンオールスターズがよくやってました。
曲に関しては作曲家がひとりで作ったとしてもメンバーで等分に割る。つまり作曲はバンド名義にする。
などが頻繁に見受けられる主な例です。
長くなってしまいました。この話はつきません。ここまでにしておきます。日を改めてまた書き進めたいです。
時代は大きく変わってるのに法律や慣習がほとんど変わってません。音楽業界の収入構造には抜本的な改革が必要です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
