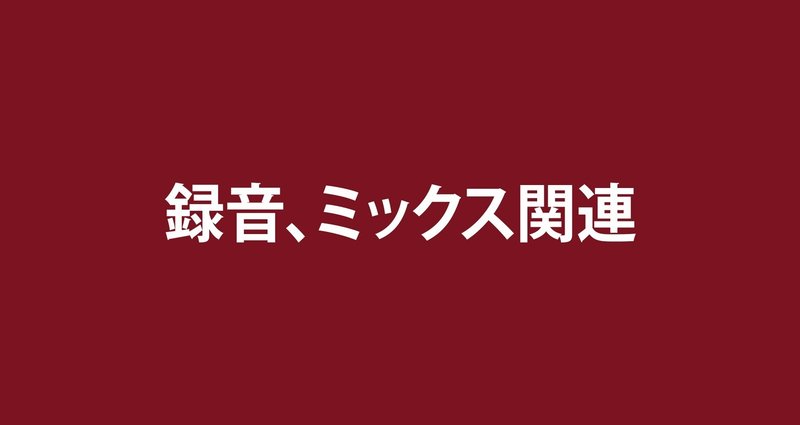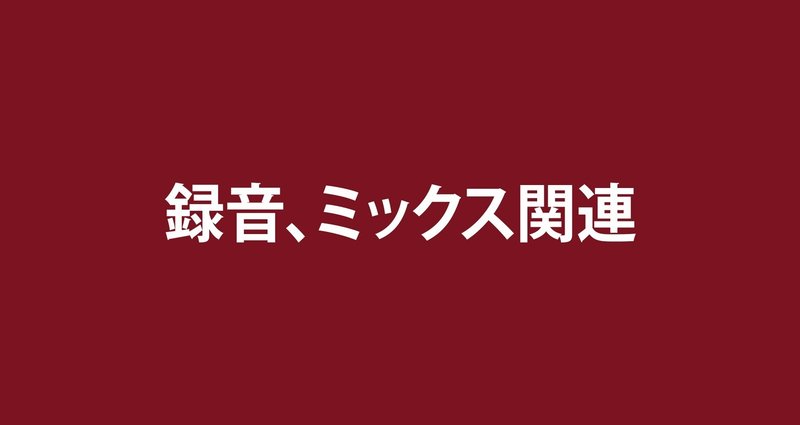ミックスを始める時に1トラック目の音量で悩まなくなる環境設定
ミックスをしていると気がついたらマスターがクリップしてた! リミッターの出番だ! みたいなシチュエーション、結構あるんじゃないかと思います。ミックスを始める時に1トラック目(例えばキックやベース)の音量を大きくし過ぎたり小さくし過ぎると最終的なミックスの音量に直接影響します。
また、多くの配信プラットフォームでラウドネスノーマライゼーションが導入され、またテレビのようにラウドネスの基準がルールとして定められているメディアもある昨今、ミキシングにおけるプロジェクト全体のレベル