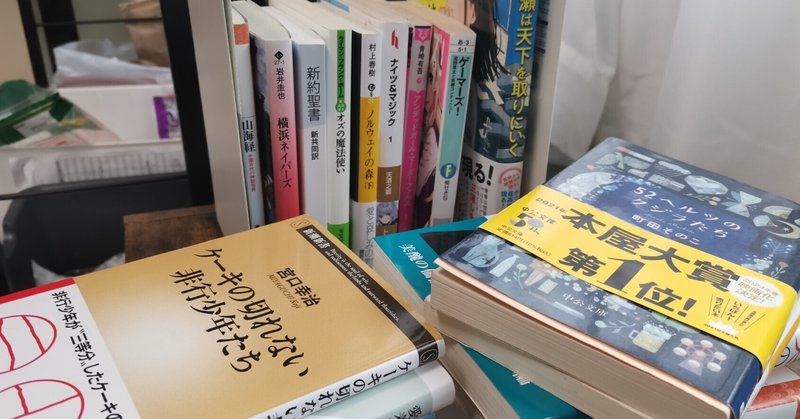
最近読んだ本紹介【日記:2023/09/22】
①「おいしさ」の科学 素材の秘密・味わいを生み出す技術
味覚や美味しさというごく個人的な話を、科学の言葉で語ってくれる一冊。意外と身近な話題が多く、それでいてしっかり疑問に答えてくれる良書です。私みたいな料理をしない理系には丁度いいかな。
特にレシピ本を見て「理由を説明しろ!」とキレているようなタイプには凄くオススメ。きつね色にとか、箸がスッと通るぐらいとか、しゃべぇ用語を使われないので落ち着きます。
もちろん、これはブルーバックス新書であって主婦の友社の本ではないので、読んでもカレーの作り方一つ分かりませんが、煮込む前に何故か素材を炒めさせられる意味は分かります。
料理は科学実験、そう思えば楽しくできる……わけでもありませんが、意味わからんくせぇ物を作らされたあげく、レポートを書かされるよかましだと我慢して、もう少し自炊を頑張ってみようと思います。
②アカギ-闇に降り立った天才
今までネットミームしか知らないにわかだったのですが、ようやく全巻読み終わりました。鷲頭麻雀の長さには本気でビックリしましたが、想像以上に好みの作品で、早く読めば良かったなと思っています。
何と言っても、主人公「赤城しげる」のキャラクター性が良い!
ぱっと見はギャンブル漫画の最強キャラのテンプレである、イカレた狂人のように思えるのですが、他の作品と違ってどこまで行っても寂しげな雰囲気なのが特に。
色々解釈はあると思いますが、意外と彼は常識人なんじゃないかなと、私は思います。狂人というよりは、哲学者。世界と自分を冷静に、理性の眼で見つめた結果、死を含めた全てを同列に考えるようになった。そんな感じ。
主観的に世界を見れないというのは、結構な不幸だとは思いますが、そんな中で博打に出会えたのは彼にとって、きっと幸せなことだったんでしょうね。
③美男子と煙草
太宰治の短編エッセイ。雑誌記者に誘われ上野の浮浪者に会いに行った太宰が、浮浪者という存在と煙草について持論を述べるといったような内容。8ページぐらいの短い作品ですが、私は結構好きですね。「走れメロス」とかで出てくる光の太宰という感じで。
途中、太宰は浮浪者のことを美男子でたいてい煙草を吸っている連中と言っているのですが、それもまた何というか含蓄がある表現で良い。私たちが何故、煙草や退廃に好かれるのかという理由の一端が理解できるような気がして。多分、カッコつけと浮浪者的な振る舞いというのはとても近い所にあるんでしょう。見た目の話だけでなく、精神的な面においても。
私も無職ですから、気を付けないといけないなと思いましたよ。本当。
④52ヘルツのクジラたち
前に見かけた時、「タイトルがお洒落だな~」とは思いつつスルーしていましたが、文庫化しているのを今さら知ったので購入。
あらすじからを読んだ時からなんとなく思っていましたが、どことなく美少女ゲームっぽい雰囲気を感じます。”海沿いの田舎町”、”家庭に問題を抱えた人々”、”過去の後悔と雨”。最近「AIR」を一気見したばかりだからそう思うのかもしれませんが、オタク的にもかなり刺さる内容でした。無論、一般文芸なので、表現は生々しいところがありますし、メインキャラも成人女性と13歳の少年と男性オタクコンテンツの文脈からは外れますがね。
「砂糖菓子の弾丸は打ち抜けない」で有名な桜庭一樹氏が後に直木賞を取ったように、かつての美少女コンテンツ文化と一般文芸の距離は意外と近いのかもしれませんね。
エンタメ特化の今風のオタクコンテンツもいいですが、感性を過去に置き去りにしてきた人間としては、やはりこういう作品を好きになってしまう。
⑤最貧困女子
こういう言い方をすると方々から怒られるかもしれないが、いわゆる『最貧困女子』と呼ばれている人々と、オタクコンテンツにおける美少女ヒロインや主人公はどこか似たところがあるんじゃないかと思う。家庭や愛に恵まれず、乾いて苦しんでいるところが特に。無論、現実の目を背けたくなる悲惨さに比べれば、創作におけるキャラの苦しみは幾分かマイルドではあるだろうけれど。埋めたがっている空虚があるというのは同じだ。
だから、私は最近この手の本を沢山読んでいます。少なくとも、創作キャラにおいては、凹んだ心を持った人間の方が魅力的なはずだから。その研究のために。
ただ、現実の陰惨さに直面すると、気分は結構やられますね……個人的には、親に指を折られてじゃんけんが出来なくなってしまった少女の話が中々キツかった……
美しい創作の世界のように、彼女たちの行く果てに幸せがあらん事を願うばかりです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
