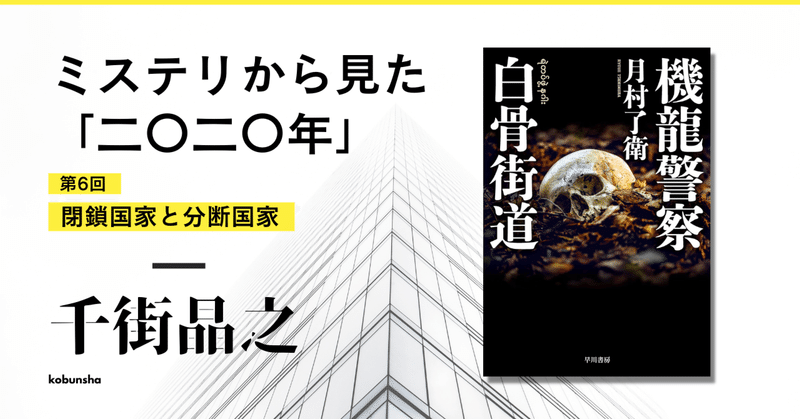
閉鎖国家と分断国家|千街晶之・ミステリから見た「二〇二〇年」【第6回】
▼前回はこちら
文=千街晶之
第三章 閉鎖国家と分断国家
二〇二二年の第百六十六回直木賞において、候補作となった逢坂冬馬『同志少女よ、敵を撃て』(二〇二一年)に対する選評が一部で話題となった。第十一回アガサ・クリスティー賞の受賞作『同志少女よ、敵を撃て』は、第二次世界大戦中の一九四二年、家族を含む郷里の人々をドイツ軍に虐殺されたロシア人少女セラフィマが、赤軍の訓練学校で復讐のため狙撃兵になることを決意し、似たような境遇の女性狙撃兵たちとともに訓練を重ねた果てに実際の戦場に出る物語である。デビュー作にして直木賞にノミネートというのは前例がないわけではないが(近年では宮内悠介や木下昌輝の例が思い浮かぶ)、比較的珍しいことは事実だろう。
《オール讀物》二〇二二年三・四月合併号に掲載された選評に目を通してみると、選考委員のうち林真理子は「確かに面白い。細部までリアリティに充ち、最後のフェミニズムの思想まで、読者をひきずり込むさまも見事である」と評価しつつ、「それならなぜ受賞作と思えなかったかというと、こうした小説を読む時にいつもわき起こる一種の違和感、『どうして日本人の作家が、海外の話を書かなくてはならないのか』というものを、最後まで拭い去ることが出来なかったからだ」と記している。また伊集院静も、「私にはなぜ日本人があの悲惨な戦争を描き切れるのか、と疑問を抱くほかなかった」と評している。
林の「どうして日本人の作家が、海外の話を書かなくてはならないのか」という疑問と、伊集院の「なぜ日本人があの悲惨な戦争を描き切れるのか」という疑問のあいだには、厳密に言えば微妙なニュアンスの違いは存在するだろう。林のそれは恐らく作家としてのスタンスから発せられた素朴な疑問であり、伊集院のそれは他国の深刻な事態を異邦人が語り得る資格があるかという当事者性の問題である(しかし、例えば現在のロシアやウクライナの作家が、『同志少女よ、敵を撃て』のような小説を発表し得るか……といえば難しいところだろう。非当事者の異邦人だからこそ遠慮や忖度なしに描けるテーマやモチーフは存在する筈だ)。とはいえ、これらの疑問はいずれも、国境を越える作家の想像力というものを軽視している。と同時に、日本と海外諸国との関係を、国境や民族などの区分で割り切れるという単純な認識に基づいているようにも見受けられる。
直接日本は関わっていない筈のウクライナへのロシアの侵攻を原因として、日本を含む世界中の国で物価が上昇したように、他の国々に影響を及ぼさない、当事国同士のあいだでのみ完結した戦争などというものはあり得ない。国家対国家の戦争のみならず、場合によっては内戦やクーデターもまた然りである。
例えば林や伊集院の立場からは、月村了衛の「機龍警察」シリーズ、中でも現時点での最新長篇『機龍警察 白骨街道』(二〇二一年)のような作例に対してどのような評価が下されるのだろうか。
「機龍警察」シリーズは、月村のデビュー作『機龍警察』(二〇一〇年)を第一作とする「至近未来」アクション小説のシリーズである。舞台となるのは、大量破壊兵器が衰退し、代わりに市街戦を想定した近接戦闘兵器が急速に普及した社会。警視庁に新設された特捜部は、新型機甲兵装「龍機兵」の搭乗員として三人の傭兵(フリーの傭兵の姿俊之、アイルランド出身の元テロリストのライザ・ラードナー、ロシア出身の元警察官のユーリ・オズノフ)に警部の地位を与えて契約を結ぶなど、異例ずくめの組織である。特捜部部長・沖津旬一郎の、警察組織の因循を打破するこの破天荒なやり方は、当然のように警察内部で反感を買い、また警察や政財界の中枢にまで食い込んでいる正体不明の〈敵〉との対決を余儀なくされることになる。
『機龍警察 白骨街道』はこのシリーズの第七作(長篇としては第六作)であり、珍しい海外出張篇となっている。首相官邸に呼び出された沖津は、ミャンマーの奥地で逮捕された日本人国際指名手配犯・君島洋右の身柄引き取りのため、姿俊之、ライザ・ラードナー、ユーリ・オズノフを現地に送れという厳命を受ける。それは、政情不安な現地で三人を抹殺し、「龍機兵」の機密を彼らから奪取しようという〈敵〉の謀略だった。やむなく沖津によって現地に送られた三人は、少数民族への迫害や国軍の専横といったミャンマーの闇に直面する。
このシリーズの時代背景について、著者は当初「至近未来」と表現していたけれども、今や「現在」の物語となっており、そのことは『機龍警察 白骨街道』が証明している。タイトルの「白骨街道」とは太平洋戦争中の最も悲惨なエピソードとして知られるインパール作戦(一九四四年、日本軍がイギリス軍の拠点だったインド北東部インパールにビルマ側から侵攻しようとして失敗、撤退中の日本兵が大量に餓死・病死した。そのルートは日本兵の亡骸で埋めつくされたため白骨街道と呼ばれた)を、姿たち三人が強いられた無謀な作戦と二重写しにしたものだが、《ミステリマガジン》二〇二〇年三月号から連載を始めた時点では、コロナ禍の中でも東京五輪をあくまで押し進めようとする政府の姿勢に絡めて、「インパール作戦」という言葉がこれほど世間で流行するとは著者も思っていなかった筈だ。
そして、「現在」とのリンクがより顕著になったのは物語の結末である。連載の最中の二〇二一年二月一日、ミャンマーでは国軍によるクーデターが発生し、国家顧問(事実上の最高指導者)アウンサンスーチーらが拘束されるという事変が起きた。まさかこんな事態になるとは著者にとっても想定外だったと思われるが、それを作中に取り入れ、これが「現在」の物語であることを強調するのに見事に成功しているのがこの小説の凄みである。なお、「機龍警察」シリーズで実在の政治家が言及されるのは本作のアウンサンスーチーが恐らく最初だと思うが、これは近年の著者が『東京輪舞』(二〇一八年)や『悪の五輪』(二〇一九年)といった作品群において、架空の人物を主人公としつつ歴史上実在の人物たちを絡ませる山田風太郎的な小説作法を取り入れていることと無関係ではないだろう。
『機龍警察 白骨街道』の重要な背景となっているのがミャンマーのロヒンギャ問題である。ロヒンギャとは、主にラカイン州北部で暮らしてきたベンガル系ムスリムが名乗る民族名とされる(『機龍警察 白骨街道』で君島が収容されている刑務所はラカイン州シャベバザル北東にあるという設定。なお、ラカイン州は白骨街道のあるチン州と隣り合っている)。ミャンマー政府と多くの国民は、仏教徒が九割を占める同国で絶対的少数派のムスリムであるロヒンギャを隣国バングラデシュからの不法移民集団と見なして国籍を認めておらず(バングラデシュ側はロヒンギャをミャンマー国民と見なしている)、長年差別してきたが、それが凄惨なかたちで爆発したのが二〇一七年のロヒンギャ危機である。この年の八月、ロヒンギャの武装勢力「アラカン・ロヒンギャ救世軍」(ARSA)が警察を一斉に襲撃したことをきっかけに、国軍はARSA摘発を名目とする掃討作戦に踏み切り、ロヒンギャの集落を破壊し、住民を無差別に殺害するに至った。正確な死者数は不明だが、一万人を超えていると推測される。
この結果、それまでにも繰り返されてきたロヒンギャの国外流出は一気に加速し、膨大な数の難民がバングラデシュをはじめとする他国へと逃れた。日本にも、群馬県館林市にロヒンギャのコミュニティが存在する。しかし、二〇二〇年からのコロナ禍と二〇二一年のクーデターが、事態の解決を更に困難なものとしているのが現状だ。
二〇二二年九月、日本の防衛省は同省および自衛隊の教育機関へのミャンマー国軍からの留学生について、二〇二三年度以降の新規受け入れを停止する方針を公表した。ミャンマー国軍が二〇二二年七月に民主派活動家ら四人の死刑を執行した件について、事前に国軍側に伝えた強い懸念について顧みられなかったため、防衛協力・交流を現状のまま継続することは適切ではないと判断した……というのが理由である。
しかし、同じ二〇二二年九月に行われた安倍晋三元首相の国葬にはミャンマー国軍の関係者を招待するなど、ミャンマー絡みの事案について、日本政府は一貫して判断が甘いところがある(因みに、この国葬のちょうど十五年前にあたる二〇〇七年九月二十七日には、ミャンマーで民主化デモを取材中だった日本人ジャーナリストの長井健司が政府軍に射殺されている。また二〇二一年のクーデター後には、ジャーナリストやドキュメンタリー映像制作者といった複数の日本人が当局に拘束された)。その甘さの原因としては、両国間の長年の関係が影響していると考えられる。
日本は一九五四年の日本・ビルマ平和条約および賠償・経済協力協定の調印以来、ミャンマーへの最大の援助国であり、一九八八年の国軍によるクーデターとその後の民主化勢力への弾圧に対し制裁を行った欧米とは一線を画してきた。二〇〇三年のディペイン事件(地方遊説中のアウンサンスーチーとその支持者が暴徒に襲撃され、数十人の死者を出した事件。アウンサンスーチーはそのまま当局によって拘束された)以降はアメリカによる経済制裁にやむなく追随したものの、二〇一一年の民政移管で再び潮目は変わり、良好な経済関係が構築されるに至った。ロヒンギャ危機に関しては、日本政府はまず避難民への援助というかたちで対処したものの、ジェノサイド疑惑に対する言及は欧米諸国ほど厳しいものではなかった。衆議院が本会議でミャンマー国軍によるクーデターを非難する決議を採択したのは二〇二一年六月であり、二月のクーデターからは四カ月が経っている。アメリカのジョー・バイデン大統領がクーデターの九日後に、軍幹部への制裁とミャンマー政府の在米資産一〇億ドルの凍結を発表したのとは対蹠的である。
『機龍警察 白骨街道』の作中では、ロヒンギャ危機とアウンサンスーチー率いる当時の政府の対応は次のように説明されている。
ミャンマー国民はロヒンギャを『ベンガル系ムスリム』あるいは『ベンガリ』と呼ぶ。絶対に『ロヒンギャ』とは呼ばない。ベンガリとは東インド出身者を意味する言葉で、極めて侮辱的な意図のもとに使われる。
圧倒的多数のミャンマー人は、ロヒンギャなどという民族は存在せず、不法入国したイスラム教徒が勝手にそう自称しているだけであると考えているからだ。アウンサンスーチーを国家顧問として戴く政府も世界に対してそう主張している。現実問題として、一九五〇年以前に『ロヒンギャ』なる名称が使われていた形跡は発見されていない。
歴史的に見て、仏教とイスラム教徒との分断を加速させたのはイギリスによる植民地化だが、日本も決して無関係ではない。第二次大戦中、日本軍はラカイン人仏教徒を訓練してイギリス軍との戦闘に利用した。イギリス軍も、ベンガル地方に避難していたイスラム教徒を武装化して対抗した。これにより仏教徒とイスラム教徒の対立は決定的なものとなったのである。
そして一九八二年、市民権法の施行によりロヒンギャの国籍は剥奪された。ロヒンギャには選挙権はおろか、国内を移動する自由さえ認められていない。教育も受けられず、就職もできないのが現状だ。アウンサンスーチーの民主化運動をロヒンギャは支持し、希望を託した。だが国民民主連盟が政権を握った後も、アウンサンスーチーはロヒンギャの存在そのものを認めなかった。
つまり、差別や迫害を政府が事実上黙認しているのだ。
現在のような事態を招いた原因に、日本も決して無関係ではないという月村の歴史認識が窺える。また、ロヒンギャに対するミャンマー国軍の迫害の手段と、それに対するアウンサンスーチーの姿勢については次のような記述がある。
ミャンマー国軍による民族浄化作戦において、最も特徴的なのはシステマティックに実行された性暴力だ。ロヒンギャの女性が暴行されたときの手口は一致していて、必ず子供達の目の前で行ない、彼女達の着用するヒジャブを目隠しに使ったという。肉体的な後遺症も深刻だが、精神的恐怖から故郷への帰還の意志を喪失させる極めて非人道的な戦略である。
政権を握る以前のアウンサンスーチーは、国内の民族対立における分断の手段として性暴力が用いられていると発言していたが、現在は正反対の主張を繰り返している。
事実上の最高指導者となったアウンサンスーチーは政権を運営する上で、長年ミャンマーを支配してきた国軍とのあいだでバランスを取り続けなければならなかった。その姿勢にはやむを得ぬ部分もあるとはいえ、対外的にロヒンギャへの迫害を正当化したことは、国際社会から大きな失望で迎えられた。『機龍警察 白骨街道』のラストでは、ある人物がアウンサンスーチーに関して皮肉な感慨を洩らす。二〇二一年二月のクーデターで拘束されて以降は、それまでと異なってアウンサンスーチーに関する各国の報道は同情的なものへと反転したけれども、ある程度は彼女自身がこの事態を招いた面もあると考えれば、この人物の感慨に私も同感せざるを得ない。
林真理子や伊集院静なら、ロヒンギャ危機やミャンマーのクーデターに関する『機龍警察 白骨街道』の描き方に異を唱えるかも知れない。何故、日本人がミャンマーの問題を扱えるのかと。しかし、これまで見てきたように、それはミャンマーの内政問題にとどまるものではなく、日本とミャンマーの外交の歴史が大きく関わっているのであり、対岸の火事として捉えるのは無責任極まりない。
しかし、安倍元首相の国葬における日本政府の軍政に対する姿勢が示すように、日本はミャンマーの諸問題をどこか深刻に捉えていないようなところがある。これはミャンマーに限ったことではなく、日本は東南アジア諸国と政治・経済面で密接な交流を持ちながら、その国民に対しては無関心または見下した姿勢を見せる場合がある。そのような日本の体質を最もよく示すのが、悪名高い入国管理局の難民に対する態度だろう。
二〇二一年三月、名古屋入管でウィシュマ・サンダマリというスリランカ人女性が死亡した。二〇一七年に留学生として来日した彼女は、交際相手から暴力を振るわれ警察に相談するも、在留資格を失っていたことから二〇二〇年八月に名古屋入管の収容施設に入れられた。翌年一月頃から体調を崩していた彼女は、外部の医療機関での受診を求めたが、入管側は外部の病院では胃カメラの検査、頭部CTスキャンでの検査しか受けさせず、ろくな治療を行わないままついには見殺しに至った。
しかし、この件は氷山の一角でしかなく、二〇一四年にはカメルーン人男性が持病の容体が悪化した際に救急搬送されることなく東日本入管センターで死亡、二〇一八年にはインド人男性が同センターで自殺、二〇一九年にはナイジェリア人男性が大村入管でハンストの末に餓死……等々、入管施設における暴行や医療放置などの非人道的行為は以前から指摘されていた。
こうした日本の入管の問題点に対しては、かねてより国連の人権関連の委員会から繰り返し改善するよう勧告されていたし、日本国内でも非難の声が挙がっていた。だが、入管はそれを無視し、外国人から人権や尊厳を剥ぎ取るような行為とともに無期限収容を行っている。そのことは、彼らにとって、外国人があくまでも「管理」と「監視」の対象でしかないことを示している。
このような事態を、日本のミステリ作家はどのように描いたのだろうか。入管の職員を主人公に選んだミステリ小説としては、下村敦史の『フェイク・ボーダー 難民調査官』(二〇一六年。単行本刊行時のタイトル『難民調査官』を文庫化の際に改題)と『サイレント・マイノリティ 難民調査官』(二〇一七年)がある。両作の主人公は、東京入管の難民調査官・如月玲奈。難民調査官とは、難民申請を望む外国人が難民条約が定義する難民に該当するかどうか、調査して供述調書を作成する役職である。如月玲奈は、「私たちは慈善事業をしているわけじゃないの。国の防波堤なの。不正者が一人、二人と抜け出したら、一気に決壊する。押し流されるのは日本国民よ」(『フェイク・ボーダー』)、「認定した難民が次々に問題を起こしたら、国民の怒りは誰に向かう? 生活保護の問題を例に挙げれば分かるでしょ。全体的に見れば不正受給はごく一部だとしても、相次いで報道されたら制度が不正の温床のようなイメージを持たれる」(同)という信念のもと、理想家肌の難民調査官補・高杉純からしばしば批判されようとも甘い判断は下さない原理原則主義者だ。とはいえ、彼女の中にも、出身国で難民を差別しているとは決して認めない法務省のダブルスタンダードへの不満は燻っており、高杉の義憤に同意する場合もあるし、理不尽な判断を押しつける上司に反旗を翻したこともある。
しかし、この二作のどこにも、近年指摘されている虐待や医療放置などの事例に象徴される入管の体質そのものへの批判は存在しない。ウィシュマ・サンダマリの件が大きく取り上げられるようになる前に執筆された小説とはいえ、入管の非人道的な体質は以前から指摘されていたことであり、そこに触れずに入管側の立場を代弁するような下村の姿勢には疑問が残る。
下村が入管の暗部をその時点では知らなかったという可能性もあるが、そうは考えにくいのは、『フェイク・ボーダー』に次のようなエピソードがあるからだ。玲奈は高杉とともに、牛久の入管センターを訪れてクルド人難民申請者たちの個室を確認するのだが、ここでは入国警備官が警棒で壁を叩いて威嚇している描写があるし、十人部屋に十五人ほどが詰め込まれているとも記されている。にもかかわらず、玲奈はそれについて感想を洩らさないし、弱者に感情移入しがちな高杉ですら「入国警備官を一睨みし、口を開きそうになったが、こらえたようだった」程度のリアクションにとどまっている。彼らが難民申請者の外国人はこの程度の扱いで充分という価値観を内面化しているように読めてしまうし、現実の入管職員たちが起こした不祥事はその延長線上にある。玲奈はこの作品で、各国の難民事情について同僚たちと意見を交わしたあと「日本は日本。日本人の性格や国民性、日本の文化や環境、状況を考えて、その中でどうするか、国際社会にどう貢献できるか。そういう視点で問題に取り組んでいくべきよ」と正論を述べているが、収容者らに対する入管の非人道的な扱いは「日本は日本」で済まされるものではない筈だ。
「難民調査官」シリーズでは正論に凝り固まって異論を受けつけない人間や弱者に過度に感情移入する人間(活動家やジャーナリストなど)が批判的に描かれており、それは下村なりのバランス感覚なのだろう。他の作品を読む限り、そのバランス感覚がプラスに出る場合もあるのだが、少なくとも「難民調査官」シリーズにおけるそれが単なる「逆張り」としてしか作用しなかったことは、その後次々と明らかになっている実際の入管の不祥事が証明している。
日本における外国人への不当な扱いが、かえって彼らによる治安の不安定を生む事態を描いたミステリとしては、深町秋生の「組織犯罪対策課 八神瑛子」シリーズの第四作『インジョーカー 組織犯罪対策課 八神瑛子』(二〇一八年。単行本刊行時のタイトル『インジョーカー』を文庫化の際に改題)がある。毒をもって毒を制する悪徳刑事・八神瑛子が活躍するこの作品では、ネパール人などの外国人技能実習生が加わったグループによる強盗が描かれるが、事件の背景には、日本の深刻な労働力不足を補う筈の中国や東南アジアからの留学生・技能実習生が、日本人がやりたがらない仕事やサービス残業を強いられ、ブローカーと化した日本語学校や協同組合への借金返済に追われている苛酷な現実が存在している。
また、二〇二〇年に放送された連続ドラマ『MIU404』(第二章で紹介済みのためここでは設定は説明しない)では、第五話「夢の島」で技能実習生制度を扱っている。都内各地で同時刻にコンビニ強盗が多発するが、張り込んでいた機動捜査隊(機捜)により犯人たちは逮捕される。彼らはベトナム人を中心とする技能実習生たちであり、謎の人物によってSNSで煽動されて犯行に及んでいた。その張り込みの際に機捜の伊吹(綾野剛)や志摩(星野源)と知り合ったベトナムからの留学生でコンビニ店員のチャン・スァン・マイ(フォンチー)は、共犯ではないかと疑われ、職場を解雇されてしまう。その夜、マイは呼び出した伊吹に泣きながら訴える――「私たち、働きに来た。日本人、働く人いない。働く私たち、ニーズ合ってる」「ベトナム、日本の家電たくさん。日本の会社たくさん。きれい、かっこいい。みんな日本行きたい。ドリーム。でも、日本は、私たちいらない。欲しいのは、文句ない、言わない、お金かからない、働くロボット」と。
これを聞いた伊吹は「みんな、どうして平気なんだろ?」と呟き、志摩は「見えてないんじゃない? 見ないほうが楽だ。見てしまったら世界がわずかにずれる。そのずれに気づいて、逃げるか、また目をつぶるか」と返す。そして集団強盗を煽動した犯人は、技能実習生をそれに関わる日本の組織が搾取している実態を知り、罪悪感を抱く人物だった。志摩の言う「ずれ」に耐えられなくなったその人物は自らコンビニに押し入り、公衆の前で「外国人はこの国に来るな! ここはあなたを人間扱いしない」「ジャパニーズドリームは全部嘘だ!」と日本語とベトナム語で叫びながら逮捕される。事件解決後、技能実習生制度を悪用して違法なキックバックで儲けていた監理団体は業務停止命令を受けるが、その際、伊吹たちの上司である隊長の桔梗ゆづる(麻生久美子)は、「この監理団体、バックにいたの永田町方面だって」と問題の根深さを明らかにする。このドラマの脚本家・野木亜紀子の態度は、先述の下村の態度とは正反対と言える。難民や技能実習生は、本国の事情、あるいは日本社会の都合によって来日しているのだが、その日本社会の構造自体の歪みが彼らへの不当な扱いを生んでいる――それが見えている作家と、見えていない作家の違い。
さて、ここでちょっと話題は飛ぶが、こうした事例に象徴される日本の対外的な閉鎖性と、関係がないようなあるような微妙なラインで、このところ気にかかるのが「分断日本」というテーマである。文字通り、戦争などが原因で分断された日本を舞台にした設定のことだ。
ミステリでいうと、古くは藤本泉に作例があるし、比較的近年なら有栖川有栖の『闇の喇叭』(二〇一〇年)に始まる空閑純シリーズ、長沢樹の『武蔵野アンダーワールド・セブン 多重迷宮』(二〇一四年)に始まる「武蔵野アンダーワールド・セブン」シリーズ、知念実希人の『屋上のテロリスト』(二〇一七年)などが思い浮かぶ。二〇二二年に入ってからの最新の作例としては、佐々木譲の『裂けた明日』を挙げることが出来る。
元来、「分断日本」テーマ自体は、アメリカとソヴィエト連邦にそれぞれ代表される東西陣営が対立していた第二次世界大戦後の世界情勢、具体的には東西に分断されたドイツ(および、その首都ベルリン)や南北に分断された朝鮮半島のような事態がもし日本で起きたら……というシミュレーションとして誕生したものだろう。実際、第二次世界大戦の敗北によって北方四島のみならず北海道や東北もソヴィエトの占領下に置かれる可能性もあったのだから、このテーマは日本人にとって極めて強い現実味を帯びていた。SF界においてこの種の設定が多く用いられたのは一九九〇年代の架空戦記ブームに際してであり、豊田有恒は『日本分断』(全三巻、一九九五年)という、そのものずばりのタイトルの小説を発表している。しかし、ソヴィエトをはじめとする東側共産国家の相次ぐ崩壊を機に、そうした設定は一旦はリアリティを失い、架空戦記小説の衰退とともにその種のSFはあまり見られなくなった。矢作俊彦の大作『あ・じゃ・ぱん』(一九九七年)が恐らく、線香花火が消える前の最後の煌きという位置づけになるだろう。もっとも、架空戦記ブームが去った二〇一〇年代にも、SF映画『デュアル・シティ』(長谷川億名監督、二〇一五年)や連続ドラマ『仮面ライダービルド』(テレビ朝日系、二〇一七~一八年。この種の作品としては珍しく日本が三つに分断される)といった「分断日本」ものが散見されたけれども。
ならば、近年の日本を舞台に、そのような設定のミステリがしばしば見られるのは何故なのか。もちろん、二〇一〇年代から二〇年代にかけての特殊設定ミステリのブームと無関係であるわけはないのだが、そのブームからは距離を置いたところで、佐々木譲が内乱で分断された日本を舞台にした冒険小説『裂けた明日』に先立ち、日露戦争で日本が敗北したパラレルワールドの占領下東京が舞台の『抵抗都市』(二〇一九年)や『偽装同盟』(二〇二一年)といった一連の警察小説を発表していることを考えると、恐らくそれだけでは説明しきれないだろう。
現在、分断という言葉自体は、近年の世界や国内の主に政治状況を語る上で頻繁に用いられている。本稿を執筆している最中にも、先に触れた安倍晋三元首相の国葬が過半数の国民の反対を無視して行われたことをめぐって、国民を分断に導くものだという批判が見られた。そもそも、この国葬の主役たる安倍晋三自身が、「こんなひとたちに負けるわけにはいかない」と国民を敵味方に分断する発言を繰り返してきた。
しかし、そういう意味の分断であれば、アメリカの状況の深刻さは日本どころの騒ぎではない。ドナルド・トランプという、それまでの共和党出身の大統領と比較してすら異様な政治家の出現をめぐり、共和党支持者と民主党支持者の姿勢は完全に対立状態となっているが、トランプ支持層のうち「Qアノン」と呼ばれる人々の陰謀論的世界観に顕著なように、それは単純な政治的立場の対立にとどまらず、おのおのの支持層の世界観の問題にすら発展している。しかも重要なのは、対立する二つの世界観がほぼ拮抗している点であり、トランプが勝利した二〇一六年の大統領選挙でも民主党のバイデンが勝利した二〇二〇年の大統領選挙でも、たった三つの州の票数が逆転していれば、それぞれ異なる大統領が誕生する結果になった筈である。正反対の世界観を支持する国民がほぼ同数いることで、片方の圧倒的勝利が困難になっているのだ。そして、従来のアメリカの二大政党制が互いに政治的に対立しつつもそれなりに妥協の余地を残すものだったのに対し、今や決して交わる余地のない「二つのアメリカ」が存在する状態となっている。まるで、同じ都市に互いの存在を認識しない二種類の住民が共存しているチャイナ・ミエヴィルのSFミステリ『都市と都市』(二〇〇九年)さながらではないだろうか。歴史を遡れば、国家が二つに割れた南北戦争という大乱も経験しているし、アメリカほど分断国家幻想に相応しい国もないように思える。
では、アメリカほど極端な状態になっていない日本で、分断国家テーマの作品がしばしば登場するのは何故だろうか。この問題について考える上で最適の作品が、マルカ・オールダー、フラン・ワイルド、ジャクリーン・コヤナギ、カーティス・C・チェンの合作による連作短篇集『九段下駅 或いはナインス・ステップ・ステーション』(二〇一九年)である。タイトルから察せられる通り東京が舞台だが、海外作家の合作による分断日本ミステリなど恐らく前例がない筈だ。とはいえ後述の通り、この作家たちの日本に関する知識・見識の深さは並みではない。
舞台は二〇三三年。作中の世界では、二〇三一年に起きた南海地震と、それに乗じた中国の侵攻によって日本は多大な打撃を受けており、九州および東京の西側は中国に支配され、東側はアメリカの管理下に置かれ、緩衝地帯には東南アジア諸国連合(ASEAN)が駐留している(皇室は比較的安全とされる札幌に移動しており、千代田区の皇居は閉鎖されている)。米中による実質的な分割統治という屈辱的状況に置かれている日本人の中からは、両国に対するレジスタンスのグループや、中国に反撥する国粋主義政党「日本再生党」などが生まれ、さまざまな火種が燻っている状態だ。
主人公の是枝都は、東側の九段下にある東京警視庁本部に奉職する警部補である。ある日彼女は、神田で起きた殺人事件をめぐって、アメリカの平和維持軍から警視庁に出向してきたエマ・ヒガシ中尉との合同捜査を命じられる。警視庁サイドにとって、アメリカから何らかの意図で送り込まれてきたに違いないエマは煙たい存在だが、かといって拒否できる立場にはない。そのような空気はエマの側も察しており、都とエマの合同捜査は最初から緊張感を帯びている。しかし、さまざまな事件を解決するうちに、彼女たちのあいだには立場を超えた信頼が生まれてゆく。
作中の二〇三三年の東京は、さほど遠い未来ではないため、米中両国による分割統治などの設定や、人体改造技術の極度の進化、ドローンによる捜査の発達といったSF的要素を含みつつも、お台場ガンダムなど現時点の東京のディテールがそれらと同居している(日本再生党や民進党といった架空の政党が誕生している一方、自民党と公明党がこの時代にもまだある設定なのは皮肉でリアルだ)。東京の地理の描写もかなり現実に則しており、伊坂幸太郎の小説『マリアビートル』(二〇一〇年)を原作とする映画『ブレット・トレイン』(デヴィッド・リーチ監督、ザック・オルケウィッツ脚本、二〇二二年)などに見られるような、誰が見てもファンタジーとわかる「トンデモ日本」を描こうとしているわけではないことは明らかだ。とはいえ、作中の日本は戦争のせいでガソリンなどのエネルギー価格が急騰してタクシーが廃れ(東西分断によって地下鉄も不便な状態になっている)、またそれに先立つ大地震により警察の指紋データベースも消失しているなど、テクノロジー面では現在より後退した部分もあるので、昔懐かしい『ブレードランナー』(リドリー・スコット監督、ハンプトン・ファンチャー、デヴィッド・ピープルズ脚本、一九八二年)的なサイバーパンクSFのエキゾティシズムを、リアルな東京描写と自然なかたちで同居させることにも成功しているのだが。
二〇世紀に発表された「分断日本」ものでは日本がアメリカとソヴィエトに分割統治されている設定の作品が多かったけれども、この小説ではアメリカと中国になっている。中国の経済成長と軍事大国化によって世界の覇権を争う国家がこの二国になり、その狭間で翻弄されがちな現実の日本の状況を反映しているのだ。
第一話「顔のない死体」のラストは、真相に辿りついて「この事件が戦争に関係あるとは思っていなかった」(吉本かな訳。以下同じ)と感慨を洩らすエマに、都が「すべては戦争につながっている」「すべてがね」と返すところで終わる。第二話以降も、それぞれ独立した犯罪を扱っているものの、その背景には戦争の影響が濃密に漂う。
そして最後の二話「暗殺者の巣」「外患罪」では、危ういバランスが保たれていた東京がついに戦争状態に陥る。だが、そのきっかけとなったある団体の国会議事堂乱入騒ぎの際には、乱入自体によって生じた死者とは別に、明らかにその団体によるものではない他殺死体が発見される。戦争状態によって殺人事件の捜査どころではない混乱が拡大する中、都とエマは、警察官として今こそ自分たちがなすべきことは何かという問いと向き合うことになる。
実はこの小説は、これから大きく広がってゆくであろう物語の第一部であり、話としては完結していない。なので今後の展開は現時点では想像するしかないのだが、ついに東京で直接交戦状態に入った米中を相手に、日本人が独立をかけた闘争に立ち上がり、都とエマは組織人としての立場に縛られながらも両国を戦争に導いた黒幕に迫ろうとする展開が予想される。
この作品では、始まりの地点が戦争であり、ラストは新たな戦争へと向かってゆく。佐々木譲の場合も、『裂けた明日』の結末のその先に平和があるとは到底考えにくいし、パラレルワールドの日露戦争後を描く『抵抗都市』や『偽装同盟』も、史実をなぞるなら未来には世界大戦が待っている筈だ。近年の「分断日本」ものでは、戦争は分断の前提として描かれているのみならず、近い未来に再び起こるものとして描かれているのである。
現実の世界では、各地で大戦前夜さながらのきな臭い出来事が続発しており、ほんの小さな火種が原因で火薬庫が大爆発しそうな雰囲気に覆われている。世界平和の維持に責任を負うべき国連安全保障理事会は機能不全状態で、もはや新たな枠組を作るしかない。第二次世界大戦の敗北をほぼ唯一の例外として国土を外国に蹂躙された経験を持たず、戦後は日本国憲法第九条と日米安保条約という二つの車輪を使い分けることで戦争に巻き込まれずに済んできた日本も、今後はどうなるかわからない。「すべては戦争につながっている」――そんな不穏な予感が、近年の「分断日本」テーマのミステリからは窺えるのではないか。
ミャンマーの混乱を日本の暗部と絡めて描いた月村了衛。外国人犯罪を通じて日本の閉鎖的・排他的体質を抉る深町秋生や野木亜紀子。そして、日本の国土が戦場となる可能性を幻視する「分断日本」テーマの作品群。それらに共通するのは、「どうして日本人の作家が、海外の話を書かなくてはならないのか」などという素朴な世界観の対極にある認識だ。日本と外国、日本人と外国人の関係が絶えず問い直されるこの世界で、その関係のありようを凝視する作家たちの営為は続いてゆく。
《ジャーロ No.85 2022 NOVEMBER 掲載》
▼ジャーロ公式noteでは、皆さんの「ミステリーの楽しみ」がさらに深まる記事を配信しています。お気軽にフォローしてみてください。
いただいたサポートは、新しい記事作りのために使用させていただきます!
