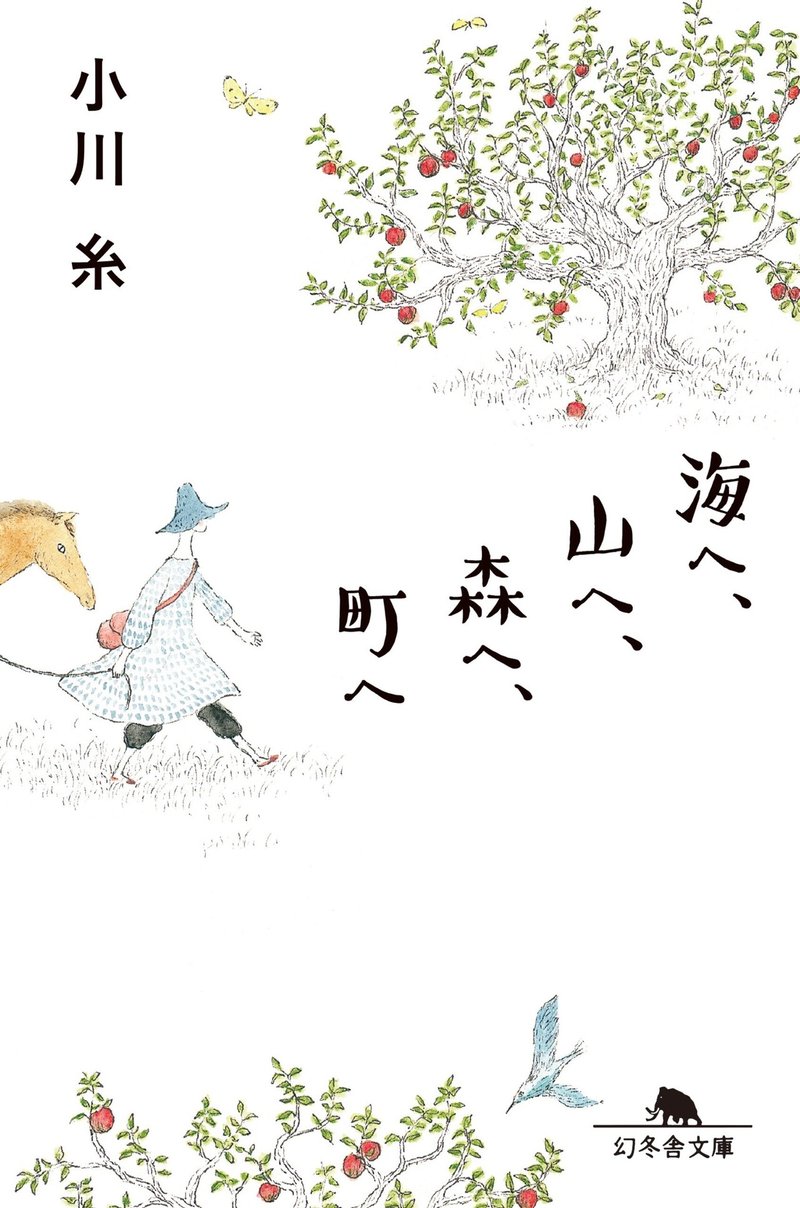葡萄がなりたい味になる ココ・ファーム・ワイナリー #2 海へ、山へ、森へ、町へ
天然水で作る地球味のかき氷。ホームステイ先の羊肉たっぷり手作り餃子。地元の山菜を使った一日一組の贅沢なレストラン。西表島で真夜中に潮干狩りをし、カナダの森でキノコ狩り…。自然の恵みと人々の愛情によって絶品料理が生まれる軌跡を辿ろう! 美味しい出会いを求めた旅の滋味溢れる、小川糸さんのエッセイ『海へ、山へ、森へ、町へ』。小川糸さんは、多くの作品が、英語、韓国語、中国語、フランス語、スペイン語、イタリア語などに翻訳され、様々な国で出版されています。それでは、本作のためし読みをご覧ください。
* * *
どうしてだろう。ココ・ファームを訪れると、体の奥に気持ちのよい風が吹き抜ける。山の裾野に立ち、遥かな葡萄畑を見上げると、またこの場所に帰って来ることができてよかったと、心の底からホッとするのだ。
ここは、私の心の楽園、ココ・ファーム。誇り高き国産自然派ワインの造り手であるこころみ学園の園生達に会うため、この年二度目となる葡萄畑にやって来た。
この日は、気温こそ低いけれど、見渡す限りの見事な青空。急峻な葡萄畑には、一年でもっとも遅い収穫を待つノートンが、キラキラと輝く透明な傘を纏って陽の光を浴びていた。
春先のことだった。ココ・ファームから素敵な贈り物が届けられた。段ボールの蓋を開けると、マスカットジュースのような爽やかな甘い香りが広がった。見ると、青々とした美しい葡萄の葉っぱ達。春先に行う「芽かき」という作業の際に切り落とされた新芽で、天ぷらのようにして食べるとおいしいと書き添えてあった。さっそく衣をつけて揚げてみると、かすかにほろ苦く、酸味もあって絶妙の味がする。こんなふうに葉っぱをいただけるのも、除草剤や防虫剤などを使っていないからなんだと、改めて気づいた。
ココの葡萄畑には、たくさんの種類の下草が生えている。除草剤を撒いてしまえば、その下草をすっかりなくすことはできる。けれどそれでは、園生達の仕事が失われる。そもそもこの葡萄畑は、障害があるとして社会の枠から外された少年達に、やってもやっても尽きない仕事をと、半世紀前に開墾された土地だ。たまたま選んだ土地が、葡萄栽培に適したジュラ紀の乾いた地層だった。
それに、下草が生えていれば、いろいろな虫が集まってくる。虫がいれば、鳥もやって来る。そうなれば、木の皮を剝いで虫を退治したり、鳥を追いやったりと、たくさんの仕事が生まれる。仕事とは、本来そういうもの。葡萄の木が週休二日で働いているのではないように、人の営みも尽きせぬものだ。
さっそく、池上知恵子さんに葡萄畑を案内していただく。池上さんはこころみ学園の園長、川田昇先生のお嬢さんで、現在、ココ・ファームの運営にあたっている。
赤ワインは、皮も種も一緒に仕込む。だから、葡萄の実のみならず種もしっかり熟すまで木に残しておくのだという。この年は粘りに粘って、十一月の半ばを過ぎてもまだ収穫を我慢している品種もある。中には、すでに水分が抜けて、干し葡萄のようになっている実もある。一粒口に含むと、皮も実もしっかりと甘く、種はアーモンドのようにカリカリとして香ばしかった。当たり前のことだけれど、おいしい葡萄からしか、おいしいワインは生まれない。
最大の天敵、カラスから畑を守る番人、コミネ君の仕事現場も見せていただく。すでに大半の葡萄が収穫を終えた後なので、コミネ君の見張り場所はキラキラの傘を被ったノートンという品種に絞られている。
葡萄栽培を始めた当初、いらなくなった楽器を譲り受け、それを鳴らしてはどうかと提案した。けれど、そうすると楽器の奏でる音色では、カラス達が逆に音楽を聴きに畑に集まってしまうという園生達からの指摘があり、楽器を鳴らすのは却下。今は空き缶(ドラム)を専用の木の枝(スティック)で鳴らしている。早く鳴らしたり、ゆっくり鳴らしたりを繰り返しながら、時には歌もうたい、実を狙うカラスらに目を光らせている。
コミネ君はこの仕事を十八年も続けている。暑い日も、風の冷たい日も。一日だけならできるかもしれない。けれど実際にやり続けることは容易ではない。他の人にはできないことができる人達、それが園生達だ。そしてコミネ君は、「来年もがんばるよー」と言いながら、その年の最後の仕事を終える。
ココでは、葡萄からワインを造る際、酵母はすべて、葡萄の皮に付着している自然のものだけを使う。だから、当然なのだけれど、たとえ同じ品種から造るワインでも、毎年毎年味が違う。「葡萄自身が、なりたい味になる」のだという。食べ物とは本来それが当然であるはずなのに、最近はそんな当たり前のことさえもが、当たり前ではなくなってきてしまっている。人間が自分達の都合に合わせて自然を変えようとすることが、果たして知恵と呼べるのかな。

とは言え、すべて自然任せにして人は何もしないかというと、そうではない。葡萄が心地よく葉を茂らせられるよう、園生達は気持ちのよい環境を整えてあげる。時には、あまり発酵が進まないワインのタンクに、電気毛布を巻いてあげることだって。ココには、人間らしいユーモアと優しさが溢れている。
こころみ学園には現在、百四十人前後の障害者が集う。そのうち九十名ほどが、施設で一緒に暮らしている。中には、この地に辿り着く前、外の世界で本当に辛い思いをしてきた園生もいる。それ故に園生達は、自分達の労働が必要とされ、質の高いワインを造っていることに誇りを持っている。けれど、思慮深く寡黙な園生達は、決してそれを声高には主張しない。そんな園生達を、池上さんは「密かに」のプロだと表現する。誰に自慢するでもなく、密かに誇りを持っているのだ。
池上さんが、杉の木立に見守られるひっそりとした場所に案内してくれた。そこは、ささやかな墓地だった。墓石には、「ここでくらし働いた人たちの墓」と書かれ、二十三名の園生の名が刻まれていた。こころみ学園が誕生して約半世紀。身寄りもなく、ここで亡くなる園生も増えている。近くには、飼っていた犬や猫、小鳥達の眠る手作りのかわいいお墓も作られていた。この世に生まれ、ただひたすらに生を全うし、そして死んでいったみんなの、ささやかだけれど確かな印のような場所だった。
取材を終え、池上さんと一緒にランチをいただく。一皿一皿の料理に合ったワインを飲みながら、青空の下に広がる葡萄畑を一望すると、遠くからまたコミネ君の演奏が響いてくる。午後になり、一段と風が冷たくなった。
海老の塩焼きを丸かじりしていると、けぃちゃんの愛称で親しまれている背の高い男性がやって来た。食事中の私達に、『君といつまでも』を熱唱してくれる。途中、みんなでワワワワとコーラスを入れながら、私達は幸福な笑いの渦の中にいた。自閉症、ダウン症、知的障害。名前をつければ簡単につけられる。けれど、世の中にはいろんな人がいていいんじゃないか。みんながみんな、同じである必要は全くないと、私はそんなふうに思っていた。ここには、けぃちゃんをはじめ、ユニークで明るい人達がたくさんいる。
ある年の初夏、雹が降って葡萄が全滅した。先生達は皆、それを見て落胆した。けれど園生達は「明日またがんばっべ」と言って、とにかく普段通り眠ったという。雹に降るなと言っても、降る時は降るもの。どうしようもないことに落胆しても結果は変わらないことを、彼らは本能で知っているのかもしれない。
密やかな誇りを胸に、園生達は今日も、静かに大地と向かい合う。冬の間にお礼肥をし、また来年の実りを心穏やかに待っているのだ。

◇ ◇ ◇