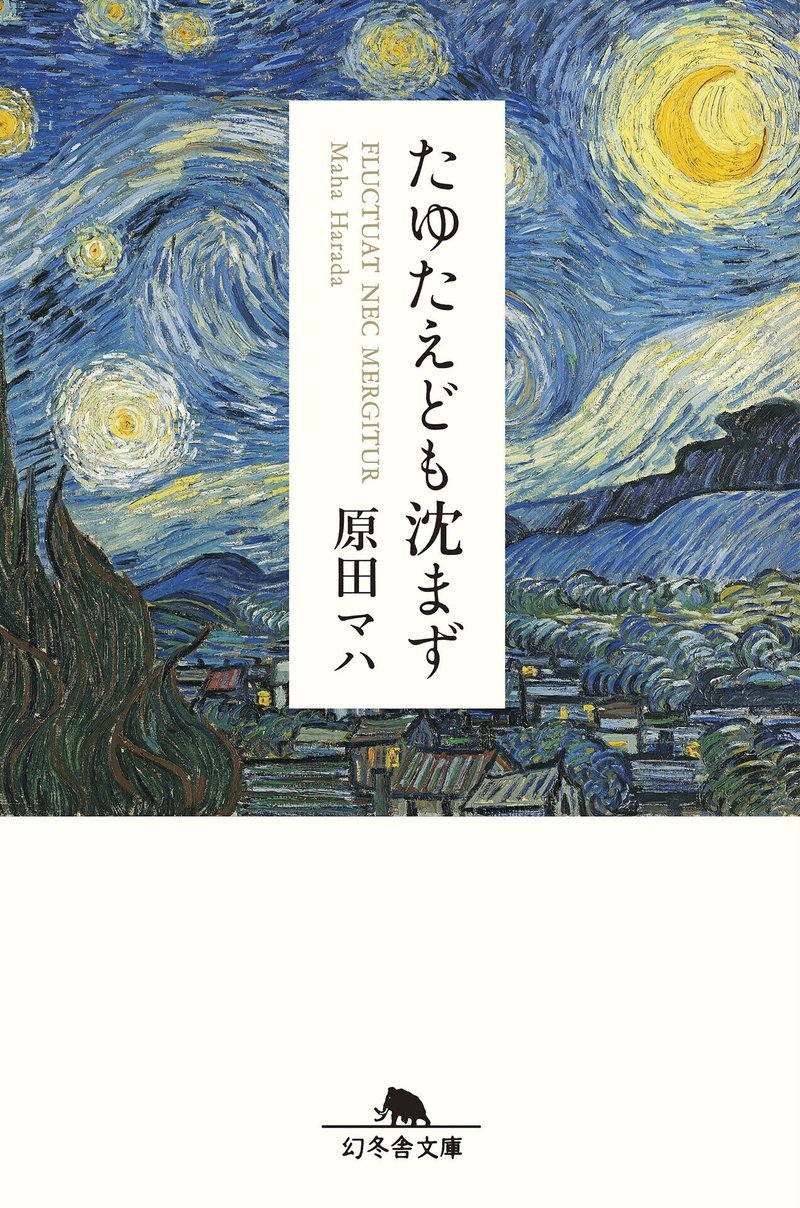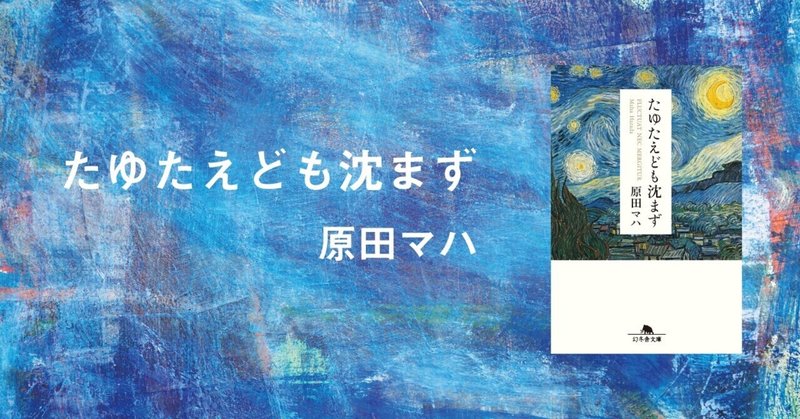
たゆたえども沈まず #3
加納重吉が林忠正と出会ったのは、かれこれ十年以上まえのことになる。
しかしながら、その日の記憶は、重吉の中にしっかりと刻印されて、鮮やかに残っている。
一八七四年(明治七年)、重吉は、旧加賀藩・石川県から、官費生として東京の開成学校に入学した。
代々高名な蘭学者の家に生まれた重吉は、幼い頃より抜きん出た秀才であり、早くからその将来を嘱望されていた。十九歳になったとき、県の支援を得て、外国語と西洋の学問を修め、故郷に帰って官吏として活躍するべく、東京へと送り込まれたのである。
開成学校は、明治維新後、政府によって開校された西洋の各学科を教える「大学南校」が、幾度かの改変ののちに外国語と西洋の学問の専門学校となったものである。最終的には一八七七年に東京医学校と合併して東京大学と総称されることになる。
重吉は、その秀才ゆえだろうか、自分はほかの誰とも違う、ほかの誰かと同じであってはいけないと心密かに思っているところがあり、少々ひねくれた性質も併せ持っていた。そんなこともあって、開成学校に入学する際、迷わずにフランス語を専攻できる諸芸科を選んだ。
諸芸科というのは、法学、理学、工学の三つの専門学科に対して、総合的に一般教養と語学を学ぶ学科で、いってしまえば雑多な学科であった。
重吉の学力をもってすれば、ほかの三つの学科のどれを専攻してもじゅうぶんに才能を発揮できたはずなのに、彼はそうしなかった。三つの学科は英語を基本として学習するので、それまでドイツ語やフランス語を学んできた学生、あるいはこれから学びたい学生にとっては、在籍するのは本意ではない。重吉は、すでに郷里で英語を独学し、習得してしまったという気持ちだったので、せっかくならば違う言語を身に付けたいと思っていた。
「明治」に元号が改まり、七年が過ぎていた。日本はそろそろ本気で諸外国に追いつかなければならない頃だった。東京府にはガス灯が点り、大通りには街路樹が植栽された。世界地図の中で、日本だけが空白のまま取り残されるわけにはもはやいかないのだ。
開成学校では、優秀な生徒を十人ほど選抜し、先進諸国へ留学させる制度を持っていた。フランス留学は、わずかにひとり、できるかできないかであったが、重吉は最初からこれを狙っていた。
──日本から一歩も出ないで外国の学問を教わったところで、しょせん、井の中の蛙じゃないか。
本気で学ぶなら、留学するしかない。アメリカやドイツではなく、フランスへ。
おれは、外国をこの目で見て、ほんものの世界を知って、金沢はもちろん、日本の役に立つようになるんだ。
そのためには、なんといってもパリだ。パリこそは、産業も文化も世界一だと聞く。ということは、世界の中心ではないか。
胸のうちに、そんな闘志を燃え上がらせていた。気分だけは「天下取り」のつもりだった。
だから、「フランス馬鹿」の偏屈な男だとか、とっつきにくいやつだとか、同級生たちから陰口を叩かれようとも、べつだん気に留めず、ただひたすらフランス語の学習に没頭した。
当初はあまのじゃくな気持ちも多分にあって始めたフランス語だったが、勉強するうちに、その奥深さにどんどん引き込まれていった。
フランス語とは、まるで言語の芸術のごとしだ。なめらかな発音。綴り。構成。──すべてが一幅の山水画のようにも感じる。
フランス人の教師が教科書として与えてくれた数々の本──ジャン=ジャック・ルソーなどの書に加え、ジョルジュ・サンドやデュマなどの小説を読むにつれ、どうしようもなく心が震えた。
いつか、必ずフランスへ──パリへ行きたい。
手が届かない貴婦人に憧れるように、重吉は、パリへの思いを募らせた。
そしてついに、日本人の担当教官、庵野修成から、君を留学生に推薦しよう、とのひと言を得た。全生徒の中でも抜きん出て語学が堪能な君こそ留学生にふさわしい、と言われて、まんざらでもない気がした。
ところが、留学先はイギリスだという。重吉は、即座に推薦を辞退した。
──本気で世界の真ん中で活躍したいなら、パリでなければ意味がないんだ。
頑なにフランス留学にこだわる重吉を、同級生たちは陰でせせら笑った。
──そうまでしてフランスに忠義を立てるなんて、ほんもののフランス馬鹿だな。
──いまや英語かドイツ語が主流なんだ。フランス語にうつつを抜かしてたら、出世できんぞ。
──あいつは出世する気なんざ、さらさらないのさ。華族の令嬢の家庭教師あたりが、いってせいぜいのところだろう。
重吉の耳に届くように、わざと近くでひそひそ話をする輩(やから)もいた。
──好きなように言えばいい。蛙どもが……。
そう強がってはみたが、留学を果たせなければ、自分だとて蛙の中の一匹なのだ。
──どうしたらいいんだ。
悶々とするうちに、次第に勉強に身が入らなくなってしまった。どんなにがんばっても、空回りしているだけのような気がしてきた。
──どうすれば、フランスへ行けるんだ。……井戸の外へ出られるんだ。
そんなある日のこと。
開成学校の校門から通りへ出たとき、ふいに背後から声をかけられた。
「Souhaitez-vous aller Paris?(パリに行きたいんだって?)」
はっとして、立ち止まった。
──フランス人?
振り向くと、見知らぬ日本人の青年が校門の傍らに立っていた。青年は、重吉の驚いた顔をみつめて、ふっと笑った。
「君は、なかなか賢明だな」
言いながら、重吉の隣へと歩み寄り、「行こう」と小声で言った。
「おれたちがつるんでいると、英国一派(エコール・ド・ラングルテール)がまたなんだかんだよからぬ噂を立てるだろう。……ちょっと付き合ってくれないか」
重吉の返事も聞かずに、そのまま、日本橋の茶屋まで連れ出した。
その青年こそが、林忠正であった。
忠正は二十三歳で、開成学校が南校だった時代に廃藩置県まえの富山藩から派遣されて入学し、重吉の三年先輩だった。諸芸科に林という名の大変な秀才がいる、と噂に聞いてはいたが、重吉が直接会うのはそれが初めてのことだった。
忠正のほうでも、三年下にとんでもない語学の秀才が入った、と聞いて、こちらは当初から注目していたという。
「どれほどの秀才か、一度話をしたいものだと思っていたんだ」
茶屋に落ち着いたあと、忠正は、手酌で熱燗を飲みながら、ごくすなおな口調で言った。
重吉は、自分が先輩であろうと高飛車に構えず、まっすぐに好奇心を向けてくる忠正の様子に、たちまち好感を持った。
「聞けば、君は、庵野先生から頂いた英国留学への推薦を辞退したそうじゃないか。大変な噂になっていたぞ。……英国留学といえば、出世の道が拓けたも同然じゃないか。誰だって飛びつきたいはずなのに、どうしてなんだ?」
「それは……」
重吉は、一瞬うつむいたが、すぐに顔を上げて答えた。
「……イギリスには、パリがないからです」
忠正は、きょとんとして、目を瞬かせた。それから、ぷっと噴き出して、笑い出した。あんまり笑うので、周りの客が皆、ふたりを見ている。重吉は、たまらなくなって、
「林さん。……そんなに笑わないでくださいよ。笑いすぎですよ」
小声で言ったが、なんだか自分もおかしくなってきて、つい、一緒に笑い出してしまった。
気持ちよく笑い合ったあと、忠正は、「いやあ、いいな。実にいい」と、涙目になって言った。
「そうなんだ。その通り。イギリスには、パリがない。パリじゃなけりゃあ、意味がないんだ。おれもまったく同感だ」
愉快そうな声でそう言って、徳利を差し出した。
「さあ、飲んでくれ、我が同志よ。パリの話をしようじゃないか」
忠正は、富山藩の医学の名門、長崎家に生まれ、その後、親族の林家の養子となり、家督を継いですぐに東京へ出て新しい学問を志した。特に、外国語を学ぼうと心に決めていた。
忠正が選んだのは英語ではなく、フランス語であった。重吉同様、彼もまた、多少斜に構えているところもあったのだが、ナポレオン公の物語に触れる機会があり、革命の嵐が吹き荒れ、ついにナポレオンが手中にした天下の都、パリに憧れて、フランス語を習得しようと決心したのだった。
学び始めた頃は、フランス語を学んでいるといえば、人の見る目も変わったものだが、最近すっかり世の中の風潮は英語一辺倒で、フランス語を学んでいるといえば、変わった人を見る目になる──と忠正はぼやいた。
「ときに、知っているか。おれたちが在籍しているフランス語の諸芸科……今期で廃止されるそうだ」
えっ、と重吉は思わず身を乗り出した。
「まさか……まったく聞いていませんよ、そんなこと。それじゃあ、僕らはどうなるんですか」
忠正は、「さあね」と人ごとのように言って、勢いよく猪口をあおった。
「フランスに行くほかはないな」
世界の列強国にくらべて、長いあいだ国を閉ざしていた日本は、もっと貪欲に自己主張をしてしかるべきだと、忠正は考えていた。
そのためには、世界中から富と人と文化が集まってくるパリで、日本人が闘っているところを見せてやろうじゃないかという思いがあった。
重吉同様、忠正もまた、フランス留学の道を探っていた。しかし、圧倒的に英語ができる生徒が増えたいまとなっては、高い公費を使ってフランスに留学生を送り込むくらいなら、イギリスかアメリカに送ったほうが人材を活かせるだろう、ということで、政府も学校も、フランス公費留学を廃止しようとしているらしかった。
「やはり、狭き門、というわけですね……」重吉がつぶやくと、
「狭くったって、入り込む隙間があればいいさ。門は閉ざされたも同然なんだ。フランスのほうが、アメリカよりもずっと長い歴史と伝統があるし、イギリスに負けず劣らず文化も芸術もあるってのに……こんちくしょう」
吐き捨てるように忠正が言った。重吉は、返す言葉を失って黙りこくった。
ふたりは、しばらく黙ったままで、開いた障子の向こう側に流れている隅田川の支流を眺めるともなく眺めていた。
ややあって、忠正は、ついと膝を立てると、
「気持ちのいい宵だ。少し、歩いてみるか」
と誘った。
川面を渡る五月の宵風が、少し酔った頬に心地よかった。ふたりは、並んでそぞろ歩きしながら、日本橋のたもとへやって来ると、どちらからともなく立ち止まった。
川岸の杭に小舟が何艘も綱でつなぎ留められ、ぎいい、ぎいいときしんでいる。ちゃぷちゃぷと川水がその腹を叩く音が響き、磯の香りが漂っている。
重吉は、橋桁が川面に落とす闇の中で、生き物のように舟々がぶつかり合ってうごめくのを眺めながら、もはや自分が活かされる道はないのだろうか──と、暗澹とした気持ちが胸の中に広がるのを感じていた。
傍らで長いこと沈黙していた忠正だったが、ふと顔を上げると、「なあ」と重吉に語りかけた。
「たゆたえども沈まず──って、知ってるか」
突然のことで、今度は重吉が目を瞬かせた。忠正は、ふっと笑みを口もとに浮かべた。
「パリのことだよ」
「……パリ?」
「そう。……たゆたえども、パリは沈まず」
花の都、パリ。
しかし、昔から、その中心部を流れるセーヌ川が、幾度も氾濫し、街とそこに住む人々を苦しめてきた。
パリの水害は珍しいことではなく、その都度、人々は力を合わせて街を再建した。数十年まえには大きな都市計画が行われ、街の様子はいっそう華やかに、麗しくなったという。
ヨーロッパの、世界の経済と文化の中心地として、絢爛と輝く宝石のごとき都、パリは、しかしながら、いまなお洪水の危険と隣り合わせである。
セーヌが流れている限り、どうしたって水害という魔物から逃れることはできないのだ。
それでも、人々はパリを愛した。愛し続けた。
セーヌで生活をする船乗りたちは、ことさらにパリと運命を共にしてきた。セーヌを往来して貨物を運び、漁をし、生きてきた。だからこそ、パリが水害で苦しめられれば、なんとしても救おうと闘った。どんなときであれ、何度でも。
いつしか船乗りたちは、自分たちの船に、いつもつぶやいているまじないの言葉をプレートに書いて掲げるようになった。
──たゆたえども沈まず。
パリは、いかなる苦境に追い込まれようと、たゆたいこそすれ、決して沈まない。まるで、セーヌの中心に浮かんでいるシテ島のように。
洪水が起こるたびに、水底に沈んでしまうかのように見えるシテ島は、荒れ狂う波の中にあっても、船のようにたゆたい、決して沈まず、ふたたび船乗りたちの目の前に姿を現す。水害のあと、ことさらに、シテ島は神々しく船乗りたちの目に映った。
そうなのだ。それは、パリそのものの姿。
どんなときであれ、何度でも。流れに逆らわず、激流に身を委ね、決して沈まず、やがて立ち上がる。
そんな街。
それこそが、パリなのだ。
「なあ、シゲ。……おれは、いつかきっと行く。行ってみせる。たゆたえども、決して沈まない街……パリに」
シゲ、と親しみを込めて呼ばれて、重吉は、水面にたゆたう小舟に放っていた視線を、傍らの忠正に向けた。
忠正の横顔は、凜として風を受けていた。その瞳は、未来を見据えて輝いていた。
◇ ◇ ◇
たゆたえども沈まず 原田マハ